
太政官って本当にユニークな人物

前回に続いて、もう一つ上司小剣。『太政官』という作品を考えてもらおう。これ、ちょっと面白いよ。というより名作に値すると思うんだけどね。しかしあまり知られてないのよねえ。まあ、他人に作品の評価を押し付けちゃあいけないけど。


確かに変に頭でっかちな小説でないだけ読みやすかったけども、そんなに素晴らしい小説でしょうかね。確かにオリジナリティーのある人物像は興味深いが、その人物の突飛な嗜好が作品の価値だということですか?そう言えるんなら、身体がゴムみたいに伸びる少年が主人公なら、もっと文学的な価値がある、なんてことになるでしょう。

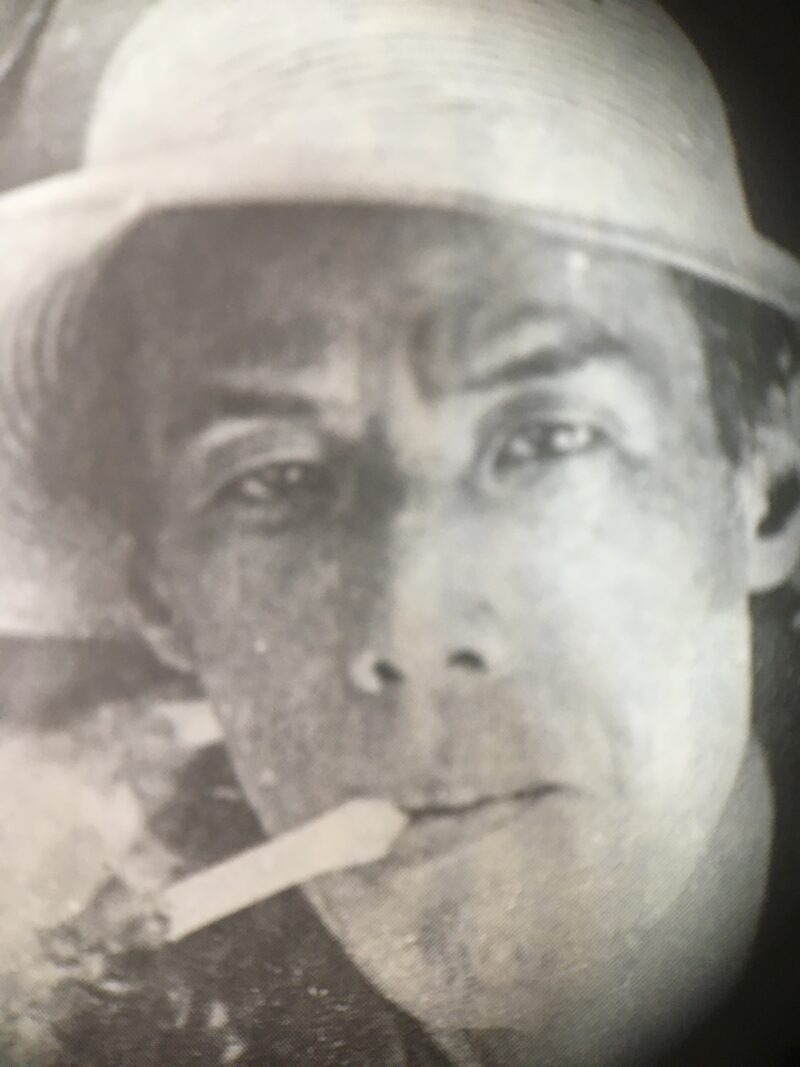
この作品が発表されたのは大正の初期でしょう。だとすると芥川の小説なんかと比べて、読者に訴えるものは何かを考えてみるのはどうでしょうか。たとえば、『鼻』が大正五年でしたね。同じように現実的とは言えない、しかも話の筋が私小説とかと違って特徴的であることを考えると、比較してどうですか。私は、やっぱり『鼻』がより名作という感じがしますけど。その意味は、なんだか、より人の心の中に迫ってくるような気がする、ということにあるんです。自意識というか、自分の心に鎧を作って傷つけられることから守る、そういう問題について問いかけてくる。

そう?私、正直にいうと今回の『太政官』の方が、物語としても人間を考えさせるものとしても、面白いと感じた。単に変なことにこだわる人というばかりでない、より普遍的というのか、広く人間全体の不思議さを見せられた感じがしたんです。
『鱧の皮』でも、大人の夫婦の温かい思いと、実はその根っこにある現実的な打算という、思いもかけない読みを聞きましたが、この『太政官』でも何かありそうな気がする。

どちらが上で、価値がある、とかそういう問題ではないことは承知の上だけど、好みとしては『太政官』かなあ。聞いたこともない話で、特に食べ物についての話は面白かった。食べ物って小説でも大きなテーマになりうるんだって初めて思ったね。考えてみると、去年古典で読んだ芋ばっかり食べてた坊さんの話あったでしょ。あれ、鎌倉時代?それ以前にも大食いの平安貴族の話もあるんだってね。日本と他の国の突拍子もない話を比べてみるのも面白いかも。

でも、『鼻』は自意識の問題を通して、人間の内部に浸透していこうとしているんじゃないかな。『太政官』はその人物の内部に入ろうとする意識はないね。小説が太政官のこだわりの拡大が外部の力によって妨害されていく。それによって破滅していく人間を描いていく。方向が内か外かという違いだと思うんです。

いわゆるグルメな人の話は他にもあるだろうけど、『太政官』てのは、特別に豪華な料理とも言えないもの求める人の話だね。ただの豪華さではなく、みんな食べる米というものの味にだけこだわるなんて、なんというか、知的なこだわりが感じられるんだ。
その上で太政官の周囲に配された村の人々がうまく描かれている、という感じがする。もちろん素人の読者の感想ですが。太政官というちょっと推しの効いた金持ちに、村人や役人がいざ面とむかうと何も言えなくなるという。でも太政官は威圧するようなことはしていないでしょう。ほんとうに興味深い人物ですね。『鼻』の禅智内供よりも、興味深い。

じゃあ、まず順番に読んでみて、あとでそういうところの話も出してみてよ。
まず、太政官のあだ名が説明されてるな。
茶瓶さん、本名は大野源兵衛。禿頭の彼が新田に住むことがすでに村の本流にいないことを示している
「太政官て何のことやいな、一體。」
「知らんのかいな、阿呆(あほ)。……教(をせ)へたろか、新田の茶瓶のこつちや。」
「そら知つてるがな、言はんかて。……其の太政官て何のことやね。
「太政官ちうたら、太政官やがな。お上の役人のこつちや。」
中の村の青年會の事務所で、二人の若い男がこんなことを言つてゐると、今一人の稍(やや)年を取つた男が、
「二人ながら知りはらんのか、あかんな。太政官ちうのは、明治十八年まであつたんで、つまり今の内閣のことや。……太政大臣がゐて、それが今の總理大臣や、それから左大臣に右大臣、參議が四五人、これだけで最高の政治をしてたんやがな。」と、下唇の裏を前齒で噛み噛み言つた。「あゝ、さよか。……そいで新田の茶瓶さんが、この村の太政官ちうことだすな。」と、常吉と呼ばるゝ、材木屋の二男は、さも感心したといふ風で言つた。
「あの太政官も、もうあけへんがな、中風で杖つかな、座敷も歩かれへん。」と、伊之助といふ中百姓の長男は、其の白く廣い額に、ラムプの光を受けて、眩しさうにしてゐた。”

と、最初に太政官の説明が出てくる。
整理すると、新田の茶瓶さんという人がこの村の太政官とも言える人物であるということ。もと村長とか議員とか、土地の有力者ということだろうが、この手の人物はだいたい物語では悪役だ。住民たちは彼らにへつらい、怖れたりしていたが、いつかその力関係が正されるような事件が起こる。これを知った時点で物語の「文法」と言ったらいいか、話の流れを予想してしまいますね。ところがこの『太政官』はそうはならない。まず、彼は有力者ではあるが、人々に名誉欲やエゴイスティックな強引さを示すような人物ではないようだ。むろん太政官もそれなりの欲望を持っている。でも、それは自分なりの物語を追求しているだけだろう。嫌味がないね。(この嫌味というのも僕らの気持ちを表現するキー・タームかもしれないね。

おっ、かっこいい言葉知ってんな。つまり太政官の「嫌味の無さ」がこの小説の良いところだ。というわけだな。これってみんなが感じることなのかなあ。つまり、例の間主観性だよ。どう?

確かに、彼の没落を願う青柳六蔵(青六、村長)が悪役を担っている。こいつの欲望と太政官の欲望とを読者は比較して感じてしまうよ。太政官の純粋さか、欲望のあどけなさとか、そういうところが彼を好意的にみてしまうところだな。
「食」米は磨いて磨いて……釜の中真ん中だけ

それが、一番現れているのが、食べ物への執着ですね。「味がわかる」というのは一種の才能なんだね。青六にはそういう才能はなさそうだもんなあ。

太政官の、その味の「才能」はどう書いてあるか、確認します。これは面白いところですよ。
酒が嫌ひで茶の好きな太政官は、奈良漬と羊羮とを絶(き)らしたことが殆んどなかつた。茶は玉露の薄雪といふのを宇治から取り寄せ、煙草は薩摩の國分を、大きな銀煙管に輕く填めて喫んでゐた。
飯のお菜には、奈良漬の外に、土佐の上節を細く灰のやうにかいて、尼ヶ崎の白醤油をタツプリかけたのが大好きであつた。それ以外滅多に魚鳥の肉や野菜やを求めようとはしなかつた。米は非常にやかましく、苗代に種子を下ろす時から自分に監督して、植ゑて作る田地まで、ちやんと決つてゐた。さうして穫れた米を足舂(つ)きにするのには、母家の方で下男が一人、かゝり切りにするほどであつた。「水車舂きの米と、焦げた飯は喰へん。」と、太政官は始終さう言つてゐた。二三升に足らぬ玄米を殆んど一日がゝりで下男が足舂きにしたのを、下女がまた殆んど一日がゝりで一粒撰りにした。舂いて舂いて、舂き拔くので、米は玉のやうに白くなつて、細く尖つてゐた。それをば、新らしい手拭を被つて赤い襷を掛けた下女が、鼻唄で調子を取りつゝ、黒光りのする母家の廣い縁側で、太い指頭に摘んでは選り分けてゐた。少し形の揃はぬ粒は皆な取り除けて、下(しも)のものゝ飯米に混ぜた。
岩山に生えた椚(くぬぎ)の三年枯れの堅薪で炊いた飯の、一番下と釜の底とが、移す時綺麗に離れるのでなければ、太政官は其の飯を口にしなかつた。一寸でも釜の底が焦げ附いてゐると、たとへ狐色ぐらゐになつたのでも、茶碗の中に盛られた飯を輕く嗅いだゝけで、あゝ今日の飯は焦げたなと、箸を投げて了つた。
「飯の皮が喰へるもんか。」と、太政官は常に言つてゐた。そんなに釜の底の方を氣にしてゐても、太政官は決して釜底に近い飯を口に入れなかつた。上の方を取り棄て、釜肌を殘して、西瓜の實を抉(ゑぐ)るやうに、眞ん中だけの飯を移し取つて、それだけを喰ふことにしてゐた。釜肌にくツ附いた飯を、飯の皮と呼んでゐた。皮を棄てた飯の實だけと、鰹節に白醤油——其の他に太政官の食慾は何物をも求めなかつた。ひよツとして、本場の上等鰹節のない時は、白醤油を皿に入れ、それを箸の尖端(さき)で舐めつゝ、可味(うま)さうに飯の實を味つてゐた。
「俺(おら)んとこの米は鮓米の上等よりまだ上等や、俺は其の上米さへ喰うてるとえゝんや。世間の奴は毎日々々、米を喰うてゐやがつて、ほんまに米の味を知つてゐくさらん。」
かう言つて、太政官は高らかに笑つてゐた。彼れは毎日々々米の味を噛みしめ噛みしめ味はつてゐたのである。
と書いてあるよ。
この執着のもとには、豊かさがある。そして、豪勢な食事とは違うことが大事で、ここに出てくるのはコメへのこだわりだ。これがもし、豪勢な食事、たとえば様々な食材の懐石料理や豪華なフルコースのフランス料理や中華料理などに対して太政官が執着しているとしたら、俗物として彼の魅力的な人物像は、全くなくなってしまうだろう。太政官の魅力的な人物創造に役立っている。
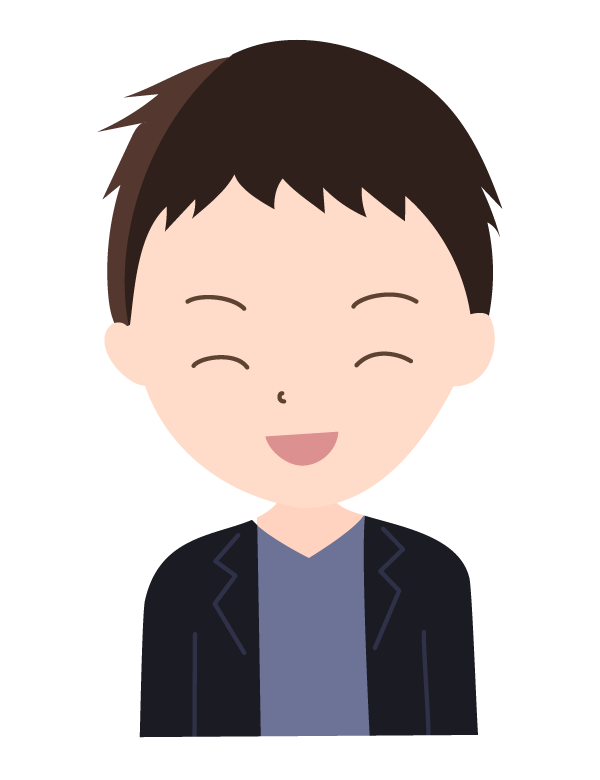
本当の贅沢とは何か。太政官は食に関しての贅沢を求めても、単なるグルメとかグルマンとかいうことではない、何かしらの単なる「食欲」とは違う感覚を読者に与える。つまり、太政官の欲望が単純なものではなく、もっと文化的な高まりを持っているような印象なんだ。さっきの太政官への好意的な読みも、読者がなんとなく太政官の欲望と一般的な貪欲との違いを感じたからなんだよ。他の作家の作品で、田んぼや畑からこだわる人物を描いたものがあるか?収穫した米も一粒ずつ選り分けていた、なんて。

またまた余計なことだけど、昔新潟の農家に婿養子に行った友人がいてね、そいつから自分の家で食べる米を少しもらったことがあるんだ。まあ、その米の美味かったこと!こっちで買う米とははっきりと違うことを知ったね。しかしたとえばその魚沼のコシヒカリ。このうまさの実感は言葉では伝えられない。食べたことのない人にはその味は実感としてわからない。経験があったとしても、同じもの、同じことをそれぞれ対応する言葉が指しているかはわからない。
神とか、善とか、伝えられないことがあるからこそ、それを小説として、物語として書く。周辺から攻める。そういうことがここでも行われている、ということかもしれないな。

教科書にもある、谷崎の『陰翳礼讃』を読んで感じるような感覚に似ていると思った。

太政官のおかずは「土佐の上節」に「尼ヶ崎の白醤油」をかけたもの。それ以外には求めなかったことは日本の家屋の闇の中、ほのかに浮かぶ輝きと同じような感覚を持つのを連想しますね。山海の珍味などは食べなかったと。ここも何品も出る豪華な食卓を連想させない。この差はどう作品の印象に影響しているか、考えてみるべきだと思います。むろんこの作品の方が、太政官への、読者の「好意度」は高いんだと思います。
話がずれてしまいますけど、たとえば、さっきの豪勢な食事と一見質素だがその実たいへんこだわった米だけの食事。その差を人間の価値として読者がどう感じるか、なんてAIは理解できるわけないわね。人間の受け取りの感情がどう違うかなんて説明ができるようになったら、もうシンギュラリティを超えたと言えるんじゃないですか、そこが「人間」なんだわ、と思いました。
今AIがすごい勢いで私たちを囲んできているんだけど、文章や音楽も作り出してくれるそうね。でも、一人一人の「印象」を理解する、ということは絶対にできないことなんじゃないかな、と思うんです。こうしたことも、これから私たちの話し合いの中にも取り入れていかないといけない観点ですよね。

小剣には『父の婚礼』という小説もある。今回事前に読んでみました。これも、ちょっと独特の雰囲気のある小説です。その中で主人公(少年)の父親が、平七という人物に壺のなかのものを食べてみろと言い、それがわかるか、と聞く場面があるです。父の友人平七は、
「分かった、海鼠腸(このわた)。……それ知らいで、可味(うま)いもん食いの看板掛けとかれまッかいな」
と言っている。「うまいもん食いの看板」というものがあるんだと思いました。さらにこの作品では、土筆の佃煮についても語っているけど、グルメ、食べ物へのこだわりは一つの才能というか、プライドになっていたんだな。美味いものを食べるということは、また美味いものを理解できるということは、「良きこと」なんだな。このことは面白いテーマだと思う。
そういえば、以前この授業でも読んだ、開高健。この人も食べることにこだわる人で、かつ関西人だった。
食べ物というのは、案外小説の大きなテーマだと思いました。

食べ物以外にも記憶に残ったことはあるかね。
女性への衝動 絵の中の清少納言

『太政官』では、もう一つ引っかかったエピソードがある。ちょっとエロティックな……という印象を持つものが時々示されるということだ。それはたとえば、太政官の家に掛けてある絵の軸だ。
床には住吉派の繪師の書いた見事な清少納言の大幅が、緞子の表裝に、牙軸(げじく)でゆツたりと掛かつてゐた。
「このげんさい(妻のこと)えゝやろ、俺のほんまの嬶(かか)はこれや。」と、太政官はよく客に自慢して見せた。
「何んぼえゝげんさいかて、おしろ(後)向きでは始まりまへんな。」
長い頭髮と、黄色の裝束と、燃え立つやうな緋の袴とを見せて、向ふむきに青い簾を掲げてゐる清少納言の、繪絹から拔け出しさうな姿を眺めて、涎の垂れるやうな口元をしつゝ客は笑つた。
「名義だけでも、俺には嬶があるさかいな、このげんさい、遠慮して向ふむいてよるんや。」
かう言つて、太政官も笑つた。彼れはこの「香爐峯の雪は簾を掲げて看る」の逸話を描いた清少納言の繪姿には、六十一になる今日が日まで、心底から打ち込んであるやうであつた。《……》
床の間の前を離れて、左手の窓のカーテンを撥ね退け、硝子戸も鎧戸も開けて見ると、外は朧の月夜であつた、眼の前には、自分が魂魄まで打ち込んだ小學校の眞白な建物が、眠つてゐるやうに聳えてゐる。鐵柵の中の老木の櫻は、疾くに花吹雪を作つて、若葉の間に實が結びかけてゐるけれど、花の匂ひはまだ、何處にか移り香(が)を留めてゐるやうである。村役場になつてゐる二階からは、あかあかと燈火が射して、階下の宿直室の障子に映る黄色の薄い灯は、何事かを囁やいでゐるやうでもあつた。
太政官の鯨の眼のやうな細い兩眼からは、ハラハラと老の涙が溢れた。
彼れはハタと室の戸を閉めて、ツカツカと床の間の上へあがると、清少納言の繪姿の頸筋のあたりを舌の尖端(さき)で輕く舐めてから、丸行燈の燈心を一筋にして、郡内の厚蒲團の上へ、埋まるやうになつて轉がつた。
実は『父の婚礼』にも、平七という父の友人が12歳の「自分」を招いた時のことが書いてあります。その平七の妻がユニークな女性で、少年に、
「坊んち来たな……さァ小母はんが裸体にして検査してやろ。」と言って追い回してくる。そのときに柿の木の下で熟柿が自分に降ってきて汚れてしまったのだが、平七の妻は、
「幼い自分をギューッと引き締めて、首筋から咽喉の辺りまで舐め回した上、更に頬までをペロペロとやった。」
と書いてあるんです。
今ならセクハラとも言えるような行動だが、とにかくこの女性は可愛い少年に対してこんな行動をするような人なんだ、ということ。
それと同じように太政官は、「長い頭髮と、黄色の裝束と、燃え立つやうな緋の袴とを見て、向ふむきに青い簾を掲げてゐる清少納言清少納言の後ろ姿の絵に「繪姿の頸筋のあたりを舌の尖端(さき)で輕く舐め」るという行為をするんだよ。両方とも何ともいえない嫌な描写ではあるが、我慢して読むと、結局太政官も、平七の家内も、どうしようもない欲望の発露をしているんだろうと思う。太政官について考えると、まさしく「目と舌の欲望」というものに対する抗しがたい感情を描いている作品だと思う。
美とは何かという以前の授業で話が出ていた問題について、美とは「味」と同じじゃないかな。美しいは旨いと同じ。そういうことではないのかな。だから、「可味(うま)いもん食いの看板」なんていう面白い自慢も成り立つんだ。絵の中の美人と美味いものは、美(味)として同等。だから、「舐める」という行動も同じ反応と言えるんじゃないの。
『父の婚礼』の大人の女の「可愛い」という行動も、「美しい」の一部なのかもしれない。とすると、この小説は「美への欲求に生きる人々を描いた物語」という話になるんじゃないか。太政官の場合、その上に建築物への執着ということもある。これも、「美」への欲求。「盆栽」など植物への執着も同じだと言える。

それと、この『太政官』では、太政官の「女への愛情の不可能性」も語られている。「太政官、あの年になって女子(おなご)知らんのやてなア。」なんて村のものに噂されたりしているし、「新田の茶瓶さん」とも呼ばれる太政官の三度の嫁取りの噂話など、若者たちにとっても興味津々の話だった。さらに、三度目の妻はうまく飯炊きさえできればそれで足りる、女中のようなものだった。名前だけの妻ということが出てくる。品のない会話だけど、太政官の倒錯した(と言ってはいけないかもしれないが)欲望が描かれている。
普通は自分の家を自慢するもんじゃないか?

彼の一番の欲望は彼の建てた学校じゃないか。学校こそが最終的に太政官がこだわった現実の「もの」だ。普通は自分の家を自慢に思うものじゃないか。それをどう読むことができる?
酒にも女にも遊びにも、爪の垢ほどの嗜好を有たぬ太政官は、二十七の年から村を一手に攫んで、それを何よりの仕事とし、楽しみとした。金を儲けることもよく知つてゐたが、金を握るよりは、村を攫む方に、手の力は籠つてゐた。
《……》
「太政官はえらいのやが、俺等と同なしで、字を知らん明盲やさかい、何にも役はせえへんのやなァ。」と、百姓が田圃で株伐りをしながら、高声でやってゐるやうに、彼れは一度も戶長や村長になってゐない。何かの都合で、學務委員といふものに、たった一度なったけれど、一月経たぬ中に罷めて了った。——一字も字を知らぬ務委員——彼れ自身にも可笑しくて耐らなかったのであらう。
村の世話方——といふ名を自身に命けて、彼れは村を自由にしてゐた。自分が明盲であるから、先づ立派な、郡第一の學校を建てて、眼の見える重宝なやつをどっさり拵えてやらう、彼れは思って、小学校の建築に半生の力を注ぎ、出来上がった其の白亜の建物に生命を打ち込んだ。
「俺の力でかいて貰うた、天満校の三字の、貴い筆跡の額になって掲ってゐる以上、どんなやつが出て来うと、この学校に指一本差させるもんか。差しもしようまい。」
かう太政官は信じ切ってゐた。

一番の欲望は「学校」だったんだ。自分が字の読み書きができないのでなのかもしれない。しかし、その一面で「学校」というものに強い執着を持っていた。建築の美に対して執着していた面もあったかもしれないが、自分の「隠居」と読んだ住居ではなく、学校に対して一番の愛情を感じていたことが気になるところ。
普通の金持ちなら、自分の住居に金を注ぎ込む人はいくらでもいるだろう。太政官も白壁の西洋館を「隠居」にして住んでいたが、彼の場合、自家についての執着よりもずっと小学校への愛情は深かった。小説の説明では、場所は「新田」と呼ばれるところで、つまり村の中心地ではなかった。彼の「隠居」は周辺に人家のない松林の中に作った。山の上から学校と隠居を同時に眺めると、白い母牛と子牛が眠っているかのように見えた。とある。
太政官は伝来の素封家ではなく、一代で植木で財を築き、村の中心地ではない周辺地に白亜の家と小学校を作った「成金」だったことが想像される。彼のクジラのように(!)細い目が人を意のままにさせた、とも書いてある。「クジラのように」ってのがいいね。本体は巨大で他を圧するような実力を持ち、人を細目でじっとみている。これ、ジブリの映画で見たことあるよ。自分の力でのし上がった自負心もあるんだろう。
そして、文盲であったこと。それだけの自負心がありながら、読み書きができなかった人物として設定してあるんだ。太政官の執着が、学校にあるということを何か妙に納得させるじゃないか。彼の心の中の深いルサンチマン。そんな感情もあったかと思う。
清少納言の軸についても、連想して思いつく。この絵は『香炉峰の雪』。僕のような男だって知っている説話だ。中宮からの質問に清少納言が機転をきかして答えたという『枕草子』で有名な話。その場面を描いた絵の中の清少納言に、倒錯した気持ちを持ってしまう。これは全く一貫した彼の欲望だね。
知的なものに衒学的欲求を持っていた人物というイメージを持ってしまうのは当然だと思うけどね。
自分にも、そういうところがあるからこの太政官という人物にはシンパシーを感じちゃうんだよ。(倒錯した欲望は自分にはないよ、本当に。変な目で見るなよ。)
*西洋風な学校って、たとえばこんなふう。参考資料として。長野県松本市に残る「旧開智学校」。これは、1872年(明治5年)に建築された。全くこの小説の小学校のイメージだな。


問題はどうも「人間の欲望」にあるらしい。太政官という人の欲望が食べ物に、異性に、また建築物にどのように向けられていたのかを整理して考えてみたらどうかということです。で、学校についてはどうして学校なのか、をみたらどうかな。

ここでみんなに読んでもらいたい評論がある。欲望についてはいろんな言説があるのだが、それらもうまくまとめて教えてくれる。
とにかくこの人の文章はわかりやすくて、納得させてくれるなあ、そう思ってね。
人の欲望ってどういうもの? 竹田青嗣の見方

単なる「欲」という言葉は、通常私たちがイメージするところでは「食べたい」「見たい」「聞きたい」という快楽追求でしかないのだが、そういう単純な思考に反省させる文章だ。特に大事なことは、「人間の欲望は幻想的なものだ」という一節だと思う。人間はほんとうの自分の快楽を満足させるためだけを欲望として目指すのではなく、存在以前に成立していた「ルール」に従ったゲームの参加者としての、幻想的な欲望に動かされるのだ、という主張だ。動物たちの欲望と絶対的な違いがそこにあるということだ。
最近、他者に「マウントをとる」っていう言葉を聞くけど、マウントを取ること自体は猿でも、何でも目指すものだが、人間は違う。東大に合格して学歴社会でマウントを取る、こんなことは幻想的な、ルールの上に乗っかっている人間だけの欲望の結果なんだ。
また、プラトンの『パイドロス』には、我々の心の中に二つのちからがあり、それは快楽への欲望と最善を目指す分別の心であるという。これは、また後で機会があったら、欲望に関する作品の時に紹介しよう。

こういう哲学的な説明が『太政官』とどう関わるのかが、問題ですね。
人間の欲望が実体ではなく、「幻想的なものである」ということ。太政官の欲望は食欲ではないんです。簡単に言えば、いわば動物にはない、高度なものであるということですか。それが究極的に進めば「超越」へ踏み出すような性格、つまり善とか、美とか、あるいは無欲への欲になる、ということね。でも、さっきの竹田先生の文章では、恋愛は美以上の一段と強い衝動的なものがあると言っています。静かな観照的な美への想いとは別の、例えば作品や対象の人間への接触を我慢できなくなったり、あるいは命がけの執着だったり……。
「美」を受け入れるにも、才能が要るんだ
竹田青嗣の欲望論 『「自分」を生きるための思想入門』 ちくま文庫
人間の欲望はゲームの欲望である
”《……》先ほど、詳しく述べたように、人間の欲望はゲームの欲望になぞらえられます。動物の欲望はいわば本能的にセットされていて、単純化して言うと、食べること、そしてセックスすること、そのためにいろいろな気遣いがあるということに尽きる。突き詰めるとそれだけです。
ところが人間の欲望は、ゲーム的な欲望であり、一定のルールの中で努力しながら勝利を得ることの喜びを最大の糧とします。ゲームに勝つまでのいろいろなプロセスも面白いし、また失敗する不安や脅えもつきまとっている。これらが人間が生きる生のエロスなのです。もちろん、食欲とか性的な快楽といった生理的な欲望も土台としてはありますが、いわばこの生理的快苦の上に、人間は幻想的な快苦(喜怒哀楽)を章積み重ねている。そしてこの幻想的な快苦の本質がゲーム的であり、これが人間にとっては最も重要なものなのです。
また生理的欲望であると考えられているセックスの欲望でさえも、人間のセックスと動物のセックスでは全然違ったものです。動物のセックスは衝動があって、それを埋めるだけです。これに対して、人間のセックスは、先に述べたように、「美」を味わう幻想と結びついています。人間のそういう性的欲望をわたしたちはエロティシズムと呼んでいます。
人間がいつでも発情できるのは、それが幻想的なものだからです。だから人間の欲望はいわば本能からずれている。本能とまったく切り離されているのではないけれど本能という杭に縛りつけられているのではなくて、いわば杭に長いヒモが結ばれていて、どこにも遊びに行けるといったものです。
欲望がゲーム的な欲望であり、「私」にかかわる幻想をその実質としていること、これは人間の欲望が実体的な形を持たないことを意味しています。つまり、人間は成長していくにしたがって、自分と他人の関係のルールとアイテムを少しずつ変えていきます。このルールとアイテムが変われば、欲望の形が変わります。この欲望の形の変容ということを支えているのが「関係」なのです。《……》
思春期以降になると、親や先生から褒められ、愛されることよりもっと重要な欲望が生じてきます。「ロマン的世界」が内面化されて、自我理想が形成されるのです。いわゆる青年期的なアイデンティティの確立を目指す時期です。これは単なるロマン化、つまり想像の世界で自分を理想化するのではなく、現実世界の中で他者一般から認められるような「価値」を身につけようとする欲望です。しかもそれは、将来社会の中でどういう人間になれるかという、現実的な自己実現の欲望につながるものです。単に、家族や先生や友達に褒められたいという欲望ではなく、この社会の中で立派な人間になりたいという欲望が、自己実現の欲望です。注意したいのは、この欲望は一面で「ロマン的世界」の内面化ですが、もう一面で空想的な「ロマン的世界」に生き続けることの挫折を契機にしているということです。
《……》
整理すると、人間の欲望の対象の「意味」(欲望の意味)はだいたい次のように区分できます。
1 自我の不安に対する「打ち消し」
明日どうなるかわからないという不安、またあいつは何者でもないと自我の価値が相対化されることへの不安を誰でも持っている。この自我の不安に対する打ち消しの欲望はとても基本的なものです。
2 自己のロマン化、あるいは自己拡大の欲望
自分をますます立派な人間だと思いたい欲望。名誉欲や権力欲はその典型です。これは可能性が導く場合は、世界全体を自分のものにしたいといった欲望にまで至ることがあります。
3 美的なもの、エロスやロマンを深く味わう欲望
基本的な衣食住の要求が満たされると人間は余剰の消費力を、「美的なもの」、エロスやロマンの消費に充てます。これは生活欲望の必然です。これについては後で言います。
4 超越的なものに対する欲望
これは、生活欲望とは異質な欲望であり、いわば日常生活の内側ではなく、そこからはみ出したい、日常を一瞬超え出てしまいたいという欲望です。恋愛の欲望やある種の(世俗的ではない)宗教的な欲望がこれに当たります。
こう考えると、人間の欲望を大きく見ると、二つの傾向に大別することができると思います。一つは自我の不安を打ち消そうという欲望です。そしてもう一つは、むしろこれを乗り越えようとする欲望です。
人間の自我はつねに不安を抱えています。自我の不安とはアイデンティティの不安と死の不安です。だから不安の根源は他者と死なのです。自己の保存及び自己拡大の欲望は、この不安の打ち消しだと考えることができます。
これに対して、美的なもの、エロスやロマンを味わおうとする欲望は、自己の維持や拡大に直接は繋がらないものです。バタイユという思想家の言葉で言うと、この味わいは、エロスの「蕩尽」ということになります。これはあえて言うと、むしろ自分というもの、自我という枠組みを、解き放ってしまうような「自己解発」の欲望だと考えていいと思います。
たとえば仕事をすることは自己の維持や拡大に繋がりますが、仕事を終わって一息ついてビールを飲むというのは、いわば緊張させていた自己のタガをはずして自分をゆるめることですね。家でテレビを見て楽しむのもそうです。こういう「味わい」の欲望、エロスを蕩尽する欲望は、「自己解発」の欲望だと言えます。
美やエロスを味わう欲望は日常的なものです。しかし、超越的なものへの欲望もこの「自己解発」の欲望だと言えます。宗教の欲望には、死や生活不安を打ち消したいという世俗的なものもありますが、どこかで自分がもっと自分より大きな聖なるものと同一化してしまいたい、自分という枠組みを解き放ってしまいたいという超越的な欲望も潜んでいる。
恋愛の欲望も同じです。恋愛は自分のアイデンティティにとって大きな意味を持っている。しかし、それにもかかわらず、激しい恋愛には、プラトンが言うような「地上のことはどうなってもいい」といった欲望、日常の、自分というものを超え出てしまいたいという欲望が潜んでいるのです。ところで、恋愛の場合には、人は恋人との語らいや恋人の美しさを愉しみます。しかし恋愛の欲望は、ビールや映画を味わう欲望とは少し違った点がある。ビールや映画を味わうのはあくまで日常の枠組みの中にありますが、そのことのために日常の気遣いを忘れてしまうことは普通はありません。ところが、恋愛の欲望の中には、この恋さえつかむことができれば、世界はどうなってもいいという性格が潜んでいます。実際は恋愛をするとすべての人がそうなると言うのではなくて、恋愛の欲望の核にはそういう日常を超え出るような性格〟が必ず潜んでいるということです。
つまりわたしの言いたいことは、日常の愉しみは美やロマンを消費する愉しみですが、同じ美やロマンを味わう欲望でも、恋愛の場合は日常という境界線を超え出て「超越」へ踏み出すような性格を持つということです。人間の欲望は煎じ詰めると、自我を維持保存し、拡大しようとする欲望と、逆に自我の枠を解き放って自我に掛かっている緊張を解き放ちたいという欲望の二つに分かれる。後者の欲望はまた追い詰めると、「超越」への欲望に近づいていくと言えます。
『「自分」を生きるための思想入門』 ちくま文庫 より p83から
人間はこの基本的な二つの欲望を、日常生活の中で必ずバランスを取って生きている。一つだけに重心をかけるとバランスをくずして日常生活は成り立たなくなります。気遣いだけで生きていることはできないし、「味わう」欲望だけで生きることもできない。それが人間が生きていく上での基本的な条件なのです。”

僕は少し、そういう感覚について、わかるような……。いやそんな目で見ないでほしいが……。でも音楽にある僕の心をおかしくするものって、正直あるよ。
それで、別に自慢するわけじゃなくて、それは「才能」なんだよ。太政官にはそれがあるんだ。

まず彼は事業として植物の生育に成功する。彼の美的なセンスが世間に認められることになる。そして、どうも性的な面での問題点からか、妻を持つことが通常のようにはできない、三度目の妻は全く生活の世話だけをしてもらっているような存在である。酒は書かれていないと思うけど、特に特徴的なのは独特の美味しさへの執着で、ここに大きな人物的な面白みがあるわけよ。そして、実際の女性ではない絵画の女性像に対する執着。その絵を愛する倒錯的な執着は、絵の姿の首筋をちょっと舐めてしまうことで表される。
あえて言うけど、こういうのは誰にでもできることじゃなんだ。奇行と呼ばれるものの多くがそうだけど、芸術的理解力のゆえなんだよ。「持ってる」から、こうなるんだよ。

それは賛成!
ちょっとおかしいくらいの奴がすごい奴なんだな。
(先生、ちょっと注意して。また校長に呼ばれちゃうよ。)
あっ、そうだった。今のナシね。

最後に建築への執着も同じことだろう。自分が文盲だということで学校への執着を刺激されたとも解釈できるが、しかし彼の思いは学校という「建築物」にあった。彼の執着は倒錯したものも含めて、全て「美」だったと言えるだろう。
「美」とは物語だよ。つまり、この人は「美の物語」に取り憑かれた男で、その様々な発露が描かれていたわけだ。その点は竹田青嗣の文章でよく了解できる。動物的な欲望とは違う、「幻想的な欲望」である美へのエロスというものなんだ。
本当の異性への恋がなされない、あるいはなすことができない太政官の欲望が、もしかしたら彼の美の追求というものを倒錯させていく原因だったのかもしれない。これがフェティシズムというものじゃないの?これは青木の言うように「才能」かもしれねえな。
しかし放縦な太政官の欲望の発露も、結局幸せな結論には至らない。彼の美追求の象徴とも言える、小学校は壊された。
自分の生命よりも大切な愛し子が、松川疱瘡にかかって、玉のやうであった顔が、二目とは見られぬ醜さになった時の悲哀は、かうでもあらうかと、太政官は縁側にたちつくしつつ、白亜姿のスラリ高く清げであった小学校が、たとへば、白瓜か南瓜になったやうに、背低の厭なものになって、杉の焼き板で一面に背中を張られたのが、かさぶたみたいだと思った。
と太政官は自分の美を否定されて、生の意味を失った。
おれはこの講座でやった、三島由紀夫の『美神」を連想しちゃったよ。
認められなかった才能の悲しさ

いやそれよりも、自分の生の意味を失って破滅するということで、カフカの『流刑地にて』だろうよ。その中では、見方によっては極めて非近代的な処刑、それを自動的に行う機械。アンバランスな新しい処刑に対しての意味を与えること。これって、わかる人しかわからないもの、ことに価値(意味)を与えるということは、全く同じ構造じゃないか。

しかし、それが認めてもらえないということは、その人にとっては「生の意味の喪失の物語」ということになる。近代小説の王道なんじゃないか。
これ、『清兵衛と瓢箪』型の物語と呼んだらどうかな。ただし志賀直哉は、古代的な精神の強さ、などということも言われていた。清兵衛は、瓢箪から新たなものに転身し、雄々しく立ち向かう。さすが志賀直哉だと思わせるね。清兵衛は新たな夢中になれるものに向かっていく。頑固な父親にも、いずれ打ち勝っていくだろう。
だって、瓢箪にしろ、次の興味の絵を描くことにしろ、いずれも「美」に関する欲求であり、事実清兵衛の瓢箪は非常に高い値段で好事家に引きとられるわけで、彼の「美」に対する眼力は確かなものと設定されているんだから。やっぱり、美しいものを直感で理解できる人間が羨ましいよ、なあ圭!

そうだね。美を求めて君は授業中にもスマホ見てるんだろう?偉いよ。




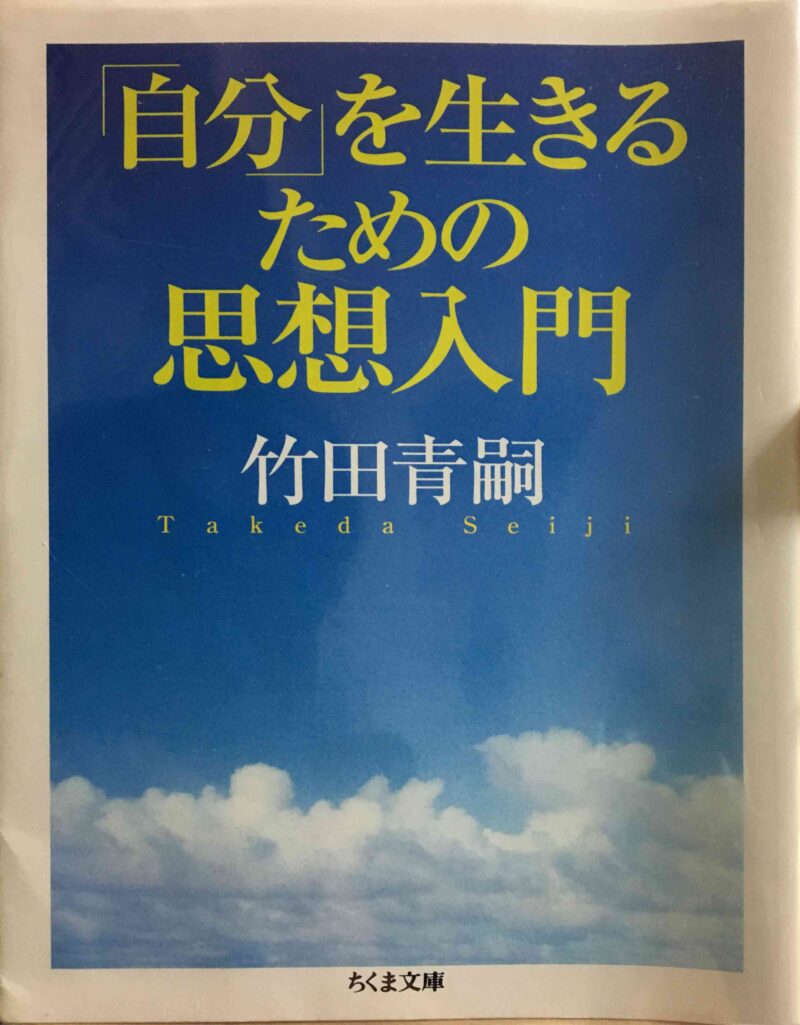



コメント