
『遠い山なみの光』
「遠い山なみ」を眺める心境では読めないね

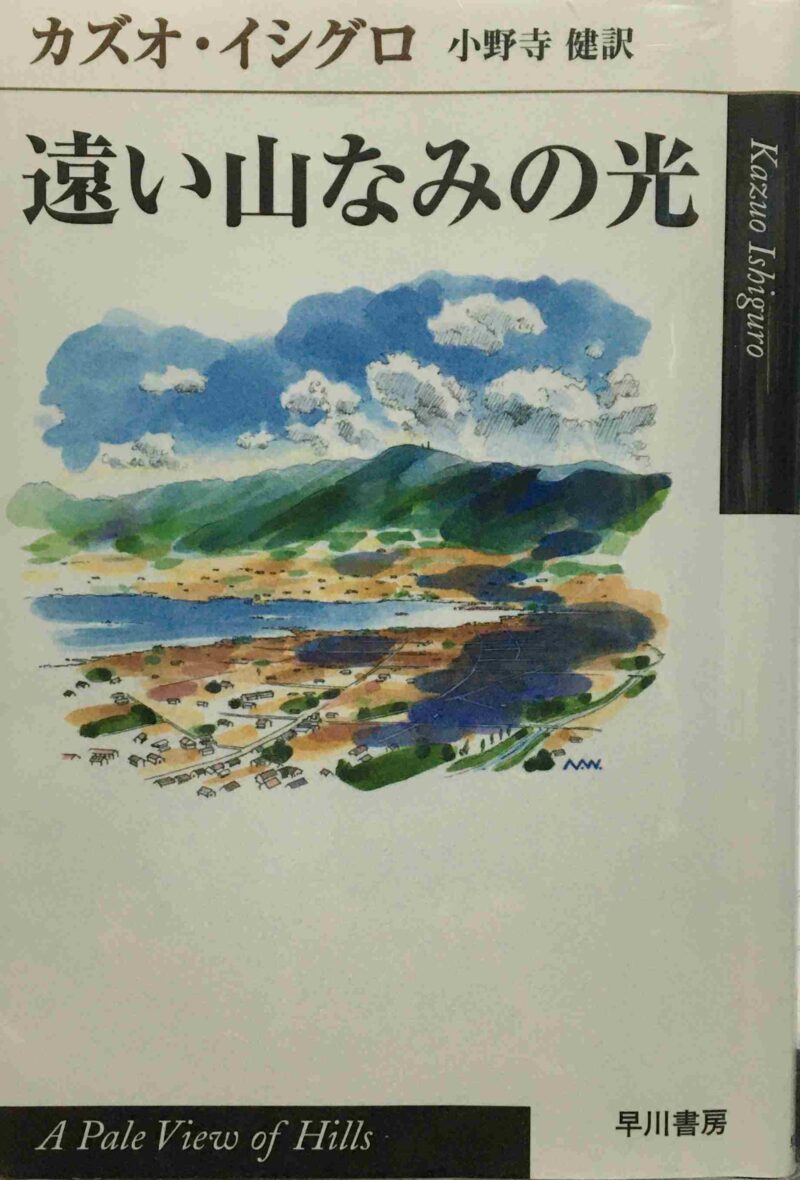
前回に続いて、イシグロの作品を読んでいくけど、今回は『遠い山なみの光』です。これは『浮世の画家』よりも前に発表された作品で、日本を舞台とした長編。二作を比べてみると面白いと思うんだ。
これもあらすじはネットで得られるから、何か確認したい人は授業中でも調べていいよ。
ただ、これはあらすじというものの作り方が難しいと思うよ。私はネットで調べてないけど、小説の進行通りのあらすじだと、何が何だかわからなくなっちゃうんじゃないかな。
まあ、それでも、単純な感想でもいいから、誰ぞ発言してみ。

これは、難しかったなあ。僕たちは小説を読んで、「これは~についての物語だ」、というのに、自分なりにひとつの結論を出す、ということを目標に置いて考えているんだけど。これはどういう物語だと考えられるのかなあ。さっぱりわからん。
たとえば、「古い考えに囚われている日本に縛られている、日本の女性の物語」というんじゃちょっと違うと思うし、また「詩学」的な観点というんですか?そういう見方もちょっと思いつかないし。いつだったか、外国の小説で中南米のわけのわからない話とも違う。

話の筋としての構造を図式化することはできそうだけど。つまり、英国と日本という地理的軸と太平洋戦争から朝鮮戦争の頃と現代という時間的な軸。語り手の①わたしと、②景子。③佐知子と④万里子。それに佐知子の恋人⑤フランク。さらに⑥緒方さんと⑦二郎。私の夫⑧シュリンガム。シュリンガムとわたしの間に生まれた⑨ニキ。
もっと拾えばいるけども、こんなところが登場人物。この中では名前しか出てこない人もいる。でも⑤フランクや⑧シュリンガムなどは、明らかに登場人物に強い影響をあたえてる。
人間関係だけ見れば、①と②の親子関係は③と④の親子関係と同等だし、①と②、⑦と⑧の関係は日本人の妻と日本人の夫との間にできた娘、その日本人の夫。そして別れた後で外国で結婚した相手。ということになり。この図式は③と④、⑦に二郎に相当する人物は出てこないが当然かつてはいたはずの佐知子の夫、そして⑤と同じ図式と見ていいですよね。そうすると、佐知子の二番目の娘、フランクとの間にできるはずの娘は、⑨のニキに相当する。こんな人は全く書いていないけどねー。
この佐知子を取り巻く人々とわたし、悦子を取り巻く人々が相似関係にあるとすれば、それは何を暗示するか。というより読者たちは何を感じ取るか?
……僕は、景子の自殺に対応して、まず万里子の自殺ではないかと思います。あんまり飛躍した読み方ですか?

いやそういうふうに読めると私も思うけど、私はもっと飛躍しちゃって、姉と妹という順番は違うけど、私はあの子猫たちが景子に相応するような気がしたんだけど。あの猫ちゃんたちは絶対にこの人間関係の中に、どんな形かはわからないけど、入れるべき存在じゃないかと思う。
ただの汚い子猫じゃないか、って佐知子はいう。おぞましいけど……。その意味するところを当然読者は感じるわよ。
そして、悦子は二郎を裏切って英国へ飛び、娘を殺してしまった。つまり、二人の母親の娘殺しの物語じゃないかと……。しかも、たぶんその原因は母親の欲望のため……。

ひえ〰︎。ちょっと竿頭ちゃん、なんとかコンプレックスみたいな心理学に影響されすぎなんじゃない?
それ、面白いけど、緒方さんを忘れてるよ。緒方さんの存在は何を言ってるの?緒方さんはただの添え物としての存在なの?あたしはそうとも思えないんだけど。だからと言って整理がつかないんだけど。
緒方さんは、次作の小野だね

そうなんだ。緒方さんね、つまり、『浮世の画°家』の小野だね。時間的にはこちらが前の作品だから、小野は緒方さんの再登場ってことになる。でも、ちょっと違うところがあるけど。過去へのこだわり方かな、違うのは……。

そうそう。
男が二人、西洋人で、それが子連れの女を連れて帰り、さっきの読み方に従えば結果的にその子供を殺してしまう?東西の文化対立みたいなことも読み取れるかも。
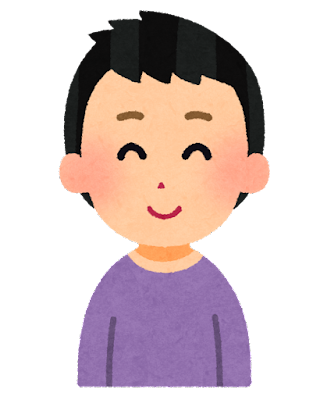
でもまず緒方さんだよ。
登場人物って、多かれ少なかれ作中で対立と協調(と言っていいのかな)が描かれると思うんだけど、緒方さんは誰と対立的なのか?二郎か、あるいは松田重夫か?どちらにしても、この人の怒りとか不満が、ちょっと作品を焦点化させないという点で、崩してしまったという感じがするな。緒方の不愉快さと佐知子たちの問題と、どう関わっていると言うんだろう?印象の分裂っていうか。この男たちの方面の物語は、当然次の作の『浮世の画家』のテーマと関わっていくんだろうけど、悦子たちの物語とは関係なくね?過去の自分との折り合いという問題は、むしろ『浮世の画家』の問題だわ。

難しいな。でも今僕はちょっと思いついたんだけど、女たちとの共通した問題として考えることもできる。

さっき、この作品をどういう物語として提示できるか、これが難しいという話が出ていたけど、この緒方も含めてみると思いつくよ。
それは、「長崎からの、あるいは日本からの、脱出」というテーマだ。佐知子は日本から脱出したい。悦子も同じだった。悦子は二郎を捨てたが、彼女は二郎を完全に否定したわけではなさそうだ。緒方は(これも理由ははっきり書いていないように思うが)、福岡に去っていった。
これは「脱出の願望の物語」じゃないのか。それに、二人の母親は、娘を殺したが(もちろん佐和子ははっきりそう断言できないが)、緒方は息子を殺す、というとちょっとはずれていそうだが、緒方は二郎と訣別する、と考えれば緒方は二郎を殺したと言えるんじゃないか。

ほう。脱出か。脱出の物語なのか。緒方は精神的には、松田や息子の二郎たちの世界から脱出したかったのか。それで福岡に帰るのか。なんで福岡に居を移したのか、ということにも、少し変な気持ちがしたもんな。戦争のゆえだろうが、松田重夫が会話の最後に、
「じつを言いますとね、ぼくはあなたのお仕事のある面についても知っているんです。たとえば西坂の教師が五人、馘になって投獄されたでしょう。一九三八年の四月でしたかね。
しかしその人たちも今では釈放されました。その人たちがぼくらに新しい夜明けを教えてくれるんです。」
と、意味深なことを言っている。たぶん緒方さんは当局の捜査に協力したんだろう。緒方さんはそのことに何の反応も示していない。というより、反論もできないということだろう。彼が福岡に転居したことと関係があるのではないかな。なるほど……。
でもさ、こういうところをサラッと挿入させて、それっきりなんだよなあ。みんなはどう思う?

なるほど、私は、その一節、気にはなっていたけど、忘れていました。そう想像してもおかしくない感じがします。
ただ、緒方さんは教師としてその時その時に、自分では恥じることのない行動を選択していたのかもしれませんね。この人の松田に対する自信を持った態度からは、そんなことも想像できます。
そんな緒方さんも、脱出しなければならない人間だったんだ、というわけですかね。
そして、こう読んでくると、画家の小野と教師の緒方、どちらも戦中まで所属する集団をリードしていった立場の人間。本人としてはほとんど悪意なく行動し、敗戦後には思いがけなく(?)責められてしまう。どうもこういう巡り合わせに作者はこだわっているようです。『日の名残り』にもそんなところがあるんじゃないですか?私たちだって、「それ、そんなつもりじゃなかったのよっ!」ってことありますよね。先生なんかそんなことばっかりでしょう?」

いや、ほんとにそうなんだよ。まったく……。お前よく分かってんねー。「授業で、生徒にこんなこと言ったでしょう」、なんてよく校長、教頭に呼び出されたけど、生徒が言いつけんだよね。まあ、それでも、それこそよく馘にならなかったよ。しかし、どうせ馘になるなら、この小説の中の教師のように、自分の主義を通すような人間であらねばならなかったな。俺もつい、すぐ謝っちゃうからな。
さて、冗談はともかく、その他で、発言しておきたいことがある人はいない?
長崎?いやそうじゃない?
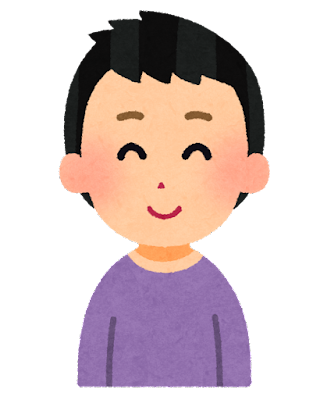
ここで読んだ二作を比較して、その差を考えてみることは面白いんじゃないかな。たとえば長崎という地名を明記している『遠い山なみの光』と、わざと書いていないと思われる『浮世の画家』その違いを読者はどう受け取るか。
住居も対比的だね。佐知子たちの家はジメジメした湿地なのに対して、小野の買った家は丘の上だし、その佐知子と娘が遊びにいったのは、僕たちも修学旅行で行った夜景で有名な長崎、稲佐山だ。佐知子の滑稽なくらいのプライドもその高みへの願望を示している。
この登場するものの差異こそが意味を作ってくるんだと学びました。

ちょっと地元の図書館で本を借りてきました。そこに書いてあった文章をみんなに見てもらいます。
実はイシグロについては英国では、当初「ジャパニーズネス」という面で取り上げられていたという。つまり「日本人」という「特殊な」観点から盛んに語られていたようです。小説が特殊な色眼鏡をかけて読まれていた、ということにイシグロは不満を持っていたらしいのです。『浮世〜』では、「長崎」という地を敢えて示したくなかったというような発言をしていたようです。そんなこことを頭に入れてこれを読むべきかもしれません。
『カズオ・イシグロの長崎』 平井杏子 長崎文献社
94ページ
ほんとうに書きたかったこととは
しかし、ひとつだけ、私たちが忘れてはならないことがある。イシグロはこの長編第一作を、望郷の念にかられて書いたのでもなければ、被爆地である長崎に何がしかのプロパガンダを込める意思まったくなかったということである。
当初は「一九七〇年代のイギリス西部」(『中央公論』 1990.3) を舞台にして書き始めたもののうまくいかず、すぐに戦後間もない長崎を舞台にすることを思いついたのだとさえいっている。 たしかに、 被爆者である母親から伝え聞いた原爆の話は、幼い頃からイシグロの胸に強く刻まれていたし、 子ども時代の長崎の記憶を書き留めておきたいという思いも、しだいに確固たるものになったには違いないが、 小説構想の段階では、長崎はまだ副次的なものだったのだ。
では、〈記憶の変容〉 という、イシグロ文学の底流を流れ続ける主題のほかに書きたかったこととは何だろうか。「私はその頃、1970年代、80年代にイギリスで育った若者として、ある問題意識、 テーマをもっていて、それを表現するのに最も適していると思われる舞台を選んだのです」(『中央公論』 1990.3) とイシグロはいい、さらにまた、終戦からわずか9年後に生まれたという境遇を顧みて、「自分が戦争という過酷な年月を切り抜けなければならなかったらどうしていただろう、その困難にどう対処していただろう」 (「早稲田文学」 2015.秋)ということを考え続けていたものの、「最初の二作では、日本の戦争責任という問題も出てきてはいますが、 僕が関心があるのはそのことじゃないんです」(『Switch』 1991.1)とも語っている。それはいったいどういうことなのか。
イシグロは、学生時代に社会の価値観が大きく変動するさまを眺めながら、「僕は他の世代がどう生きてきたかを振り返ることで僕自身への警告にしたかったんです。歴史がどう動いたかを見据えて、どういう人達が時代の変化によく適応したかを見たかった。そうやって僕自身を戒めていきたかった」 (『Switch』1991.1)というのだ。つまり、これまでグレゴリー・メイスンほか数多くのインタビューに答えていったように、何がじっさいに起こったのかということより、人間の「感情の激しい変化」 (Conversations with Kazuo Ishiguro, 2008) そのものを描くことが目的であったというのだ。
ということは、『遠い山なみの光』 のエツコの心の嵐を描いたのと同様、サブプロットであったオガタの生き方をもっと追及したかったのである。 教育者として生きてきたオガタは、戦後、共産主 義思想に染まった教え子から厳しい目を向けられ、 胸中に苦悩を抱えながらも、時代の流れにうまく対応しきれずにいる人物なのである。
しかしイシグロの内で、小説を書き進めるうちに、しだいに記憶の長崎が大きく膨らみ、そのオガタさんをどうやら片隅に追いやってしまったらしい。
96ページ
主題はイシグロ自身の生き方
『浮世の画家』は、『遠い山なみの光』のサブ・プロットであったセイジ・オガタの物語を、オガタと境遇の似たマスジ・オノのひとり語りで書き綴った物語である。イシグロは、「本当は、この部分は私にとって非常に重要な部分でした。しかしどういう訳か、他の部分が書き進むにしたがってふくれ上がってしまいました。そして重要と思っていた〈緒方さんストーリー〉が、サブ・プロットになって隠れてしまったのです」(『イギリス人の日本観』1990)と語り、このふたつの小説のあいだには、「主題の鍛錬という要素」 (Conversationswith Kazuo Ishiguro, 2008) があったといっている。
イシグロにとっての「重要な部分」とは、『遠い山なみの光』の章でもあげた、「私はその頃、1970年代、80年代にイギリスで育った 若者として、ある問題意識、 テーマをもっていて」 (『中央公論』1990.3) という発言とかかわっており、 それから四半世紀を経た後の講演でも、それが 「20代の作家にしかない独特の何か」(NHK、2015.7.17) であったとふり返っている
イシグロが5歳で英国に移り住んだ翌年の1961年から始まったベトナム戦争は、イシグロが高校を卒業した1973年の米軍撤退、 75年のサイゴン陥落で終結を迎えた。 卒業後にイシグロが一時期 身を置いたアメリカ西岸を中心にしたヒッピー運動もしだいに衰退 に向かう時期であり、みずからを〈遅れてきた世代〉と称するイシグ ロには、何かをやり遂げたという充足感はなかったのかもしれない。 高校時代に、学生運動に身を投じていく仲間の危うさを目にする一方で、何もしないでいることの危機を感じてもいたという。
98ページ
ここは長崎ではない、とイシグロ
『浮世の画家』の舞台はどこかとグレゴリー・メイソンに問われた とき、イシグロは即座に 「想像上の都市です」 (Conversations with Kazuo Ishiguro, 2008) と答えた。 自分が知っている唯一 の都市である長崎をふたたび描けば、西欧の読者はすぐに原爆 と結びつけるだろうから、 原爆が主題ではないことを、改めて明確 にしたかったのだというのだ。 『遠い山なみの光』 出版の翌年、 1983年に 『グランタ』 誌に発表した短編 「戦争のすんだ夏」で、戦争の被害が残る鹿児島を舞台に選んだことからも、 『遠い山なみの光』で批評家の関心が原爆に集中したことへのイシグロの苛立ちがうかがえる。
「戦争のすんだ夏」 は、『浮世の画家」の原型ともいえる小品である。 かつて画家であった祖父の家に身を寄せている7歳の戦災 孤児、イチロウ少年が、 戦時中に祖父が戦意発揚のために描い た絵をひそかに覗き見る話である。 軍旗を背景に剣を掲げた侍が 描かれた絵は、暗褐色の背景が血の色のように見えて気持ちが 悪くなり、イチロウは「がっかりした」という。『浮世の画家』は老年 となったオノ自身の語りによって過去が描かれるが、「戦争のすんだ夏」では、イチロウ少年という幼い子どもの視点から眺めた祖父の姿が描かれている。イチロウ少年は『浮世の画家」で、オノの孫であるイチロウに姿を変えてふたたび登場するが、そこには子ども時代のイシグロと祖父の姿が、生き生きと描写されている。蓋をしたはずの長崎の記憶が、物語の表面にふと顔を出しているのだ。
それにまた、『浮世の画家』の町から、原爆のイメージが完全に払拭されているかといえば、必ずしもそうではないようだ。爆風によって煽られ。大きく波打ち、床板がひび割れて、雨の降る日にはひどい雨漏りがしたという話を思い出さずにはいられない。
また『浮世の画家』全編に漂っている、〈煙〉と〈ものの焦げるにおい〉は、焼夷弾に焼かれたオノの妻や、爆撃によって壊滅したこの町の記憶であり、終戦から3年後の今も、いつ終わるとも知れぬ復興作業のさなかに、あちらこちらの瓦礫の山から立ち上がる煙のにおいでもある。空に立ち上る煙のにおいでもある。空に立ち上る煙を〈ためらい橋〉に立って眺めるオノの胸にそれは、「打ち捨てられた人を火葬する弔いの煙」に思えるのだが、その姿に、被災地長崎への、イシグロの祈りの姿を重ねることは、牽強付会に過ぎるだろうか。
ここに書いてあることが唯一の正解だという読み方は、避けなければならないことですが、それでも、ちょっと参考になりますね。特に、気になるのは小野の妻が原爆ではなく、おまけのような(?)焼夷弾によって亡くなったということです。これはむしろ、「原爆」というものを隠す意図を感じてしまいます。世阿弥の言ったとおりです(これ、前回でも指摘されてました)。隠すことによって、かえって意識されてしまうわけですね。
これ、イギリスが戦勝国であって、原爆に対する一般の人々の意識を忖度しているのかもしれません。そういう意味で、政治的なものを感じてしまうんです、私……。
この文章を簡単に言えば、小説に、「ジャパニーズネス」を、あるいは「原爆」という極限的な現実の厄災を含ませたくなかった、ということでしょうね。そういう小説ではないんだ、という作者のメッセージを読み取ってしまいますね。
開いてる?閉じてる?


二知の作ってくれたプリントは、そうとう君たちに影響を与える内容かもしれないね。ただし、特に作者がいろんな種明かしをしているようなところがあるけど、こういうところは注意したほうがいいね。作者が作品をどう読者に読んで欲しいか、ということはあると思うよ。でも、ぼくらはそれに従わなければならないルールはない。たとえば、『説き語り記号論』という本の中で、篠田浩一郎という学者が説明している章がある。これは1980年当時、一般の人々への講演会で話されたものだ。
――構造分析的な読解(レクチュール)というのは、せんじつめると文章のなかに含まれている対立的な関係を読み取っていくということになりますが、《……》
という言葉から始めて
建築とか絵画とか村落構造を扱うときには相手のかくしていることばをひき出してくるわけですが、文学はことばを露呈させていますからね、いわば化粧しあげた女性の素顔を逆に見抜くような操作が必要なわけでして、……これに対して、いわゆる従来の「解釈」は化粧したものを化粧したものとして扱い、結局化粧の仕方からその意味とか内容とかを取りだしていこうとするとするものでして、素材としての言語記号の存在の在り方のほうから問題にしていこうという記号学の方法とは逆の生き方なわけです。
〈朝日カルチャーセンター講座〉
と言っている。つまり、文学はことばが露呈しているから、そのことばを記号として見直して考える、ということだろうね。
そこでちょっとみんなに一つ聞いてみたい。
第十章の最後、佐知子母子の記述の最後のところだ。万里子を探しに出て、悦子は万里子が走っていくのを見る。その時空中に月を見る。
「川の上に、半月が出ていた。わたしは何分か橋の上に行んだまま、ひっそりとその月を見つめていた。」
これで佐知子母子と悦子の交流の記述は終わる。なぜ、半月がそこに出ているのか?なぜ半月なのか?
どう?

その本の中の、「素材としての言語記号の存在の在り方」ということばの一例として問われているわけですね。この記述によって読者はどう誘導されるのか、ということですね。「半月」じゃなくて、「三日月」でも「満月」でも、ただ「月」でも構わないわけですもんね。
……さあわからんなあ。もし月ではないとどうか、と考えてみると、万里子が外にいるのは夜だから太陽ではおかしい。月であるのは良いとして、満月ではなくて半月ねえ?何にも意味はない、という可能性はないの?

もちろんある。でもさっきの「素材として」、「月」を出しているのはなぜか、と疑ってみることが大事なことだ、ということ。なんか意味をでっちあげでもいいから考えられないか、ということよ。思考の練習をさせたいのよ。

半月はこれから満月になる途中であるということを意味する。満月とはどういう状況か、ということが問題だけど、考えられることは佐知子母子の米国移住が現実になること。あるいは佐知子が裏切られて何かしらの悲劇的状況で終わること。あるいは、佐知子母子ではなく悦子の英国移住という結果になること。そんなことを「半月」という記述で寓意させている、寓意させられている、と考えられるんじゃないか。
もちろんその後の悦子の辿る話に従うならば、満月は悦子の英国移住。そして娘の自殺をも示している、と考えることができるような……。
それにしても、こんなことを考えるにしてはあまりに飛躍した想像が必要じゃないかと、ちょっと本当に……?と思っちゃうなあ。

そうだよな。話を誘っている私だって、そう思うよ。それでも、この小説はあまりにいろんなことが中途半端なままで、読者に提示されていると思わないかい?それに応じて読者もなにかしら結論を持ちたいと思うじゃんか。
ブランコじゃダメなんだ


それです、それ!
ぼくの場合、一番の引っ掛かりは、ブランコの女の子の夢、なんですよ。文庫本ではまずp64で女の子がブランコに乗っている夢を何度も見た、と言っている。公園で見た女の子の夢だと思っていた。
p76では、公園の女の子の夢を見ることを悦子はニキにいう。夢が単純なものではなく佐知子に関係するものであることを、密かに感じている。
次は飛んで、p135。悦子はある朝、庭仕事をしてから、ニキと話をする。その時母は娘に言うところ。
わたしは持っていた剪定鋏を置くと、彼女のほうを向いた。「おかしいのよ、今朝、またあの夢を見たの」
「きのう話したでしょう。あなたは聞いてなかったみたいだけど。またあの小さい女の子の夢を見たの」
「どの女の子?」
「このあいだブランコにのってた子よ。村でコーヒーを飲んでいたとき」
ニキは肩をすくめた。「ああ、あの子」彼女はこう言っただけで、顔も上げなかった。
そして、このあと悦子は語り手としてこう締めくくる。
「じつは、今朝別なことに気がついたの。あの夢について、ちょっと別なことに」
娘は聞いていないらしい。
「じつはね、その女の子はブランコになんかのってないの。初めは乗ってるみたいな気がしたんだけど。でも、のってるのはブランコじゃないの」
ニキは何かつぶやいたきりで、新聞を読みつづけていた。
これで、第一部が終わるんだ。
ここに、こだわっちゃったんだ。ブランコに乗ってる、乗ってない。この女の子って何?

……みんな思いつかないよな。
そこで、さっき大隈くんから「脱出の物語」なんて聞いて、何となく「ブランコって行ったり来たりだよなあ」なんて思ったんです。脱出ってブランコじゃないよなあって……。脱出する女にブランコは似合わないなあ、なんてね。
悦子は思ったんじゃないですか、自分も、佐知子も、万里子も。ブランコには乗らない。ついでに緒方さんも。景子は、たぶん万里子も、本当に戻れない世界に脱出してしまった。だからブランコじゃいけないんだと。何だか、あまりにトンチンカンだけど。

ブランコは先に進んでも帰ってくる、ということなんだね。だから女の子はブランコに乗ってるんじゃない、と思うんだね。
……なんか、なるほどとも思うけど、ちょっともう一度精密に読まなきゃ、と思うね。
考えさせる小説だねえ。

そう思う。イシグロの小説って、すごく話の筋が興味深くって、面白いことは面白いけど、読む人への情報が、あまりに中途半端であり、やりっぱなしのような印象です、僕の読みの力が足りないのももちろんあるでしょうけど、もう少しきまりをつけて、読者を納得させてってよ、という感じなんですねえ。
このイシグロって、通俗的(というと語弊があるけど)な物語読者を誘導しながら、詩学的テクニックにも凝る、という特性がある、そんな気がする。これは作者の基本的な姿勢じゃないかとも思います。「信用できない語り手」という手法だって、この人の大事な手法なんでしょ。つまり、この手法って、作者は死なない、ということじゃない?作者の意向は作品発表後にも残っているということ。それともこれは死者の遺言の内容だというの?
バルトとエーコ

いや、バルトの「作者の死」を読むと、もちろん作者は何の意味も持たない存在ではない。
現代思想の冒険者たち 21 講談社 われわれは今や知っているが、テクストとは、一列に並んだ語から成り立ち、唯一のいわば神学的な意味(つまり、「作者=神」の《メッセージ》ということになろう)を出現させるものではない。テクストとは多次元の空間であって、そこではさまざまなエクリチュールが、結びつき、異議を唱えあい、そのどれもが起源となることはない。テクストとは、無数にある文化の中心からやって来た引用の織物である。《……》
ひとたび「作者」が遠ざけられると、テクストを《解読する》という意図は、全く無用になる。あるテクストにある「作者」をあてがうことは、そのテクストに歯止めをかけることであり、ある記号内容を与えることであり。エクリチュールを閉ざすことである。
《「エクリチュール」ということばはもともと「書かれたもの、特に文学言語を指す」と説明されるが、現在それぞれの階級や集団の特定の言葉遣いという意味で使われる。そして、特にここでは何かの特定の意味が付け加えられた言い回しについて、(作者ではなく)その「匂い」みたいなものを意識して表現を解釈していく。こういうことを」主張しているんじゃないか、と私は思うんだけどね。》
バルトの『物語の構造分析』という本の中の、「エクリチュールの教え」では、バルトは、日本の文楽について、「切り離された三つのエクリチュール」と言っている。「操り人形と、人形遣いと、叫び手」と言っている。叫び手とは「語り手」だよね。それぞれが別々に「エクリチュール」を発しているというんだろう。それが「エクリチュール」なんだよね。泣いたり笑ったりするその物語ではなく、観客が見ている、聞いている、その「エクリチュール」によって、「前代未聞の効果」が生まれて、「ある種の麻薬に帰せられる知的機敏性と同じくらい特殊な」ものが生じるのだ、と。物語の言い回し、人形の使い回し、そんなものが「文楽」を成立させているんだ。
「作者の死」ってちょっときつすぎる言い方なのかもしれないね。この表現も独特のエクリチュールと言えるかもな。まあとにかく、万能の作者への帰依が読解する時の姿勢でないことは確かだな。
そこでよ、この中途半端な読中、読後感はどういうことなんだろう。こういうことについて、話し合ってみようじゃないか。

問題は作品の中途半端な印象ということになりますか。

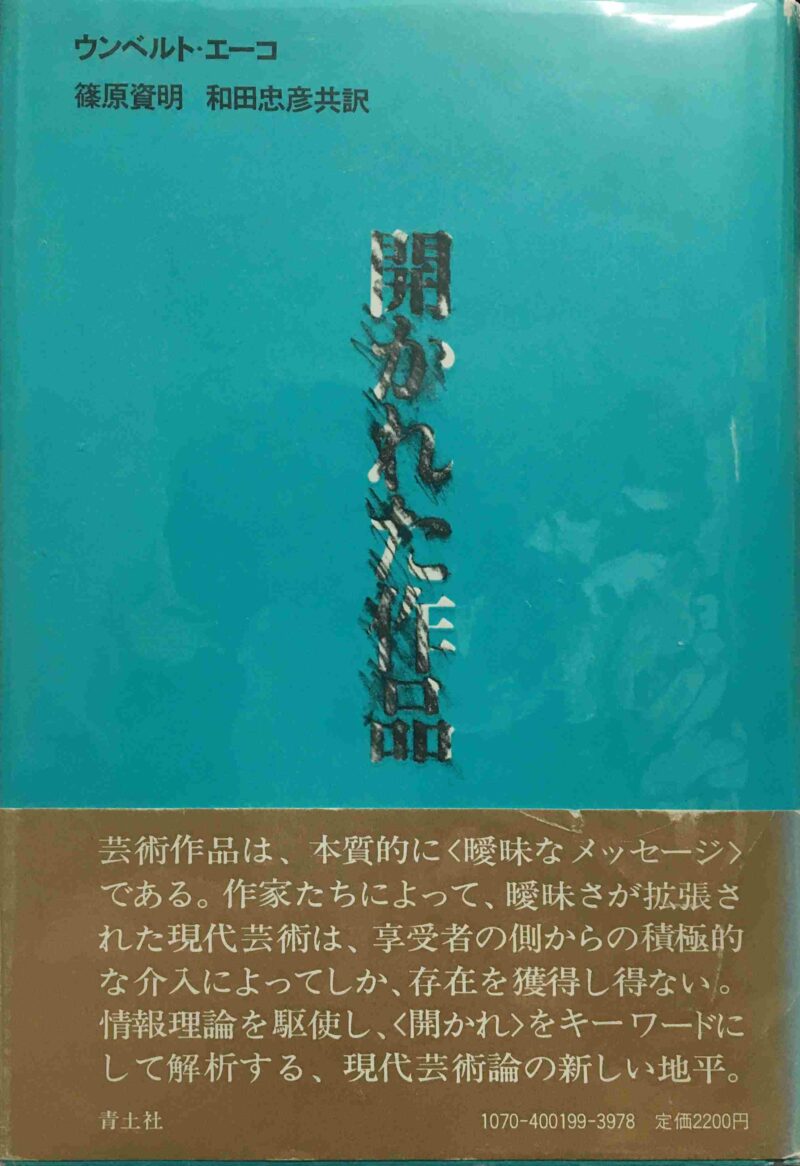
そうよ。
そこで、紹介したいのは、前回だったかな、話題にしたウンベルト・エーコの『開かれた作品』という本の中の、同じく「開かれた作品」という考え方だ。この題名の「開かれた」ということばが与える比喩的効果をまず考えなければならないような気もするが、そのヒントとして、この第一章に出てくる例が参考になる。
エーコは最初に音楽について書いてるんだ。
(例一)カールハインツ・シュトックハウゼンは、『ピアノ曲第一一番』において、演奏家に一枚の大きな紙面に書き込まれた一連の楽譜の部分を提示して、演奏家がまず弾き始めるべき部分を自分で選び、それから続く部分をそのつど選んでいくようにした。この演奏において、解釈者の自由は楽曲の組合せ構造に基づき、楽節の継起を自主的にモンタージュすることになる。p34
指示通りの演奏を作曲者は要求せず、作品に介入する自由を解釈者が持つという楽曲があるのだというのだ。もちろんモンタージュは完全な自由とは言えないが、即興的な演奏も認めるとなると、これはモダンジャズと同じ発想だ。
また、十九世紀フランスの詩人、マラルメの主張も引用している。
万物を名指すこと、それは詩の楽しみの四分の三を取り去ってしまうことである。詩の楽しみは少しずつ推察していく幸福から成る。即ち、事物を暗示すること……そこにこそ夢がある……。p45
詩についてはほんとに疎い私なんだけど、この短文はよく理解できる。詩ではなくても、小説でも、戯曲でも私たちが「読む」「見る」という行動は、作品の完結点へたどる重要な要素なんだろう。読者が参加することが必須ということね。だからその重要な役割を持つ鑑賞者に対して、作者は特権的な影響を持ってはならない。こういう考え方が現代的な読解というものなのかもしれない。
この本は私には難しくてね、なんたって途中で「熱力学」だの「エントロピー」なんていうことばが出てきちゃって、きちんと全体をしっかり理解できてない(まあ、いつもそうだけどね)。ただざっと流し読みをしたところでは、いろいろ面白いフレーズに出会った。
以下の文章は、「物語の秩序は前提となるものとして世界の秩序に対しての信念の上に成り立っている」ということについての、エーコの注釈である。つまり、物語には読む人に従うことを強制する秩序がある、ってことね。全くの自由が物語にあるわけではない、ということ。長いけどじっくり読んで、どういうことを言ってるのか理解する訓練をしてくれ。文中、エーコらしい表現にぶつかる。こういうところが、単なる学者でないエーコという人の魅力なんだ。
現代思想の冒険者たち 29 講談社 例を挙げる。これは、考えられる限り最も味気ない状況の一つに置かれた読者の身に起こりうる例である。つまりたった一人で、憂鬱なときに、しかもできれば見知らぬ土地とか外国とかで、時間つぶしにカフェに入って、無意識のうちに孤独の流れを断ち切ってくれる何かを、お定まり通り裏切られながらも待ち望んでいるといった場合である。これ以上耐え難い状況はないであろうが、いずれにせよ、こういう状況に陥った人は必ずといっていいくらい、状況をいわば非常に<文学的>に捉えることで、状況に耐えることに成功してきたのである。それはなぜか。我々が文学というものによって、一人の人間がたった一人でカフェで飲んでいるとすれば、その人間の身には必ず何かが起こるという約束事にすっかり慣らされてしまったからである。例えば推理小説なら、目も醒めるような金髪の美女が現われるとか、ヘミングウェイの場合であれば、さりげない出会いから対話が生まれ、やがて<虚無>nadaがあきらかになる、といったことが起こるわけである。つまり物語の秩序といったものが、誰かが一人でカフェで飲んでいる場合には何かが起こらなければならないということを、あらかじめ制度的に設定しているわけである。だからこそ最も味気なく無意味な行為が、少なくともその瞬間自分が感じている味気なさを認識するためにありのままに認識されるべきものにもかかわらず、秩序を帯びることで不当にも受け入れられてしまうのである。物語構造を適用することによって生ずる欺瞞のおかげで意味をもつわけである。物語構造は、ともかくも、ある前提の解決、整理された結論、冒頭の終結を要請するもので、終結しない冒頭は許されないのである。しかし小説や映画のなかには——例えばアントニオーニのように――ものごとが実際に起こるとおりに創ろうとするものがようやく現われてきた。しかも芸術が、我々が始めるあらゆる言述について、主音への回帰という終結を我々に与えるということで我々を慰めることなく、この事実を明らかにするのは、従って正しいのである。
p335
どう?カズオ・イシグロのこの作品の全体的な印象に対する答えのヒントが示されているように思えないかな。ちなみに私は「アントニオーニ」という人については知らなかったが、1960年の「情事」という作品で有名な映画監督らしい。ウィキペディアによれば、「観客の期待を裏切る『腑に落ちない』結末で話題になったそうだ。
まさしく、「なんか中途半端」な感じ、という君たちの感覚に合っているね。ここんところが、「開かれた作品」というもののひとつの典型ではないかと思う。しかし何も「開かれた」作品がいい作品、というわけではなく。エーコは”〈開かれた作品〉という概念に、価値的考察は含まれない。”と言っている(『開かれた作品』)エーコは「開かれた」という概念が”芸術的メッセージの本質的曖昧性”と関係しているんだということを言って、これは時代的に古い、新しいとは関係ないと主張している。
考えてみると、全ての作品にこの「開かれ」があるからこそ、魅力があるんだ、ということを言ってるんじゃないかなあ。そりゃあそうだよ。我々に開かれているからこそ読んでいて楽しいんだもんな。全部伝達されるなら、恐れ入るばかりで、ちっとも面白くないわな。
実際、エーコの批評文も確かに開かれている。自分の主張を説明する場合だって、彼の使うことばそのものがまさしく文学的で、開かれているって感じなんだ。文学・言語学の理論の、ひとつひとつの例が、どこか読者に驚きや意外感を与えようとしているのが感じられる。読者は難しそうな理論の説明でありながら、そこに「あれっ?」というユーモアを感じる。そしてなぜそんな感じが起こるのか、エーコの説明をもう一度考え直したりする。こういうところが魅力なんだな。
私も引き続きエーコを読んでいきたいと思う。今回は勉強しながらの話だったんで、中途半端だが、それこそ「開いたままで」終わりにするよ。それでまたパースや認知言語学もちょっとのぞいてみようと思う。きっと、他の作品を読んでいく上でエーコの記号学などは面白い視点を与えてくれるんじゃないかと思うよ。その上、エーコの小説もあるしなあ。これは大変だよ。







コメント