
ドストエフスキー 安岡治子 訳光文社古典新訳文庫
巨大な山 ドストエフスキーの処女作

今回はまた厄介な作品だけど、チャレンジしてみたい。私にとってもこれは難敵だったんだけどね。ドストエフスキーの『貧しき人々』だ。ドストエフスキーってのが私にとってもほんとに厄介で、まず読むこと、内容を、話の流れを理解することが、大変なんだ。


先生!ちょっといいですか。私、まず先生に訊いておきたいんだ。今回の『貧しき人々』ね、読んできました。これを先生が選んだということ、それには先生なりの私たちに対する「こういうことなんだ!」とか「こういうことをわかって欲しいんだ!」いうところがあったんですよね。たとえば私すごく印象的だったのは『よじょう』でした。人間にとって物語というものが、いかに重要で必須なものか、なんていうこと、本当に印象的でした。いまやってる勉強だって、好きなゲームだって、友達とのおしゃべりだって、なんだってかんだってみんな物語にとり憑かれているんですよね。有名大学志望なんて、職業選択だって物語の追求です。大谷選手なんか、その最たるものですね。あの人、物語を追いかけすぎてますよ。それをみんな称賛してさ。物語の欲望をずっと追いかけていくんでしょうね。それをひとつずつ成し遂げて、そしてさらに……。
私には、これ思ってもしないことを気づかせてくれるものだったんです。
さてそれで『貧しき人々』ですよ。この小説を読んで先生は何か気づかせてくれるんですよね。いや、こういう言い方はいけないですね。つまり、これ読む価値のあるものなんですよね。いや、これもまずいです。私たち高校生の段階で、この小説は私たちに相応しい小説なんですね?
正直いうと今回全くそれを実感できなかったんですよ。
変なこと質問しちゃってごめんなさいね。

………………
わかんねぃな。私の予定している地点は……無いんです。私はみんなと一緒に考えます。もちろん多少の知識はあるけど、それもあやふやで、難しくて、ある評論を私自身理解して君たちに知らせられるか、これはちょっと正直わかんない。とにかく、今回も「そう読んじゃったんだから仕方ねー……」と、こういうのを許してもらうしかないね。でも、これだって絶対に有意義な授業だとは確信しているんだ。

そうですか、じゃ、まあ、あんまり力入れすぎず、自由な、勝手な読解をさらに自分たちで進めよう、ということでいいんですね。

そのとーーーーり。納得できなくてもいい。私自身全然自信ない。どの読み取るか、どんな感想を持つか、それは全く君たちの権利だ。
ただできたら何かその感覚を持った理由が言語化できたら、すごくいいということだね。
あまり評判は良くない?


じゃあ、私から。
全く面白くなかった。バカみたいな中年男のラブレター?「天使ちゃん」なんて、いい加減にしてよって感じ。何がドストエフスキーだよ。よくこんなの、かの国の人々は文豪として認めているなあ。
まあ処女作ということで、もちろん長編の名作なんかはそんなことはないと思うけど。

おれも同じような感想。
まず、この男の手紙、唐突感がいっぱい、矛盾の連続だよ。最初から……。
”昨日は幸せでした。”なんて。いきなりですからねえ。まあ、彼女の顔を窓越しに見られたのが幸せだった、ということですかね。
それ以上にわからないのは彼女への自分の気持ちの表明です。彼はワルワーラ・ドブロショワに対して、保護者的な愛情を感じていたのか、それとも彼女に対して恋人となるような希望を持っていたのか。このギャップがずっと引っかかっていて、こっちの気持ちが整理できなかった。もしかしたら本人にも分からないことだったのかも。中途半端な、いやーな気分で読み進めることになった。
次がカーテンの位置をちょっと変えることで示す、秘密の意思疎通方法です。なんか現代の日本の高校生にこんなこと読ませることも、気恥ずかしく感じてしまうんじゃないでしょうか。確かにこのおじさんはこういうことに無常の喜びを感じているようだ。そのこと自体、”キモい”。ここにはおじさんが先生しかいないから、先生がそんなことをやっているところを想像しちゃってなおさら”キモい”。これは多分ドストエフスキーも効果として自覚していたはずだ、たとえ十九世紀半ばの小説家だとしても。
年は取りたくない、と言ったあとすぐに

天使みたいに愛らしくて優しい微笑みが、ぱっと明るく輝きだして、ちょうど私があなたにキスしたときみたいな――ワーレンカ、私の天使さん、憶えているでしょう――そんな気持ちになったんですよ。それに、あなたがちっちゃな指を一本立てて、ダメよ、
と私をたしなめたような気さえしましたよ。ねえ、そうでしょう、お茶目さん?こういうこと何もかもを、あなたのお手紙でもっと詳しく書いてくださいね。
と書いてます。声に出して読むのも恥ずかしくなる。そんなことを書いているマカール・ジェーヴシキン、それを小説として書いているドストエフスキー、両者の気持ち。これはなんでしょうねえ。
たぶん、作者の悪ふざけじゃないの?違いますか?

翻訳文を読んだわけだからわからないが、私も作者のくだらん悪ノリだと思っていたんだよ。ドストエフスキーってなんだか哲学的な、大作家のように思っていたんだけど、この処女作を読むとなんだかそうじゃないみたいだな。そういうドストエフスキーを想像しても、絶対違う!とは言えないんじゃない?

わざと読者をしらけさせようとしてるんですか?なんのため?くだらない中年男、という印象を意図的に読者に植え付けようとしている……ということでしょうか?

まあ、もうちょっと先へ行こう。それからいろんなことが出てきたら、その時に……。
中年の恋 だったら興味はないよ

同じ下宿屋にいる人々を紹介していますね。これは読者対象なんじゃないかなあ。改めてすぐ近くで生活している(しようとしている)ワルワーラ・ドブロショワにそんことをする必要はない。自分の部屋が台所の一角で家賃がどうこう。こんなことは書簡に入れなくても良さそうです。これ読者に情報提供をしているんです。
この「なになにちゃん」という言い方が本当に気になる。いやらしい。昔の翻訳作品に多く使われている印象があるけど。指小辞っていうんだけど、「江戸っ子」とか「阿Q」とかね。こういう用語が使われるその意図が問題ですね。
このことばを選択する登場人物のいやらしさ、軽薄さ、そんなことを印象付けるという意図のもとに使われているんでしょう。
つまり私は作者の誘導のもとにこの小説に嫌悪を感じたんです。この中年のおじさんに対する拒否感は、作者の意図なんですよ。作者はこの男を「嫌(きら)え」と言ってるんです。

僕は、何より「いきなり」という点が、つまり唐突な作品の出発が不満でした。この二人がどういう状況で知り合ったか。はっきりさせなくてもなるべく早く、然るべき段階で読者に知らせるようにするべきだったんじゃないでしょうか。


それは違うだろ。だってこれは「手紙」なんだから。自然な手紙としての形ができていないといけない。それを目指しているんだから。いろんな二人の前提条件みたいなものはもう二人には了解済みなんだから。
ここがまずポイントなんだよ。この二人の手紙のやりとりって、ずっとそうだろ。どういう状況なの?って、僕もストレスを感じながら読んでいった。だから話が頭の中に入らないくらいだった。これは作者の意図だと思うよ。
バフチンの「ポリフォニー論」とは

実は今回初めてロシアの批評家、哲学者ミハイル・バフチンという人の本を読んだ。いや正直いうと全部じゃないんだけど。今回の授業で参考になるところはないかと、ざっと見てみた。そこにあった言葉が「ポリフォニー小説」という概念だった。
君たちの印象の原因はこれじゃないかと思った。
ポリフォニーについてはウィキペディアの説明をみてほしい。
バフチンはドストエフスキーの小説の画期性を、その登場人物があたかも独立した人格のように多面性を持ち、解釈の主体として振舞い、時には、独自の思想の主張者として振舞うことで、人物相互の間に「対話」が成立し、そのような対等かつ劇的な対話性において、小説以外のジャンルでは表現困難な、現実の多次元的・多視点的な表現が可能になっていることであるとした。
ポリフォニーとは多声音楽とも言われて、主旋律だけでなく複数の旋律によって表現される楽曲。混声合唱とか四部合唱とかいうでしょ。
バフチンの『ドストエフスキーの詩学』では(私の読みでは)、その音楽的イメージと同じことで、登場人物が自分自身の思想や感情を作者と関係なく持っていて、それに従って彼らが同時に動き回り、話をし、主張し、感情を爆発させる。それがドストエフスキーの小説だといい、その特徴は処女作の『貧しき人々』から『カラマーゾフの兄弟』のような長編大作まで貫かれているんだと。そういうことだと理解している、
ベリンスキーの『貧しき人々』への熱狂ぶりは、ドストエフスキーのその後の大作を知る私たちにとっては、いささか大袈裟に思われるほどなのだが、ロシア文学における西欧ロマン派の模倣者(エピーゴーネン)を排し、ロシアの現実を再現し批判するリアリズム文学を求めていたベリンスキーにとって、この小説は理想的な作品に思われた。ドストエフスキーの登場以前は庶民の日常を詳細に描写する文学は「生理学的スケッチ」と呼ばれており、その重点は写真のように正確な外形描写に置かれ、人物の内的心理を深く掘り下げたり、語りに工夫が凝らされることはほとんどなかった。『貧しき人々』は「自然派」と呼ばれた作家たちのこうした「生理学的スケッチ」に足りなかった点を補い、深みを加え、さらに社会的メッセージを性も備えた真のリアリズム小説として歓迎されたのである。

(Mikhail Mikhailovich Bakhtin)
1895-1975年。ロシアの文芸学者。ペトログラード大学に学ぶ。革命後の混乱の中、匿名の学者として活動。スターリン時代に逮捕され流刑に処された後、モルドヴァの大学教師として半生を過ごした。
50年代後半から国内での再評価が始まるが哲学、言語学、文学、文化史、心理学などの諸領域に及ぶその仕事が幅広い影響力をもつのは、没後のことである。著書に、「小説の言葉」「フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化」などがある。
なんと『浮雲』の話と似通ってるではないか。つまり、つまらなさが、だよ。明治の日本でも同じようなことが起こっていたんじゃないかな。日本に、ドストエフスキーは生まれなかったのかもしれないが、ロシアと同じようなムーブメントがあったんじゃないかなあ。ちょっと専門家に笑われてしまうかな。
そのころロマン的な文芸は飽きられていたんじゃないかな。ショーペンハウアー流に言うなら、物事の退屈期に入っていたんだろう。そこにドストエフスキーのインスピレーションが起こった。ポリフォニーだ。こう考えたらなんとなく納得しちまったのよ。
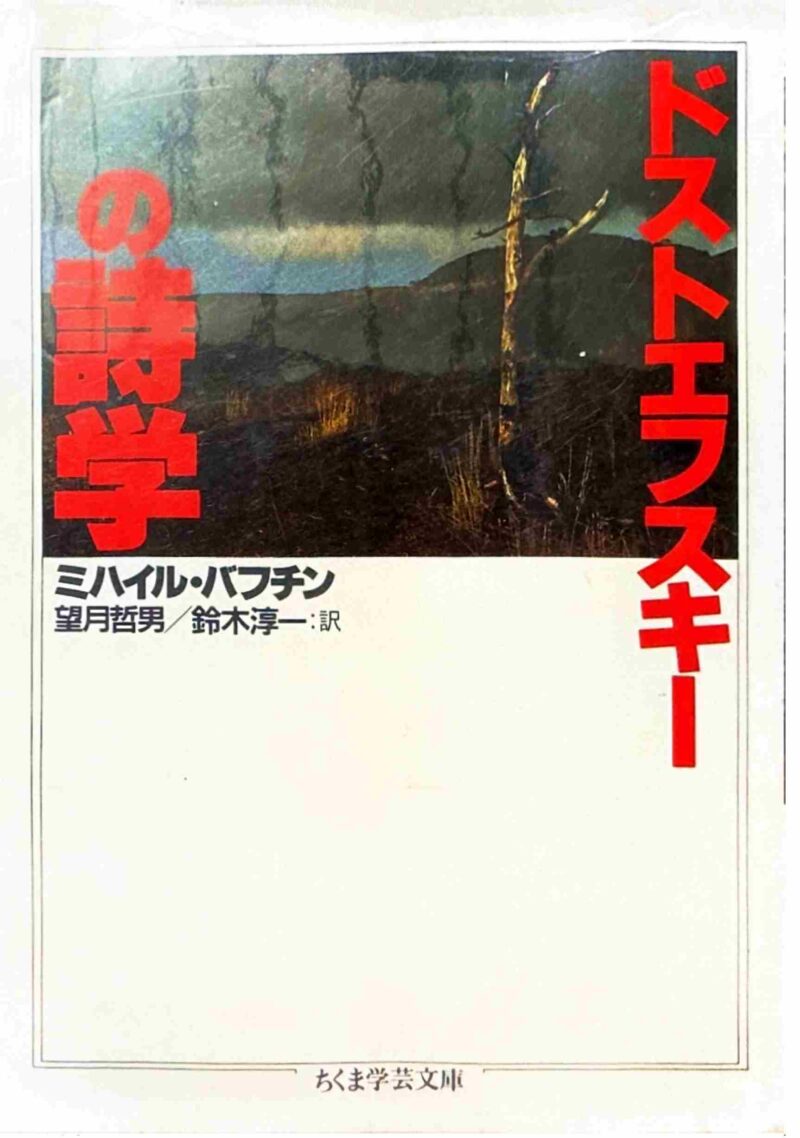
私、恥ずかしながらドストエフスキーは全然読んでない。高校生の頃『罪と罰』を読み始めてすぐ挫折してしまってそれ以来再チャレンジもしなかった。まず最初に人々の名前が覚えられなかった。同じ人の呼び方が変わるのもついていけなかった。この辺の工夫が当時は全然無視されていた。もう少し注釈などで人物関係がはっきりできればよかったんだが、とにかく我慢できなかった。
『カラマーゾフ』はすごく気になっていたんだ。文庫本も揃えて、いつかは……と意欲だけはあったんだがな。もっと早く読んでおくべきだったが、いまだに読んでない。だから、ポリフォニー小説というものについても、知らなかった。これが失敗だったな。だからこそ今回は私にとっても、良い機会なんだ。
ところが……。『貧しき人々』を一読して、やっぱり興味を持てなかったな。何も感動というものが湧いてこなかった。そして、その主たる原因が、このポリフォニーという点だったんじゃないかと思った。これが理解できなかったんだな。
こんなことが前にもあったな、と思っていたら気づいた。あくまで私の感覚なんだけど、二葉亭四迷の『浮雲』を読んだときの感想が、ちょうどそんなだった。なんか心に残るものがなくて、後味の悪いものが残った。二作品が同じ方法をもって書かれている、ということはないけど、確かに同じ味の作品だと感じた。そのこと自体が私自身の理解力の無さの結果であったんだろうが、正直なところ、そうだった。
『浮雲』(うきぐも)は、二葉亭四迷の長編小説。角書「新編」。第1編1887年6月20日、第2編1888年2月13日、金港堂刊行。第3編は『都の花』1890年7月から8月まで連載。合本、1891年9月。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
しかし、この光文社古典新訳文庫では安岡治子という人の解説は、わかりやすかった。解説は作品の読解を導いてくれるものでなくてはならないのに、解説にならない難解な表現を、わざと選んでいるようなものもあるのに。
そこにはまず『貧しき人々』が1846年に発表されたとき、それを読んだ人々がいかに驚いたか、どんなに新時代の到来を喜んだか、が書いてある。当時の批評家ベリンスキーにも激賞された。ドストエフスキーも「あなたは偉大な作家になれます!」と言われたと、書いているそうだ。
まずこれに驚いた。たった十ページ読んだだけで、皆がそう言ってきたというんだ。君たちはどう?
私は信じられなかった。この小説のどこが……?という気持ちだった。でも、この一節が気になったんだ。

『浮雲』とかもよくわかんないけど、明治のリアリズムの誕生だった、ということなんですか。それじゃあ話がつまんないのは当然だと?

ほんとだ。だって、ポリフォニーって、登場人物たちに自分勝手にいわば演技させるんだろ。音楽なら各パートに楽譜があるよ。つまり、縛られるコードはあるんだ。小説はないじゃん。

またも外国の批評の翻訳の受け売りで、申し訳ないんだけど、たまたま古本屋でめくっていた本、R.M.アルベレスという人の『現代小説の歴史』。その一節に、
単一のメロディーからなる作品が、あまり機械的に見えてくると、多声楽的な構成な構成が要求されるようになる。連作長篇ないし総体小説が、もっと錯雑した小説的素材を暗示するようになるのである。こうした小説の中では、読者はある一つの筋を追うのではなく、いくつもの運命の交錯するさまをたどってゆく。ドラマの単一な線上に――メロディーの、といってもいい――何本もの他の線が重なり、まじり合い、すべてがつき合わせられ、、干渉し合い、ひとつに落ち合い、とけ合う。和声とフーガと対比法との芸術なのである。もはや、単純な一つのテーマに圧縮された物語ではなく、中心的な幾つかのテーマをめぐる、平行的あるいは拡散的な変奏からなる物語である。(p111)
これは、ドストエフスキーの小説を説明した文章ではないんだけど、この説明がそのままポリフォニー小説の説明になってるんじゃないかな。

その説明って、なんか『貧しき人々』に当てはまんの?当てはまってないように思うけど。そんなに大掛かりの長編でもないし……。
ポリフォニーって自分勝手ってこと?

その通りだね。ただ、ドストエフスキーの『貧しき人々』が、こういう複雑で、糸の絡み合ったようなものを指向していることは認められるんじゃないかな。わざと絡み合う話にしているとも見えるじゃないか。そう思わないか?

確かに。思えば、この手紙のやり取りは常に(といっていいほど)先行の文学の感想や解釈や、そんなものへすぐ話題が流れていきますね。本の貸し借りなんかも。最初のマカール・ジェーヴシキンの手紙には、
なにゆえ私は鳥にあらぬか、自由に獲物を追いかけるあの鳥にあらぬか!
などといった考えが、そこにはまだいろいろ並べられているのですが、それはまあ、どうでもいいでしょう!
なんですかこれは!こんな文が彼女への手紙に必要なんでしょうか?それこそ鳥のように自由に、意味もないフレーズを並び連ねて、勝手な手紙を書いているくせに。
その勝手な手紙文の傾向は、ワルワーラ・ドブロショワの方だって同じようなものでしょう。手紙で伝えなければならないことから、すーっとどうでもいいことに移ったり。もう勝手なもんですよ。
つまり、これは作者の意図として認められるものだと思いますね。その実験を処女作でやってるような感じですね。

でも、いくら形式で旧来のマンネリを打破する、ということが認められても、僕らが読む、そのモチベーションはそこにあるだろうか。もちろん専門の研究者にとっては新しい発想は大変重要なことだろうけど、僕たちからすれば、何かの生きる指針を得たいわけよ。それは道徳的なことじゃなくてもいい。現状批判でなくてもいい。でも何かを発見させてくれないとつまらない。その発見は文学研究者のものだけではないもの。これが要るんじゃないか。

最後の手紙が何を意味するのか、がわからないからね。ワーレンカはこの下宿屋を去って、ろくでもないやつと一緒になって悲しい一生を過ごすのだろうか?それともマカール・ジェーヴシキンの引き留めを受け入れるんだろうか?
そういうことが割合読者に納得させてくれるのが、バフチンのいう「モノローグ的小説」というもので、この本『ドストエフスキーの詩学』では、トルストイの『三つの命』が例として示されているね。これ、短いからちょっと読んでみて。
モノローグっていいな


『三つの死』 トルストイ
裕福な地方貴族の妻が旅先で、病で死を迎えるような状態になっていた。彼女は田舎で死を迎えることを拒み、療養のためにモスクワからイタリアにへ行くための馬車の中にいた。転地によっての回復を夫人は信じていたのであるが、同行していた医者は心中ではそんなことは思っていなかった。
馬車は村に入り、駅場で停まった。夫や医者は夫人の身を案じたが、彼女の顔色は悪く、医者は最後の日を安らかに迎えることを夫に告げるのだった。夫人は夫に対してこの旅をもっと早くにしたかったと、不平を言ったが、自分で言った「死」ということばに気づき天を仰いで、「ああ、神様!なぜこうなのでございます?」と涙を流すばかりだった。
……ひとりの馭者が馭者部屋に入ってきた。竈(かまど)の上ではひとりの老馭者が重い病で寝ていた。年若な馭者は、老馭者に靴を借りたいと申し出た。「爺さんにはもうそんな靴はいらないだろう。」と。老人はやっと鼻で呼吸して、手を動かすこともできないようだった。部屋の飯炊きは、そんな靴はもう老人には必要ないだろうことを遠慮なく言い、「それ、あんなに呼吸(いき)がつまるじゃないか。もう他の部屋か、どこかほかの場所に連れて行かなけりゃならん。」と言う。
しかし、老人は「お前、靴を持って行け、セリョーハ。」とやっと言った。ただことばははっきりとしていた。「ただな、いいか、おいらが死んだら墓石を買ってくれ」とつけ足した。周りの人々に、「お前さんたちは証人だよ。」とも言った。その次の朝、老人は冷たくなっていた。
春が来た。
領主の館には瀕死の夫人が死の床についていた。彼女の老母は「なぜ神はあの女(こ)をお召しになるのでしょう?この私を召されないで。」と烈しく泣いていた。そして、その夕方夫人な死んだ。
一ヶ月後、彼女の墓には礼拝堂が建てられた。そしてあの老馭者が埋められた土の上にはまだ墓石がなかった。
馭者の仲間は若者を責めた。なぜ墓石を、せめて十字架を立ててやらないのだ、と。
次の日の朝、若者は斧を持って森へ出かけ、一本の大樹に斧を打った。樹はその全身をふるわせた。且つよろめき且つ速やかに立ち直り、奥の根本の危うきを気遣って戦慄(おのの)いた。樹々は、彼らの真ん中に作られた空間の上に、前より喜ばしげに枝を広げた。鳥は飛び回り、幸福を歌った。生ける大樹の枝は、緩やかに、また荘厳に、死んで倒れた樹の上に揺らいだ。

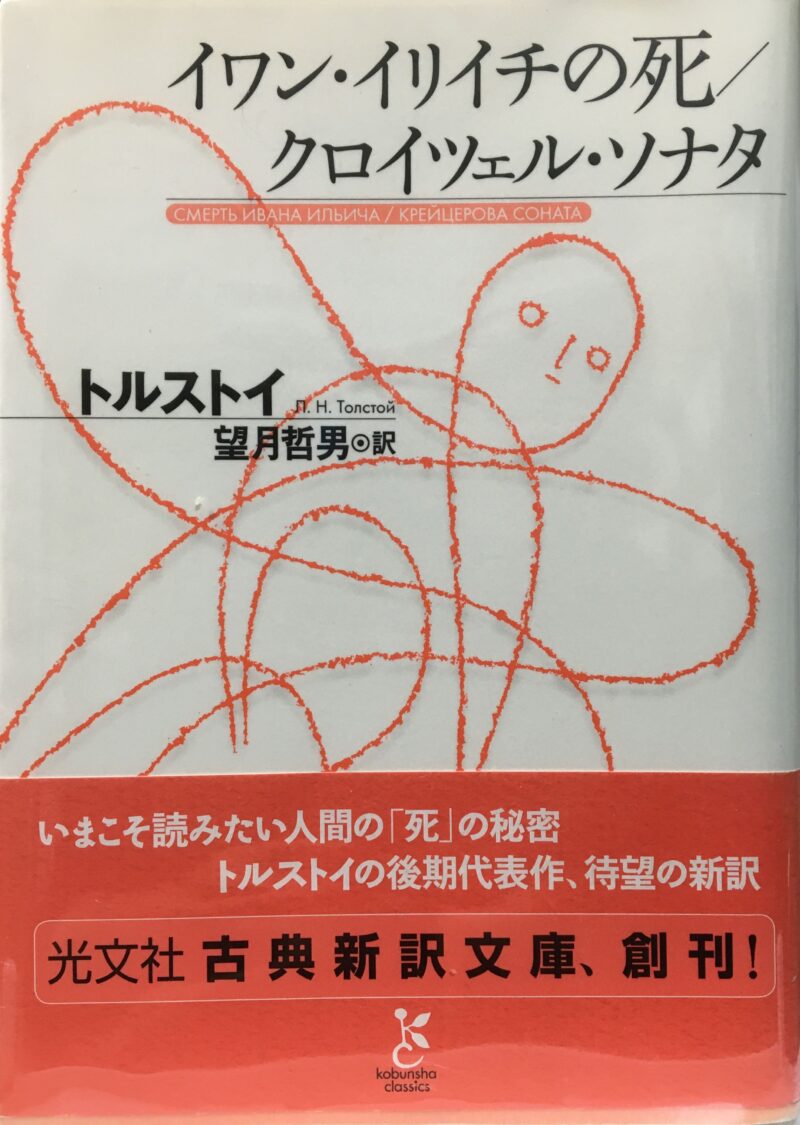
かつて、トルストイでは『イワン・イリイチの死』を読んだことがあるけど、人間の一番の問題である「死」について、死んだこともない人間がこんなことを書いて良いのか、とも思ったことがあった。でも、この「死」が本当なら救われるんじゃないかと思ったよ。若い頃、「救われたい」と思うほど苦しんでいたわけじゃないのに……。
でも、このイワンの死よりも、むしろこっちの方が名作だと感じたなあ。今まで読んだことなかったけど。
この『三つの死』が、バフチンの『ドストエフスキーの詩学』でモノローグ小説として例に出されているんだね。両方読んで、どう思ったかね。

『三つの死』の方が良かったな。ある種、経験したことがある感動が生まれてきたような気がする。これだって、人間のエゴを読み取る人がいるだろうし、それをも含めた「命」あるもの全てに限界あることの「素晴らしさ」を読み取る人もいるだろう。

私もこちら、トルストイの小説に親しみを感じました。
小説では夫人の、生に執着した死。その母はなぜ順番に死なないのか、この娘はあまりに短い生しか与えられなかった、と嘆いています。長い生の方が幸せなんですね。短い生は不幸なんです。だから余計執着する。それに経済的豊かさも関係してくる。配偶者との関係も。
それに比べて老馭者の死はすごくシンプル。本人もよくわかっているし、親類縁者もいない。その部屋にいた「飯炊きの女」の言いようも驚きで。病人への気遣いもなさそうだが、それでも実際には暖かな気持ちもあるんだよね。この「ナスタシア」が良いんだよねえ。
さらに老馭者の墓の十字架にされる大樹の死。全くこれが死と再生の様子です。悲しさなんてどこにもない。ただ周りの喜びのうちに死が現れる。
どれが高級でどれが低級だというのとは違うかもしれない。けれど、どうしたってそういうことを考えてしまう。

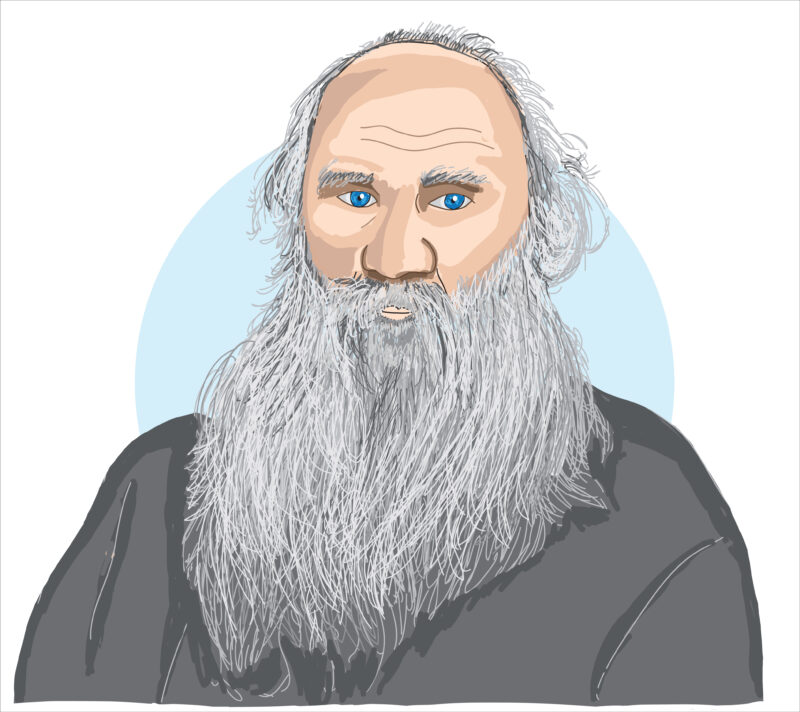
「死」というものが、多面的なもので、悲しいとか、怖いとか、忌避すべきとか、そういうものではないことを教えてくれた。……ということはトルストイとは『先生」なのかもしれない。詳しくないし、読んだこともない人だけど、トルストイっていつも何かを教えてくれんの?
もしそういうところがあるなら、まさしくバフチンがいうように、モノローグ的だね。テーマに対して、一貫した姿勢を貫いている。それを読者に表白している。一貫してこういう作品を書いている。
それでも決して悪くないよ。むしろ僕にとっては魅力的な小説家だよ。考えさせるものがあるよ。ポリフォニー的な小説は僕を考えさせないよ。いや違う。別の意味で迷わせてくれるね。
でも、その目的は何なの?作者のメッセージというものはないの?
『三つの死』にはあると思う。僕の読みが間違っている、誤解であるという可能性はあるが、少なくとも僕は、「死」というものが「個体の終了」ということだと捉えることに正当性があるのかどうか、ということがこの小説のテーマであるような気がするんです。
命 それは個人のものとは限らないという、トルストイのメッセージか

ショーペンハウアのことを思い出すね。人が、というより、「意志」がさせるものとして、「分化」させる衝動というか、力があるってこと言ってるけど、この「個別化の原理」ってことかな。生物の枝分かれ図を考えてみればいいよ。
参考までに『意志と表象としての世界』第四巻に書いてあることを見てみよう。
このわれわれの毎日の全生活を成り立たせているものは、徹頭徹尾、物質の不断の新陳代謝であるというほかはないのだが、物質の形態はどこまでも限定したままである。そしてまさにこのことあるおかげで、個体は消滅するが、種族は不滅なのである。毎日の栄養摂取と(細胞の)再生産はただ程度のうえから生殖と違っているというだけのことだし、毎日の排泄分泌はやはり程度のうえから死と違っているということにすぎない。
『意志と表象としての世界』西尾幹二 訳 世界の名著 中央公論社 p506
なぜ個体の存続の永遠性を求めるのか?種族の永遠性がすでに担保されているじゃないか、ということ。死は排泄分泌と違いはない、と哲学者は言っているんだね。髪の毛が抜けたからといって、髪の毛の死だと悲しむ人はいない……こともないか。最近おれも……って、また違う世界へいきそうになって怒られちゃうけどさ。
まあ、ショーペンハウアーって面白いなあ。訳者は最近亡くなった。私、この本はすごくいい本だと思うが、訳者自身の政治的傾向には大反対だった。


だからってさあ、自分の死も、肉親でさえ死は大変な悲しみのもとになることは変わらないじゃん。死は新陳代謝だって言ったって、何の意味もないですよ。
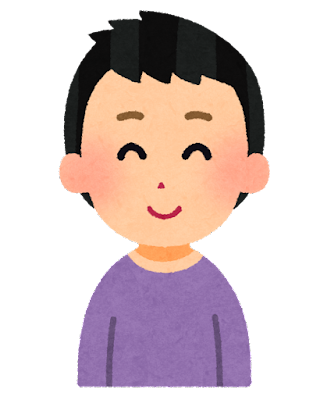
でも、それも要するにわかっている奴とわかっていない奴の差でしかないのかもよ。ショーペンハウアーって、死への恐怖について、要するにどうにでもなれっていう心境になれば良い。事実そういう心境になれた人がいるって主張している。「個別化の原理」によって「個人」というものが強調され、「個人の権利」も発見されたんだろうけども、それも「見かた」でしかない。単位を細胞とするか、器官・臓物とするか、個人とするか、種族とするか。どこの消滅と生成に注目するか、ということでしょう。まさしくソシュールの言語観の問題であり、それを乗り越えちゃったら「死」なんかありませんからね。
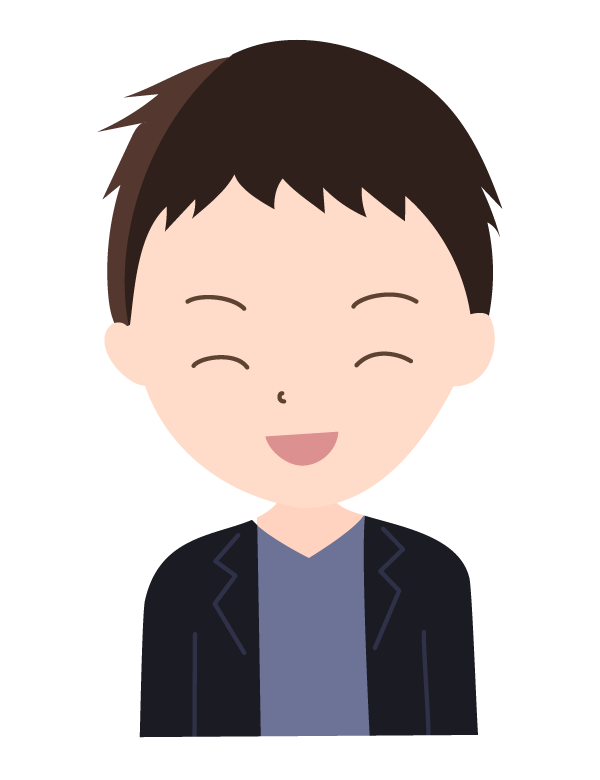
そんなことをトルストイは考えているのかなあ。ちょっと信じられないけどなあ。
「人生のよい指針」が文学の目的ではない。これもまた、言えるのでは?
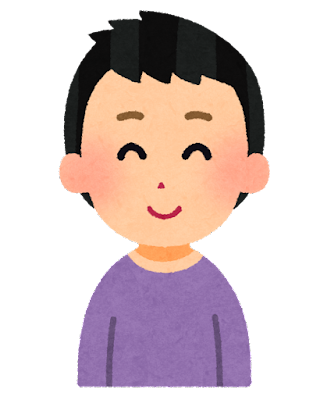
いや、読者が権利としてもつもの。あくまで読み方だよ。正解なんてないんだよ。
とにかくモノローグ的小説として名作だと思いますね。僕たちにも了解できる。トルストイはうまいですよ、啓蒙してくれますよ。作者が作中の全てを支配していて、登場人物同士の交流、軋轢がなくても文学として残るんじゃないですか。僕もこっちが好みだな。

それに、物語としての機能を持ってるんだよ。『貧しき人々』は物語として価値を持っているのか?技法的には画期的作品だという記憶は残っても。うーん、どうしても内容の話になると、パッとこんな話だったというふうに言いにくいと思うけどねえ。

これも大昔に読んだ本。もうほとんど忘れちゃったけど、最初の方で筆者はこう書いているのを、ちょっと前に本棚で見つけた。
文学が言語を素材として成り立つということは余りにも自明のことであるがために、この事実のもつ基本的な重要性はしばしば見過ごされてしまう。そのため、多くの場合、関心は作品の「内容」に向けられ、例えば人生に対するよい指針を与えてくれるのがすぐれた文学作品であるというような考え方が出てくる。しかし、もしそれが文学の本質であるとするなら、文学は哲学や倫理学に含められてしまい、文学に固有のものは存在しないということになる。しかし、同じ人生観でもそれが哲学的に表現された場合と文学的に表現された場合とでは違うとわれわれは感じる。何がその感じの違いの原因であるかと問えば、表現の仕方の差であるということになろう。同じことは一つの詩とそのパラフレイズとを較べてみた場合にも言える。パラフレイズが正確なものであればある程、原詩の「内容」は忠実に保たれているわけであるが、文学性の方はそうではない。何が文学性を失わしめたかと言えば、言語表現の変更ということしかない。”
『詩学と文化記号論』 池上嘉彦 筑摩書房 1983年
どのように書くのか、という点の重要性をこの言語学者は教えてくれている。「文学とは何なのか」という根源的な問いに、「表現の仕方の差」だということにもし納得するならば、その「表現」がどうなの?ということになるね。
落語の人情噺に感動して涙するのはその落語家の「腕」であり、だからこそ同じ話が何年も生き残っているんだ、ということも、そういうことなのかなあ、とも思っている。
そして、授業のお仕舞いに、ドストエフスキーの言いたかったことについてバフチンの主張を一応みんなに知らせておこうと思う。つまり、ドストエフスキーの内容としての主張というわけだ。バフチンはこういっている。それは、《人間の内部にあってけっして完結しない何ものか》の存在だそうだ。どんなに他人が自分を規定しようとしても、そんな言葉やイメージでは納得できないものがある。これはドストエフスキーの貫いたものだそうだ。そういう存在を示す、それがドストエフスキーだった、ということ。それは、モノローグでは表現できない、ということだそうだ。たしかにマカール・ジェーヴシキンも、ワルワーラ・ドブロショワも、それぞれの自分の価値観を主張しあっているけどな、その結果はどういうことになるのかな。
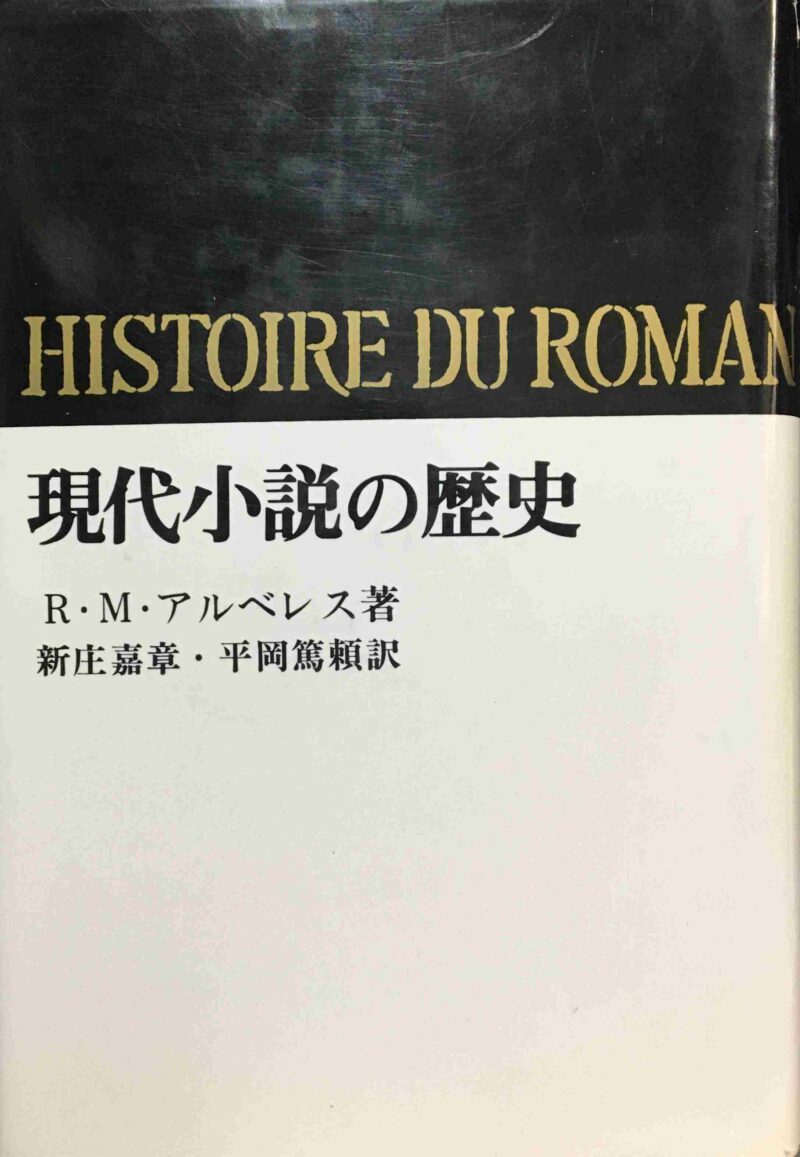
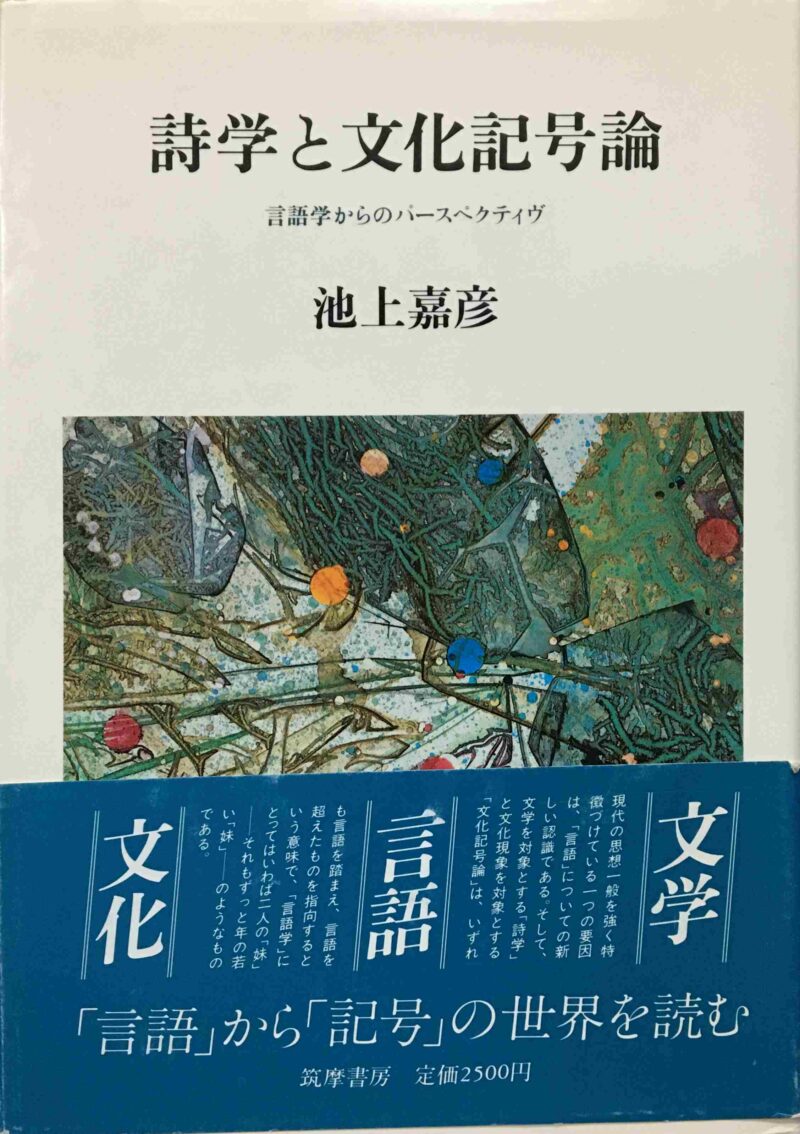


コメント