
自分をうつすものへの視線を感じるか

いわゆる私小説といわれているものを二つ、続けて読んでみようと思う。私小説、心境小説といわれているものとして、前に『城の崎にて』を読んだが、意外にみんなの反応が良かったように見えたんだが、今回はどうかな。まず島木健作という人の『黒猫』という作品だ。こういう小説はゆっくり読むとなんだか淡い感動を覚えるけど、どう?

病気が少しずつ良くなっていく時私は旅行記を好んで読んでいた。最近の本の中である人の樺太旅行記が連載されていた。そこの大山猫の人間を恐ろしく思わない精悍さ、獰猛さが私の興味を引いた。私は絶滅に瀕している大山猫の孤独さと共に、私にその闘志、気位も精神的な感動さえも与えた。
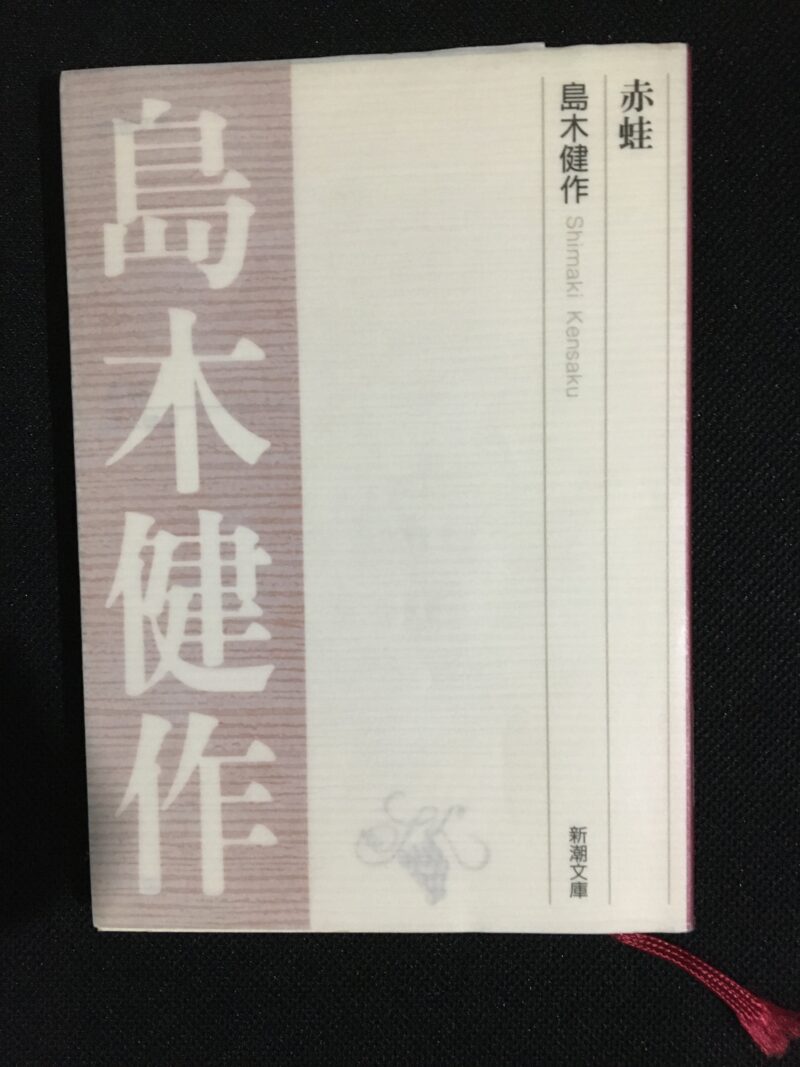
それから数日の後に野良猫が我が家の内外に出没した。私は何匹かの野良猫に対してはこれを嫌った。そんな時に大きな黒い雄猫が出没した。威厳のある、実に堂々たる黒猫だった。彼は決して人間を恐れず、いつも重々しくゆっくり歩いていた。
郷里の人が塩鮭を持ってきてくれた日の夜、私は台所の騒々しい物音に眼を覚ました。どこかの猫が台所に入ってきたという。次の晩も同じことが起こった。誰も黒猫のことは言わなかったが、母が疑い出した。そしてある晩、台所に大きな物音がした。犯人はやはりあの黒猫だった。猫は風呂場に縛り付けられているという。
翌朝は母猫を裏の木に縛りつけた。母側の家族をそこに寄せ付けなかった。若い者は見るものではない、と言っていて、私も命乞いをしてやろうと思いながら言い出せなかった。病人の私が母や家族に強いている苦労がわかっていたからである。
午後になって外に出ていた妻が帰ってくると私に言った。
「おっ母さん、もう始末をなさったんですね。今帰ってきて、芭蕉の下をひょいと見たら、筵でくるんであって、足の先がちょっと出ていて……」
次の日から卑屈な猫だけが集まってきて、私は今まで以上に彼らを憎んだ。
原

なぜだかわからないけれど、妙に心に残る小説でした。私猫が好きなのでなおさら印象深かった。これはいつ頃の話なんですか?

たぶん昭和の初め頃のことだと思う。発表はもう少し後だったかな。

この「私」、病気であったことがまず気になりました。肺病でしょうね。この「私」という人について、変な言い方ですけど、真面目さという感じを強く持ちました。黒猫の毅然とした様子に対して、しっかりと認めている。他の猫たちとの差が、彼に強く訴えてくるんです。そこにはあまりに感情移入が激しいような感じもします。でも、それこそがこの小説のキモですよね。厳しく自分自身が生きようと思うから、黒猫に注ぐ視線が好意的になるんです。だってこの黒猫って見ようによってはただの凶暴なボス猫じゃないですか。私たちは、黒猫の立派な精神を読んでるんじゃないですよ、「私」という男の精神を読んでるんです。

僕は、そういわれると、なるほどと思った。この黒猫という動物は毅然とした男の気持ちにふさわしいのかもしれない。別に立派なリーダーとしての女がいても良いのだが、妙に強い黒猫のイメージには合わないな。
それで小池さんが発言した。
大山猫は単なる強さをあらわすものではなかった

最初に「私」は樺太の大山猫に心を寄せますね。黒猫の出現の前に、この大山猫を知るんですが、これが「私」の心を呼び起こすんです。ここが大事だと思うんです。

樺太全土のなかで、絶滅に瀕している、というところです。「なんという孤独であろう!しかしそこには孤独につきまどう侘しげな影は微塵もない。あるものはただ傲然たる気位である。満々たる闘志である。」そして私たちは、この後の話、人間の頭上から小便をひっかけるという話に引っ張り込まれるんです。孤独なのにすごい気高さ、プライド、そういう山猫にやられちゃうんです。
この山猫が後の黒猫に、「私」の中で生まれかわっちゃうんですね。この人のこだわったのはあくまで山猫だ、ということとに、私もこだわりたい。実在しない山猫がいたから黒猫に、という「私」のあこがれの転換(?)というか、それこそ、記号の記号、ということになるんじゃないかと思って……これ面白いなーって。

つまり、孤独の中で気品を保つということの記号(山猫)が、また別の記号(黒猫)を作った。黒猫は本来粗暴の記号だったのに、というわけね。なるほど。そんなこと考えたの?すごいね。

前にやったコノテーションって話ね。記号が幅を広げていく。そして、それがまた広がっていく。という現象と似てるね。黒猫の写真を見ると、確かに子猫の写真は可愛いけど成長した黒猫の写真には、独立した精神とか、孤高とかいう言葉が似合っているように思える。白猫だとどうだろう?例えば、気品とかいう言葉がふさわしいと思うな。勝手な評価だけどね。
仮に『始末された猫」が純白な猫だったら私たちはどう感じるだろうねえ?やっぱり黒猫とは違うだろう?考えると我々の感情というものが勝手なもんだという気がする。

小池さんは恥ずかしそうだった。「そんな大したことじゃないですよ」と言いたそう。
このお父さんも「孤独」なんですね

小池さんの話の中にある孤独ってことについてね、そこんところが引っかかるな。この人の孤独感が想像できるね。


どこが孤独なのよ。

家族と生活していますけど、母親、妻、子供と。でも一家の柱という立場でも、療養していなければならない身体です。その引け目は自分自身が自分に感じさせてしまうものかもしれませんがよくでていますよ。黒猫の命乞いをしたくても、自分の療養が強いている母の苦労を思うとできない、というひとこと。母が猫の始末を自分でしなければならない、ということもそこです。精神的な柱は「私」の母親なんです。当然『私」がその位置にいなければならないはずなのに。「私」の孤独は想像できますよ。

そうなんです。この春にも、ちょっとした衝突が母との間にあった、なんてことも書いてありました。伝統的な男性の責任感としてジェンダー論的には批判されなくてはならないことかもしれませんが、私はちょっと猫を語りながら、自分を語っていて、しんみりとした感情を持ってしまいます。
最後のところで、他の猫たちを憎む、みたいなことが書いてありますけど、これは自分自身を憎む、否定しているということですね。確かに客観的には家族のお荷物みたいな立場であったのかもしれませんが、そのことに対する孤独感がうまく出ていると思いました。

実生活でも、作者は色々苦労しているしなあ。家族だって苦労の連続だっただろう。
ここで、ひとつ作品を紹介しておこう。石井桃子という童話作家がいるんだが、(『ノンちゃん雲に乗る』という児童文学で有名だ)その作品で『迷子の天使』という小説がある。これもまあ児童文学というものかもしれないが、非常に良くできているものだ。対戦中のある学者の奥さんが、空襲の中やっと生き延びた時から近所の人たちが捨てていく猫を仕方なく引き取っていき、人間が生きるのに精一杯の中でも猫たちをなんとか生かしていく。現在の我々から見たらたいへんな主婦としての仕事も明るくこなしていく。戦後の混乱期もたくましく……。
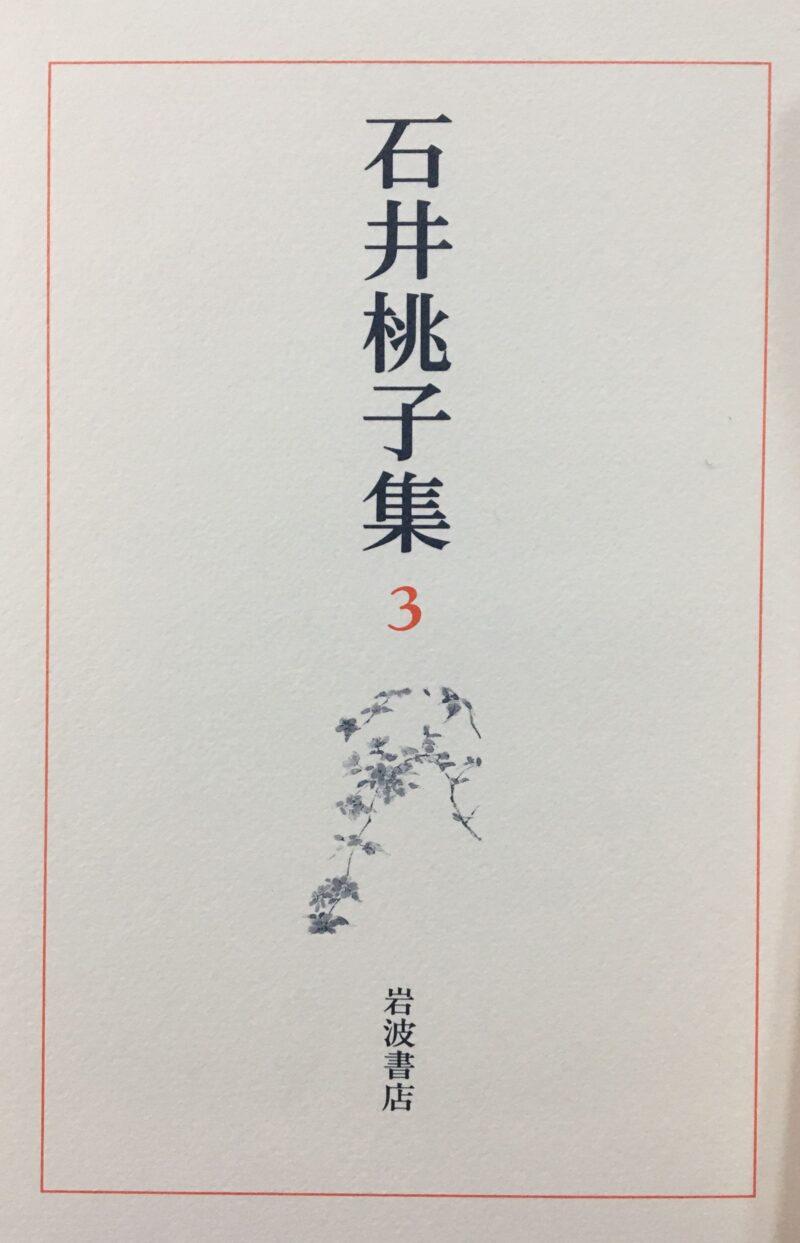
この小説の一部「ねこのめいめい伝」だけを読んでも、動物たちへの日本人の思いをうかがうことができる。すごく野良猫を大事にしてやっている奥さんの話だ。いろんな人がその人の庭先に猫を捨てにくる。その家のお母さんは困ってしまうが、それでも猫を引き取ってしまう。当たり前だけど同じ猫でも、ここではそんな気高さなんかより、ただただ人を暖かい気持ちにさせる。
さらに河合隼雄の「解説」も秀逸。ちょっぴり以前の「センター試験」批判もあったりしてみんなにも読んでほしい本だ。(岩波書店 「石井桃子集 3」)図書館にあると思うので、機会があったら読んでみて。
では、続けて私小説を……。その後で、もう一度この小説も考えてみよう。



コメント