
小さな虫たちから教えられたもの

前回の『黒猫』と同じような設定で、違った小説。主人公も違った感想を持っていく。その辺の比較も考えながら読んでいこう。

晩秋の陽ざしの中、私の病気は少しずつ悪くなっていくといったところだった。私は部屋の中で天井のしみをしみじみと眺めていく日が多かった。
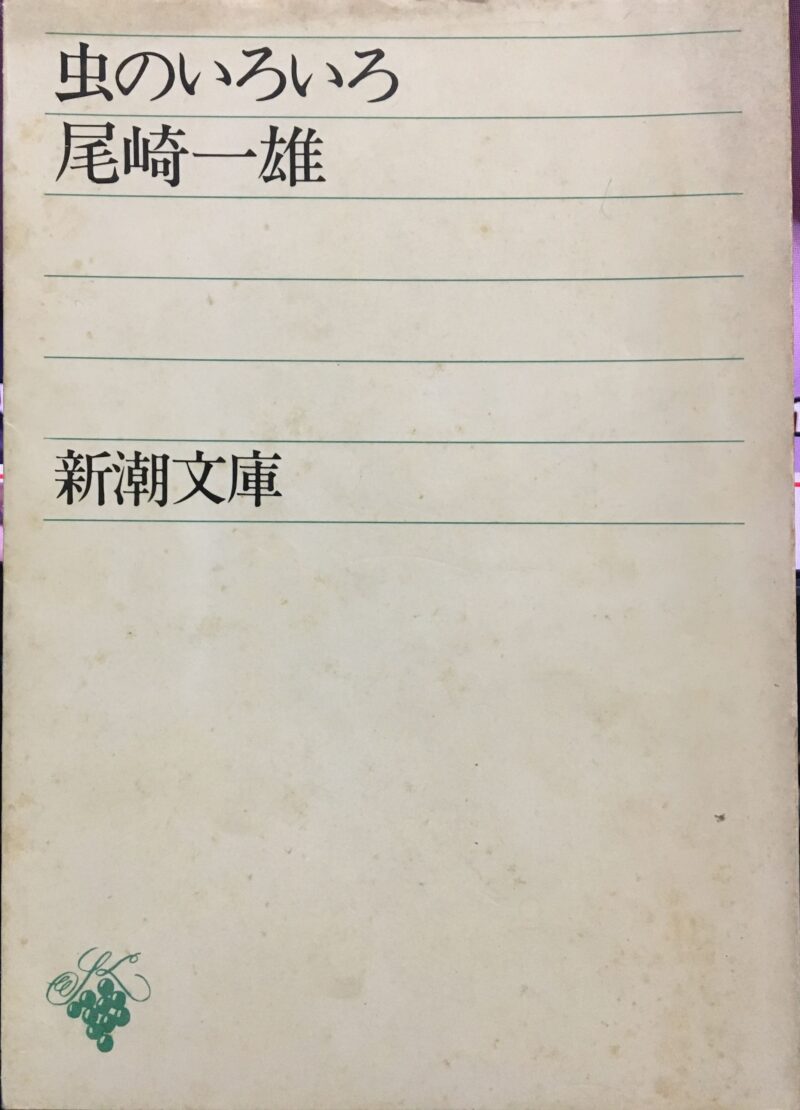
壁の角からスルスルと出てきた。蜘蛛だった。レコードの音楽が聞こえるとそれは動き出し、曲が終わるともとの所へ入っていった。妙な感じだった。そして夏の頃に瓶に蜘蛛が閉じ込められていたのが半年後、私が栓をとった時、間髪を入れずに脱出したことを思い出した。
もう一つ。便所のガラス窓の間に閉じ込められているのを発見した。2枚のガラスに閉じ込められていた。私は家人に蜘蛛を逃さないように伝えておいた。蜘蛛の様子を観察したかったのだ。
半年が経った頃、蜘蛛は細くなってきたようだったが、もう2ヶ月になろうとした頃逃してしまった。まるで待ち構えていたようだったそうだ。しかし私はどちらかといえば病気くらべのような気持ちでいたのが、大儀になっていて、良い方でかたがついた感じだった。
*
私は二十代で病気に倒れてから48年間死というやつと歩いてきた。つまるところこっちはどうしても奴のいく所へついて行かなければならなかった。この諦めきれないところにある人間の築いたものについて、私は考える、天井を見ながら。
*

また、虫のこと。蚤の曲芸について、その訓練は人間の残忍さの現れだと痛感した。私は友人にそんなことを話したが、友人は言った。蜂は飛行することが力学的には不可能なはずなのに、実際にはできる、と。私はそれで物憂さから立ち直ることができた。
*
私は長女に時々身体を揉ませる。そういうとき私と長女はいろいろな話をする。先日は宇宙の有限・無限について話をした。私は無限ということ、人間にはかり知れないことがあることなどを話す。私はふと神ということを思った。蜘蛛は立派だった。偶然を待ちつづけ脱出した。私はどうだろう。私は蚤に似ている。自由というものはあるのか、私を見ているものはいるのか。
*
私は額のしわで蝿をつかまえた。家人を呼ぶと長男が来た。みんながやって来た。みんなゲラゲラ笑い出した。私は「もういい、あっちへ行け」と言った。少し不機嫌になって来たのだ。
蝿は私の頬に止まる。首を動かして追うとまた戻ってくる。これを三度繰り返すと気を変えてしまう。家人に言っても興味を示さない。

これも名作と言われる『虫のいろいろ』。心境小説の代表作……
と、ここで広田が先生の話を遮った。何かまず聞きたいことがあるらしい。

すみません、その前にまず尋ねたいんです。なんで『いろいろな虫』ではなくて『虫のいろいろ』なんですか?先生どうです?

こりゃまた、難しいね。でも、全然違う感じだなあ。『虫のいろいろ』の方がいいなあ。
なぜって?
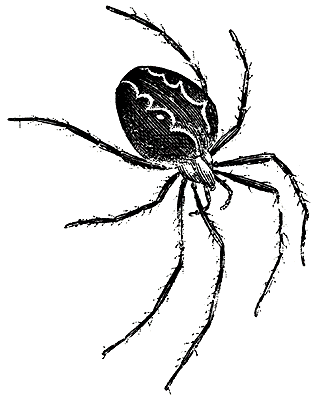
それは「虫」について考えようとしているのか「いろいろ」である点について考えようとしているのか。昆虫記というものではなく虫の属性の多様なところが問題なのか。これ重要なところかもな。ここでは蜘蛛だの蚤だのの特性が自分との関係で何かを影響を与えた、感じたということだから。蜘蛛と同じところが蝿にあったのならそれでも構わないということだから。虫の、いろいろ、なんじゃないかな。
では、それでいったんおいといて、今回も、どんなふうに読んだのか言ってみてよ。拝出がーなんか発言してみる?
よく考えながら……二度目に読んで気づくこと

僕、実は下曽我に祖母がいるんです。もう八十近いんですけど。それが縁で『虫のいろいろ』も読んだことあるんです。今回は読み直しです。でも、前に読んだ時には全然印象が薄くて、内容もよく覚えていません。はっきり言えば、つまんなかったです。

今回は?何か再発見があった?

不思議な感覚ですね。おやっていう疑問が湧いてきたり、忘れていたとか読み飛ばしていたことがありました。それでね、まず蜘蛛ですね。

この人も病気で天井や壁を毎日毎日見ている。蜘蛛の個体も見分けられるほど。この事実こそ病気の様子を示しています。うんうんうなって苦しんでいるような状態ではない、しかし布団から起き出して労働するような状態でもない。蜘蛛が音楽によって出てくるのが確認できるくらいの静養をしていなくてはならない。自分の今後のことや家族のことをこの人も考えていただろう。しかし、この人はユーモアを忘れない。音楽で出てくる小僧の蜘蛛の話なんかで(私小説だったら作家だろうから)この小説家としての文学精神なんかも感じられそうだ。
そして、「チゴイネルワイゼン」。曲名をわざわざ特定していることも、意味を感じさせる、と思います。この曲はサラサーテ、ジプシーの哀愁たっぷりでしょう?「私」の状況に合っていませんか。運動会の行進曲とか、ウィーンワルツじゃあちょっと変ですね。日本の曲でもない。田舎でありながらちょっとしゃれてる。どこか知的な感じの家なのか?などと感じる。イメジャリーとして有効なもので、読者は作者の誘導に誘われてしまいます。
それでまた、曲が終わると「しまった、というような少し照れたような様子」と蜘蛛のことを書く。完全にこの作家の術中にハマってしまいました。これは芸の力ですか。

僕は今回も級友の”読み”に驚いた。そんなふうに読むことが僕にはできなかった。正しいとか間違ってる、ではなく、何か吸い込む気体が違うような気がした。拝出の読み方は、注意深く、小説から立ち上がるものを吸っていくように文を読む、そんな感じじゃないだろうか。ちょっと僕は上っ面で小説を読んでいたようだ。

丹念に読んでるね。じゃあちょっと交代して他には?遠慮なんかいらないぞ、福生、こっち見てるな。
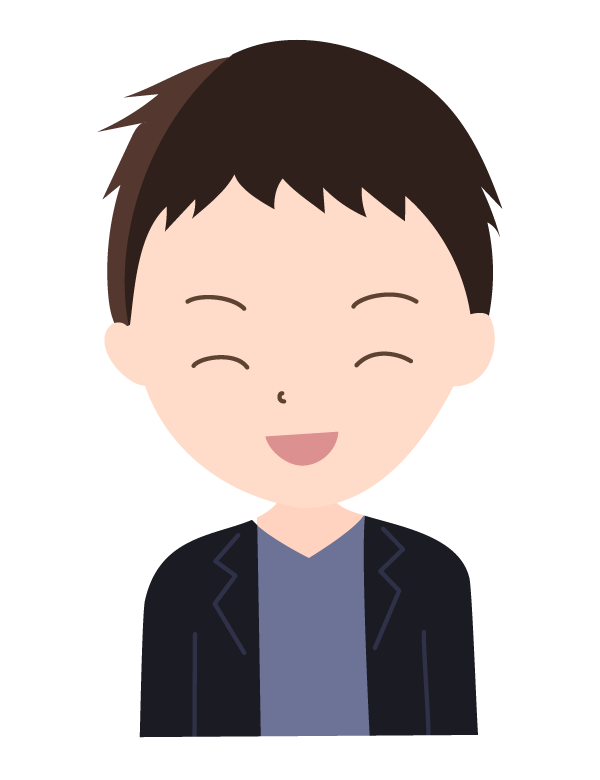
じゃあ、お言葉に甘えておれも。
蜘蛛のエピソードはあと2つあります。エピソード2は外の空瓶に入っていた蜘蛛。半年ほど閉じ込められていた。半年間その蜘蛛は外に出るためにスタートラインで(クラウチングスタートを連想する)その時をじっと待っていた。じたばたせず、あらゆる脱出の努力が無駄になったとしても。これは全く作者の創作した蜘蛛の感情ではあるが実に読者に訴えるものがある。蜘蛛にそんな意志があるはずもないが、僕たちのイメージに、来るはずもないチャンスをじっと待つ蜘蛛の姿を植え付ける。先生が言ってた「物語」を読者は作っちゃうんです。

そうそう、人間は物語を作って、作って、作りつづけるんだよな。

でも、エピソード3の閉じ込められた蜘蛛。どうしてこんなふうに閉じ込めちゃったんだろう。逃してやればいいのに。単純にそう思う。それがフィクションでなかったら、もしかしたら小説のタネのため?

それはどうかな?でもそんなことを人間は面白がってしてしまいそうだがね。
閉じ込められた場所が場所なんだ

「根気くらべ」という言葉が使われていますね。「私」は病気によって閉じ込められ、「蜘蛛」は私によって閉じ込められた。どっちが降参するかやってやろう、という「私」の気持ちです。ちょっとO・ヘンリーの「最後の一葉」を思い出します。自分の命を仮託する。
でもこのエピソードはそれだけじゃない。よく考えられているのかもしれませんよ。

どういうこと?

まず、窓の場所が西向きの男子便所。その目の前がガラス窓2枚に挟まれた空間。よりによってそんなところに幽閉か、ということ。しかもですよ、その窓から富士山がよく見えるんです!曽我山に行ってみるとわかるんですが、足柄箱根連山の奥に富士山がでっかくこちらを見下ろすんです。その景色を見せられながら蜘蛛は自由を奪われてガラスとガラスに挟まれているんです。彼は(彼女かもしれないが)井伏鱒二の「山椒魚」とはまったく違う世界の中でじっとしているんです。毎日毎日用を足しながら富士山を眺める「私」と蜘蛛が重なって来ますよねえ。広く雄大な光景を眼前にしての幽閉なんですから。まさしく「我慢くらべ」です。どっちが早く諦めて死を迎え入れるか、ということです。

面白いねえ。他は?
自分が自分を監視しちゃうの?

蚤もいましたね。
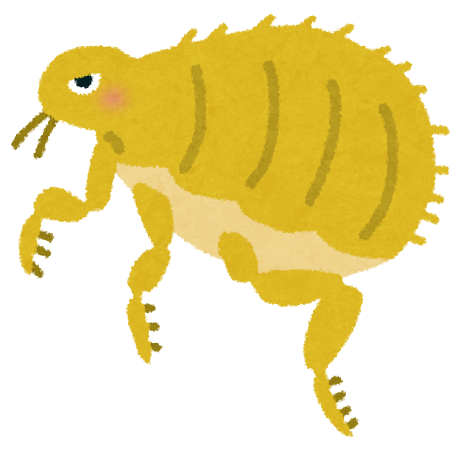
死についての観想というのかな。思いを語っているのに蚤のエピソード。蚤は絶望して完全に従順な存在にならない限り、閉じた世界から離れられない、ということね。
私はこれを聞いた時、教科書に出てきたパノプティプコンの話を思い出したわ。自分が自分を監視する、という例のアレ。

おいおい、フーコーかよ。すごいね連想力。
ここでまたちょっと余談だけど、そういう連想力がどこかで小論文書けって言われた時の武器になるのよ。たとえばさ、管理される現代社会なんかに関係する小論文が出題されたら(こんな出題はけっこうあるはずよ)、フーコーと尾崎一雄の小説を絡めて書いてみなさい。採点者はびっくりするよ。ただし、知ったかぶりでないように控えめに書くの。いいね。
さて、蚤の話で、自分で自分を管理し、抑圧するようになるってことね。こういう精神の怠惰なあり方は本当に現代の私たちの問題でもあるよね。自分を含めてだけど、先生も生徒も本当に大人しく、飼い慣らされてきちゃったなあ。人のこと言えないけど、君らもよく考えてみないとな。
さて、他には?

そして、その後で、ちょっと物理的にはありえない蜂の飛翔の話が出てきます。自分が飛ぶことが不可能であるはずだ、ということを知らない蜂は飛べてしまう、という話。そして家庭内で娘と話された宇宙の広大さの話、人間の限界、神について。人間の至らなさを自覚し、それをどこかで見ているものの存在も考えてしまう。
最後に額のしわで捕まえてしまった蝿。卑近なユーモアで小説は締められる。つまりこれは現実に生活していく他には道はない、ということなんじゃないでしょうか。こういう話の終わり方もこの小説家の芸でしょうか。この作家の優しさと言ったらちょっと違うかもしれないが、決して冷たい視線でない、暖かさも感じてしまうんです。
日本の私小説への批判もあることは聞きましたけれど、こういう小説は僕は好きだなあ。

でもねえ、お茶漬けおしんこだけでは生きていきたくねえなあ。

確かにそうよ。それは否定できないけど、何日間も煮込んだ料理だけでは私はいられない。日本に生きてきて日本のオリジナリティーが感じられるもの、慣れ親しんだもの、そういうのが意外や外国で認められてまた日本に逆輸入されたというものはいっぱいあるじゃない。小説だってそうよ。日本の文学を「痩せさせた」と言われる、と教わったけど、いまこういう心境小説の評価は高まるべきじゃないの?

まあ日本の小説の豊かさの一つとして考えればね。

じゃあ最後に『黒猫』と比較してみると、どういうことになるんだろう。作家としては同じ時代だし、病気療養中での動物観察という点でも同じような構造を持っているけど。二人の「私」についてはどう?
家父長の責任感?

『黒猫』の私にとっては、黒猫に対する倫理的な憧れみたいなものまであるような感じです。『虫』の私にも蜘蛛に対してある点で目標を見ているんですが、力強さというものを持つ黒猫への感情はより明白です。読者としては、『黒猫』で私の、一番胸を打つ言葉が、家族、特に母に対するすまないという気持ちの表出です。病という仕方がない事実のもとそれでも黒猫に気持ちを託す。それを母親が始末するのは象徴的です。
この母親も大した人物ですね。猫を殺せるからというわけではなく、たぶん逃げない人物よ。強いですね。
対して、『虫』の私は経済的に余裕があるのか、『黒猫』の私より封建的なものを感じる。あるいは責任感かもしれないけれど、少なくとも家父長的匂いがします。家族に対して負い目はないですね。『黒猫』では家父長は母親でしたね。主人公に関する限り、『黒猫』の私の方に親しみを感じますね、小説としてもそちらに人間の本当の姿を感じます。

家父長か。こんな言葉よく知ってるね。戦前の日本の社会を成立させていたのが家父長制だなんて言われるけど、今君たちの家庭で親が独裁的権力を持っているなんて家ないだろう?頼りになる親がいる家はあるかもしれないけど、権力を持つ親はなかなかいないんじゃないかなあ。そういう面では、尾崎一雄はそういう匂いを感じさせる作家だね。そう思わない人もいると思うけどね。

これは、彼のお師匠さんというか、目指した人が、志賀直哉だったこととも関係すると思う。その精神的な強さは正直私なんかも非常に惹かれる。自我を発揮することこそ正義だなんて、そうありたいよ。小説にもそれが出てるよね。
対して、島木健作は苦労して学校を出て、そこから左翼運動に加わり、しかも実は権力によって転向させられているんだ。転向って前にやったね、誰の時?そう、中野重治だ。たぶん中野重治も島木健作も一生その事実を背負って生きていったんだと思うよ。太宰なんかもそうだよ。どこかで自分の敗北感がからだに張り付いているんだろうなあ。
作者のことをあんまり話さないようにしたいけど、やっぱりどうしてもね。尾崎氏は本校の先輩だし。前に言ったよね……、覚えてない? うそ――!

私は両作の二人の「私」ともに家庭人としての責任感を感じますよ。少なくとも、小説の中の「私」は自分の健康も、その家族への責任という意味で捉えているような感じがします。『城の崎にて』も昆虫や小動物からの学びがありましたが、それよりむしろこっちの方が私には感動がありました。

そうか。その比較も面白いテーマだね。



コメント