
名作だ、という話は聞いていたんだ

学校の授業に相応しいかどうかわからないが、私自身ながく気になっていたのに読んだことがなかった作品だった。
読み始めてしばらくして話に引き込まれてしまった。なんとなく今まで手を出さなかったが、どこかで日本文学の代表にもなる名作だと批評していた人がいて、読んでみると確かに名作だと思ったわけだ。人物が類型的で、単純というふうにも思えるし、通俗的ということも言われるが、それでもやはりいい作品だと思う。

信州の山間にある村「根っこ」と呼ばれている家におりんが嫁に来たのは五十年も前のことだった。亭主はとうに死んで今息子の辰平と辰平の息子と住んでいた。辰平の嫁は去年死んでいた。
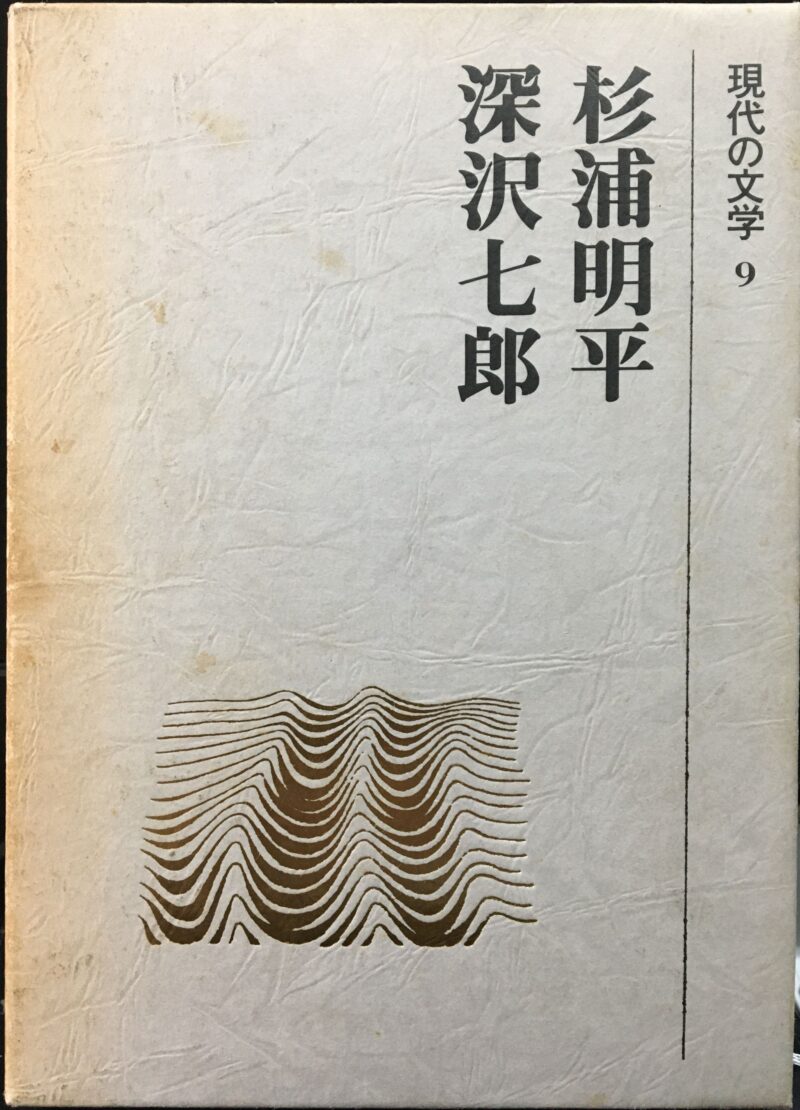
この村では七十になれば楢山まいりに行くことになっていた。彼女は今年六九だった。辰平も母の楢山まいりを気にしていた。
村では山に行くというと、仕事の意味ともうひとつ、冬に神の住む山に行くことを意味した。おりんは楢山へ行く準備をしていた。歳を取っても歯が達者であることを恥ずかしがって自分の歯を欠いていった。食糧の乏しい村ではなんでも食べられる歯はむしろ忌むものだったのだ。村ではよく昔からの俗謡を子供なども唄ったのであるが、おりんの健やかなことを意地悪く唄うものもいたのであった。おりんの孫もその歌を唄った。
根っこの隣は銭屋といった。村一番のけちんぼで、七十歳の親がいても山へ行く支度をしていない。その隣は焼松といい、またその隣は雨屋、またその隣が榧の木。多産の家は四代も続くと食料の乏しい家になる。そのため唄にされて老人は馬鹿扱いされた。
おりんは息子の後妻を気にしていたが。向こうの村で後家ができたと知らせが来て、ほとんど彼の後妻は決まってしまった。彼女は玉やんといって辰平と同じ四十五であった。
辰平の後妻をおりんは待っていたが、孫のけさ吉は家政は「俺の嫁がする」と嫌がった。けさ吉は池の前の家の娘の松やんを貰うつもりだった。ここでは晩婚が奨励されていた。
三十すぎてもおそくはねえぞ。一人ふえれば倍になる
という唄は、独り者に嫁がくると食が倍になると諭したのである。

祭りの日、向うの村から玉やんがきた。おりんは彼女が気に入ったようだった。おりんは山へ行くときに村中に振る舞う食べ物ややまべ(魚)をつかまえる場所を玉やんに教えてやったりしていた。松やんはよく飯を食べた。そして妊娠した。おりんが山へ行くことを孫のけさ吉は早くいった方がよいと言ったが、玉やんはおそくていいと何度も言った。おりんは山へ行くときには銭屋の又やんなんぞとは違って、村人への振る舞いを祭りの時以上にするつもりだった。米も椎茸も乾やまべも腹いっぱい村人に食べさせて、山へ行って新しい筵を据えてきれいな根性で坐ろうと考えていた。
一晩中風が吹いた夜明け、焼松の家に忍び込んで盗みを働いたものがいた。雨屋の亭主だった。それに対して村では掟があり、その家の食べ物全て奪って分配してしまうのである。雨屋からは他の畑から抜いた芋が出てきた。雨屋は十二人。「泥棒の血統だからうち中の奴を根絶やしにしなけりゃあ」と言い合っていた。村中が食い物の心配だった。

その日辰平が突然「おばあやん、来年は山へ行くかなあ」と言った。おりんは「わしだって行かなきゃア」と言った。玉やんは、赤ん坊が産まれたら「わしが捨ててくる」と、またけさ吉も「おれがぶっちゃる」と言う。松やんも「たのんだぞ」と言った。
おりんは辰平の顔を見た。急に辰平がかわいそうに見えた。冬を越すことも苦しいし。楢山まいりの供も、自分のことを考えてくれる息子を彼女は思った。石臼の音が止まって玉やんが飛び出して、前の川へ行って顔を洗っていた。
あと少しで正月という日「山へ行った人たちを今夜呼ぶ」とおりんは言った。人が集まり、掟、しきたりを聞いた。山中では、言葉を発してはならないというしきたりだった。
その次の夜、辰平の背負う戸板に乗り山を目指した。楢山頂上近くに来ると、岩影に死体があった。岩があるとそこにまた骨がある。頂上付近でおりんは足をバタバタさせて、降ろすように催促した。岩影に筵を敷き、辰平に自分の分の白萩飯(白米)のむすびを持って返そうとする。辰平は怒ったそぶりでそれを拒否した。おりんは筵の上にすっくと立ち、辰平の手を握り、そして辰平の背中をどーんと押した。帰りを促したのである。辰平は歩み出したが途中で雪が舞ってきた。辰平はまた禁止された道を登り、掟を破っておりんに叫んだ。「おっかあ、雪が降ってきたよう」と。おりんは何回も手を振り、帰れ帰れと手を振った。

下りる途中で、銭屋の息子が父親を崖から突き落とすのを見た。父親の又やんを倅は指をはがすように突き落とそうとしていた。しまいに倅は又やんを蹴とばすと又やんはごろごろと転がり落ちていった。
家ではけさ吉が酔っているらしく、「運がいいや、雪が降って。おばあやんはまあ、運がいいや。ふんとに雪が降ったなあ」と感心していた。辰平は玉やんの姿を探したがどこにも見えなかった。

「棄老伝説」、つまり老人を家から山などへ連れて行って捨ててくる、という話で有名なのは『大和物語』にある。中国やヨーロッパ、アフリカなどにも広く分布している話だそうだ。地名としても各地に残っている。有名なのは長野県更級だな。姥捨という駅もある。さて、深沢七郎のこの小説。実は映画にもなっているんだが、私はみていない。なんだか暗くて嫌な話、という感じがしたから。しかし、小説は名作だという声が高く、そういう評価は知っていたので改めて今回読んで見た。
みんなはどう思うか知らないが、正直私はショックを受けるくらい名作だと思ったよ。
それはともかく、またこの『楢山節考』についてもやってみよう。まずは感想があったらどうぞ。

二知 恵という女子、あまり喋らないが今回初っ端に発言した。いつも鋭い目線で先生を追っている子だったが、はっきりした発言をした。いきなりの批判だった。
むごいし、気持ちわる〜

私はこんな小説授業で取り上げるべきじゃなかったと思います。読後の後味の悪さは学校にふさわしくないと思いました。一応最後まで読みましたよ、でもここから何を学ぶんでしょう。
悲惨でむごたらしい話ですよ。山に母親を捨てに行くところだけではなく、ずっとむごく、そして利己的な人々の描写が続いていくだけじゃないですか。先生はどういう点でこれを評価するんですか?

そう?それは悪かったねえ。もしかしたらそういう感想が出てくるんじゃないかなとちょっと私も心配していたんだけどね。教科書には絶対出てこない小説だよな。
ただね、これをいっぺん読んでおくか、読まないかっていったら、読んでおいた方がみんなのためにはいいんじゃないかと思うんだ。無理強いしたようで(というより、ずっと無理強いなんだが)すまないが、まあこういうものを読むのも経験だと思ってくれないかな。これ気持ちの悪いホラー小説なのかな。

そりゃあそうですよ。老人の命を捨てさせるということになんの疑問も持てない。とくに孫のけさ吉なんてとんでもない奴です。フィクションにしても、こんな人間は許せない。

でも二知さん、この「おりん」というお婆さん。うちの婆さんがこんな感じだったから好感度高かったよ。しかも悲しくて仕方ないくらいだった。婆さんが死んだ時のことを思い出しちゃった。

確かに、この物語に読者を救ってくれるような人もいるな。おりんと息子の辰平だよな。もう一人いたな。

「玉やん」でしょ。それは感じる。でも、この結婚形態の安易さというか、それも私の嫌なところ。この三人によって、小説が読めてしまう、というところはありましたけどね。辰平が母親を山に置いてくるのに一言も声を発せずにいたなら、つまり掟を破ってでも母親に声をかけるようなことがなければ、物語の読者への衝撃も全然違ったものになったでしょうね。
ということは、私の拒否感も、小説からの影響を受けている証、ということかしら……。


そうなのよ。優しくて、いい男なのよ。それで、その辰平はオレなのよ。

こらこら。こいつとんでもないやつだ、と僕は思ったが、この教室の中の男子で、自分が辰平だと思った奴はけっこういるんじゃないか。正直いうと僕もそうなんだ。
そして、この捨てられる場面はおりんにとっても望ましい、正しい人生の完結のあり方ということなのかもしれないな。死体だらけの楢山は決してホラーの描写ではない、ということかも。
美しい死とも言えるんじゃない?

私もしばらくして、雪が降ってお婆さんは凍え死ぬんだろうけど、それもいいんじゃないかって思っちゃって。ごめんね恵ちゃん(二知)。

ただ、言っちゃあいけないかも知れないけど、このおりんさん、見栄っぱりですね。でも、それを貫いた。みんなが食糧不足という絶対条件の中でなんとか生きてきたんですね。ここを、今の感覚でどうこう言ってもどうしようもないし、七十歳になったら山へ、という掟も、その中で生きて、捨てられるっていうことをなんの疑問も持たずに従う人々。それをどうこう批判するのもちょっとおかしいとも思う。今の私たちだってなんの疑問もなくしていること、おかしいことだらけじゃないの。日々そのおかしな行動や習慣を繰り返して生きているんだよね。
この「根っこ」と呼ばれている家じゃあ、おりんは山にいかなければならない経済状態じゃあないみたいよ。それなのに山に行かなきゃならないことを疑問なく受け入れている。本人も、息子も、あくたれ孫も。だからこそ、美しいという感覚を私は持っちゃうのかも知れない。
最後のおりんの立ち姿はやはり美しいですよ。
私、演劇部で、なぜだかおばあさん役をさせられることが多いんですよ。時々いやになっちゃうんですけど、おりんの役ならやりたいですね。

それにしても、この話は、私は嫌だったよ。泉ちゃん(原)の言うことも理解できないわけではないけど、つまり私は生きるっていうことが罪だというのが低音で聞こえてくる感じがするのよ。それが嫌だったの。


そしてもう一つ。どうもそれぞれの人間性が一面的じゃないかっていうこと。ダメな家の連中はなんでもダメで、いい人はずっといい。玉ちゃんは天使みたいよ。それってあり?銭屋の又やんなんか最期まで……。あれが人間なのよ。だから同情しちゃうよ。だいたい私は死後の世界を夢見る、なんていうことは嫌いだ。それは現世の世界の弱者の世迷いごとですよ。もっと人間は強くなくちゃあ。

そうだねえ。それもごもっともと言うしかない。近代小説としてどうなの、という感じもするし。一方で、現代にだってイニシエーションに従って私たちは生きているんだということ。玉ちゃんみたいな人はむしろ庶民にはいっぱいいるだろうし。善人悪人という簡単な類型でもないような気もするんだがなあ。こういう感想は教員は言わない方がいいのかも知れないが……。
小説なり詩なりの効用として、古来カタルシスという語があるのを知ってるか?えーと、ほら大野!

へいへい。カタルシスね。……アリストテレスの語。悲劇の与える恐れや憐れみの情緒を観客が味わうことによって、日頃心に鬱積しているそれらを放出させ、心を軽快にすること。浄化。です。

ということもあるな。
それからもう一つ。村の共同体というものの持つ根本的ないやらしさだ。私、これを感じたねえ。
日本人のエゴイズム・ムラ意識


そうよ、先生。この人たちの社会は本当に嫌いだわ。それぞれの屋号で、それぞれのエゴイズムがはっきり出てて、悪口言い合って。ほんと日本的だよ。これも気分悪くなるモト。

いやー、二知さん、飛ばすねー。けど、だんだん授業しているおじさん先生の術中にはまってきちゃったんじゃない?

作品に出てくるこういう下地がずっと続いてて、日本では21世紀の今日でも亡霊のように田舎では生きているらしいわ。地域に生き残る呪縛よ。これは、そういう物語なのかも知れない。

ということは、二知。考えようによっては、どうにもならないくらい暗く、苦しい生活の中にこそ綺麗な花が咲くんだということじゃないかな。

ちょっと先生、あたしはまだこの小説を評価していませんからね。きれいな花とか言いますが、おりんは山に行かなくても家族は生きていけたかも知れない。「根っこ」の家では冬を越せたかも知れない。だって、おりんは結構な蓄えを作っていたんですからね。
つまり彼らは七十になったら山へ行く、という合理的でないイニシエーションに従って楢山まいりをするんじゃないですか?これこそ誰も気づかないおりんの罪なんじゃないですか?そして、かわいそうですが、おりんの判断基準はいつも見栄なんですよ。他人からどのように見られるか、というのが彼女の価値判断なんです。ちょっと言い過ぎかも知れませんが。

そうかな。ついでに、『笛吹川』という小説についても一言紹介しておく。武田信玄が活躍していた時代の庶民を描いている。甲州という風土と戦国時代という中で理不尽な力によって流されていく人々、その人々が狭い人間関係の中で憎んだり、好きになったり、嫉妬したり、バカにしたり……。でも私は一気に読んでしまった。やめられなかった。
さて最後に批評家たちがどのように評価しているのか例として示しておこう。
この小説の舞台となったムラは、銭など使い道のない山奥の孤絶したムラであって、ぎりぎりの食物しかとれず、食べることをめぐって、すべての秩序がつくられている。人間の尊厳を許さないこの世界では、棄老も集団制裁もごく自然な習俗としておこなわれていて、日常の全てが調整されている。こうした自然化された自己調整の意志(タブー)にしたがって行動していた人間がおりんであったわけで、この小説では、おりんの詩の準備とお山まいりの儀式だけが描かれていた。あるいは、〈通過儀礼〉としての死の準備の過程だけが、時間の順序にしたがって描かれていたのが、この小説であったといってもいい。
こうした近代とはまったく異なった世界を描いた原図のうえに、この小説では、近代的ともいえる人物たちの動きが重ねられていた。人物相互のエゴの葛藤も、おりんの家族たちの行動も、近代の人間概念の常識をはみ出すことがなかったというよりは、むしろ、近代人のエゴと欲望が、力学的に、拡大され、確認されるかたちで描かれていたといっていい。
《……》
もちろん、この小説の場合、民話のオリジンに当たるものと、それが生かされた部分が、はっきり分けられていたわけではない。なるほど、棄老伝説が生かされていたことはたしかだが、それも、民族特有の記憶といった性格をこえるものではなく、小説のヴィジョン自体は、あくまでも作者のものだったからである。それにもかかわらず、そこに明らかにされたものの意味について、作者が十分に語り尽くしていたかといえば、そうとはかぎらない。そのことは、また別のことである。つまり、この小説では、作者のメッセージは、作者をこえてあったわけで、メッセージが作者をこえてあるという、文学作品特有の原理を認めないかぎり、この小説の考察もはじまらないことになる。
《……》
飢餓は、始原的な時代から、人間のあり方と結びついていた。むしろ、人間は飢えていたからこそ、動物的な自然から分離することができたのであろう。(正宗)白鳥は、「甘んじて滅亡するように生物はつくられていないので、足掻きながら藻掻きながら、一日一日を過ごしているようなものだ」と書いていたが、文化も文明も、そもそも人間が生活のなかで滅亡に抗して藻掻いてきた行為としてあらわれていたわけで、この小説は、そうした文明の構造を透視化していたと同時に、そうした藻掻き方をこえたところにこそ、本来の人間の尊厳、あるいは文化の自然があったことを示していた。精神的なもの、宗教的なものと一見無縁であったかにみえるこの小説は、実は、精神的なもの、真に聖なるものが発生し自立する土壌と気候そのものを提示し、伝えていたのである。
「楢山節考」黙示録的世界の牧歌 中村博保 『いかに読むか 記号としての文学』中教出版

難しいけど、言ってることはわかったかな?
そして村をなぜ「ムラ」と書いているのか、ということも考えてみよう。
この小説をただの気持ち悪い物語と考えたり、欲望むき出しの田舎者の話、とみるのとは異なる読み方が理解できただろうか。評論文を読む練習として考えてみて。

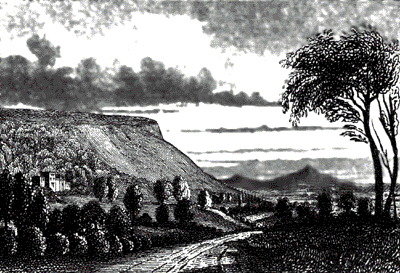


コメント