
今回も難敵 登場人物の感情を追うか、作品の新しさを追うか
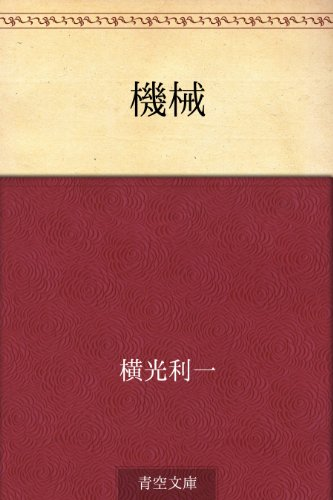

「私」は九州から出てくる途中で知り合った夫人のつてでその弟の会社に入った。薬品を扱う会社で、危険な仕事だったが、その仕事を頑張って覚えて将来に役立てようと思っていた。会社の中は使い道のない人間たちばかりで、その一人が軽部という男だった。彼は「私」を仕事の秘密を盗もうとしていると疑るが、社長は私を認めてくれているようで、軽部を差し置いて「私」に仕事を教えてくれる。軽部はそのことに我慢ができず、「私」に暴力を振るう。私は軽部の人間的レベルを軽蔑するが、そういうところがまた軽部を怒らすのである。
その後仕事が忙しくなり外部の会社から応援を招く。屋敷というその男に対して今度は「私」が疑いを抱く。今まで軽部に対していた立場から屋敷の場合は逆転してしまっていることを「私」は自覚する。
ある日屋敷が会社の重要な事項を盗んでいたらしいことを軽部が発見し、二人が格闘となった。それに「私」も加わってしまい、三つどもえの暴力沙汰となるが、その後いちおうはおさまる。
主人は製品に対する意欲は非常に高く有能だったが、外に出ると必ずと言っていいほど金銭を落とす。非常な忙しさの中で頑張ってきた成果の売り上げを、それを主人がやってしまった。売り上げを全部帰り道で落としてしまったという。この主人の奇怪な頭を持っている点が我々を惹きつけるところでもあったので怒ることもできず、ただ酒を飲むだけだった。この三人の酒盛りの際に屋敷が間違えて薬品を飲み、死んでしまった。
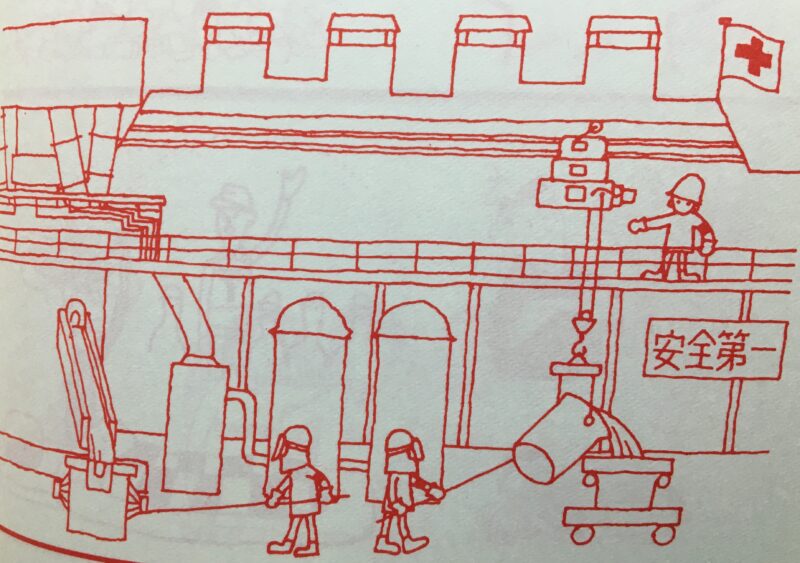
疑われたのは軽部だった。しかし、酔ったときに「私」が屋敷を殺さなかったとどうして断言できよう。「私」はもう自分が分からなくなって来た。「私」はただ近づいて来る機械の鋭い先尖がじりじり「私」を狙っているのを感じるだけだ。誰かもう「私」に代って「私」を裁いてくれ。「私」が何をして来たかそんなことを聞いたって「私」の知っていよう筈がないのだから。

これも不思議な話だろう?まあとにかく自由に感想など言ってみなさい。
段落なしや会話文の表記法にストレス

なぜ段落をつけないの?6つしかない。それから、かぎかっこで会話を示していないのも変なストレスを与えるよ

なんかあ、美しいものとか、正しいものとか感動を教えてくれたりするのが小説ですよね。今回のこの講座はそういうのが少ないけど……。でも、これも本当に何言いたいんだろうって感じ、正直……。
大体「正義は必ず勝つ」とか「現実には悪が闘争して勝つこともあるんだ」とか、そういう話ではないし、汚い薬品によって美しさが生まれる、なんていう意外感もない。

わたしは、書き出しから、危険な薬品を扱う、非人間的な職場という感覚から、またプロレタリア文学かと思いました。基本的な労働の基準を無視した、中小企業の現場の話かな……と。昭和の初めってこんな工場ばかりなんですかね。
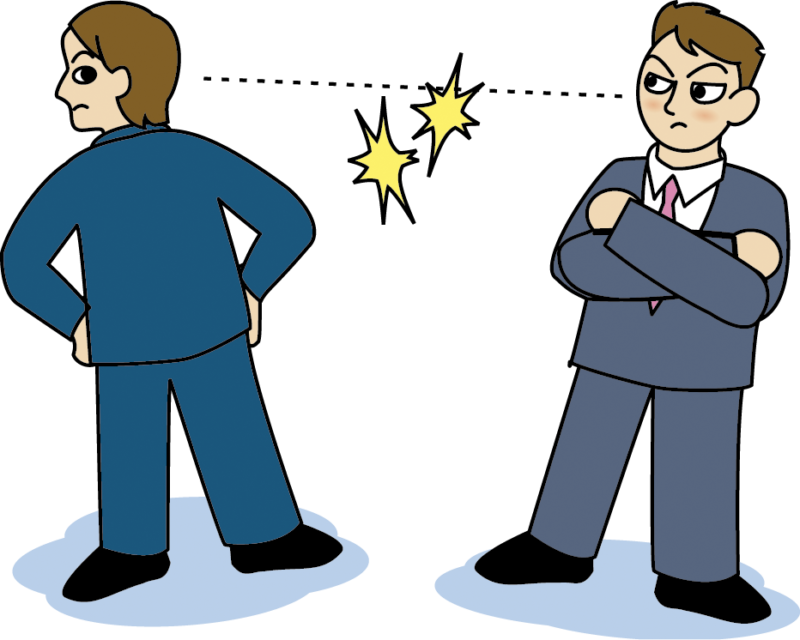
ところがそれが全く違う展開。この話のキーワードは私の見方では「嫉妬」ですよ。悪役の仕事は一手に資本家や会社の上司が受け持つのがプロレタリア文学でしょう?ジャンルは違うけど、それがこの小説では軽部という人間です。それを「私」は、バカにして、軽んじる。だからこの「私」こそが悪役にふさわしい。しかもそのことを十分意識できている、という複雑さ。なんだか訳わかんなくなっちゃう。

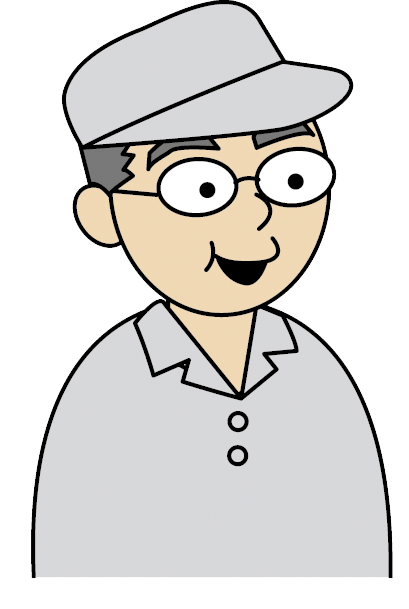
それで、悪役であるはずの資本家役の「主人」は結構いい奴だったりする。金儲けだけじゃなくて仕事の内容や自分の研究の成果にこだわりを持っている。金を持って外に出ると必ず紛失する、という非現実的な人間設定は、荒唐無稽だが、決して嫌な感じはしないよ。この小説はまことに奇怪だ。
そこにもう一人乱入。この屋敷っていう人はどうなの?

この人がまた不思議な位置に立っている。同業の工場から「手の空いた職人」を借りてきたと言っている。「手の空いた職人」と実際の屋敷という人物とは合わないじゃないか。もっと”できない”人物が来るべきでしょう?この人物に軽部は「私」への悪意のひとつの手段として近づいていく。「私」は軽部の心理を引き受ける形で屋敷を見る。そして疑う。三つどもえの闘争となっていく。どいつもこいつも悪役の資格があるようじゃないの。実際に他人の発明を盗むことは社会に対して道徳な行為だとわたしは考えている。

だからと言って、善悪が絶対的なものではない、と読者は読み取る必要はないだろう?作者はどちらへも誘っていないと思うけどなあ。

そうですね。別にこの善悪について何か感じることはないですね。
「私」も軽部も、お互いさま。それが「私」にはわかってる

善悪の相対化というのかな、それが読者に響いてくるとも読めないがねえ。つまり善と悪が絶対なものではないという主張、ということよ。

で、そのうちに軽部が今度は屋敷がスパイであることを見てしまって、殴りつける。軽部はわたしの方も疑って三つどもえのケンカになる。

それって、何を言いたいのかなあ。
「いったい本当はどっちがどんなふうに私を思っているのかますます私にはわからなくなり出した」とあるけど。

つまりね、どうもそういう「何を言いたいか」という話から脱却しなければならないんじゃないか。僕は筒井康隆の小説を思い出す。

ずっと前に、『俗物図鑑』っていう小説を読んでびっくりしちゃったんだけど、要するに描かれるのはドタバタなんだよ。その小説全編がドタバタ劇とは言えないと思うんだけど、登場人物に良いも悪いも、ない。善悪美醜を全部超えちゃったスラップスティックという物語なんだよ。チャップリンの映画って警官と労働者と通行人と……みんながごちゃごちゃ殴ったり蹴っ飛ばしたりする場面あるでしょ。それなんじゃないかという気がしていた。この『機械』も全てがそうだとは言えないけれど、従業員三人の軋轢はまさしくこのスラップスティックを連想させるものだと思う。なぜだかわからずある男がある男を殴る、なんていうのは小説の進行に意味ないでしょう?

ただ三すくみの闘争という見方から離れると、各人の感情の推移の物語という側面があると思う。たとえば「私」は入社時は 偶然の出会いで決め、入社直後は自分の将来のための実力涵養のために仕事に向かい、さらに主人に仕事が認められるようになると軽部への軽侮と主人に対しての承認欲求が満たされているという、ちょっと甘美な気持ち。そしてその後の屋敷への疑惑から三人のわけのわからない和解。まとめられないけど、そんな感情の変化が語られている。結構「私」も不思議な感情を持った人ですよね。
するとこれは「私」の感情変化の物語として読めないこともない。ちょっと自分でもつまらない解釈と思うんですけどね。

三すくみ、といえば勝者はいるよ。
「いったい人というものは信用されてしまったらもうこちらの負けで、だから主人はいつでも周囲のものに勝ち続けているのであろうと……」と「私」は言っている。この小説で一番おいしいところを取っているのが主人だね。この人はたぶん金を落としても、心理的に”腐る”ということはないんだろうな、羨ましい限りの性格だよ。持って生まれたものか、そうとうのタヌキだよ。
機械のように決められたように……

僕はそれがどうして『機械』という題名なの?と疑問を持ち続けてしまう。確かに人間同士、疑惑が生じたり、信頼されるのを感じたり、子供っぽい主人への好意を感じたり、嫉妬したり……こういう感情が語られていくんだけど、それが『機械』という題名になる。これがわかりにくいんだ。
そもそも機械って、どういうものか?前回カフカの『流刑地にて』を読んでいったけど、先生はたぶんその継続でこの小説を読ませたんだ。いやそうに違いない。そこで前回の機械とどこが違うか、僕はこの小説で「機械」という語が出てくるところを挙げてみた。小説では「機械」は4回出てくるんだ。その中で最初に出てくるのは主人が暗室で「私」にプレートの色変化について指導してくれた場面だ。
これは興味を持てば持つほど今迄知らなかった無機物内の微妙な有機的運動の急所を読みとることが出来て、いかなる小さなことにも機械のような法則が係数となって実体を計っていることに気附き出した私の唯心的な眼醒めの第一歩となって来た。
どうもここが大事な部分らしい。プレートの色の変化をさせるのに重要なのは、熱する時の色変化の途中の見極めだという場面だ。色変化の見極めは「機械のような法則」があることに気づいてそれを理解する職人的な感覚だ、というんじゃないかなと思ったんだ。それが「唯心的」っていう意味じゃないかなあと……。誤解している可能性も大いにあるんだけど、そう思った。
結局この題名は「機械=唯物的なものと、感覚=唯心的なものが結局融合してしまう」というわけわからんこの世界を描いてみたということじゃないかな。もうこじつけだけなんだけど。
ちなみに、あと「機械」という語が出てくるのは最後のほうで、
なるほどそういわれれば軽部に火を点けたのは私だと思われたって弁解の仕様もないのでこれはひょっとすると屋敷が私を殴ったのも私と軽部が共謀したからだと思ったのではなかろうかとも思われ出し、いったい本当はどちらがどんな風に私を思っているのかますます私には分らなくなり出した。しかし事実がそんなに不明瞭な中で屋敷も軽部も二人ながらそれぞれ私を疑っているということだけは明瞭なのだ。だがこの私ひとりにとって明瞭なこともどこまでが現実として明瞭なことなのかどこでどうして計ることが出来るのであろう。
それにも拘らず私たちの間には一切が明瞭に分っているかのごとき見えざる機械が絶えず私たちを計っていてその計ったままにまた私たちを押し進めてくれているのである。そうして私達は互に疑い合いながらも翌日になれば全部の仕事が出来上って楽々となることを予想し、その仕上げた賃金を貰うことの楽しみのためにもう疲労も争いも忘れてその日の仕事を終えてしまうと、いよいよ翌日となってまた誰もが全く予想しなかった新しい出来事に逢わねばならなかった。それは主人が私たちの仕上げた製作品とひき換えに受け取って来た金額全部を帰りの途に落してしまったことである。全く私たちの夜の目もろくろく眠らずにした労力は何の役にも立たなくなったのだ。しかも金を受け取りにいった主人と一緒に私をこの家へ紹介してくれた主人の姉があらかじめ主人が金を落すであろうと予想してついていったというのだから、このことだけは予想に違わず事件は進行していたのにちがいないが、ふと久し振りに大金を儲けた楽しさからたとえ一瞬の間でも良い儲けた金額を持ってみたいと主人がいったのでつい油断をして同情してしまい、主人に暫くの間その金を持たしたのだという。その間に一つの欠陥がこれも確実な機械のように働いていたのである。勿論落した金額がもう一度出て来るなどと思っている者はいないから警察へ届けはしたものの一家はもう青ざめ切ってしまって言葉などいうものは誰もなく、私たちは私たちで賃金も貰うことが出来ないのだから一時に疲れが出て来て仕事場に寝そべったまま動こうともしないのだ。
というところ。この辺もまさしくドタバタ喜劇そのものだな。でもまあ機械のようなものが私たちを「推し進める」のだ、という。機械とは運命のようなものとして私たちが服従しなければならないということなのかな。わけわからなくても運命のようにわたしたちの背中を押して進めてしまう力、こんなのを描いた作品。こういう読み方をしたらどうでしょうか。
そして、最後に出てくる「機械」という語は、
私はもう私が分らなくなって来た。私はただ近づいて来る機械の鋭い先尖(せんせん)がじりじり私を狙っているのを感じるだけだ。
というところだよ。これはその前の引用部と同じことを言ってるだけだな。

今「唯心論」って調べたら、
「心、もしくはその働きこそ至上の要因であるとする存在論における立場の一つ。」
とあるよ。「唯物論」の反対だって。
世界の全ての基礎はものではなく精神とか心なんだという考え方だろ。すると、おれたちを突き動かすものは機械だという表記はどういうこと?これ唯心論的な考えじゃないと思うけど。
むしろ、我々を押し込む機械に対抗する唯心論的なものの表象は三人が最後にたどり着いた共通のモノ。それは「酒」じゃあないの?でも酒を飲んだつもりで薬品飲んじゃって死ぬ軽部は、要するに機械に敗れてしまう人間。唯物論的ものに勝てない人間を表現している、とおれは読んだけどね、どう?少なくとも最後の一文では、人間が個人として主体的には生きることができないというところを主張しているような感じ。

その説明はなんか納得できるような気がするけど。でももう一度読んでみないとわからない。
ただし、もひとつ気になりながら読んだのは、何か表現手法で経験したことのない変な感じがしたこと。「私」って、妙に変な高みから見わたして説明してるような感じがしない?

それはおれも感じた。劇で、殴り合いの芝居をしている時にその一人の役者が同時にその時のナレーションをしちゃっているような感じがしたよ。
そしてやっぱり段落、会話文の独特なところだよ。何を意図してんの?

これは覚えておく必要はないけど、作者は「四人称」ということを言っているらしい。一人称の三人称化されている記述、とでもいうのかな。それと関係あるかもね。
あっちこっち疑問だらけだけど、その分勝手な考えができて面白い。『機械』という作品をそう読んじゃったんだから仕方がない、っていうひと言でみんな好きなように解釈をしてみようよ。じゃあ、まずよく考えて文章化してごらん。あえて難しい言葉を使わなくてもいいよ。

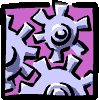



コメント