
ダラダラ?続く物語。それなのに意外に読ませる


明けましておめでとう。今年もよろしく。現実の授業なら1月に長編小説を教材にするわけないし、まして3年相手にこんなことできるわけないが、まあ妄想してるだけだから、どんな授業したっていいよな?
まあそこで、漱石以外の長編小説もひとつやってみようか。選んだのは『細雪』。ちょっとこれもどういう読みができるか、解釈するのが厄介だな。だいたい教科書には採択されない作品だろう。どの部分を抄録できるかということも想像できない。読んでいて、なんか主張しているわけでもなく、なんだかある家族の戦前戦中のたわいない生活が描かれているだけ、という感想しか持てない。確かに彼らには日々問題点が噴出する毎日なんだろうが、この時代の人々にとっては、なんという夢のような生活!という感想しかないだろう。まさしく太平洋戦争前までの都会の上流階層の生活ということかな、本人たちは中流階級と考えているようだが、気持ちとしては当時の最も平安な人々の毎日が描かれているという印象だ。
今回私は二度目の『細雪』だが、読んでいて妙に面白かった。一度目はちょうどみんなと同じ高校生の頃読んだんだが、その時も面白く感じていたことを覚えている。どこが面白かったのか、は全然記憶にないし、今回もこんなシーン記憶がない、というところがいっぱいあったけどね。
作者は谷崎潤一郎だね。有名だろ、知らない?文学史の知識として『刺青』くらいは覚えておいた方がいいかもよ。これは全然面白くなかったなあ。なぜこんな小説が文学史の教科書に載っているのかわからんね。でも、谷崎自身は今でも一部のディープな文学好き高校生にも強い人気がある。専門の研究者や実作者にも。
谷崎はこの市に住んでいたこともあるんだよ。年譜によれば1919年、大正8年に転居してきたとある。この地で佐藤春夫と谷崎夫妻の間で問題が起こり、佐藤春夫の有名な『秋刀魚の歌』という詩ができる原因になったことは知ってる?まあこんなことは知らなくてもいいが。

さて、『細雪』だ。あらすじはネットにあったから、これを借用する。
これを読んでみても、小説本文を読む気はあんまりしないだろう。つまり簡単に言えば、ある関西の裕福な商家の次女の縁談の有様を中心にして、四人姉妹が生活していく様子を描いた長編小説、とでも言おうか。あるいは大阪の旧家を舞台に、四姉妹の日常生活の悲喜こもごもを綴った作品、と説明しているものもある。
しかし、私が『細雪』を読んだ後の印象は、面白かったけどたわいのないお話、というものだった、正直にいうと。たとえば『こころ』とも違う、あるいは『暗夜行路』とも違う。あるいは誰か言ってたけど、(中学生の頃に読んで感銘を受けた)『次郎物語』とも違う。小説がそれぞれ違うのは当たり前だが、何かモヤモヤした、感動というものとは程遠いあやふやさ。これが『細雪』だったね。
だいたい結末らしい結末がない。「何?これ。未完で終わっちゃったの?」という、非常に不満な結末だった。確か「おしまい」とか書いてあったんじゃないかな。ヤマ場といえばたぶん関西大豪雨の場面かもしれないが、それもまあなんということもないエピソードと言えるだろう。それでまた文体が、悪くいえばダラダラした感じ。内容と言っても大事件はないし、生きることの切迫さもないし、何かというと見合いの話ばかり。こういうとどうしようもない小説、という評価しかできないんだが、でもそうじゃなく傑作なようにも思えてくるんだ。
さて、みんなはこの小説をどのように解釈する?あるいは、感想でもいいし、思いつきでもいいよ。印象に残ったシーンや登場人物でも構わないけど。

僕は実は『細雪』をまあ読んでみるか、と思いながらこの2週間くらい手をつけることができなかった。やはり長い。長すぎる小説はよっぽどワクワクするような話でなければ続かないと思ってしまった。今回はどういう物語解釈になるか、あらすじだけを頼りに聞いてみるより仕方がなかった。みんなこの長い小説をまさか全編読んできた生徒がいるとは思えないが、と感じていたのだが、触毛が突然挙手し発言した。

先生。僕、この3週間で『細雪』を読破してきました。これまでにない体験です。面白かったですよ。
「へえ!読んできたの?君すごいね。」

自分でも驚いてんです。それに先生には悪いけど、こんなことしてていいのかという気持ちでもありました。オレ、理系なんですよ。こう言っちゃあなんですけど、今の時期に小説を読ませる授業なんて、出席してればそれだけでいいくらいのもんでしょ。それがなんか、この関西の空気感から離れられなくなっちゃって。だから、今回だけは発言させてもらって、後の授業はまたモグラのように教室に隠れさせてもらいたいんですけど…。

まあ、そうはっきり言われちゃうと、ちょっと私も困るけど。まあいいから、感想なりを言ってみな。
雪子の結婚は決着せず。しかもおしまいは下痢って……。

はい。わたくしは(と彼が言い出した途端、誰かがプッと吹き出し笑いした。)この『細雪』は闘争のない物語だと思いました。闘争で勝つ、負けるということのない、そういうこととは無縁の話というふうに感じたんです。今までわたくしが読んできたものには、必ず何かの対立が中心問題としてありました。その闘争や競争によって、ハラハラしたりヤキモキしたりするその感覚こそが読者の小説から受ける作用だったんです。今回は実はヤキモキしたことはしたんですが、その感情が勝つか負けるかではなく、決着つけてくれるのくれないの、という観点で起こるんです。で、決着つかないで終わるんです。わたくしは、むしろこういうのが世の中なんだ、と教わった気がしたくらいです。

えーと、四女の妙子。最後の方で、赤ちゃんが死産だったというふうになっていますね。これでこの家は世間体的に救われたんですかね、バーテンだった男との間にできた子が死産で、妙子が救われたという、なんかそういう読み方に誘導されているような感じがして、わたくしは、問題は中途半端なままだという感想を持ちました。
それで最後の雪子の東京での挙式のための旅。この途中での下痢の話で終わるんです、小説が。妙子のいろんな事情を雪子の相手がたに知られないようにしている挙式。この車中の雪子の腹具合の話で終わるんですね。これで挙式がうまくいくにしても、全てめでたく終わる話になるわけないでしょう?そういう解釈がこの小説にはあるみたいじゃないですか。それこそ小説の『行間を読む』ことに反してませんか?

結末については、私自身も君の意見に賛成だね。そして、解決されない問題の連続という視点は面白いね。また後でも私の意見は言うよ。
他の人はどう?ちょっとでも読んでみて、何か感じるものがあれば言語化してみてくれないか。この講座の目標はこういうとこにもあるんだから。読み流さない訓練とでもいうかね。
尽明さんがチャレンジしてみた。『舞姫』の時も冷静で厳しい発言をしていたな。

わたし、長編小説というものをまともに読んだことないし、興味もなかったんだけど、このまま大学へ行って他の人が普通に語る読書体験っていうのかなあ、そんなものを知らないのもどうかと思って『中』まではザーッと読んでみたんです。食わず嫌いだったということを素直に感じました。ただし何か訴えてくるものはないような感じがして。これ映画にもなってるんですよね。ネットで予告編とか流れていて、そんなのも見てみたんですが、実は美人女優の皆様のおそろいでどうやらこうやら…、とこれも面白そうじゃなくて。結論としては興味は湧きませんでした。
長編小説って、何かきちっとした設計のもとに、すみずみまで構成を考えて話が進んでいくようなものじゃあないかって思ってたんだけど。それである事件や体験や観察が後々の結果につながっていくような、建築物のようなイメージを持っていました。映画とかドラマとか、「あああの時のあのエピソードがこういう結果になるのか」っていうような納得感がないと、感動もないような気がしていました。この小説はどうもそういうところがないような気がするんだけど、どうですか?
佐々木も口を出した。

僕も長編というと、アニメの『ワンピース』を連想したなあ。あれなんか一つの騒動というか、事件があってそれを乗り越え乗り越えして話が進んでいったけど、それぞれのエピソードがある程度の満腹感というか、小さな解決みたいなものがあって、そういうものがないととっても読者、視聴者にはついて行けないよな。僕は『細雪』読んでませんけど(すみません)、そういうものがあるんですかねえ先生?単純に言えば、それぞれのエピソードとそのエピソードが全体のどういう位置にあるかをはっきりさせて、バラエティーを広げるという手法がないと読者は裏切られてしまうんじゃあないですか?

なるほどね。読者も物語についていく何かを作者に求めていきたいところだよね。
ちょっと先にまずひとつ問題を語るよ。
今思い出したんだけど、前に「物語の文法」っていう話をしたろう?覚えてない?それと関連して「期待の地平」という言葉も知らせたかな。
前にもちょっと紹介したジョナサン・カラーは『文学理論』の中でこう言っている。
…もうひとつのタイプの読者中心の現象学的批評は、「受容の美学」(ハンス・ローベルト・ヤウス)と呼ばれている。この批評では作品は「期待の地平」によって提起される問いへの」答えであるとする。したがって作品の解釈は、個々の読者の経験に焦点を合わせるべきではなく、作品の受容の歴史に、さらには、別の時代になってもその作品が読まれることを可能にする美的規範と期待の変化とその受容史の関係に焦点を合わせるべきだとする。
と。難しい“現象学的”という言葉に引っ掛かっちゃうかもしれないが、これはつまり証明できないような根本的な問題や言葉はちょっと置いといて、意識にのぼるこの世界についての記述をひとまず認めるように考える、ということだ(と思う)。現象学的批評とは、ひとまずこの世界で普通に認める範囲で考えられる批評、とでもいうことかな。現象としてあるこの世界で認める批評、とかね。つまり読者が読みながら、自分で文の隙間を埋めて意味を見出していくさまを分析するということなんだろう。
また、こんな文章も本の中から発見したよ。
時間性をめぐるフッサールの議論からとられたこれらの用語は、読者の家庭の基礎をなす「修正された期待」と「変形された記憶」を指すものである。テクストを読むとき、われわれは、絶えず、未来への期待を念頭におき、過去を背景として評価と知覚を行なう。期待していなかった事態が生じることは、それゆえ、われわれが、この出来事にしたがって自らの期待を編成しなおし、すでに発生したことがらにわれわれが賦与してきた意義を解釈しなおす奇縁となる。
「空白」を読む RCホルブ
《……》
このような読書経過の叙述の背後にあるのは、「一貫性希求型」とでも称すべき前提である。テクストを構成するさまざまな記号あるいは層に対峙するとき、読者は、それらの振る舞いに統一性を与えるような関係を想定しようとする。イーザーは、意味生産に携わる過程において読者は形態(ゲシュタルト)を形成しようとすると仮定する。想像上の形態と齟齬をきたすようなことが生じると、読者は、一連の補正作業を行なうことにより、状況をふたたび一貫性のあるものにしようと努める。まさに、「幻影の形成と中断という一種の弁証法」こそは、それに関連する「幻想にひたったり、あるいは距離をとって観察する絶え間のない浮動状態」と並んで、美的対象を構築する基盤となり、テクストをめぐる経験を「なまなましい出来事」として解き明かすものなのだ。たとえテクストの意図が、ー現代小説で見かけられるように…一貫性を拒絶するところにあったとしても、その意味の生産に関与する読者は、一貫性形成を原理とすることによってのみ、そうした結論に達することができるわけである。
さあ、難しいことになってきちゃったね。こういう文章にみんなも慣れていってほしいと思って、紹介してしまったんだが、なんかちょっとでも、「こんなこと言っているのかなー?」っていう感覚を養ってもらいたいと思ってね。
実を言えばわたしも自分が本当にこれらの思想書の内容をちゃんと理解しているかどうかが、いつも心配なんだよ。自分が大学生の頃にはこんな文章を読んでレポートとか卒論とか書かなかったしね。全部読書による独学。だから本当はどこかの先生に確認してみんなに砕いて話をしたいんだが、なかなかそういう機会もなくてね。でも、まあ完全な当たりではなくても、大きくは間違いないと。だからもう一度。この文を読んで、なんとなくでいいから、何を言いたいのか頭の中で理解できますか?って言うんだけど、どう?」

問題は「期待の地平」とは物語の中でどういうことをいうのか? 以前からよくわからないような感じがしていたが、まだそんな気持ちがする。
でも、僕はその話はなんとなく少し理解できたような気がした。
目指すところは何?

はい。よく理解できているのかどうかわからないけど、自分なりに言ってみたいとおもいます。
まず、僕たちは毎日毎日物語を作って生きているということ。
だから、映画や人との会話なんかもそうだけど、小説を読むときには、自分の物語を下敷きにして読んでいる、ということ。
しかし、それは自分に都合よく結末を、あるいは話の進み方を予想して事前に進む道を決めているのだ、ということ。
ところがそれは自分の自由意志で決めているのではなく、実は前からある進行方向を無意識のうちになぞっているだけだということ。
現実の物語進行がその道筋と違ってくると、作者の意向と折り合いをつけながら受け入れていくんだということ。
そういう読者の予想の目標地点を「期待の地平」という。そんで、それは作品によって修正されたりしていき、自分の新たな意味を作ることになる。
てなことですか。なんか前からの話を付け加えちゃって、今日の問題の答え以上の余計なことまで言っちゃったような気もします。すみません。

いやいや圭。私の言いたいことをうまく言ってくれてるよ。『細雪』もそういう「期待の地平」を持ちつつわれわれは読んでいってる、ということを言いたかったのよ。でも、こういう作品受容のありさまについて反対だという意見ももちろんあっていいのよ。私は「期待の地平」なんてもんは認めない、という人があってもいいし、日々物語を生成しながら生きている、という前提に違和感を持つ人も大勢いるだろうし。ただ、いま君たちが置かれている受験生という状況からしても、意味なく生きるというのは無理だろうね。

でも先生。この『細雪』っていう小説、私たちの描く「期待の地平」に全く外れているじゃあないですかあ。少なくとも結末はそうでしょ。作者の意向には従おうって思っても、その意向もはっきりしない。つまり尻切れとんぼですよねえ。これは失敗作じゃないんですか?
「そう思う?」

だってねえ。話のスジを、抽象的に説明することができないような…。それに登場人物たちに私ちょっと反感を持ってしまったのもあって。
「そう、そこはおれも思ったよ。だいたい貧乏人や庶民をないがしろにしてやがるんじゃないか。」
「そういうところを問題にしてもしょうがないよ。」
「でも、使用人たちとご主人様たちは差があって当然です、みたいな雰囲気は問題にされないの?それが名作だなんて…。」
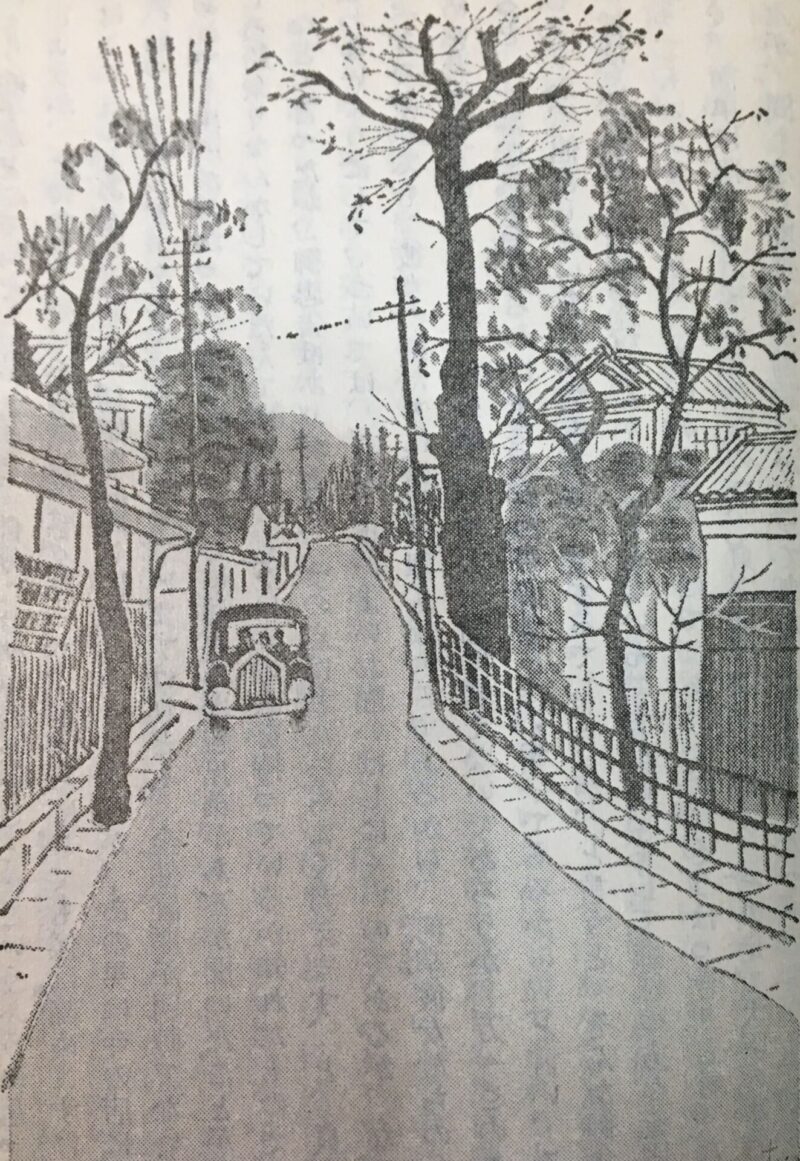

…と、あっちこっちで勝手に話が噴き出てきた。先生はにやにやしていた。こういうのがいい授業なのか?まあ、うまく乗せられてしまった一人が僕なんだけど。そういえば、前回の『砂の女』の次の小説にこれを出してきたのは意図したものだったのか?「開かれた物語」という言葉に関連して、小説の価値を考えるというようなことを気付かせたいのかな。
先生が
「ちょっと待って。もう一度考えてみよう。」
と教室を静かにさせた。

あからさまな政治的な主張だったり、道徳的な主張だったり、そういうものがはっきり読み取れなくてもやはりなにか作品全体から感じられる作者の意見がないとどうも中途半端な感じが残るんだね、そこが不満の一つではないかな。どう?それはある?ある、という人が多そうだね。そこんところ考えてみようよ。名作かどうかは別にしてさ。つまり『細雪』は何を語っているのか、ということだ。
金持ちのくだらん生活だよ。いや、そうではない。
「第二次対戦前の関西の金持ちの生態、なんてのはどうですか。」
問いの後、しばらくして誰かがそう言った。

なるほど。みんな大体それでいいかな?ただもうちょい狭めて表現できないかな。難しいかね。
じゃあ、実は私が素晴らしいと思った解説文があるので、それを紹介する。こんなふうな、なーるほど、という解釈ができたら素晴らしいと思うんだ。解説はよく出てくる内田樹。ある文庫本の解説なんだけど。その一節を見せるよ。そこで、私が答えとしていいなと思った文は、
不可逆的な滅びのプロセスのうちにある「日本における『よきもの』を描いた物語。

谷崎が『細雪』の稿を起こしたのは昭和17年(1942年)、太平洋戦争勃発の翌年である。翌18年の『中央公論』の新年号に第一回が掲載されたとき、すでに帝国海軍はミッドウェー海戦で艦隊主力と大量の航空機を失い、組織的な反撃が不可能な状態になっていた。もう負けるしかないのだが、どう負けるのか誰もその下絵を描くことができない。そういう先の見えない時代の暗鬱な大気圧の下で、谷崎は自分が愛してきたものはどれももう二度と戻らないと直感して、その「失われてしまった悦楽的経験のリスト」を網羅的に記述するという作業に没頭した。
http://blog.tatsuru.com/2016/08/03_1751.html
いかなる政治的主張も含まないこの小説は、それにもかかわらず、陸軍省報道部の忌諱に触れて発禁処分を受け、私家版の頒布さえ禁じられた。
おそらく検閲官は『細雪』の全篇の行間から流れ出る「日本における『よきもの』はことごとく不可逆的な滅びのプロセスのうちにある。だから私たちの最優先の仕事はそれを哀惜することである」という谷崎の揺るぎない作家的確信に、一種の恐怖を感じたのだろうと思う。この耽美的な書物のうちに黒々とした「日本の未来に対する絶望」を感知した検閲官の「文学的感受性」に対して私は敬意を示してもよいと思う。
というのはどうだろう?
そこにはこんな解説もある。ぜひしっかり読んでくれ。

この耽美的な書物のうちに黒々とした「日本の未来に対する 絶望」を感知した検閲官の「文学的感受性」に対して私は敬意を示してもよいと思う。
というところ、うまいねえ。すごい皮肉と言おうか、検閲官の文学的眼力が素晴らしい、と言ってるんだね。もちろん、たぶん本当はそんな慧眼などではなく、「ご時世にそぐわない」なんていう感情だけで発禁処分は決められてしまったんだろうけど。あるいは、無意識に感じさせてしまう文学の力ということかなあ。
こういう文章の書き手になりたいね。他の人には真似のできない解説のお手本みたいなものだと思わないか?

さて、すごくまとめにくい小説ではあったがいちおうこれで終わりにしたいが最後に、私なりの『細雪』のまとめを言っておきたい。
実は先日テレビで音楽関係のドキュメンタリーらしきものをやっていたんだが、その中でミリマルミュージックという言葉が出てきた。知らなかったのですぐネットで調べたら、
比較的シンプルなメロディーやリズムのパターンをこれでもか、というほど繰り返してパターン化し、それを複数重ねたり、それらをずらしたりして同じパターンを繰り返し聴いている中にも少しずつ変化が現れ、ずっと聴いているとそれらが大きな音楽のうなりのようなものになって聴こえてくる…というようなスタイルを持つ音楽。
と書いてあった。ラベルの『ボレロ』なんかそうだという。私は『細雪』も一種のミリマルミュージックといってよいのではないかと思う。何も解決されていかないエピソードの連なり。それが『細雪』ではないだろうか。
小説の構造を考えてみると、主要な登場人物たち。次女から四女までの姉妹に何度か顔を出す準主役たち(長女、二人の婿、そして使用人の娘、周囲の男たち、隣のドイツ人、ロシア人たち)に対して、関西と関東、服装、職業や身分、天災などの事件、病気(これが結構多い)などという事態や事件がさまざまに組み合わされることになって、無限のエピソードに展開される。これがこの『細雪』の構造である。

だからこそ、雪子の結婚はうまくいくはずがない、と思う。そうでなければ、最後の車中での雪子の腹具合の記述などあるはずはない。こんな不自然な描写は意味ないじゃないか。
主要な三姉妹✖️長女・夫たち・恋人・外国の友人・見合いの相手・紹介者など✖️事件・社会経済情勢・行事などの組み合わせによって、エピソードが連なっていく。
と、私はそんなふうに思っている。そういう物語構造がこの小説の骨格じゃないかな。みんなはどう解釈する?
もう一度考えてみて。なかなか面白い課題だと思うが。
この構造が結末の中途半端さとも関係しているのかもしれない。内田樹の解説もなるほどと思わせるが、その“滅びゆくものへの哀惜と共に、こうして人間の営みは延々として続いていく、という思想が低音部に流れているとも言えるのではないだろうか。

うーん、谷崎潤一郎には深い洞察が隠れている、ということですかね?」
なんて誰かが呟いたのが聴こえた。ちょっとカッコ良すぎ。誰だ?
しかし。僕もいろんな読み方があるもんだなと思った。というよりも、いろんな読み方を無理矢理に開拓していくことを、強いられているような気がしなくもなかった。自分が自然に、わけわからないなあ、と感じていることをそのままにしておくのはいけないのかなあ、とも思った。
でも先生の言う通り、そういうところから自分なりの解釈すること、つまり物語を創生していくことが人間の性(さが)ということなのか。そうだな、科学にしろ芸術にしろ“意味”を付け加えることがその使命と言えるのかもしれない。だって数学も、基本的な数字だって人間がそういうものとして作り上げたものだし、また色だってそのものとして存在するものではないんだ。
そう考えると、なるほど物語に意味を付け加えて読み、感動したり批判したりすることは当然のことなのか。でも、そうすると、谷崎潤一郎の小説には何かが隠されている、という表現は適当じゃあない。読者は何かが隠されているように見えてしまうけど実は僕たちが何かを作っちゃう、ということではないの?
そうか、タモリの番組の話もそういうことだったな。それがどう聞こえるかは音のせいではなくて、聞き手の頭の中の脳のせい、ということなのかな。
うちの爺さん、近頃耳が遠くなって、よく「何?」って聞くけど、あれももしかしたら爺さんの頭の中の衰えが原因で、耳の器官までは正常でも、頭の中の反応というか解析能力のせいで聞こえないようなそぶりをしてしまうんじゃないだろうか。まあ、これこそ妄想だな。でもいろんなことを考えてしまうなあ。



コメント