
作者は、ある手紙で、純真な人も描けるんだと言ったそうだ

彼女はオーバン夫人のもと、誠心誠意仕事に励んだ。女主人には変わることなく忠実だった。オーバン夫人は寡婦で、ポールとヴィルジニーという二人の子供がいた。子供の世話でフェリシテは穏やかで幸福な生活ができた。
フェリシテは優れた召使だった。父親は石工だったが、事故死した。ついで母親も死に、残された娘たちは離散した。フェリシテはある小作人に引き取られたが、酷い仕打ちをされ、家から追い出された。別の農場に引き取られ、そこで彼女はテオドールという若者に言い寄られた。彼は兵役に出なければならなくなり、それを免れる金を得るため他の女性と結婚してしまった。フェリシテはそのため今までいた場所から出て行こうとして、ボン=レヴェクへと立ち去った。そこでオーバン夫人と出会い、召使いとして雇われることになった。
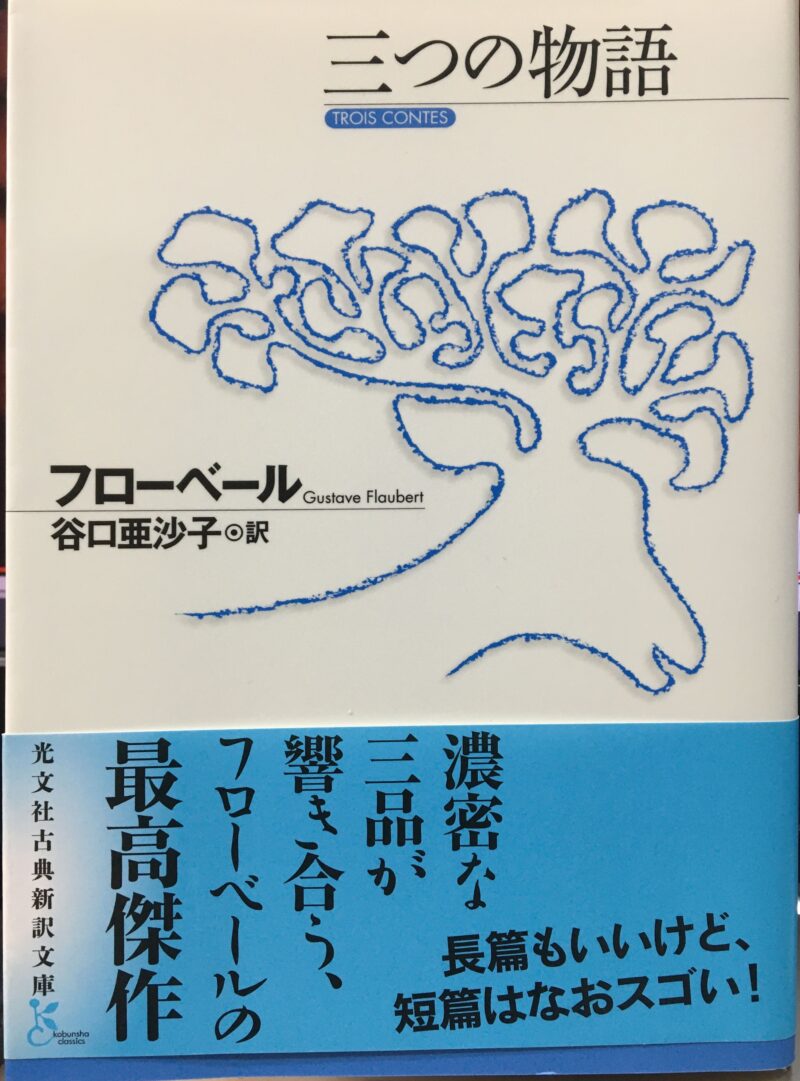
この家で彼女と交流ができた人は、ロブランとリエバールという小作人。彼らをフェリシテはみごとにさばいた。グルマンヴィル侯爵は夫人の叔父で、夫人から多少のおこぼれをもらおうとしている人物だった。また夫人は彼に家政的な管理(不動産管理)をしてもらっていた。子供たちの教育はギョイ氏が受け持っていた。
フェリシテは特にヴィルジニーにのめり込んでいった。ある秋の晩、みんなで外出して、牧草地を抜けて帰宅しようとしていた時だった。一家が牛に追いかけられたということがあったが、フェリシテの機知によってみんな無事に帰宅できた。ヴェルジニーはこの時の極度の恐怖によって転地して海水浴療法ををする必要があった。このおかげで娘は徐々に回復していったが、フェリシテはこの時生き別れになった姉と会うことができた。姉の息子のヴィクトールを知った。彼女はこの甥をこよなく愛するようになっていった。1891年にヴィクトールは遠洋航海の船員になり、フェリシテは目の前が真っ暗になっていくような気がした。ヴィクトールはアメリカに行ってしまった。
ある日フェリシテに手紙がきた。愛する甥の死を知らせる手紙だった。彼女は大きなショックを受け、自分の部屋で布団に身を投げなげ枕に顔を埋め、拳で頭を押さえつけ、とめどない悲しみに身を委ねるのだった。
いっぽう修道会の寄宿舎で学んでいたヴィルジニーは身体がだんだんと弱くなっていった。秋は無事に過ぎたが、しばらくして彼女は亡くなってしまった。オーバん夫人は娘の足元にすがりつき嗚咽をもらした。フェリシテは二晩のあいだ死者の元を離れなかった。
何年か経った。フェリシテの優しい思いやりは多くの人へと向けられたが、一人一人と知り合いも亡くなっていった。
ある年ここの郡長が知事に昇進して町を出る時に、夫人への置き土産として鸚鵡が送られてきた。夫人はうんざりしてこの鳥をフェリシテにやってしまった。ルルという名の鸚鵡に、フェリシテは言葉を覚えさせようとして夢中になった。彼女にとっては一番大事なものになっていったが、ある時ちょっと目を離したすきにいなくなってしまった。ルルは見つかったが、この時からフェリシテは体調を崩してしまった。1837年の冬ルルは死んだ。フェリシテの嘆きが度を超しているので、夫人は「そんなに悲しいなら、剥製にしたらいいじゃないの」と言った。剥製となったルルは自分の部屋に置き、決して外には出さなかった。ルルとキリストの版画をいっしょに飾っていると、ルルは聖化された存在となっていった。
1853年に、オーバン夫人が亡くなった。夫人の息子とその嫁が相続人となったが、彼らは屋敷を売りに出した。フェリシテはしかし買い手が出てこないので屋敷の部屋に居続けることができた。
復活祭を過ぎたころ、フェリシテは肺炎となり、日に日に呼吸が苦しくなっていった。聖体祭の日には終油の秘蹟をした。フェリシテは何かに語りかけているようだった。世話をしてくれていたシモンの女将さんはルルをフェリシテの顔のそばに持ってきてくれた。ルルはもはや虫が喰ってボロボロになっていたがフェリシテはじっとそのまま頬に抱いていた。聖職者が中庭まできて香炉の青い煙がフェリシテの部屋まで登ってきたころ、彼女は鼻孔を上に向け、神秘的な官能に浸されながらそれを嗅いだ。最後の息を吐き出した瞬間、フェリシテは、窓が開かれてゆくところを見たように思った。とほうもなく大きな鸚鵡が、自分を包み込むようにして、羽を広げていた。
安心して読んでください、ていう物語

一人の使用人の女の一生を描いたフランスの小説家フローベールの名作と言われている中編小説だよ。『三つの物語』という題名の一冊で、『素朴なひと』『聖ジュリアン』『ヘロディアス』の3遍が入っている、その一つの作品を取り上げる。もっと長い小説になるべき内容が適当じゃないかと思われるのがこの『素朴なひと』だ。これを読むと、大河ドラマにしてもいいような内容なのがわかる。
私はフランス文学の詳しいことは知らないが、フローベールという作者について、もっと現実の厳しさを伝える人だと思ったんだが意外にそうでもなく、まあ「いい話」という感想だった。そういうことから、名作という評価についても納得できる印象だったが、本当にそれでいいのか、君たちはどういう感想?

僕は正直、どこにこの小説の価値があるのか、名作に値するのか、という疑問が浮かびました。ストーリーは単純です。
かわいそうな環境に生まれた女性。常に金持ちの召使いとして働き続ける。ただし、この人は人間的には非の打ち所がないような人です。無学だが真剣に人生を生きている。僕はこの作品が名作と言われている所以は、ここにあると思っています。こういう人に悪い人生はないはずだ、という期待どおりと言っていいんでしょう。だから、読後感も良いし、安心できる物語だったんです。当然、名作の仲間入り、ということになるじゃありませんか。

フェリシテという不運な女の、召使いとしての人生を描いたもの、ということですが、彼女が順番に様々な人と出会いながら何かしらの影響を与え、また自分も影響される。その繰り返しという構造はやはり単純と言えるんじゃないかなと思います。その積み上げによって小説が進み、彼女の死によって終わる「女の一生」物語ということで、短中編としてはちょっと無理したんじゃないかな、という印象を持ったんですが……。

フェリシテという女性がすごく好人物であることは確かでこういう人が不幸な人生を送ってほしくない、と思います。でも、周りの人たちに好意を持って尽くしていく、その見返りはないですね。誰かモデルになっている人がいるのかもしれないけども、たとえばヴィルジニーという主人家の娘に対する愛情のわりに、この娘とフェリシテとの間の心の交流は印象に残らない。娘が早く死んでしまうので仕方がないけど。同じことは甥との間もそう感じました。
なんだかフェリシテがつくしてばかりいて……。そういう点でわたしは物語に不満を感じました。もちろん私自身が作品を通俗的に読んでしまっている、という自覚もあるんですけど、彼女がかわいそうという感じてしまうんです。読者として、中途半端な感じがしてしまうんです。
鸚鵡という持物(じぶつ)

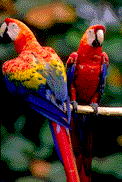
なんであんなに最後に鸚鵡に執着するんだろうか?他の執着とはわけが違うよね。自分に残ったものが剥製しかなかったからそれに執着したの?まさかねえ。いくら綺麗だからってねえ、鳥の剥製に執着なんて、ちょっとキモい。主人も死に、知り合いもみんな死んでしまって孤独な人生だったということなの?そうすると全然ハッピーエンドじゃないよ。
もしそうなら、最後にいてくれるシモンのおかみさん。この人をもっとクローズアップしてもらいたかったなあ。シモンのおかみさんて、フェリシテの精神的な「跡継ぎ」でしょう?それがなんで鸚鵡なのよ、最終最後が……。これだと、天国に連れていってくれるのが鸚鵡のような感じなんだけど。

それにはひとつ材料がある。先日街の古本屋で買った文庫本があるんだ。この授業のために買ったわけじゃない。全くたまたま面白そう、と思って買ったんだけど、今回の授業にドンピシャ!『モチーフで読む美術史』宮下規久朗著。(ちくま文庫)

たとえば中世の夫人の肖像画があって、その真っ白な帽子に何故か一匹の蝿が止まってる絵があるんだ、あるいはキリストの肖像の胸にも蝿が描かれている。これはものすごく不自然で、なぜこんなところに蝿がとまってるの?と思わせる。本書では蝿は美術史学では邪悪や死の象徴とも考えられるが、作者の技量を誇示するものとして書き込まれるものもあるという。
では、鸚鵡は何を表すのか?あくまで絵画の場合だが、鸚鵡は「聖母の純潔」や「無原罪の象徴」にもなり、また「忍耐や雄弁の擬人像の持物にもなったと書いてあった。持物(じぶつ)という。これアトリビュート( attribute)は、”西洋美術において伝説上、歴史上の人物または神話上の神と関連付けられた持ち物。その物の持ち主を特定する役割を果たす”という。

ということはまさしく鸚鵡が彼女の死の場面に登場することにより、彼女の昇天を保証した、ということになりますね。なるほど、だから鸚鵡なんだな。鳩じゃあいけないんだな、ということか。当然フランスの読者もわかっていて読んでいるんですね。鸚鵡が出てくりゃあ天国行きだ、ということね。

そうそう。日本でも『更級日記』の作者が『源氏物語』を読ましてくれとお願いするのは、どんな仏さんだった?「お薬師さん」だろ。現世利益の仏さんだよ。阿弥陀仏じゃあ具合悪いわけよ。死んだ後に読ませてくれっていうわけじゃあないのよ。

なるほどね。つまり、その文化の中の暗黙の了解とか、符牒とかを知らないと読解の方向が変なものになっちゃうかもしれないということですね。ただし、それは前にも話があった、間主観性の問題で、作者の意図が必ずしも生かされなければならないということではないでしょう?読者の権利になるわけでしょう?
贈与する者は救われるのだ、ってホント?


でも、たとえばここに蝿が描かれているのは不自然だ、という感覚はたぶん誰にでもあるはずだ。これはほとんど誰にとっても共有できる感覚だろ?そしたらそこになんかしらの意味を求めるのはこれも必然だよ。これが人間が持つ物語創造の欲望だ。そしてその意味とはなに?と尋ねられたら、なんと答えるだろう。蝿の場合、まさか「勇気」とか「純潔」とか考える人はいないだろう。鸚鵡の場合は、そこがわれわれにはわからない、という問題がある。そしたら、それ以前に鸚鵡の出てくる絵画や文章を確かめて、人類史上どう扱われていたのかを調べてみる。こうして読者は納得する。あるいは小説の解釈を完成する。つまり鑑賞するんだ。これは読者の権利を行使していることになるんじゃないのかな

でも先生、わたしはこう考えるんです。
フェリシテは家族の中で成長できなかったのに、ごく真面目に生き続けましたね。そして他人への奉仕をし続けるのです。最初に言い寄ってきた男、女主人、その子供たち、甥っ子、誰にも助けてもらえない老人。彼らに思いやりを持ち続ける。それから最後に鸚鵡に執着します。これは簡単に言えば、人間不信の物語じゃないでしょうか?人間たちへの奉仕は裏切られはしなくても報われなかった。いやフェリシテが何か報酬を求めたというわけではないけど、助けられてほうも彼女の奉仕を受けた結果を自分のものとして十分に受けとめたとは言えないと思うんです。

人間の基本的な欲求として「贈与」は存在するんだという考え方は知りましたが、確かにフェリシテは贈与し続けますが、他の人からの贈与はどうだったんでしょうか?ちょっとせこい話でしょうか?
しかし、最後に鸚鵡によって最大の贈り物を受け取るわけです。考えようによっては人間不信の物語ですが、しかしそれでも彼女は与えた以上のものを贈られたとも言えますね。これは贈与の物語ですね。

ルルという鸚鵡は剥製になって、最後にはボロボロ。腹からおが屑がこぼれてしまっていた、というふうになっているのはどう考える?別に生きているままの鸚鵡であっても構わないのに。さっき持物ということを聞いたけど、その持物がボロボロだったということには意味はないか?僕は冷たい読み方かもしれないけど、ここをフェリシテが最後まで幻想を持っていた、勘違いのまま昇天していった、と読みたいと思う。剥製がボロボロだっただけでそう読むのはちょっとひねくれているかもしれんけど、そんな良い話かなあと……。漱石の時も話題になったけど、作家に騙されるのが読者なのかもよ。名作とは、宗教的な論理に従ったもので、読者が安心しちゃうから名作なんだ、ということもあるんじゃないの?


いやあ、皮肉な読み方だなあ。まあ、それも自由だ。「作者の死」ということからもね。でも、剥製の状態が悪いのはあくまで貧者の崇拝にふさわしいとも考えられるし、そういう状態の「聖なるもの」は、たとえばワイルドの『幸福な王子』を連想させるじゃないか。

その勘違い昇天説は面白いけど、もうちょっと証拠があればなあ。さらに細かく読んでみてよ。そして、三つの物語を全体として考えなければならないのかもしれない。
それから今回結末までのそれぞれのフェリシテに関係する人々のエピソードを少し飛ばしてしまったね。やはりオーバン夫人と二人の子供、特に娘のヴィルジニーに対する思い入れだね、それから甥のヴィクトールへの思い。どこにどういう違いがあるのかを調べて比較してみたいね。単に彼らに対する愛情(贈与でもいいけど)とひとくくりにしてはいけないという直感も私にはあるんだけどね。ここは自分でも整理がつかないんだ。「持物」で読む贈与の物語、だけではないかもしれないね。


コメント