
職場の女の子とバーのおねえさん さて妻はどうする

『舞踏』
結婚5年たち夫婦には5歳の女児ができた。夫は市役所に勤めていて、一家三人は平穏に見えたが夫は同じ課に勤めている19歳の少女と恋をしているのである。妻もそれを察していて、夫の机の上に自分の気持ちを書いたものを置いておいたりするのだが夫はそれを無視する。妻はしかし面と向かっては夫には何にも言えなかった。妻は不安な気持ちをどうすることもできず、どんどん孤立感の中に陥ってしまった。ある晩夫が帰ると妻は子供のそばで眠っていた。夫は妻が睡眠薬で自殺を図ったかと思った。妻の自殺の新聞記事まで頭によぎったのだが、妻は不安定な心のためウィスキーを何杯も飲んだらしいのだ。夫は自分の立たされる立場への心配のために狼狽し、そして妻への怒りでいっぱいになった。
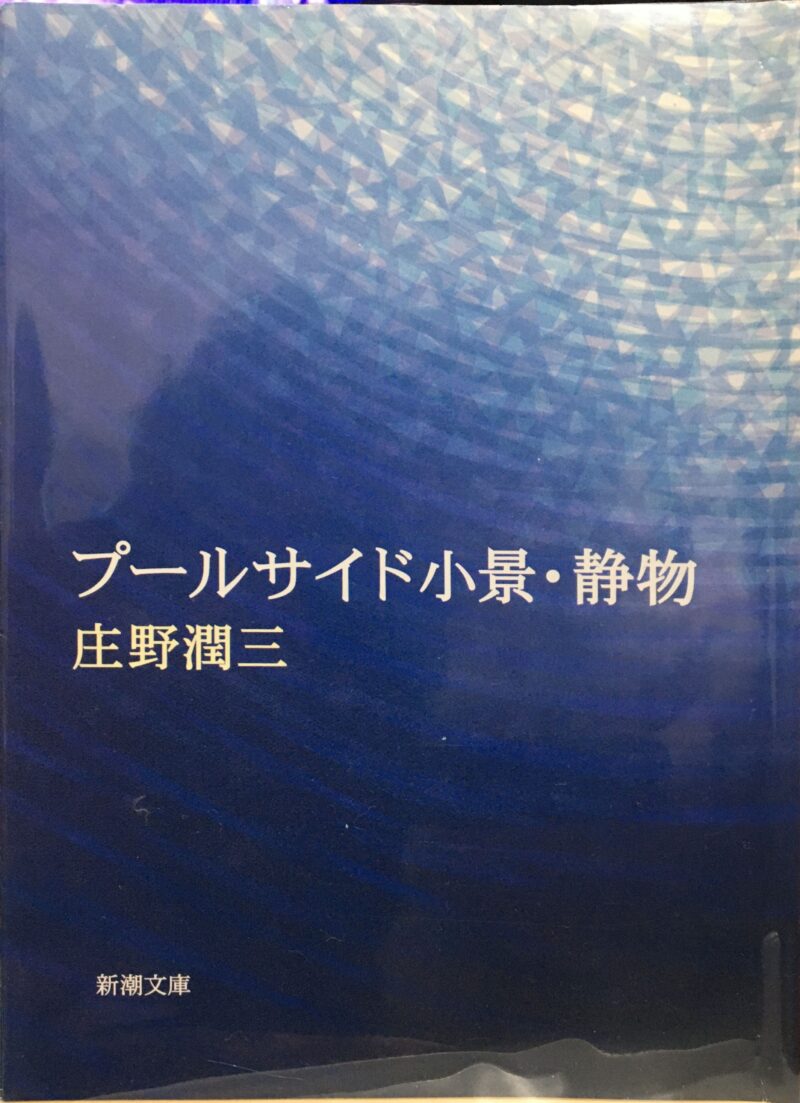
彼女は絵が描きたくなるとたまらなくなる。ある日彼女は子供を隣のおばさんに頼んで絵の具箱と画板を提げて家を飛び出した。近くの高校の中に入って行った。空っぽのプールを見ていて、一人で笑ってしまい、自分のことがわからなくなってしまったと感じた。いけない母親と言われても、自分のことで精一杯なのだ。
日記をつけていた夫は階下で妻のすすり泣く声を聞いた。この時彼は少女と音楽会に行きその音楽会は妻が行きたがっていたものだった。啜り泣きの声を聞いて、(本格的になってきたぞ。これは厄介なことになった。)と思う。あくる朝、夫は妻に向かって言った。「神経が少し疲れているんだね?そうだろ、疲れている時はね、何でもないことが、ひどく応えるものだ。それに、人間は誰だってめいめい不幸なんだ。みんな、その人の不幸を背負っているんだ。ただそれが他の人には分からないだけだ」と。妻はますます空しい気持ちに落ち込んでいった。
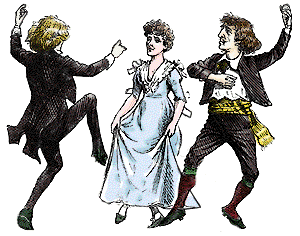
7月14日パリ祭の日。妻は夫に「ダンスしませんか?」と言った。夫婦はワルツを踊ったが、夫は妻の髪にあるリボンを、少女の髪につけたら、と思うのだった。
『プールサイド小景』
青木氏は自分の子供を学校のプールで遊ばせていた。学校のコーチの先生とは顔馴染みで、邪魔にならないように息子の泳ぎの稽古をさせてもらっていたのだった。やがて青木夫人が現れた。家族はそろって帰宅していった。
青木氏は、一週間前に会社をクビになっていた。彼が使い込みをしたのが分かったのである。彼女は夫の仕事についてほとんど何も知らなかった。素人もしていなかった。
少し落ち着いてから、自分たちの生活がいかに他愛のないものだったかを見にしみて感じた。(人間の生活って、こんなものなんだわ)と。
ある時彼女は夫にバアの話をするように言った。夫がバアの女性に金を使っていたことは気づいていたのである。

Oというバアを青木氏は話し出した。美貌でそっけない姉とその妹でやっている店で、その姉に彼は夢中になったのだった。事情を聞きながら、妻は自分が迂闊だったことに気づく。夫に女がいて、その女のために会社の金を使い込んだのだ。しかし妻が気付いたのは女がいたことではなく、その話の裏にある夫の言わないことが「メデューサの首」なのだ。彼女はそれに触れてはならない。それを夫に話させてはならない。
僕は思う。彼ら(会社の同僚たち)を怯えさせるものは、彼らが家庭に戻って妻子の間に身を置いた休息の時にも、なお彼らを縛っているものなのだ。それは、夢の中までも入り込んで来て、眠っている人間を脅かすものなのだ。もしも、夜中に何か恐ろしい夢を見てうなされることがあれば、そん夢を見させているものが、そいつなのだ。

妻は思った。夫の話を聞いていると仕事が終わってもまっすぐ帰ってこないのは、勤めていることに始終苦痛を感じていたからだが、家へ帰っても心の休息を得られなかったのだろうか。妻や子供たちを見ると苦しくなって、バアやキャバレエで女と一緒にいると苦痛を忘れるというわけなのだ。すると、一体自分は夫にとってどういう存在なのかしら?と。男が毎朝背広に着がえて電車に乗って遠い勤め先まで出かけて行き、夜になるとすっかり消耗して不機嫌な顔をして戻って来るという生活様式が、そもそも不幸の元ではないだろうか。青木氏は出勤するようになった。近所の目があり、子供たちにも休暇と言ってある以上そろそろ新しい働き口を探さなければならない。妻の頭の中には見知らぬアパートの階段を上っていく夫を想像したりしてしまう。妻は、失業者だって構わない、帰ってきてくれさえすれば……、と思った
プールは、ひっそり静まり返っている。たったひとり、コーチの先生が真ん中で底に沈んだごみを足の指で挟んで拾い上げていた。プールの向こう側の線路に電車が現れる。乗客たちの眼にはひっそりとしたプールが映る。いつもの女子選手がいなくて、男の頭が水面に出ている。
日常は不意に壊される

さて、戦後の作品として、庄野潤三という作家の短編を選んでみた。わざわざ2編読んでみて、同じような状況を書いているんだが、どう読むかを考えてみたい。こんなのこそどう自分が読むかをひねくり回して解釈する小説だね。これも、要するに何を言いたいの?とか、何を描いているの?とか焦点をどこに合わせるのかを問いたい。当然小説の中に読者が判断した材料があるはずだから、それを指摘する。そしてそれを君たちがどう受け止めているのか、を表現してもらいたい。もちろん、二作とも同じところ、違う面を持っているからそこをうまく絡めて説明できたら素晴らしいこと。まず二作メモ取りながら読んで、言いたいことが心に浮かぶか考えてみよう。いわゆる不倫について拒否感を持ちながら読むことになると思うけど、そこは我慢してね。
さて、どんなふうに読んだかな?

まず、今回も普通に生活している家族にふってわいた非日常の事件ですね。私の母親はどうもテレビで以前に向田邦子のドラマを見て、すごく影響受けちゃったんだそうです。まあ、ハマっちゃったんですね。そのストーリーを聞いていて、私、同じような匂いがしましたね。つまり、テレビドラマにある家庭の危機という話ですか。今こういうシビアな家庭危機は流行らないようですが、以前はあったんでしょう。後味悪いドラマが。

そうそう。よく言われる「偽りの幸せを糊塗する家庭の物語」なんていうものなんじゃないの?

必ずその家の親父が不倫してるんだよなあ。あまりに安易な類型化じゃないかなあ。うちの親父を見てると、絶対にそんなことしてないと思うけど。男の性(さが)としてあるように思われちゃうよ、そういうドラマ見てると。この教室にいる男だって、そんなヤツいないでしょ。もちろん先生も。

もちろんだよ。ただ、そういうドラマがこの小説の本質というか、テーマというか、それ以外に何かニュアンスの違う読みもないかなあ。
旦那に好きな人ができたら幸せなの?そんな……

僕はそういう話とはちょっと違っていて、二作とも旦那に恋人ができたということに、奥さんから嫉妬をあまり感じられないのが、すごく不思議なんだが……。だってさあ、『舞踏』には妻の心中の言葉として、
夫が懸命にあたしに隠していること、それがどんな事なのか、あたしには想像できる。でも、どうしてそれをあたしにおっしゃってはくださらないのだろう。あれほど様子が変わってしまうくらい、好きな女の人ができたのだったら、どんなにか素晴らしいひとに違いない。あたしには、そんな気がする。それなら、どうしてそのような人にめぐり会ったよろこびを、あたしに分けては下さらないのだろう。どうしてあんなに隠そうとなさるのだろう。あたしが気付かないと思っていらっしゃるのかしら。それは、あの人に好きな人ができたら、あたしは随分苦しい。だけど、あんな風にそのことを一口も言わずにいて、そのためにあの人がいつもいつも自分を苦しめているのを見ていることの方が、ずっと苦しい。あたしがいることが、あの人をひどく不自由にしているような気がして来るのだ。そして自分が夫を苦しめているように思われて、苦しい。
と書いてあるよ。これバカじゃない?

何言ってんだよ、素晴らしい女性じゃないか。なあ岡野?

俺にふるんじゃないよ、ばか。

まあちょっと待て、そこのところ私も気になったな。いくら昔の小説だって、そんな女性の感情はあり得ないと思うよ。まるでそれこそ女神とか何か極端な宗教的な話のように聞こえるよ。
で、だとするとなぜそういう女性像が描かれているんだろう。そんな女性像が読者にどんな読みを促すんだろう?どうだ?

わからない。だって自分も苦しいと言ってるんですよ。全く矛盾しているじゃないですか。あるいはその矛盾がこの小説のテーマなんですか?ドユコト?

私は、こういう女性を作り上げているということに作者の意図を感じる。作者の意図を追い求めるのが小説鑑賞ではないと言われたけど、あえて言えば、こういう女を描く作家に、むしろ女に対する悪意を感じる。悪いのは男だ、という意識はありながら、この小説を読んでこの妻に100%の同情を持つ読者はどれくらいいますかねえ。

確かに女に同情してないし、同情しろとも読めないなあ。それなら女が持つ生まれながらの悪か?いや、僕はそんな読み方してないよ。だって、男はもっと悪だよね。女房が自殺したんじゃないかと思った時に何を思ったか、それでわかるよ。さらに女房が行きたがっていた音楽会にわざわざ少女を連れて行く。女房の啜り泣きが聞こえてきた時には、(いよいよ、ヒステリーの症状を呈し始めたな)(本格的になって来たぞ。これは厄介なことになった)というようなことを思ったと書かれている。本音かもしれないけど、これはひどいよ。やっぱり一番悪いのは旦那だよ。
男の誠意のなさ 空疎な言葉

あおちゃん、偉い!そうだ、そうだ。あたしゃ(とこんな言い方をしたこの人初めて!と僕〈圭〉は驚いた。)この夫に単純に怒りを覚えた。小説の登場人物だということは承知の上だが、この男の言うことがいちいち気に食わない。妻の泣き声が止まらないのにいうことは、「山出しの女中がホームシック起したみたいに、台所でヒイヒイ泣くのは止めてくれ。無智だよ」だって。次の朝、さすがに気に咎めて「ゆうべは、ひどいことを言って済まなかった。許してくれ。あやまる。神経が、少し疲れているんだね?そうだろ?疲れている時はね、何でもないことが、ひどく応えるものだ。それに、人間は誰だってめいめい不幸なんだ。みんな、その人の不幸を背負っているんだ。ただそれが他の人には分からないだけだ。」なんて言ってる。「分ったかい?」「へこたれたら、駄目だ。強く図太く生きるんだ。」だと。こんなバカ男はいないわ。ほっぺた引っ叩いてやりたい!

それが、ですよ。妻は何度も頷き、子供のような素直さを見せるのよ、この妻は。そして最後に二人はワルツを踊るの!今日は巴里祭だからって。僕はむしろこの女にも呆れるわ

なるほど、ちょっと結論じみたことをいう前に、先に次の『プールサイド小景』を語り合ってからにしようか。

考えようによっては、こっちはもっと強敵だ。読者は『舞踏』に比べてそれほどの批判、嫌悪感を登場人物に向けられないんじゃないですか?何が書かれているかという見方も多様になると思います。

でも、構図としては同じものじゃないかなあ。夫と妻との心の離反ということは同じでしょう。夫の横領という事実を前にして妻はどういう態度を取ったか、ここが問題です。彼女は今までの平穏な毎日がいかに大切であり、そして無自覚であったかを思い知る、ということですね。それに夫の使い込みの原因が女性関係にあることを知ってますます自分が迂闊であったことに気づくんですね。

この小説のキモは、妻が夫に今回の事件のいきさつを話してくれと要求した時のこと。彼女は「何か話をして」と夫に要求して、夫からバアの女のことを聞くが、この後夫への質問が罠だと悟るんです。
夫が話したことは、それはどうでもいいようなことなのだ。彼が秘密にしなければならないのは、もっと別のことである。彼が秘密にしなければならないのは、もっと別のことである。(彼がしゃべったバアの女に惹かれたきっかけについては、《……》多分、一種の陽動作戦のようなものなのだ。彼女は本能的な敏感さで、それを感じ取ったのである。
もしも彼女がせがむならば、夫は今のとは別の、ちょっと気を持たせるようで、実は危険なものではない。女とのかかわり合いを、いくつか彼女に聞かせるかも知れない。だが、その手に乗ってはならない。どうでもいいことは、全部さらけ出したかのようにしゃべる。そして、それらの背後に、男が針の先もふれないものがあるのだ。
メデューサの首。
彼女はそれを覗き見ようとしてはならない。追求してはならない。そっと知らないふりしていなければならないものがあるのだ。
ここが大事なのではないですか?これは何を言っているんでしょうか?

時代が離婚した女性に不利な社会であったからですか?それとも夫にやはり信頼する心があったからじゃないですか?今とはちょっと違う。そのどちらかということははっきりとは分からないし、そんなに分けられる話でもないと思うんですけど、とにかく妻は怖かったんじゃないですか?

でも、この夫婦の信頼関係は成立していないんじゃないかなあ。そこで『舞踏』と比べると、両方の夫婦に、既に夫婦の関係が冷め切っているという印象があるんだ。というより関係を断ち切りたいという意欲が男の方には湧き上がっているんじゃないかな。
だいたい、夫の女性関係がわかった時、この奥さんはどういう態度を取ったか。バアの女性に対する執着に対して奥さんは全く嫉妬していないように思えるんだけど。それ『舞踏』の奥さんもそうだけど、すごく違和感ある。つまり、この両方の家はすでに家庭の台所の床の下で崩壊のマグマがグツグツ沸騰しているんじゃないの?それを押さえつけてるのが、妻の力だ。いずれ噴出するマグマを女が押さえつけている。そのマグマの力は自分の力も含まれているはずなのに、女はその下からの圧力を抑えつけようとする。そんなイメージで僕は読んでる。

なぜそんなに妻たちは押さえつけるんだ?何だか君の話では、悪いのは男じゃない。現実を糊塗しようとする女に非があるように聞こえるけど。

それが僕の思うこの物語のまとめ文です。この二つの小説は「どうにもならない日常生活というものにあらがって、現実を糊塗しようとする妻たちの物語」と言える。こういうことです。焦点は男じゃない。女だと思います。
ヤモリは家守り 妻は家の問題を糊塗する

今の話は、『舞踏』の冒頭の文、「家庭の危機というものは、台所の天窓にへばりついている守宮のようなものだ。」というのから連想したイメージじゃない?台所の下からのマグマ、とか。それを押さえつける守宮ってのはきっとメスのヤモリなんだろう?また、ヤモリは「家守り」なんだから、この家の奥さんの表象だと考えてもぴったりだな。

さすが先生鋭いですね。
ただもう一つ読み飛ばしちゃいそうなものがあります。

プールだろう?両方にプールが出てくる。なぜプールが出てくるんだ?青木氏が彼女を連れて行ったのは水泳大会だったな。何も水泳大会じゃなくたっていいのにな。

そこが、小説の面白いところだ。プールにある水。水が熱を冷ますものなんだ。冷めなくても、冷まそうとする人はプールへ行くんだよ。男も女もプールへ行こうとする。しかし、プールが空になっていてがっかりする女もいる。

なんかこじつけが甚だしい感じがするけど、まあそう読んじゃったんだから仕方ない、というわけね。

この講座では、みんなこじつけて見せろ、って言ってるんだからそれはそれでいい。もっと他にも主張していいぞ。

そもそも、二作を読んで私は最終的に諸悪の根源は「生活」なんだなと思いました。太宰治が「家庭の幸福は諸悪の根源」と言ったそうですが、生活こそが諸悪の根源じゃないでしょうか。もっと言えば「生活の日常性」ということですかね。私も何だかそんな感じなんです。毎日学校に来て部活もやらず帰る。週に何回か塾に行って、帰る。これが生活でした。この日常の繰り返しの果てに受験があって、大学があって、仕事があって、恋愛があって、結婚して、子供ができて、そのうち退職して、そして死ぬ。これが「生活」です。社会では何回か事件があって、危機があって、何とかなって、と、こういう進行のうちに流されていく。そうなっていくのはもしかしたらいちばん幸せなのかも知れませんが、でもそういう「生活」をもう壊しちゃったり、あるいは作り直したりしたいという気持ちがどうしても自分の中に湧いてくる。そういうことがあるんです。
「生活」なんかない一生ってありませんからね。でも、そういう毎日って、ずっと続けていくのが嫌になる時がありますよね。うまく言えませんけど、生きるのが嫌なのではなく、生活するのがいやなんです。生活なしに生きていきたいということです。そんな感じを小説読んで持ちました。
それから、この二編では女は生活を守りますねえ。どうしてかなあ。女の私もそういうところあるんです。いやですね。
対象がないのが本質 不安の本質観取

これ、全く原典を読まないで言うんで申し訳ないけど。すごく難しいことで有名な哲学者にハイデガーという人がいる。その人の本では人間は生の中に放り込まれる、というように書いてあるそうだ。投げ入れられる、という感じなのかな。前に紹介した竹田青嗣によれば、ハイデガーの本質観取というのがあって、「不安」についてこう言ってるらしい。
「恐れ」はたとえば強盗や病気、台風などという対象を持つが、「不安」は明確な対象を持たない。「不安」の対象は「世界そのもの」である。「不安」の主体は人間自身であり、「不安」の内実は我々の実存可能性(よりよく生きられること)に対する「不安」である、と。

なんか今の話を聞いてて、ちょっと前に読んだ本をこのように思い出しちゃったよ。本当はピントはずれなことなのかもしれないが、たしかにここに出てくる女性たちは「不安」でしょうがないのかもしれないな。単に打算で、愛していない男にしがみついている、ということではないかもしれない。
もう一つ。この文庫本には『イタリア風』という短編も載っている。これはアメリカ滞在中の矢口夫妻がイタリア系のアンジェリーニ氏一家に招待されるが、どうもアンジェリーニ氏は妻と別れるような雰囲気である。今は彼は両親と住んでいる。小説ではこのイタリア系の家庭の日常の家庭観と当地アメリカの家庭観の違いによる問題が描かれている。
アンジェリアーニ氏はイタリアの価値観での家庭を念頭に置いてしゃべる。
「初めから今のようではなかった。子供も両親の言うことには絶対に服従していた。それが普通であった。だから、家庭は堅固なものであった。」
「アメリカの国民が初めの頃に持っていたこのようなしっかりした家族の精神を失ったことは、本当に残念だ」
こういう会話がアンジェリアーニ氏から発せられる。それが元なのであろう、彼は妻と別れるようになるらしい。
驚くべきことは、これって今でも日本の保守主義者の家庭観ではないか。これは発表が一九五〇年代なのだが。
いや、いいとか、悪いとかということじゃなくて、要するにここでもある家庭観に取り憑かれた人間が描かれているということ。ここでも固定観念、つまり日常的な生活、当たり前のことが我らを縛る諸悪の根源なんだなあ、ということ。それがこの物語なんじゃないかな。全く諸悪の根源だよ、日常性が……。
いやまことに文学とは実学であるなあ。
でも、一度庄野潤三のお墓にお参りに行くか。南足柄らしいから。



コメント