
どういう物語か、って難しいけど。なんとなくいい小説って雰囲気。

十月のK岳。杳子は谷の岩の中で一人坐っていた。彼はケルンを見つめている女を見つけ、近づいていった。杳子は疲労困憊しているようで周りの岩を身体に感じ取っていた。

彼はこの不思議な娘を連れて、やっと下山することができた。彼女の言動は彼に奇異の感を与えた。二度目に彼が杳子に出会ったのは駅だった。電車に乗るためにホームにいた、その線路ひとつ隔てた線路に入ってくる電車に乗っていた杳子は彼を認めて降りてきたのだった。あの山の出会いの後で二人はほとんど言葉を交わさなかったのだ。いま喫茶店で向かい合って坐ったとき杳子は椅子の上で、上半身をゆったりと支えて腰がにわかに女らしくなっていた。白いうぶ毛がいっぱい生えた腕に、彼はかすかな不快感を覚えた。
谷での奇妙な素振りに、彼女は「病気だったのです」といった。高所恐怖症だといった。谷底は「高さの感じ」が集まるところで、そこにくる人間に敵意を持っているという。彼は彼女の顔を見つめ直した。
杳子はもしも部屋がレンズのように膨らんでいたら辛いでしょう?そんなところでは暮らせない。みんなはそれでも平気なの?、などとしゃべった。彼が、本当にそんな感じでいたのかと尋ねると、「わたし、嘘を言ってるようですわ」などと答える。
次の週にも二人は同じ喫茶店で会った。杳子は席に、軀をぎこちなく前へ折り曲げて坐っていた。細い軀を固くこごめる姿勢だった。病気のことを話しだすと彼女は曖昧になる。話が矛盾だらけになる。病気はあれからなおったんです、ともいった。

何度か彼女と会っていると、彼は杳子の病気に怖れを抱くようになっていった。午前中は神経の具合がいいというので待ち合わせは早い時刻にした。ある駅前広場の人が少ない隅のベンチで会った。杳子の道の覚え方は異様だった。駅では一番線か二番線かで迷った挙句に判断を下し、目的駅までの駅の数にもこだわる。自分の家の階段の数も数えながら上下し、14段という数字に合わない時は階段の途中でいったんタバコを吸ってひと休みするそうだ。そんな会話をしているとき、杳子の目の中には嫌悪の光があった。
彼はだんだんと杳子の存在に重荷を感じだした。彼女との関係に危険を感じてもいた。彼女を病気に繋ぎ止めているのは彼女自身で、その重みを彼は感じだしていたからだった。
三月末。前回の二人の公園巡りのあとで次の場所を彼が指定し、説明しておいたところで会うことにした。彼はその日、林の中の池のほとりのベンチに坐っていた。杳子はなかなか来なかった。彼はその時、駅が改装で改札口の向きが正反対になっていたことに気がついた。一時間以上待って、杳子は目をギラギラさせて妙に上機嫌な様子でやってきた。神経がだいぶ高まっていた。
改札口のことを知って、杳子の軀から精気が消えるようだった。しばらくそこで立ち尽くしてしまった時の気持ちの中へまた沈んでいくようだった。そのうちふと目を輝かせてベンチから立ち上がり、一人で公園の中をひと回りしてくる、とものに憑かれたように走っていった。彼もしばらくして杳子を探しにいく。すると、杳子がまた戻ってきて、「今度はあなたがそっち、あたしがこっち」と林の中に走りだした。二人はときどき交差して道をたどった。彼が手を伸ばして杳子をつかまえようとすると笑いの中にかすかな嫌悪をのぞかせてすり抜けてしまう。
しばらくすると林の中の四辻にさしかかった。向こうから杳子は例の前かがみの姿勢でやってきた。彼は忍びよる獣のようなものを自分に感じながら、彼女と並び、そして見上げようとする彼女の唇に自分の唇を近づけた。杳子は受け止めるでもなく拒むでもなく感触を漠としたひろがりの中へぼかしてしまった。
それ以来公園めぐりはやめて街中の喫茶店で会うことになった。それは以前にそうだったように二人だけの孤立した時間と場所の中へ押し込まれていく。そんな気が彼にはした。
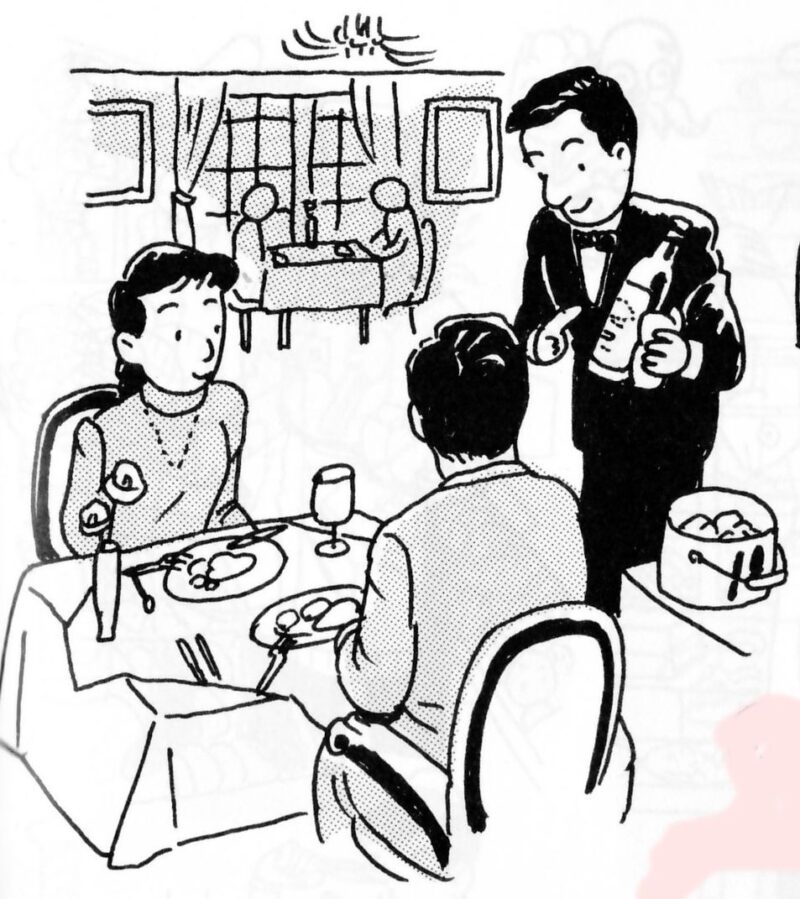
ある夜は杳子から初めて聞く言葉があった。「お腹がすいたわ」という言葉は彼を奇妙に和ませた。レストランで料理を選んで注文する、そんな行為の一つ一つが杳子をなごませた。ところが、ナイフとフォークを見ての彼女の失調を彼は感じた。わざと何気なく食べ続けても、彼女は杳子の視線は彼の手から離れずにいた。「だって、ナイフとフォークを食べてるように見えるんでうもの」とすでに甲高いガラス質の声であった。杳子の目に映っているふたつの醜怪な金具を、彼はふと思い浮かべた。「食べろよ」という言葉をかけても「あたし、だめ、できない。こんなむづかしいこと」という。彼の食欲はとうに失せていた。杳子は四分の一ほど食べたところで、「もう、カンベンして……」と哀願した。
それから二時間ほどして、二人は薄暗い旅館の一室で冷えた軀を二つ並べて、横になっていた。冷たい毛布とシーツの間に横たわって、彼の軀は内側からの存在感を失って、不安な輪郭の感覚だけに痩せ細っていた。杳子は少女の顔つきになって投げやりな物腰で自分を寝床に横たえた。しかし杳子の少女のような様子に似合わぬ軀に、彼女に自分自身のことについて、はっきり自覚させてやりたいという欲求を、彼は情欲の引いてしまった後にも、蒼白く残していた。
二人は以前と同じように喫茶店で逢って時を過ごした。二人の話は杳子の姉のことになった。姉のことになると杳子の話ぶりは冷たいものになった。憎々しげに天井を見つめたりした。
「あの人、むかし、おかしかったのよ」ちょうど今の杳子と同じ歳の頃、家から駅までの十分ほどの単純な道を実際に歩くと、思った通りにならなくて、引き返したりしたそうだ。でも、じつは何もかもわかっていて、ただ強情で、身勝手で、毎日一度自分の感じ方を通さなくては気が済まなかったんだと姉のことを言う。階段の降り方も必ず右から足を出し、不安そうに降りてくる。リズムが乱れると初めからやり直したり、入浴を拒絶して、部屋が臭ったりしたと言う。今そんな姉は杳子を気味悪がっているそうだ。
ある日彼は杳子の家に訪ねていった。そこで初めに姉と話をしてから杳子と会うことになった。姉は杳子を医者に診て貰いたがった。姉は自分たち二人が双子のように思えるから杳子の様子がわかるらしかった。「あの子は病気です」とはっきり言うのだった。「あの子が病気であることは間違いありません。なぜって、私もむかし病気だったことがあるんです」と姉が言う。《杳子が今病気で、あなたがいま健康だと、どうして言えるんです》と、彼は言いそうになった。
部屋での杳子は案外病気と馴染んでいるようにも見えた。おそらく杳子は自分の病気の根を感じ当てているのではないかと思われた。姉が部屋に紅茶とショートケーキを持ってきた。姉がテーブル上の物などに強いこだわりを見せながら去ると、そのカップやスプーンを見ながら、杳子は置かれた位置への姉のこだわりも指摘する。自分たち姉妹に杳子は泣き声になって、両手で顔を覆った。「癖っていうものは誰にでもあるよ」と彼は言いながら、どこの夫婦だって、お互いの癖に耐えていることを言うと、「自分の癖の露わさで、相手の癖の露わさと釣り合いを取っているのね。それが健康ということの凄さね」と杳子は言う。
”「だけど、あなたに出会ってから、人の癖が好きになるということが、すこしわかったような気がする。」
「どんな癖だろうね。僕は健康人だから、わからない」ものを食べる頑なな悲しみの中から、彼は目を挙げずに答えた。杳子の言葉を撥ねつけるのではなくて、嫌悪の中からようやく差し伸べられた彼女のやさしさを、理解したという気持ちからだった。杳子も彼の言葉を誤解せずに受け止めた。”
杳子は食べ終えると立ち上がって、しばらくはためらうようにテーブルの上を見つめていたが、いきなり残酷な手つきで自分の皿と彼の皿を、自分のカップと彼のカップを重ね合わせて、テーブルの真ん中に置いた。そして、窓辺へ行ってカーテンを細く開き、赤い夕日の光の中に立った。
「明日病院に行きます」と言い、「ああ、美しい。今があたしの頂点みたい」とつぶやいた。
障害の話とかでちょっと微妙なところもあるけど

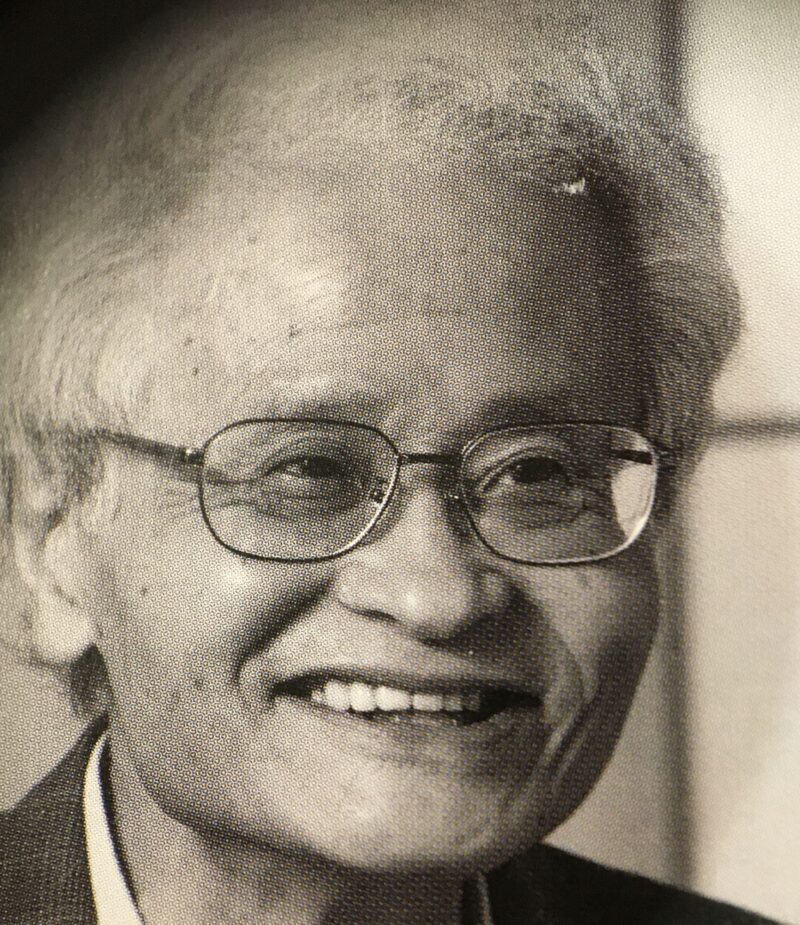
さて、今回は難敵だぞ。
古井由吉という小説家の芥川賞をとった『杳子』。古井由吉は2020年に亡くなった。授業で取り上げるような小説でないとも思うが、まあ、あくまで私の妄想授業だからいいよな。でも、本当はもうちょっと皆さんが歳をとってから感想を聞きたかった小説だがね。

一見すると明快な文章で、わかりやすいような気もしますが、なんだか矛盾だらけのようにも見えて……。二人の気持ちの表現でも、何か首尾一貫したものがないですよね。たとえば、杳子の心の描写でも、病気といったり、癖といったり。もちろんその二語の違いは大事だけど。
作品自体を大きく捉えるときは、恋愛小説となるのかなあ。でもそれじゃあ何も言ったことにならないような気もするなあ。何を描いた小説か、ということはなかなか難しいものがある。普通僕たちが恋愛小説といったら、人を好きになっていって、その過程がいろいろあって、そこにある危機を乗り越えて二人の気持ちがピッタリくる、とか。あるいはうまくいかなくて失恋するとか。中心は恋愛というものだよ。それがどうも曖昧じゃない?

僕は、そう捨てたもんでもないと思うよ。すごく新鮮な感じがしたよ。言い方がいいか悪いかわからないけど、この杳子という女性は”障害”のある女なんでしょ?特に道順とか食べることや仕草とかに強いこだわりを持っている人ですね。彼女と知り合った彼との交流の上で、すこしずつ二人が変わっていくことを描いている、という作品です。それに間違いはないんだけど、僕には特に『彼』という人物が杳子に引っ張られていくような気がしているんです。変な言い方ですが、杳子に取り込まれていくように感じました。

それから、公園での二人の追いかけっこみたいな行動がありましたね。ああいうのがこの二人の関係をよく表しているんじゃないでしょうか。つまり、単なる恋愛じゃなくて、違う道を辿ったり、たまに接近してみたり。これが二人の恋愛の表象として語られているんじゃないかと思うんです。単なるデートのエピソードではないと思います。公園のデートをやめた時、二人はともかくも本当の恋人になれたのかもしれません。違う道を辿る、また近づく。これをやめた時ですね。
二人の世界の行き来の物語

そう。そういうふうに私も感じた。それは結局は杳子の方に彼が引っ張られた結果だとは思うけど。二人の間にはもともと溝があって、少なくとも彼にとって別世界の存在だった杳子。その杳子が溝を越えそうで越えられない。男の方は彼女をこちらに引っ張ろうとするが、それがなかなかうまくいかないという、そんな物語かな。彼の方は、杳子の様子から自分にとって重荷になることも感じる。一種の打算の思いを自覚しながら一方で強く惹かれるものもあったんだろうと思います。それは彼が杳子と出会った頃を、「自己没頭」という「健康な病い」の中にいたという記述。そして、その後は「女の澄んだ目で、幼い山男のガサツな、自信満々な振る舞いを静かに見まもる気持ちになった」とあります。杳子の奇妙な振る舞い自体が彼を惹きつけるものだったということでしょう。
二人が付き合い出してからは、境界線を互いの糸がらせん状に絡み合いながら行ったり来たりする様子ではないかと、私も感じました。ということで、この小説は社会、世の中が線引きした健康・病気の溝を中において(中間に線を引かれてしまって)互いに向こう側への欲求を持ちながら、行き来する物語である、というような印象。彼が杳子の世界を忌避したり興味本位で見てはいないと思います。前にやった『小フリイデマン氏』の構造も連想されますね。

いま、障害のあるなしの境界という話が出たけど、私にはこの杳子という人が障害を持っているというふうには見えない。この作品には、病気とか健康などという言葉が出てくるけど、その言葉の持つ意味、というかそれらの言葉の差異がどう読者に伝わるかがよくわかんない。差別という観点からもどう考えていいのか、どう感じを表現していいのかもわかんない。
ただ彼女がすごくこだわりが強いことは随所に出ている。これが杳子にとって問題なのはよくわかる。私の友人にも、たとえば朝登校前に自分の髪型が思ったとおりにならなくて遅刻してしまったり、一日憂鬱になっちゃうと言っていた子がいます。私自身、そういう傾向が強い人間だという思いもある。このクラスにも、携帯のゲームアプリにハマっちゃっている人もいるでしょ。でもこういう言葉が現実を切り分けて、障害を作っているという現在の様子を描いた作品とも思えない。

でも、杳子が姉との軋轢を彼にさかんに訴えているところがありますね。家でショートケーキを食べるところ。ここで杳子は姉の一挙一動を冷たく観察して、彼はその杳子の様子に恐怖に近い感情を覚えます。そうした杳子を宥めながら、そのこだわりを「癖」という言葉を選んで使っている。杳子もそれに従って「自分の癖」と呼んでいる。「自分の癖の露わさで、相手の癖の露わさと釣合いを保っているのね。それが健康ということの凄さね」と言っています。まさしくそのとおりですね。私もそう思います。

そして、「だけど、あなたに出会ってから、人の癖が好きになるということが、すこしわかってきたような気がする」と言い。彼は彼で、「嫌悪の中からようやく差し伸べられた彼女のやさしさを、理解したという気持ち」を感じている。
続いて彼女はこう言います。
”あなたには、あたしのほうを向くとき、いつでもすこし途方に暮れたようなところがある。自分自身からすこし後へさがって、なんとなく稀薄な、その分だけやさしい感じになって、こっちを見ている。それから急にまとわりついてくる。それでいて中に押し入って来ないで、ただ肌だけを触れ合って、じっとしている……。いつも同じだけど、普通の人みたいに、どぎつい繰返しじゃない。”
彼は、この杳子の言葉の後で、自分自身も「健康人としても、中途半端なところがあるから」と応じているんです。
やっとここで二人は互いの境界を、溝を埋められるという実感を持てたんじゃないでしょうか。私、この部分を読んでちょっと感動しちゃいました。二人は互いに行ったり来たりしないで一つの領域にいることができたということじゃないかな。
しかも、そのまた後、杳子は二人の食べた後の皿を重ね合わせてテーブルの真ん中に置く、というより置くことができた。ここも当然二人の溶解の表象ですね、なんてったって重ね合わせちゃうんですから。《みんなは顔を見合わせた》
私もここでも『小フリイデマン氏』を思い出しました。こっちのほがいい小説の終わり方という感じがします。

なるほど。自分なりの読み方ができてよかった。
もしかして、杳子はメンター?

前に戻りますけど、二人が初めて肌を合わせたときから《またみんな顔を見合わせた》、「自分自身の軀のことを気づかせてやりたい、そして自分自身のありかを確にしてやりたい。そんなはじめの欲求が、情欲の引いてしまった後にも、まだ蒼白く残っていた。」とあります。軀のこと、とは彼女がもう痩せ細った少女ではないことを指すのだろうが、情欲が引いても蒼白く残っていることとは、彼女に対する励ましの気持ちではないでしょうか。僕はもうこの時から、彼は杳子の助けによって新しい世界に入ることができたと思う。このすぐ後で、杳子が待ち合わせにすこしでも遅れると「途中で失調に陥ってうろついている杳子の姿をなまなましく思い浮かべて、いても立ってもいられない気持ち」になった。とあります。心配ではなく、うろつくような状態を彼自身のこととして恥辱に思えたからだった。
これどういうことでしょうかね。僕は杳子が、「彼」という人物の新しい世界に入るガイド、というかメンターだった、ということじゃあないですか。そう、『羅生門』にあった「老婆」の役割を杳子がしたんだというような……。変かなあ。

僕も、変な引っ掛かりがありました。杳子がこだわりの世界に入っている時、頭が前に出ていって上体がまがっている姿勢でいることです。何回かそう書いてありますよ。何を表象しているのか、よくわかりませんが。腰が曲がっているから、といって、『羅生門』の老婆、ということはないと思うけど。
ついでにもう一つ。杳子の姉の夫。この人が出てこない。姉は昔「病気」だったと書いてある。しかも妹が入浴しないと言っているように、自分の過去の状態と似ている思うと妹のことを心配している(あるいは忌避している)。こうした姉と結婚した杳子の義理の兄はどういう人だったのか。これは書かれていなくてもいっこう構わないことなのか、どうも気になるんだ。兄も「彼」と同じような心理的な成長の上で結婚したんだろうか?
この姉は面白いよ。言っちゃ悪いけど。
杳子が姉について語るところで、こう彼に向かって言う。
「あの人、むかし、おかしかったのよ」「ちょうど今のあたしと同じ年の時だわ。あの人、家から駅まで歩いて十分ほどの道を、三十分かけても駅に行きつけなくて、梟みたいな目をして家にもどってくるのよ。」と姉の毎朝の家から駅までの行動を説明した後、「……でも、じつは何もかもわかってたのよ。正気だったのよ。あの人は。ただ強情で、身勝手で、毎日一度自分の感じ方を通さなくては気が済まなかったんだわ。その証拠に、いったん駅まで送って行ってもらうと、あとはケロリとなって学校へ行って、ちゃんと戻ってくるんですもの」と言っています。彼は、それを聞いて、かえって杳子の冷ややかな現実感覚に驚いたのだが、もし杳子の認識が正しいなら姉は詐病であったということになるんじゃないか。少なくとも意識的な異常行動だったと杳子は言ってるんですね。そういう杳子はどうなんだろう、と読者もわからなくなります。
どうも、杳子も彼も意識している「境界」感覚はあやふやなものだという感じがしてきませんか。
フーコーと内田樹、三木卓の言ってることを紹介しよう

うん、ちょっといいかな。
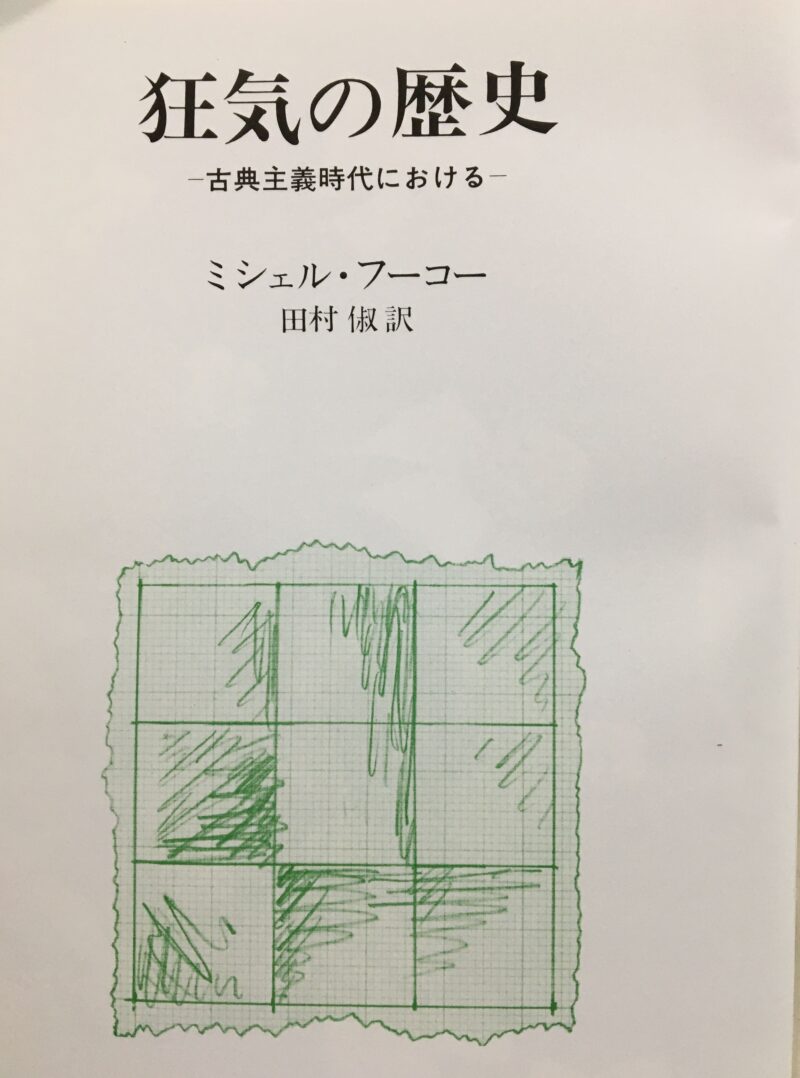
これは言葉として強烈なものなのでどうしようかとも思ったんだが。ミシェル・フーコーに『狂気の歴史』という有名な著作がある。その表題がこの小説で語られるのがいいか悪いかわからないけど、ともかくとして、これを以前拾い読みをしたことがあるんだ。しっかりと、どころか全体を流し読みもしてないんだけど、その一部を紹介しておきたい。
”病気が位置している社会空間は、かくして完全に新しくなる。かつて中世から古典主義時代の終わりまでは、この空間は同質なままであった。貧困や病気におちいると、どんな人間にも他の人々の憐れみと心遣いを受ける権利があった。人間はひろく普遍的な意味で各人の隣人であったし、たえず万人に自分の事情を申し出ることができない。しかも、その人間が遠方からやってきてくれていればいるほど、その顔に見覚えがなければないほど、その人間がおびる普遍性の象徴はますます生き生きとしたものなっていた。当時は、この人間は<あわれな人・ミゼラーブル>、とりわけ<病ある人・マラッド>だったのであり、その無名性のうちに神の栄光をたたえる力を隠していたのだった。”
となれば、近代でないならば杳子は杳子のままで、本来的に健康と病気の間の溝などなくそのまま生きることができたはずだ、ということにならないか。
このあとフーコーは18世紀以降の、この病の領域は見捨てられたのではなく、「救済にいっそう多くの自然的な強烈さ」を与えようとした、と記している。「施療院は病気を生み出すところ」なのだとも言っている。
つまり本作の「彼」という男は、この近代性のせいで、杳子の世界への欲望を高めてしまった、というふうに読めないか?例の内田樹は『寝ながら学べる構造主義』で、狂人は「別世界」からの「客人」で、あるときには共同体に歓待され、「この世界の市民」に数え入れられると同時に、共同体から排除されたのです、と書いているが、これはフーコーの文章とは違っているような気がする。むしろ境界を作って歓待できなくした、と受け取るべきではないか。別世界と言いながら、同質的な空間と意識を失っていたという状態の認識が大事なのじゃないかな。
フーコーのいう、時代が作った境界線のせいで杳子はあっちとこっちを行き来する感覚を持ってしまったと言えないか?構造主義の言語観と同様、分節によって事実が出現するということで、そこに生きる男女の物語、というふうなことかな。
また、この文庫本の解説では三木卓という作家が書いている文が本の末尾にある。
世界という不可知なもの、そのことを過敏ともいうべき形で意識せざるを得なく、未知の闇の深さのなかで現実を確実・絶対なるものとして把握することの不可能を知っている男と女。世界を錯覚し幻想しつつ、それにひきずられながら盲(めし)いた者として生きざるを得ないことを意識している者たちが同行者を見つけ出し、共同で生きることを試みようとしたものがたりである、といえるだろう。
まあ、よくわからないんだけど、こんな読みでなくてもいいよ、各自でこう読んだということがあったらよく整理して書いてみてください。



コメント