
誰が裸の王様なんだろう?

今回も開高健の小説『裸の王様』雑誌「文學界」1957年の作だ。前回の『パニック』『巨人と玩具』の自分なりの読み方も頭に入れてこの小説を読み解いてみよう。
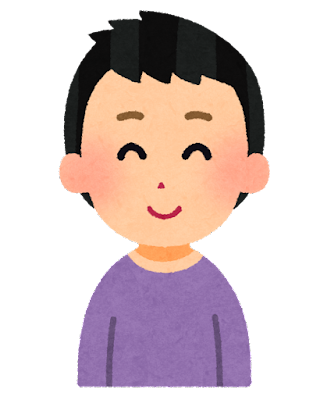
話はわかりやすい。最後にはちょっとした気晴らし感もあってそれが印象の良さにつながっている。ただ悪役がはっきりしていて、これまで読んできたさまざまな短編と比べて、単純な構成だと感じてしまいました。
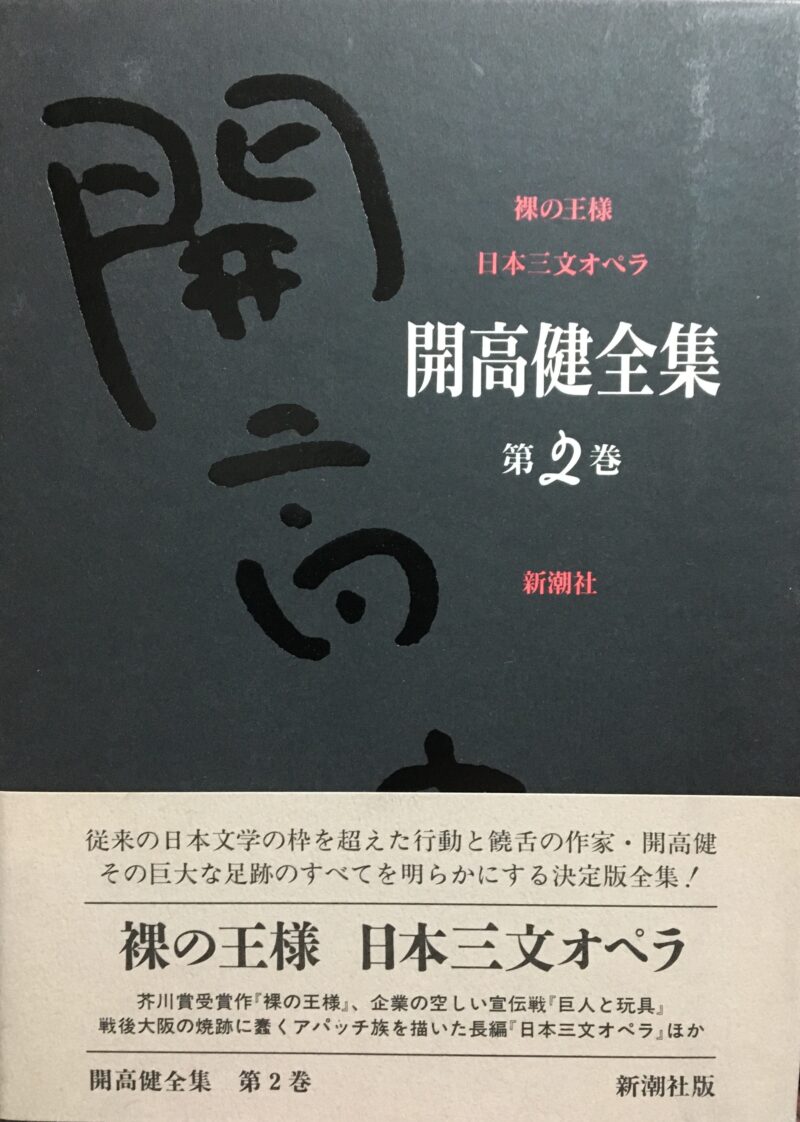
実は僕、昨日図書館で全集を借りて、その第一巻の月報を読みました。それに向井敏という人が、『パニック』が世に出たのは平野謙が最上級の評価をしたからだと書いてありました。僕は平野謙は名前だけは知っていたので、ちょっと意外だった。平野謙がこういう小説を評価するとは思えなかった。もっと私小説的な(?)ものが好みだったのかなと思っていたんです。平野謙を知ってたのはたまたまで、何か戦争中の転向のようなことと関連して、名前だけ知ってたんですが……。もっと政治的な色がついた小説を評価する人だと思ったてた。そういう人が「小説をよむオモシロサを、ひさしぶりにこの作品は味わわせてくれたのだ」と書いているんです。
ちなみに向井氏は開高健の友人なのに『パニック』が発表されていたのを知らずにいたらしい。それは掲載誌が『新日本文学』だったからだと書いています。それを「まさか彼が、あんな幼稚な政治と文学論議に明け暮れている雑誌に作品をあずけていようなどとは思いもせず、手に取ろうともしなかったのである。」と書いているんです。この月報の最初のエッセイは石原慎太郎だし、どうも胡散臭い人たちだ。

でも私もこれは良かったわ。それはテレビドラマの『半沢直樹』でみた復讐の爽快感と同じじゃないか、と思いました。それは低俗で悪いことですか?私はそうは思わない。そうは思わないけど、そういう感覚を、毎回の読書で体験したいわけではない。つまり『檸檬』や『城の崎にて』を読んだのとは違う面白さでした。
ただちょっと思ったのは、悪役たちに勝ったことで良かったというのがこの作品の最終地点なのか、というと、どうかなという疑問が湧いてきます。別の解があるような気がする。

つまり、「〈ぼく〉という画塾の先生が生徒の太郎に自由な発想をさせて成功した物語」という読み取り……ではない、ということかな。
めでたし、めでたし……ではない、としたら?

そうですね、「画塾で児童画を指導していた〈ぼく〉を利用した、既成児童画教育界の権威たちへの復讐の物語」なんていうことも考えられる。えーっと、「本来あるべき美術教育の手法を使って既成の権威たちに一泡吹かせた男の物語」というようなのも考えたんだけど。

整理してみると、まず〈ぼく〉が塾で追求したものとはなんだったのか、ということ。太郎を友人の山口から一時的に任された時どうしようとしていたのか。太郎は何に対しても反応がない。母親は実母ではないが、相当太郎に関わり合って、干渉的でもある。太郎は全く反発しない。〈ぼく〉は太郎になんとか自由な自分を出させたいと思う。そしてそれはだんだんと効果を発揮する。
ここで、注意したいのは〈ぼく〉という先生が画塾の中で特に太郎だけを取り出して教育しているように書かれている点でしょう。なぜ太郎が〈ぼく〉のターゲットにされたのか。〈ぼく〉の児童画に対する戦略はいかに児童たちに、大人から与えられた道筋を捨てさせるか、ということにある。その方法論は、ひとつは児童の心を溶かしていくこと。ひとつはなるべく物語の背景や時代、その他の知識から遠ざけること、だった。そしてそれは太郎を少しずつ変化させていった。
なぜ太郎だったのか。その〈ぼく〉の戦略の対象として最も適当だったからだ。太郎の父は息子に関わらない、母は彼に過干渉。そういう彼こそ〈ぼく〉にはふさわしかった。しかも、太郎の父親は絵の具の会社社長、というわけだ。なんという好都合だろうと思いませんか。〈ぼく〉にとって絶好のチャンスが巡ってきたわけだ。自分の指向を児童画で完成させるための外国の児童画との交流も実現する。〈ぼく〉の勝利は間近だったでしょうね。


その読みに僕も賛成だな。ひとりの生徒と自分の交流を描いている語り手の〈ぼく〉は、その幸運を利用している自分を意識していないね。コンクリートの橋の下で「今日は遊ぼうや。カニでもとろうじゃないか」と太郎に囁く言葉は、いかにも共犯者的な信頼感を子供に植え付けただろう。こういうパターンはいろんなドラマに使われるものだね。
僕はここらへんを読んでいて、前に聞いた「信用できない語り手」という言葉を思い出したよ。他の画塾の生徒のことは、まるで無視されているように、よくわかんないしさ。まさしくこの画塾の先生ってそれじゃないか。
前にも出てきましたね、デイヴィッド・ロッジという批評家の本を検索して見つけて、「信用できない語り手」という項目をさらっとめくったら、『日の名残り』について、もし語り手の執事スティーヴンスが「信用できる」語り手であったら、「死ぬほど退屈な小説が出来上がっていただろう」と言ってる。面白いだろ?開高健の場合も、もし〈ぼく〉が信用できる語り手であったらこの小説は退屈な小説である、ということになるなあ。
これ意地悪な読み方かなあ。

そうよ、意地悪よ。でもそれが正しいような気がするのよ。

そういう悪意ある読み方、いいなあ。もっとやってみろよ。

どうも、先生も「信用できない指導者」のような感じがするけど。いや、失礼しました。
さて、重要な言葉が〈ぼく〉がデンマークに書いた手紙の中にある、と発見しました。
その手紙のなかでぼくは自分の立場と見解をつつまずのべた。自分が画塾をひらいていること、その生徒の数、年齢、教育法。ぼくはできるだけくわしくそれを説明し、創造主義の立場から空想画が児童のひとつの重要な解放手段であると思うことをフランツ・チゼックの実験などを引用して説明した。こんなときは地を這うような、糞虫のような誠実さよりほかに迫力を生むものはなにもないと思ったので、ぼくはなりふりかまわずくどくどしゃべった。そして、結論として、子供にアンデルセンの童話を話して挿画を描かせ、おたがい交換のうえで比較検討しようではないかと提案したのである。共通のテーマをあたえれば、風土や習慣の相違がもたらしやすい誤解をさけてかなり公平に画の背後にあるものを観察しあえるのではないかとぼくは考え、またそのように手紙にも書いた。
ここではオーストリアの美術家・美術教育者のチゼック(聞いたこともない人でしたが)を使って、美術教育の新しい道を探し、「児童の解放手段」として協力を求めたんです。簡単に言えば、教育のための実験を提案したというわけです。児童の観察をしようということですね。そしてそれは彼らの「解放」のためだ、という。さて、それは本当でしょうか。僕は、これを信用できない、と思うんです。この数行を読んでも、「糞虫のような誠実さ」という言葉からも感じます。彼自身のピュアな動機とはどうも感じられない。だって太郎は〈ぼく〉の観察の対象とされているわけでしょう?
〈ぼく〉先生の目的は、「解放」? それとも……

ちょっと前に本校で研究会があったんだよ。研究授業をして国大の先生とか教育研究所の研究員とかのご講評を伺うというやつだったんだけどね。彼らはみんな今までの高校の授業に知識注入型だと批判をしていた。こっちもそれがわかっているから、班別話し合いなんかをずいぶん取り入れて研究授業をしてね。
ある研究員は北欧の教育をずいぶん推していた。ああならなくてはならないというふうに。問題を自ら提示し、解決していくような「力」を付けるように促さなければならない、と。他日別のルートで横国では受験生にそういう力を求めているんだと言っている、と聞いた。

しかーし。みんな考えてくれ。何年かののち高校ではそういう授業がどこでも盛んになされるだろう。彼ら教育学者や役所の人たちが考えているような授業になるだろう。そのとき彼らはどういうふうに身を翻すだろうか。彼らはその教育理論からまた新たな理論に着物を取り替え、新たな教育「こういう教育こそ正しい」という理論を学校に押し付けるだろう。私は予想しておくが、あまりに基礎的知識が足りない優秀な生徒(?)が増えて、そこにまた反省が起こる。そう思うよ。その新しい教育の研究会はまたこの学校で行われるんだろう。
さて今聞いた読み方はつまり〈ぼく〉は自分の自己実現のために行動しているのではないか、はっきりとした、明瞭なエヴィデンスはないけれど……という読み方だね。これは難しいところで、確かに太郎のような児童を「解放」してやるということは、ひとつの教育の使命ではある。でもそれをしたいというのが、指導者のピュアな思いなのか、それとも自分も一発花を咲かせたい、という欲なのか、それは難しいな。『パニック』だって社会のための公務員の仕事、ということを否定できないだろ。ネズミの件は俊介にとって「たいくつしのぎ」だというが、同時に公務員としての正義であり、かつ点数稼ぎでもあったんだね。〈ぼく〉においても同じだよな。まさしく点数稼ぎ無くして仕事の意欲なんかありえないよ。さっきの教育研究者たちもそうだ。正直言って、点数稼ぎのために先端的教育理論の紹介、輸入を学者の使命と思っている連中もいると想像するがね。
……ただし私だけは、君たちの国語力向上しか考えていません。

えっ?……まったくいい加減にしてもらいたいよ、真面目に聴いてんのによ。
でもさあ、なぜこの〈ぼく〉という画塾の先生って、どこか信用できないっていうふうに見られちゃうのかなあ。実際ひとつの芸術教育界の壁を打ち破ったということは言えるはずじゃあないか。最後の場面でも、審査員たちの態度はさっきの先生の話に出てきた教育関係者たちの様子と通じるものがあるねえ。でも、どうして〈ぼく〉は読者にそう悪く受け止められちゃうんだろう?

それは作者が、明らかに意図している。そういう人物として書いて、そういうふうに僕らは読んでいる。
その根拠を具体的に言えば、「〈ぼく〉の笑い」だよ。読者は〈ぼく〉の笑いに彼への「?」を感じる。特に最後の「哄笑」には反感を持ってしまうね。勝利の笑いだもんね、ざまみろという感じでね。それで、思い通りの作品を太郎が描いた時にも、腹を抱えて笑っているんだ。「自分の思った通りの作品」というより、「自分の思った通りの児童の完成」に満足しているように感じるからだと思うんだ。
そういう満足感は他の大人の目指しているところとそう違わないんじゃないかという思いなんだよ。ぼくはこれ作者の意図だと思う。

そうだね、〈ぼく〉の胡散臭さ(?)は感じちゃうね。最後は「はげしい憎悪が笑いの衝動に変わる」と言っているからね。
さて、そもそも『裸の王様』という題名よ。この原典を読んだことある人いるの?……誰もいない。誰もが知ってる「王様は裸だ!」は知ってるけど、あんまりアンデルセンなんて読んだことないよな。でもどんな話だかはみんな知ってる。要するにということだろ。
実験は完全に成功した。途方もない成功だ。昨日、ぼくは『皇帝の新しい着物』を話してやったのだが、話すまえにぼくはこの物語がほかの物語よりはるかに装飾物がすくないことを発見して、即興で抽象化を試みたのだ。
太郎はそれを「大名」というイメージでとらえた。そのため背景には松並木とお濠端が登場したのだ。
「むかし、えらい男がいてね、たいへんな見え坊な奴でな金にあかせて着物をつくっちゃあ、そんな調子でぼくはこの物語を骨格だけの寓話に書きかえてしまったのである。この物語にふくまれた「王様」や「宮内官」や「御用織物匠」などという言葉は例え内容がわかっても子供を絵本のイメージに追いこむ危険があった。『シンデレラ』や『錫の兵隊』や『人魚のお姫様』ではこんな操作ができなかった。太郎の描いたあとの四枚の作品は根本的に書物の世界である。外国の童話を話せば外国の風物が児童画にまぎれこむのは当然だ。だからぼくは子供がほんとに描きたくて描くのなら絵本の既成のイメージが画にまぎれこんでもしかたがないと思う。しかしぼくはネッカチーフをかぶった少女やカボチャの馬車を描かせることを目的としているのではないのだ。『皇帝の新しい着物』では権力者の虚栄と愚劣という、物語の本質を理解させてやりたかったのだ。
権力者の失敗、虚栄、愚劣。これを絵にさせたかった、といっているのだ。結局これ、誘導ではないの?とぼくは尋ねたいんだ。この後の文で〈ぼく〉は太郎の実体験による発想から描かれたものだと主張していて、この疑問に対する予防線を張っているんだけど、たとえばさ、ありえないけど太郎の絵が、裸のバイデンとか、裸のプーチンなんかを描いてあったとしたらこの先生はどんな顔をしたんだろう。むろんこの小説が現代の小説であったら、外国人の顔を見て、それでも大笑いしたろうか?これが、現代の話であって、太郎の親がバイデンやプーチンへの批判を常にしていたとしたら、それは大人の誘導じゃないのか。
『皇帝の新しい着物』って実際はどんな話?

それに、私には「権力者の虚栄と愚劣」が物語の本質だと本文中で言っていますが、それは本当なのかと思うんです。それこそ、この物語に別の読みの可能性があるとすれば、〈ぼく〉先生の基本的な立場がおかしくなるんじゃないかと思うんですが……。どうですか、もう一度アンデルセンを読んでみませんか。
あらすじだけでも「権力者の虚栄と愚劣」とは違う読みが可能だと思うんだけど、どうですか、先生?

うん。少なくとも王様には同情するなあ。強権的な人物というより、大臣や家来たちの意見に流されて悩んでいるようだよ。

そうですよね。虚栄と愚劣はむしろ最高権力者より下位の人々に現れており、それに王は同調していっただけですよ。
つまりわたしからすれば、この童話は「人間というものの虚栄と愚劣」くらいの感じなんです。陳腐ですけどね。権力者だってそんな人たちなんだよ、というふうな教訓を感じます。
だとすると、この〈ぼく〉という先生がやはりこの童話をどう読んだか、という問題がどうしても生じてしまう。いずれにしても指導者の読みが児童の作画に大きく影響するということです。本文の、「むかしえらい男がいてね、」の「えらい」という一語がまずバイアスをかけている。「たいへんな見え坊」を「ちょっと人に流されやすい」と言えば、むしろ気弱な男を想像するかもしれない。だいたい「男」にするか「女」にするかも説明で必要かどうか。すごく難しい問題だと思うんですよ。教えたい「物語の本質」こそ恣意的に、あるいは時代や環境や何かに縛られているものですよ。

さらに、先生がまえに言ってたことを思い出すと、僕らは全員「遅れて席についたゲームプレーヤー」だという話がありましたよね。それなんとなく頭に残ってんですよ。遅れてきた時に先着者たちから提示されたゲームのルールに則ることは、必要なことなんじゃないでしょうか。というか多かれ少なかれ、それ以外に道はない。王様を西洋風に絵に描く、描かない、ということはそんなに生徒の感受性の問題とはならない、と思ってしまいました。

絵を描くかぎり真に自由に描くことはありえない、ということだね。あるいはなんであれ子供は自由に描いているんだ、ということかな。本文には「太郎はあくまでも内心の欲求にしたがったのだ」とあるけど、それが〈ぼく〉先生の勝利を自覚させたわけだけど、どう考えるか……。
太郎の絵を見て、〈ぼく〉先生は「焼酎を紅茶茶碗にみたすと、越中フンドシの殿様に目礼して一気にあおり、夜ふけのベッドのうえでひとり腹をかかえて哄笑する。自己満足の笑いとしか感じられないです。

仕事というものの根っこにあるものだね。仕事とは誰かになんらかの影響を与える快感。それを食って生きていくのが僕たちだということかね。思い出すのは、裁判官という職業の人たちはものすごいプレッシャーがかかるんだそうだ。当たり前と言えば当たり前だけど。でも彼らの給料は、そりゃ高いけど仕事が日常生活に与える抑圧に見合うものじゃあないんだって。24時間が道徳的なものでなくてはならない、ということで。
じゃあなぜそんな職業を選ぶのかというと、もちろん正義感も強いんだろうけど、彼ら彼女らに、法廷で全能の神的な力を持たせてくれるからだ、という。そんな話を聞いたんだ。被告、被告人の生殺与奪を握る権力が判事たちの職業倫理の元にもなっているって。
そんな支配感が元にある、なんて信じられないし、これは言い過ぎだとは思うよ。でもなんらかの影響を他の人、ものに与えたいという欲求を持つものであるとは想像できる。職業ってそういうもんじゃないのかな。ただ金儲けしたい、いい暮らしをしたい、楽して過ごしたい、だけじゃないよね。サラリーマンだって、商売人だって、みんなそういう欲求を持っているんでしょう。先生だって、そういう存在でしょう?いや、先生という職は最もそういう欲求の中にある職業です。先生、わかってんの?

こら!調子に乗るな。
でもさ、それを「贈与」というのじゃないかなあ。みんなにとっては私からの贈与なんかいらないよ、というかもしれんけど。でも授業に参加してもらうことは私にも贈与していただいているんだね。だから、そういう感覚がサービスとは違うというわけだ。サービス業だって贈与なんだろうけど、学校はもっとストレートな意味で贈与なんだよ。たとえつまんない授業でもね。
「贈与」なしじゃあ生きていけない

だから、この作品での〈ぼく〉先生の態度も当然なんですかね。彼が物語る自己満足の印象もそれだけ彼の嬉しさを表しているのかな。


こうして、開高健の小説を読んできたけど、全て職業ということを考えさせるものだった。必ずしも仕事の素晴らしさを書いたものではなかったが、何か職業を持って生きていく、ということがどんなことなのか、一例を見せてくれた。私のようにいい加減に働いていても仕事として一応は成り立つし、仕事の上で、すごい荒波を繰り返す人もいる。もっと気楽に、莫大な報酬を得る人もいるだろう。君たちももうすぐ現実に向き合うわけだが、ほらこの各作品の人物のようにみんななんとかなってる。決して恐れないで生きていってほしいな。
この言葉も、贈与だよ。
追加の講習での生徒への話
以前読んだ本で、この授業にもいろいろなところで参考にしてきたものに『新文学入門 T・イーグルトン『文学とは何か』を読む』大橋洋一著』がある。大変面白い本なんだが、そこに「裸の王様」についての記述があった。本に自分で傍線を引いてあるんだけど全く忘れてしまってるんだよ。ホントに自分で自分がいやんなっちゃうよ。でもここで、その引用をしておこうと思います。「脱構築」という言葉があるけど、これは、いったん今までの考え方をまっさらにして組み直すこと、くらいに考えておいて読んでほしい。
ここにあるのはテクスト(これが織物と関係する語であるのは象徴的ですが)に対する二つの姿勢です。ひとつは見えないものを見えるということ。もうひとつは見えないものを見えないということ。この二つは二項対立の関係にあります。そしてすでに脱構築の手続きに慣れた読者なら、これが簡単に脱構築できることを予想するでしょう。たとえばこの童話を、学校で先生が生徒に聞かせ感想を言わせるとします。その時、先生が求めるのは、人間は見栄をはってはいけない、正直にものを見たり、いわなければいけない。そうでないとあとで罰があたるといった教訓めいたことでしょうか。もし生徒が、このような教訓を引き出せずに、ただあら筋をなぞったり、面白いだのつまらないだのという感想を述べることに終始したら、先生は、その生徒になんとか教訓を発見させるよう努力するかもしれません。しかし考えてみてください。この時、先生は、この童話のなかの詐欺師の仕立て屋のように、そこにないもの、見えないものを見ろといっているわけです。《……》つまりこの童話は教訓話として、そこに書かれていないことを見つけるよう読者に促している。しかるに、その内容は、見えないものを見てはいけないということなのです。これは見えないものを見る姿勢を愚かなものとして物語の中では排除してしながら、物語そのものは、見えないものを見ることを読者に要求しているわけですし、またそうでなければこの物語は教訓話として成立しません。したがってこの物語のメッセージが、見えないものを見ることなのか、見えないものを見ないことなのかは最終的に決定不可能になります。脱構築終わり。
岩波セミナーブックス55 p154
なんぼなんでもこの童話を教訓として読まなきゃいかんぞ。っていう授業は高校ではしないけど、つまりいろんな読み方があり、そのいろんな読み方をひとつひとつ検討することができる。その検討こそ私が面白いと主張していることなんだ。
それに、考えてみると、こういう教訓的読み方を押しつけてくるような先生がいるからこそ、それを否定する、新しい読み方を主張する生徒が出現する。言っただろ。ビートルズが世界を席巻したのはあの髪型を嫌がった大人たちがいたからなんだって……。
実はこの後筆者は教訓話しという読み方自体をイデオロギー的読解として、新たに「脱構築」していくんですが、その後の論もなかなか面白い。これはぜひ、時間があるときに読んでほしい本だな。





コメント