
「水車小屋攻撃』朝比奈弘治 訳 岩波文庫
貧しくても淡々と、やる


ジャン=ルイ・ラクール。七十歳。ラ・クルテイユという人口百五十人ばかりの、町とは遠い村で生きてきた。とても貧しいこの村の中では、彼の家はそれほど貧しいとは言えないまでも、懸命に働きながらも食べていくのがやっととの生活だった。
家族は子供三人で、上の二人の男と一番下のカトリーヌ。この娘は結婚したが夫の死で、十二歳の息子一人を連れて帰ってきていた。
ジャン=ルイは今まで病気をしたことがなかった。彼の皮膚は黒く、まるで樹木のようだった。歳をとるにしたがって寡黙になり、言葉は無駄だと心得ていた。
ところが二ヶ月前に突然動けなくなり、そのまま寝込んでしまった。次の日には何とか畑に出たものの、土はもう以前のようにいうことを聞いてくれなった。息子たちは父のことを心配していたが、この日は強情に家に帰ることを拒んだ。そして家に帰ってくるとそのまま床から起き上がれなくなってしまった。
こんなことは初めてで、息子たちは次の日医者に来てもらおうと相談する。しかし送迎にはまるまる一日使わなければならない。老人は怒ったように、金がかかりすぎる、医者は必要ない、と家族に告げた。息子たちは、いいのかい?自分たちは仕事に行かないと……、と言うと、老人は言った。「もちろんだ。早く行け。世話をしなきゃならんのは畑の方だ。俺が死んだとしてもそりゃ俺と神様だけの問題だ。もし収穫がダメになったらみんなが苦しむことになるんだぞ。」と。
こうして2、3日が過ぎた。彼らも運命を甘受していた。土が老人を取り戻そうとするのを恨む気にもなれないのだ。朝に一瞥、夕に一瞥、それしかできないのである。
ある日老人の頼みで、昔なじみの、彼より年寄りの田園監視員を呼んだ。そのニコラはやってくるとルイのそばに腰を下ろし、二人は何も語らずに、ただ見つめあった。そしてその番、子供たちが爺さんの死を見つけた。

「お父っあんが死んじまった」と息子たちは言い合った。とにかくお父っあんはずいぶん頑張った。たくましい男だった!そう思うと子供たちもなぐさめられた。
その日も次の日も子供たちの半分は働きに出ていった。司祭を呼んで棺を墓に運んだ。墓穴はまだ完全ではなかった。途中で司祭は立ち去ってしまった。
墓穴が完成してから、棺をみんなで降ろす。
ああきっとラクール爺さんもこの穴の中でおちつけるだろう。爺さんと土とは古くからの知り合いだ。これからも仲良くやっていけるに違いない。もう50年も前に爺さんが初めてつるはしを土に打ちこんだ時から、土との約束はできていた。たがいの愛情はこういう形で終わりを迎え、土が最後に爺さんを引き取ってくれることになっていたのだ。それにしてもなんと心地よい休息だろう!
カトリーヌ、アントワーヌ、ジョゼフがそれぞれひと握りの土を墓穴に投げ、カトリーヌの息子、ジャキネはヒナギクをたくさん摘んできていっしょに投げ、彼らは家に帰った。
自然主義?いい話じゃん

ゾラの短編小説だが、ゾラという人はフランスの自然主義の作家の代表格とみなされている、自然主義というのは現実を観察し、真実をそのままに描こうとする派、と説明される。現実の醜さを美化したり、隠匿したりしない、リアリズム。当然、愛だ、恋だ、美だ、というロマン主義とは対立する。と言われるんだけど……。
で、この小説はというと、私は決して醜くはない小説だったと思うんだけど、君たちどう思う?

いま、現実の醜さみたいなものを描く、というふうに先生は言いましたが、まず現実は醜いというのが固定的な見方じゃありませんか?それこそ、美しい、醜い、という観念がまず問題だったでしょ?醜い現実があるからこそ、その中にちょっと光るものが小説の種になることがある。この小説こそその良い例です。厳しい現実、そして自然。これがこの作品を支えている。現実や自然が厳しければ厳しいほど農民たちの物語は完成されたものになっていきますよ。
もし現実が、僕たちのいるこの世の中ということなら、自然主義文学なんて何の興味も持てない、物語にならない文学ということになりますよ。そんなものに何の意味があるんですか。

僕は正直に言うと、この小説が好きです。今の話で、僕たちはいま極限の厳しさというものの中にはいないけど、ぬるま湯の中にいても訴えてくるものがあります。少なくとも、僕にはありました。金儲けや栄達という目的じゃない一生もあるのかなと、ちょっと思いましたね。実際には僕の未来はそうはならないと思いますが。

いや、それは僕も同じだが、自然主義というのがよくわからないんだ。自然主義とかいう考え方の根本には、中心に、あるいはどこかにロマン主義っていうものがあるんじゃないか、って思うんだ。なんの感情もなくそのまま現実を描くなんてことできるんですか?
当然どちらの主義にも厳密な定義があって、僕が誤解しているのかもしれないけどね。

その思いとは、たぶんズレた考え方だとは思うけど、自然主義という言葉に惹かれて思ったんだ。この小説の主人公は誰だろうって。主人公がいなくてもいいのかもしれないが、つまり作品の狙った中心の”対象”は誰なのか、っていうこと。
僕はこれは爺さんじゃないと思うんだ。前にも主人公が通常の読みとは違うという意見はあったが、ここでもそれが当てはまるんじゃないか。
つまりこの小説の主人公は「土」だ。
土こそが農民を生かし、苦しめ、貧しくさせ、そして「取り戻す」。この土が「取り戻す」という言葉が読者をすごく捕まえる。そうだろう?単なる隠喩ではない。


それはそう思うなあ。「土が人を取り戻す」のか。土に帰る、のではないんだな。
お父つぁんは頑張った

これまた後でやりたいんだけど、こういうのまさにアレゴリーっていうんだな。土にこそ我々全て、生き物全て、を生かし、殺す力を持ち、そうする権利、能力も持つものなのかもしれない。ああ、それで自然主義という連想なんだな。アレゴリー(諷諭)についてはまた回をあらためて考えてみたいと思う。

老人は医者も拒否しますね。これはかえって現代的というべきかな。そして司祭はほとんど義務的な仕事ぶりという感じ。老人はあのフローベールの『素朴な人』のような祈りもないんだなあ。作者二人は同じくらいの年代を生きた人らしいけど。

このゾラの小説の面白いところは、老人に友人との会話をも拒否させている点だ。
いや、そう言い方は良くないかもしれない。ジャン=ルイ・ラクールは言葉も拒否したんだ。決してコミュニケーションを拒否したんじゃないよね。いわゆる神との交流は拒否したのかもしれないが。この人唯物論者かもな。

バルトは「神話は言葉だ」と言っているから、老人は物語をも拒否したということか。物語もなしに生きて、死んでいけた男なんだな。もしそうなら、大変な人物かも。

いや先生、たったひとつ老人が執着したことはありますよ。畑ですよ。畑仕事といいたほうがいいかな。爺さんは畑仕事には最後まで執着し、そして子孫にもそれを強制した。この「労働」の象徴が「土」なんじゃありませんか?ルイ・ラクールにとって意味のあることは、畑仕事だけだった。決して死に際して、後悔とか悲嘆とか残った家族への心配とかも、全然文章から感じられないね。生活の苦しさへの恨みもないみたい。こんな生活、休みもなく、報いられることもなく、「やってられねー」なんて思ってない。神への感謝なんていうものもないみたい。でもこれはこれで、彼に物語はあったと思うんです。
働きづめの人生をどう思って生きてきたのか、そういう男の人生を僕たちは個人個人でどう思うのか、を問うているような気がしますね。無知かもしれないが至高の徳を持った人じゃなかったのかなあと思う。

それはどうかな。僕はそういう読み方とはちょっと違う。

子供たちの、父親への言い方を読んでみてよ。「お父つぁんは頑張った」とさかんに父親を称賛している。父親はその誇りを保って土に帰ったんだよ。何に頑張ったのか、はいうまでもなく「畑仕事」でしょう。働きづめに働いて、そして安らぐ、地に戻る。それがたぶん彼の誇りだから、安心してしに臨めるんでしょうが。実際に子供たちも父の死を知った日にも仕事をする。というかしなければならないことを知っているし、それを当然だと受け入れる。病気をしても医者に診せないことも、父の意志どおり。運命として諦めるというより、もっと平然として受け入れてるように読めた。それは「至高の徳」とは少し違うんじゃないか。きっとお父つぁんがしたとおりに子供たちもして、死んでいくのを当然と思っていて、もちろん畑仕事も死ぬまで頑張って……。
なんだか東洋的な生活観、幸福観のように思えるんだけど、そういう影響はないのかな。
上には登らなくても下に安らぎがある

「土」は小賢しい「知」とは違うから。それがまさしく自然主義だってのは、面白い。
19世紀ってこういう話で、脱”神”なんていう思いが人々にも受け入れられたのかもしれないなと、ちょっと思った。だって、神様って天にいるわけでしょ、いやざっくばらんな言い方をすればさ。土は地べたじゃん。天上と地面、その対立に面白みを感じる。反キリスト教的な意識も作中にあるんじゃないかな、司祭の行動の記述を見て。さらに言えば、医者を拒否しているところでは近代科学にも。人を幸せにすることとは別のものだという思いを持たせる。
いま話があった言葉も同じだ。僕たちにも、国際的な人間になれということが押し付けられているし、そのためにはコミュニケーション能力を高めろと言われる。でも、このルイ・ラクールは昔からの友人となんの話もすることなく旅立つのだ。死ぬ前に友人に会いたいという願いをしても、二人の間にはなんの会話もなかった。これは人間の本質を語っているのかもしれません。なんだかロシアの小説を読んでいるような気がしました。
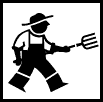
最後に老人はまっすぐ、広大な田園の中へ最後の息を吐いて死んでいった。穴には孫がヒナゲシの花を投げ入れた。この花は、別れの悲しみ、休息、眠り、慰めなどを連想させる花だそうです。老人は永遠の休みをとり、孫は彼の精神の後継者となったんでしょう。これは競争の苦しみや自意識の悩みとは関係ない生き方と言えるでしょう。

でも、土ではないコンクリート、日常となった耕作ではなく競争の仕事を選んだのは現代に生きる僕たちと言えるんじゃないか。もしこういう生活を否定するなら、少なくとも成長しなければならないという経済を、みんなで止めなければならない。でも、それに賛成する日本人がどれだけいるだろうか。もちろんフランス人だって……と思う。よくこういう物語がありがたられるけど、それはいつも私たちの選択なんだと思うんですよ。政権選択もそうだし、人間関係もそうです。これは当事者の選択なんです。そんなふうに僕は物語から連想しますね。

たとえば、最近の僕たちと同世代の女の子の環境活動家(名前を忘れたけど、確かグレタとかいったっけ?)も聞いたことあるけれど、それに賛同する声は僕たちの世代でも、大きなムーブメントになってない。つまり、多くの人に選択されてないんです。残念だとは思いますけど。

最後の場面で、「それから彼ら(遺族)は家に帰る。家畜たちも野から戻ってくる」とあるのは、人間も「土」の家畜だったんだな、と思わせる。私はそう読みます。だから、いまの話については、現在の私たちは「土」の束縛から解放されたけれど、その地位を得た代わりに、私たちはある安逸を失った。そういう物語だったと言いたいです。
私自身はこの流れは間違いじゃないと思うんです。いつまでも変化しない時代精神はそれだけで良くないことだし、安逸を願うのは弱者の論理ですよ。

そこが間違いじゃないかなと私は思います。
この小説は今読むから意味があるんです。数パーセントの人々の獲得する富が半数の人々の持つ富と同じだとか、あるいは暴力的な領土拡大だとかの現代の問題と、この小説に出てくる農民の意識は関係ないでしょうか。このお爺さんの生き方を、少なくとも立派だと称賛する感覚はいつまでも大切だと思うんです。

ということは、みんな貧しければいいんだということかよ。「一家は何とかかつかつで食べていける」と書いてあるけど、みんなそうなら確かに格差はないよ。そういう世界ならみんな仕事に疑問なく精出して、安心して土の中に入っていくよ。それでいいの?俺に言わせれば、それこそ、むしろロマンチックな話だよ。
フローベール『素朴なひと』との差を考える

いま話してるのはルイ・ラクールという老人の生き方、死に方について、それが良いのか、悪いのか、という話になっているような気がします。それは個人の考え方や価値観の違いであって、それぞれの主張の言い合いでいいと思います。それでも、互いの一致点は、働くことの厳しさがかつてはあって、それは休息がなかったり、生活の余裕がなかったり、圧倒的な貧しさがあった、などという問題点があった。そしてそれでも安穏な死に方をすることができていた、ということ、そういう貧しさを生き抜いた男の物語である、ということは一致しているんじゃないでしょうか。
私が話し合いたい問題は、そこ以外の小説の読み方があるのかないのか、ということです。

フローベールの『素朴なひと』との対比で考えると誠実に生きることは共通していても、その差が際立っている。それは宗教的な道徳観、倫理観だ。片方は鸚鵡が象徴している神の恩寵にしたがっている敬虔な女。もちろん過酷な現実に長く苦しんでも、その心にはいつも強い道徳心が宿っていた。一方はさっきの話にもあった、神とは言えない「土」への信頼感で生きてきた老農夫。フローベールの女主人公は天へと導かれ、ゾラの農夫は土に囲まれて安住の地下に帰る。女は自分の精神を継承する人を持たなかったが農夫は継承者としての孫までを持った。キリスト教をキーワードにして考えてみると、前者はまさしく宗教によって救われ、後者はもっと原始的な、自然によって安心する。ということで、ひとつ宗教的な観点から見て物語を説明できるんじゃないかと思いました。たとえばゾラの小説を、反キリスト教的とは呼べないかもしれないが、まさしく「自然に帰るような安らかな死を、神の意識なしに迎えることをを達成した一人の農夫の物語」とか、どうですか。


いま思い出したんだが、何年も前に甲府の美術館に行ったことがある。この美術館が当時話題になったのは、ミレーの絵を購入したことが理由だった。それで実際に見に行ったんだが、正直言うと私にはピンとこなかった。が、そこに描かれている落ち穂を拾う農民の妻たちや種を撒く人がちょうどこの小説の登場人物たちの暮らしだったのかな。それだとけっこう社会批評的な味もしてくるね。ミレーも「農民として生まれ、農民として死ぬ」と言う言葉を口癖にしていたという。
やはり、撒いて育てるということは食うための仕事という以上の、なにか崇高さを感じさせることだったのかもしれない。ミレーという画家も農業それ自体に何かを感じ取っていたのではないかな。
というわけで、ゾラのこの小説にまだまだ違う読み方が発見できそうだけど。たとえば、安逸な死というけれど、それは絶え間なく厳しい作業が保証するものであり、それはつまり現実には絶望しかないことを語っている、とかね。同じことでも表現の仕方にも工夫が要るよな。各自自分の言葉で表現してみてよ。


コメント