
(特にこの本について、わかりやすく、周辺知識もコラムで説明しているなど、初学者に丁寧な配慮があったことを記しておきたい。こういう本が文学理論や哲学にもっと出てきてほしいと願う。)
脱構築って読む姿勢のことなの?

さて、『作者の死』という小説を読みながら、これは文学理論というものには、こんなものかなという了解が少しはないといけないかな、と思ったね。簡単にいうと『脱構築』という考えかたなんだろうけど、かつては日本でもすごい勢いで広がっていったものだったらしいな。これをちょっとでも理解していこうと思う。今ははやらない思想のムーブメントなんだと説明される、つまりもう時代遅れなのかもしれないが、きっと近い将来の生活にも知っておいて損はないしと思うよ。
『構造主義』だってなるほどと思う考え方だったでしょ。そういうのは知っておいた方がいいよね。
昔私たちが小説や評論を読んでいた時は、それに関する文章は極めてエモーショナルなものばかりだった。「かっちりとした好短編」とか「ロマンティシズムの華」とか「リアリズムの姿勢に徹した作品」とか、そんな言葉で説明されていて、それで私たちも満足していたんだ。その上、批評に道徳上の規準が使われたりした。太田豊太郎がエリスを捨てたのはけしからん、てな調子だな。倫理や道徳そのものを否定するわけではないが、そんな文章ばかりじゃあな……。読者がなぜ道徳的な価値観にばかり引っ張られるのか、そのこと自体をわかりやすく書いてくれたものは読んだことなかった。
そして科学としての文学なんて、考えた人がいるとは思わなかったなあ。物語には「文法」がある、とかな。それを初めて私に教えてくれたのは、まずロラン・バルトだった。前にも言ったが、「コノテーション」の説明はなるほどなあ、と思ったもんだ。現代の神話だな。これが我々に、いわゆる文学と称するものを感じさせてしまう根本的な原因だったのではないか、と思ったね。そうだ。感じちゃうんだから仕方ないんだよ。俺の名前はレオだ。と書いてあったら、それを言ったやつは自分がライオンのような勇者だということをその文の中に含ませていて、それがラテン語の文法の教科書に書いてあったら、その中にある意味とかは関係なくなってしまって、ラテン語の文法を示している文なのであり、そして……とどんどん膨らんでいくわけだ、と了解できる。

前回の話を聞いていて、ちょと興味があったので、図書館で『ポストモダン事典』という本を借りて、ペラペラめくってみたんです。「ディコンストラクション」の項に、1960年代、ジャック・デリダという人の説明の中に、
「真の意味、一貫した視点、統一的なメッセージを所与の作品に見出そうと努力するのではなく、《……》テクストの抑圧された矛盾すなわち内在する脆弱さに注意深く配慮する読みの方法
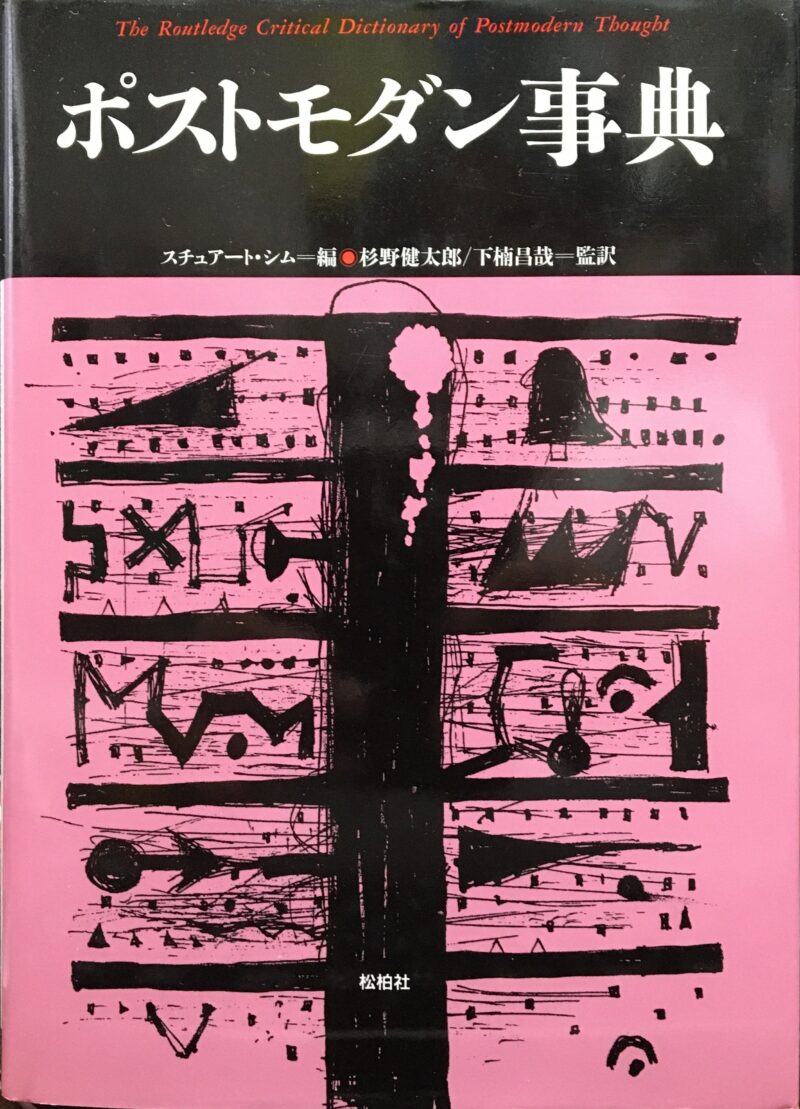
と書いてありました。
さらにテクスト、言説(ディスクール)全体、諸信仰の体系全体については、一貫性の欠如、不平等、ヒエラルキーに注目するらしいです。なんのことやら……
これを読んで、なんとなく『作者の死』という小説のあちこちでその理論を話の筋に使っているような気がしていました。それで、「脱構築」という考え方が大まかに理解できてきた。これまで僕たちが当たり前と思っていた、いいことや正しいことや常識が、思い込みだったんじゃないかという「AHA!」感覚がありましたね。
一番印象に残ったことは、どうも「真の~」「一貫した~」「統一した~」という言い方に反発する感じですね。(これも誤読ですか?)小説の読み方にしてもこういう読み方が正しい、ということを否定している感じがします。

「ロゴス中心主義」という言葉を批判的に使ってるね。脱構築ってそういう主張らしいね。言葉って思ってることを正しく伝えられるツールじゃないという感じがあるのかなあ。だから、むかしの自分の文章を今の自分が責任持たなくていいっていうことなんだ。いや、そう解釈してはまずいか?でも、いいとか悪いとか、そういうことからも脱しなくちゃいけない。ところが「~から脱しなければいけない、ということからも脱しなければいけない。でもその脱した地点からも……とぐるぐるしちゃってわけわかんなくなるよ。
誤読は必然 意味は宙吊りにされている

『ポール・ド・マンの思想』という本をしばらく借りて、前の方だけですけど、読みました。この本は確かに初心者にもわかりやすくて、なんとなくド・マンも、『作者の死』との関連も分かりかけてきたような気がしました。特に『盲目と洞察』つまり小説では『あれでも/これでも』に当たりますが、その中での「誤読」の問題が僕にとって面白かったです。

『ポール・ド・マンの思想』での説明でわかったのは、ひとつの作品に数多くの異なる理論的アプローチが存在するということ。「各論考によって提起される相容れない立場が全て正しいものではあり得ない以上、文学言語の性質は(すべてではないにせよ)いくつかの論考においては誤読されているに違いない。」ということでした。「ロゴス中心主義」が成り立たない理由がここにあるんです。
僕は単純に、言葉というものが常識的な見方と違って、不完全なものだからじゃないかと思いました。だとすると、大学入試の現代文問題で、本文の作者が出題者を批判することがままあるようですけど、それは作者の批判自体が正当性を欠くということですかね。だって、早稲田の入試問題に、作者が文句言ってるのをネットで見ましたよ。いつのことだかわからないし、問題文も知らないから、言ってはいけないことかもしいれないけど、こういうことはよくあるんじゃないですか?選択肢の正答に疑問があるというのは当たり前のことなんですよね。

私の好きなショーペンハウアーは、「言葉を見いだすことのない思想もある。しかも残念ながら、これが最高のものなのである。(『根拠率の四つの根について』)と言ってる。今の入試問題の話とぴったり合うことかはわかんないけど。
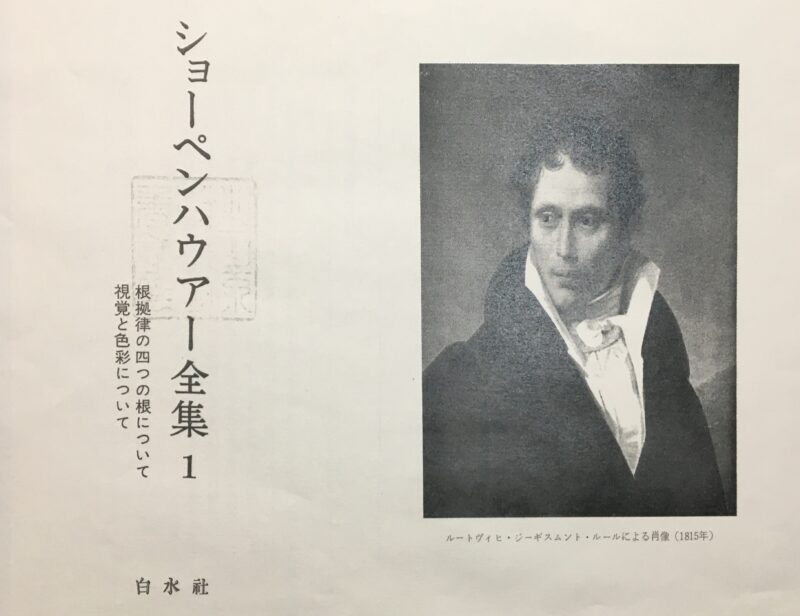
ということで、「脱構築」については少しずつわかってきたような気がするな。もちろんそりゃ違うよ、と言われるかもしれないけどね。
さて、アデアがこの架空の本に『あれでも/これでも』というタイトルを付けたのはなぜなんだろう?「イーザーかアイザーか」という英米の単語の発音の違いを何か言ってるようだけど、まあどっちでもいい、ということだよな。でもなんか作者のメッセージがあるはずだとも思うんだが。

話題のA Iを使ったらいいかもしれないけど、私がネットで検索したらキェルケゴールの作品が出てきました。あの関係の関係がどうしたこうした、という人ですよね。ええと『死にいたる病』ですか?その人の著作に「あれか・これか」というのがあるんだって。それを借りて題名にしているのかどうか知らんけど。全くわからんわ。

私も何もわからないのにこんなこと言っちゃあいけないけど、『悪循環』にしろ『あれでも/これでも』にしろ、つまりはいま話に出た「誤読」のことを暗示しているのじゃないかな。不透明とかアポリアとかいうことをどうもド・マンは主張していたらしい。としたら、このスファックスの著作もそういう線で考えられるような気がする。それに、キェルケゴールの著作はむしろ『あれでもこれでも』を批判してんだろ?あれでもいいし、これでもいい、じゃなくて本当の選択は個人の実存に任されてるんだ、ということを言ってるんじゃないの。それをパロって書かれたもの(エクリチュール)の受け入れの困難さを題名にいれたかった。そう思ったんだけど。まあ、私にとってもこれも宿題だな。しかし、どんどん誤読しちゃっていいのかね。

同じ意味でも発音を変えていってしまう、綴りは同じでも発音を変えていく人間の頭。その力を持っていることをなんだか感じさせる。そんなことを思いました。この言葉はアイザーでなく、イーザーになっていったわけでしょう、アメリカでは……。英語でも黙字ってありますけど、あれ本来もっと明瞭に発音されてたんじゃないですか?
表記と発音がずれていくことはどんな言語にもあるんでしょうけど、発音が二つあったらどっちが正統かなんてわからない。書かれた字が同じでも、何かのずれが出てくる。この問題を題名が示唆する。なんてのはどうですか?

本の題名の由来・意味もまさしく、「イーザー/アイザー」だね。
そうそうこの英単語をどっちを先に発音するか、というようなことも小説に書いてあったね。先と後によって、英米か米英かによって違うのかな。なんだかいろいろ思いつくな。
意図・志向ということ

ところで前回にも挙げたんですけど、スファックスが時計を見た時が、2回あって、その意味が違うという記述がありました。そこに随分こだわって記述していた。客に帰ってもらいたいという意味と単なる時刻を知ることとの違いなんでしょうか、そこの説明がどうも僕にはわからなかったんです。なにか哲学的な説明をしているんですか、ここの記述は……?

一回めはp.45で二回目はp.49だね。いかにも何かありそうだよね。p.45では「私が文字盤に求めたものは自国ではなく、いわば時であるということを、どうやって彼女(アストリッド)に伝えることができただろう?」と言っている。よくわからないね。
さらに「秒針と分針が」「ひどく狡猾に、目に見えぬようにこっそりと」進んでいるのをみて、「いまの状況が、まるでとうとう”出番”が来たとでもいうように出現するのを、私が十七年近く待っていたということがわかっただろう?」と言う。これはどういうことなんだろう?
私が思うに、このアストリッドのスファックスの伝記を書きたいという提案が、スファックスの腹を決めさせたということ。その時がいよいよ来たんだ、という時間への感慨が、彼に時計を見させたということなんじゃないか。もちろん彼は全てを告白し、自分の過去を世間に曝け出す、という考えではない。前回もあったが、その危機を将来的にも不安のないように切り抜けたい、ということだ。そのために彼は方法を考えていたね。
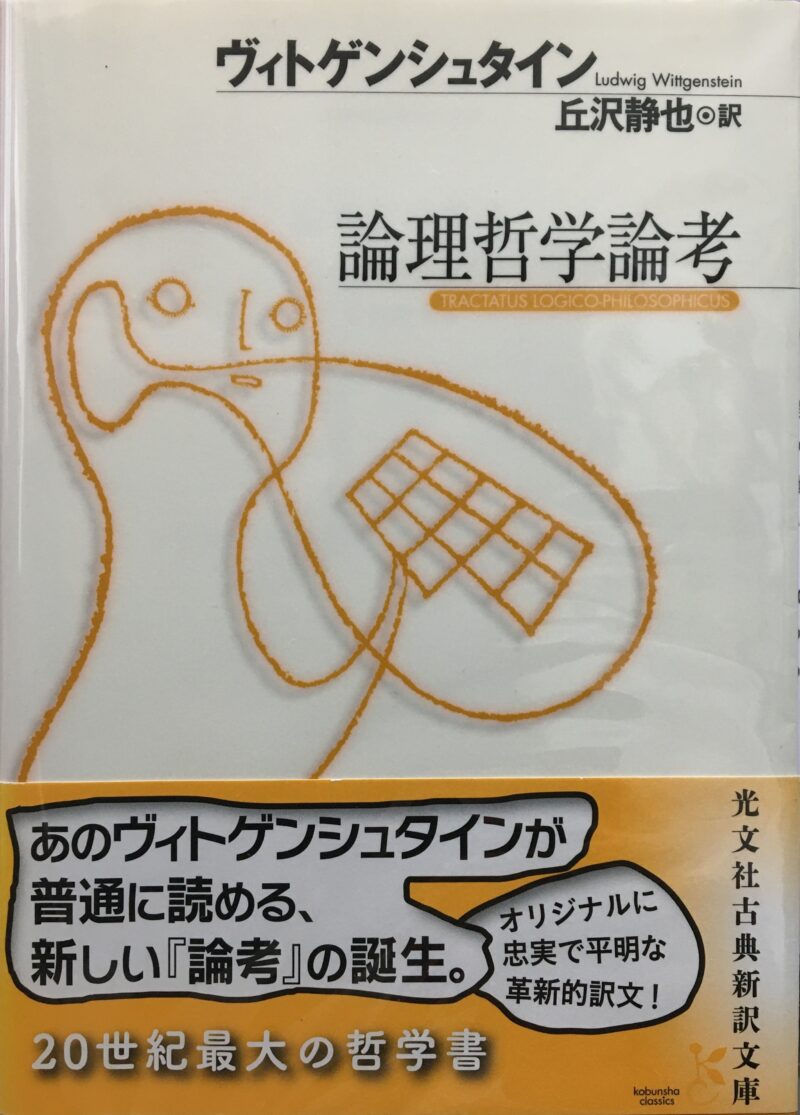
つまりスファックスは自分が勝負をかける時を知ったわけだ。p.46とp.105に同じ場面が出てくるが、「語らねばならないときは、語らねばならない。」と言っているのは、「あることについて」と限定しているのだ。そこが彼の戦略なんだね。因みに前回驚いたのはウィットゲンシュタインの有名な言葉のパロディーだろうということ。
さて、p.49で今度はただ時刻を知るために時計を見る。
これ、私が確信を持っているわけじゃないんだけど、ちょっとド・マンの著書から関係あるんじゃないかというところをひっぱってきているんだ。
『盲目と洞察』というド・マンの著作があるが、その中に「アメリカのニュークリティシズムにおける形式と意図』という文章がある。難しいんだけど、非常に面白かったのはその中で、ウサギを狙う猟師とクレー射撃の選手の対比だ。
「猟師がウサギに狙いを定めるとき、彼の志向=意図はそれを食べること、あるいは売ることであるとわれわれは想定してよい。この場合、狙いを定める行為(狩猟)は、当の行為の外にある別の志向(食べること、売ること)に従属している。だが、彼が人為的な標的(クレーパイプ)に狙いを定めるとき、彼の行為には、当の行為そのもののために狙いを定めるというという以外の志向=意図は一切ない。この行為は、完全に閉じた自律的な構造を構成している。その行為はみずからに跳ね返り、みずからの意図の射程内に収まり続ける。これが、道具(ウサギに狙いを定める銃)と玩具(クレーパイプに狙いを定める銃)のように異なる志向的対象を区別する本来の仕方である。美的な実体は玩具と同じクラスに属する。p.52」
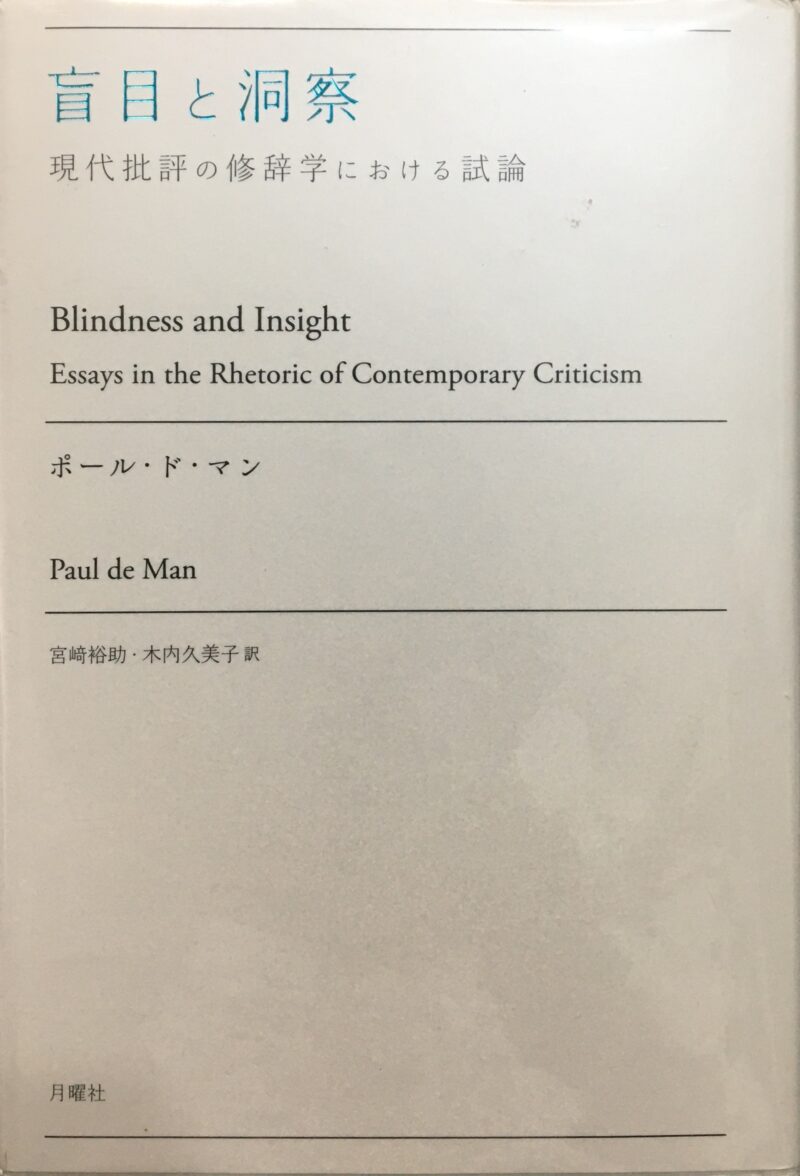
この区別を自覚せず、文学的なものを自然的対象へと物象化してしまうという間違いを多くの批評家はしてしまう、と言っている。これはド・マンのそれまでの批評家たちへの批判なんだが、これがテクストを表層へ硬化させている、と言っている。
小説の中で「時計を見る」という行為ってこれを示しているような気がするんだ。最初の方(p.45)は「ついに決断の時が来たのか!」という意識を持った時の行動として、二番目(P.49)は単に「いま何時だろう」と時刻を確認する行動として意図=志向の違いということだろうよ。意図っていうのは意味とは違う。時計を見るという行動も、銃で狙いを定めるという行動も、その意味はそれぞれひとつずつでも、意図はそれぞれでいくつもあるということだね。
ただ、この意図がどういうものか、をはっきりさせることは狩野王なんだろうか、と私は思うんだ。
たとえばクレー射撃の選手の狙いを定める意図をド・マンは本の中で、彼の「当の行為そのもののために狙いを定めるというという以外の志向=意図は一切ない」と書いている。しかしクレー射撃の選手が狙いを定めた時、その人の意識の中に、観客から称賛されたい、とか観客の中にいる自分の彼女に能力をアピールしたい、なんていう気持ちは起こらないものだろうか。これは漁師も選手も同じkとではないか。そして、その意図はどん詰まりの結論というものに行きつかないのではないかな。狙いをつけて、獲物を取って、それを金に変えて、あれを買って、それをあそこに置いて……とどこまで追ってもどん詰まりに行きつかない。
これは、子供が大人に「それはどうして?」とどこまでも疑問を投げかけてくるのと同じだ。「無限後退」という言葉がある。言語はその疑問に最終結論を与えられないんだ。言葉の意味を辞書で引いてみても、その定義された語句をまた辞書で引く、の繰り返しになってしまう。
結局、小説の中でアデアが次の著作を『悪循環』という名前にしたのも、そういう作品の批評について、言葉の果てしなさをイメージさせたかったのではないかと思う。実際「循環」という言葉はド・マンのキーワードになっている。
それから、今思い出したけど、私が過去の秘密を持って目立たないように気をつけながらも名声も求めたことについて、その自分の欲に「どうして抗うことができただろう?いったい誰が抗うことができただろう?」「どうして退け、拒否することができただろう?」と言い、出版のチャンスに「私が抗わなかったといって、誰が責めることができよう?」と何度も疑問の形で書いていることについて、あれ?って思った人も多かっただろう?そういう感想、疑問が出ていたね。これも、一種の出典があるんだよ。ド・マンの『読むことのアレゴリー』という著作。イェイツの『学童に交わりて』という詩』について説明している部分。詩の
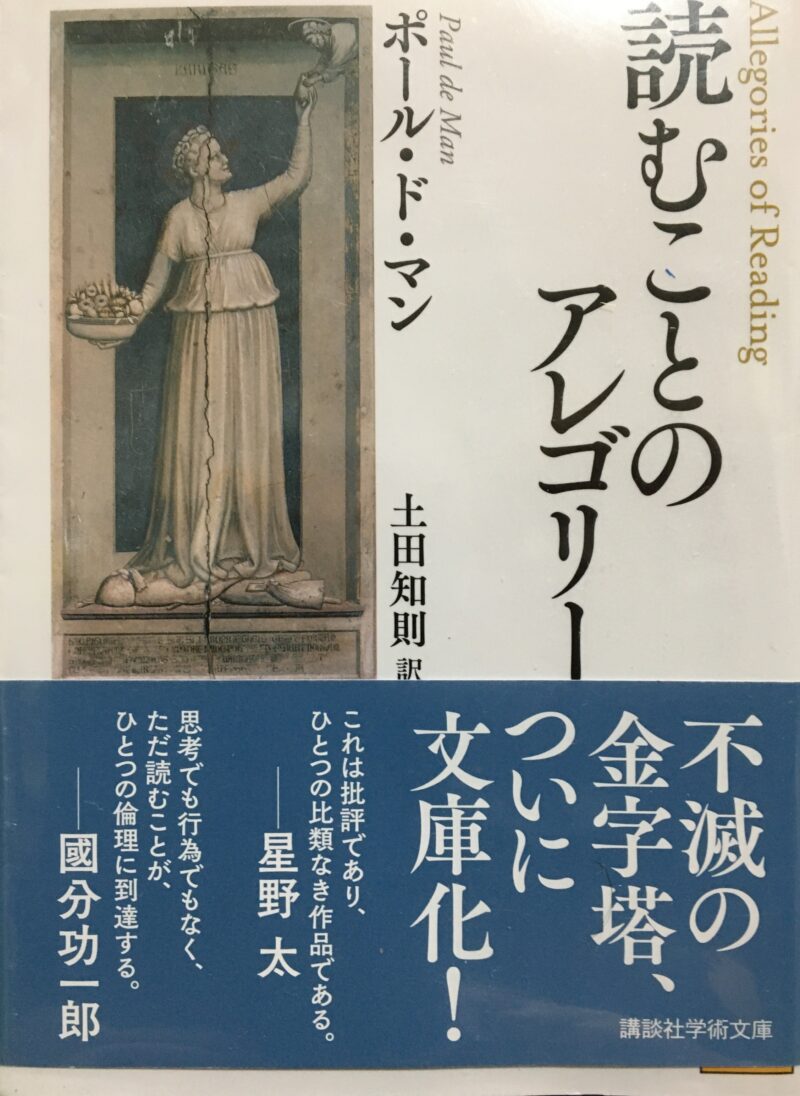
おお、大きく根を張って花咲く栗の木よ。
おまえはいったい葉なのか。花なのか、幹なのか。
おお、音楽に乗った肉体よ、おお、輝くまなざしよ。
踊り子と舞踏をどうして切り離しえようか。
という部分について、まずド・マンは最後の一行が「修辞疑問」というものだ、といっている。これは古典・漢文でみんなもお馴染みの「反語」というものだね。現代語訳するときは「いったい~だろうか、いや~だ」としなさいって教えている例の構文だ。疑問文のままにしないで、反語の構文として口語訳していくのだと……。つまり、二行目の疑問と四行目の疑問は同等とは言えないということ。
四行目は普通に考えて切り離すことができるか、いや切り離せないよ、ということじゃないかと思うのだが、これについてド・マンはこう書く。
しかしながら最後の一行を比喩的にというよりもむしろ字義的に、つまりは、われわれが先に現代批評のコンテクストにおいて問うたような問題を、ある種の火急性を感じながら問うているものとして読むこともまた可能なのだ。それは要するに、記号と指示対象があまりにも絶妙に一致し合うので、時として両者間の差異が全て消されてしまう、という読みではない。それはむしろ、本質的に異なる二つの要素――記号と意味――が、詩が語りかける想像的な「現前性」の中で非常に複雑に絡み合っている以上、いかにして同一視得ないものを同一視するという誤りから脱するような区別ができるのか、という読みである。
まったく分かりにくい文章だが、普通の読み方をすると、最後の一行は、踊り手と踊りを区別することが不可能であるといっている、と読める。でも、そんなことある?踊り手と踊りを見分けるとか見分けられないとかいう方がおかしい。そう思うよね。そんなわけのわからない対比を同等のまな板に乗せてみているような文はナンセンスだ、と私は思う。
でも、これはいかにも修辞疑問文らしい、だとしたら踊り手と踊りを見分けることはできない、ということになる。
そこで、ド・マンはこれをあくまで疑問の文だと扱うのがよい、といっているんだ。(こういうふうな解釈は私の読んだ解説にはなかった)ド・マンのいいようでは、栗の木は葉とも、幹とも分けられない。そんなら踊り手と踊りをどうしたら切り離せるように思えるのか(踊っている学童は一体じゃないか)どうしたら切り離せるように思えるか、誰か教えてくれよ。という「火急の疑問」なんだ、といっているんじゃないか、ということなんだろう。(これは本当に私の誤読かもしれない)
まあつまり、反語と思ったものも、いや疑問の文だと言われればそっちの方がよりよい、という結論になりはしないか、ということなんだ。「字義的に読む」ことのほうが「誤読」にならない、ということだな。
もとに戻ると、意図の追求は「宙吊りの無知状態」ということになる、これがド・マンの結論だ。そのことの種にされたのがイェイツの詩なので、『作者の死』では修辞疑問文が局所的にやたらに使われた、ということなんだろう、これが私の説明。絶対、違うという人がいると思うし、多分私が勝手に読んじゃった結果かもしれないが「そう読んじゃったんだから仕方ない」ということだな。
それから、余計なことをまた言うと、この『読むことのアレゴリー』と言う本には、ルソーの『告白』について分析している部分がある。ルソーという思想家は『告白』の中で、あるエピソードを書いている。自分の罪を無実の女性になすりつけてしまったことを。その自己保身を『告白』執筆している時点でも、してしまっていることをド・マンは書いている。
このエピソードを自ら晒すことに「こうした選択自体は恣意的で胡散臭いが、われわれ読者に対しては、否定できない解釈的重要性を秘めたテクスト的出来事《……》を提供している。」と言い、また「告白するとは、真実の 名において罪や恥を克服することである。つまりそれは認識論的な言語使用であり、そこでは善悪という倫理的価値が真偽という価値に置き換えられる。」と言っている。
これを書いていた時、ド・マンというその派のカリスマは、自分の過去を少しも考えていなかったのかな。少なくともルソーは告白らしきものをしたが、それを批評するド・マンは告白せずに死んでしまったんだからね。ここはやっぱり面白いテーマじゃないか。
理論の知識がないと読んだことにならない?

いろんな仕掛け(?)が潜んでいる、ということですね。それについてはまた先生に聞いてみたいこともあるんです。
前回の新聞記事の解釈の前提の知識のことと関連していることです。それは、こういういろんな文学理論、特に今回の場合は「脱構築」という理論ですけど、これについての知識がないとこの作品を読んだことにならないことになると思うんです。
『文学部唯野教授』はある程度作品の中で解説もあって小説として成立していると思うんですが、『作者の死』はそういうサービス(?)がないんです。これを小説と言っていいんでしょうか。理論を学ぶためにはいいんですが、自立した作品として成立していないと思いませんか。

でも、読んだことはないけど、映画にもなった『薔薇の名前』なんてのもあるよ。主人公の役をショーン・コネリーがやってることが、この作品の中で「007」との関係を示している、ということらしい。
つまり、こういう遊びみたいなことこそが作品の重要な要素になり得るんだよ。これは作品の意図解釈の、つまり読むという行為の中心事項とも言えるんじゃないの?やっぱり読解の前提はあるんですよ。

それはわかる。何かの連想を引き出すという作用は、最も根本的な文芸の作用だし、表象から連想するからこそ感動もある、と僕は思った。しかし、作品中のある記述から文学理論を連想して、そこに感動はありますか?(これは修辞疑問です)たとえば、幸田文の『父』『終焉』ですよ。あの感動はどうも「文学理論」を超越しているような気がする。

しかし、文章の意図を志向的に辿っていくことがアポリアだという結論は、むしろ自由に循環する楽しさがある、ということじゃないか。これこそ「ロゴス中心主義」からの離脱だと言えないかな。それにロゴスって言葉のことでしょ?言葉についてのいろんな考察は、まさしく人間の研究じゃないか。これに関わる全ての研究って、作品に感動することと密接なところにあると思わない?
いずれにしても、理論は常に乗り越えられることを前提にしている。現実に脱構築だってもう時代遅れというような主張だってあるようだよ。だからさあ、そういう理論が中に隠されている作品を読み解いていこうとすることは、それで、新しい視界が広がるっていくことに繋がる、ということじゃあないか。いま「新しい視界が広がるっていくことに繋がる」って言ったけど、この隠喩がどういう効果をもたらすか、考えてみ。

ふん。先生、その隠喩という言葉も最近のご勉強の成果ですか?

へへ。今のよし子さんのご発言の中に、なぜか私に対するちょっとした揶揄も感じさせるねえ。なぜそういう感覚が生まれてくるのか、って面白いだろ?
まあ、もう少し勉強したら、諸君に「アレゴリー」という言葉を説明してしんぜよう。
これも信用できない語り手、でしょうか?不真面目にも感じます。

もうちょっとあるんですが、いいでしょうか。「私」が死んだ後も、「私」が語り手となっていること、これも何かこの派の人々の主張に種があるんですかね。語り手の存在自体が非合理です。
それと、犯人が特定できたのは、ヘルメスの文体と明らかに違っていたということ。つまり最後に文体という問題が出てきたことです。文体については何かド・マンは書いているんですか。

……ごめん。これについて何の材料も持ってない。さらに「見せけち」についてもちょっとある。そのほか作中にはいろんな話の種がありそうだが、もう今回はやめておこう。特に「文体」というのは厄介だ。これについてはもっと勉強が必要だ。でも、一言。ある本でざっと読んで発見したフレーズを読んでみるよ。
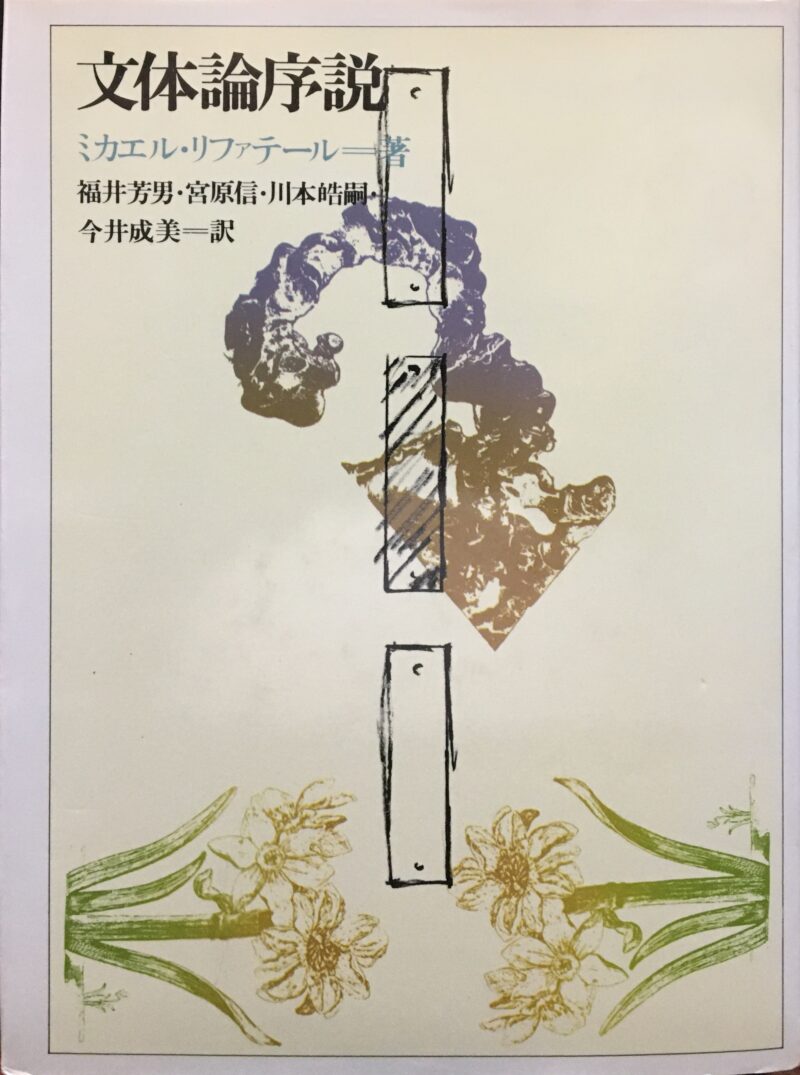
文体とは、語連続のある要素に対して、読者の注意を否応なく喚起する浮き彫りであって、読者がもしこの浮き彫りにされた要素を排除してしまえばテクストは必ず損なわれるし、また一方この要素を解読すれば、それがなにかを意味し、なにか特徴的なものを示していることが予感されるのである。(読者はそこに芸術の一形式、人格、意図といったものを認めることによって、この感じを合理化する)
というわけで、これじゃあますますドロ沼にハマっていく……
言い忘れたけど、作品中に、デイヴィッド・ロッジという批評家が出てくるけど、ロッジの『小説の技法』という本にはギルバート・アデアが出てくる。アルファベット中のある文字を排除して作ったものを字忌み文(リポグラム)というんだそうだが、”e”を使わない小説『消滅』というのをフランス人が書いて、それをアデアが英訳しているんだいうことだ。そんなことができるのかね。またその翻訳をする意図はどこにあるんだろうか? あーむずかし。


コメント