
埋もれていた名作……らしい

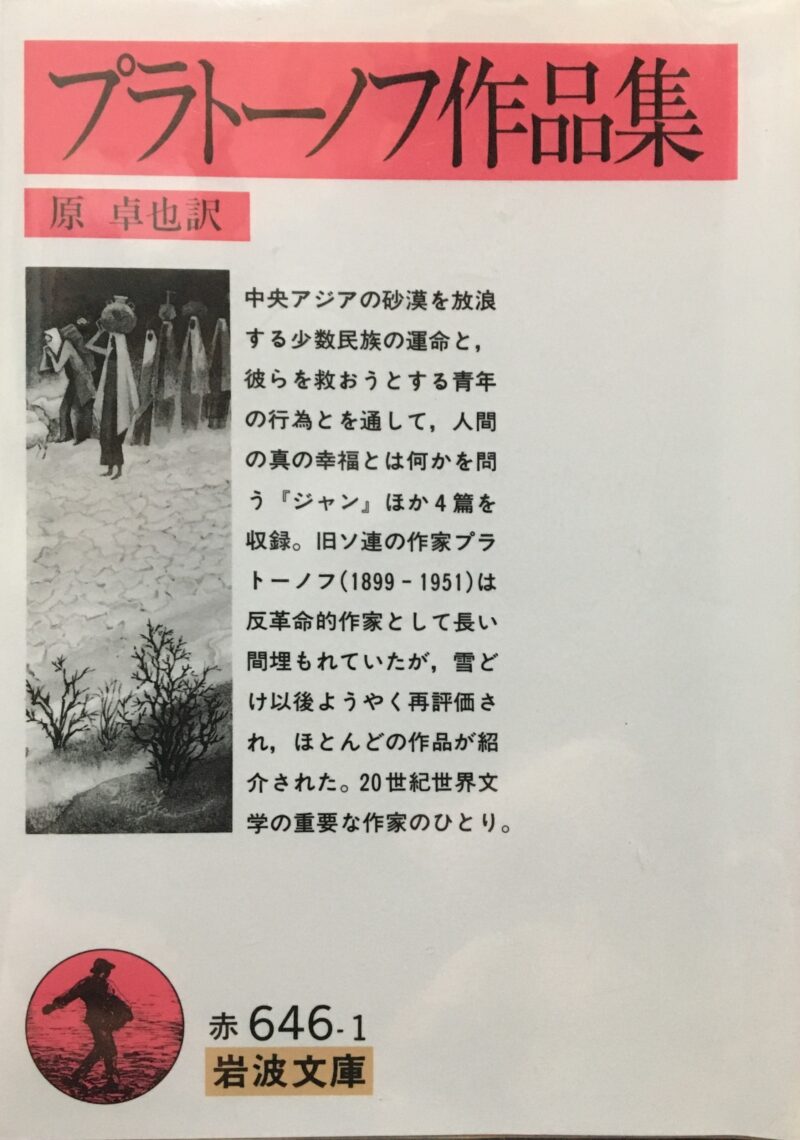
ナザール・チャガターエフという男が経済大学を卒業した。その祝いの宴席で彼は一人でいるヴェーラと出会った。二人は恋人になったが、実はヴェーラは結婚しており、夫は死に、彼女は妊娠しているということだった。チャガターエフはそれでも、生まれてくる子供の父親になると言い、二人は結婚した。夏、チャガターエフは仕事を任され、故郷の中央アジアの砂漠に赴任することになった。
彼の母は、トルクメン人のギュリチャタイといった。幼いチャガターエフを貧困のため育てることができず、息子を砂漠から旅立たせたのだった。彼はペレカチー・ポーリェと呼ばれるさすらいの灌木が、風もないのに転がっていくのを見ていた。「お前と一緒に行くよ。一人じゃ寂しいもの」と言い、歩き出した。そして、羊飼いに助けられ、さらに長い時が経って少年はソビエト政権に引き渡された。
チャガターエフは任地に列車で旅立った。列車はモスクワを出て、すぐに曠野を走っていった。夜更けにうす暗い中に止まってしまい、彼は下車した。思い出の中で一人歩いて行きたかったから。芦のなかを歩き7日目にタシケントに到着した。党中央委員会に出頭すると、書記がサル・カムシュとウスチ・ユルト地区アム・ダリヤ河のデルタ地帯のどこかにさまざまな国籍の遊牧民が放浪して貧困に苦しんでいる、と言う。この希望も持てない民族は自分の故郷の人々だとチャガターエフは言った。ジャンという名を自分たちでつけ、生命以外何一つ持たない民族だと。書記はその人々を助けてやるのが、君の仕事だと言った。

チャガターエフはその後、十数日かけてヒヴァのオアシスに行き、そこから故郷のサル・カムシュに向かった。途中砂の吹き溜まりに前脚を突っ張って座っている一頭のラクダを見つけた。ラクダは飢えと病のために毛もほとんど抜けてしまっていたが、生命の尽き果てるまで主人を待っているのかも知れなかった。チャガターエフはラクダの心情を理解し、引っぱって旅を続けていった。
さらに進むと丘の斜面に穴を掘って寝起きをし、台地の谷間にいる小動物や植物の根を常食にしている世捨て人、スフィヤンと会った。彼はチャガターエフを見知っていて、いっしょに行方の知れないジャンの人々を探しに出かけたのだった。
その昔、サル・カムシュの人々はヒヴァの領主に酷い仕打ちを受けていた。人々は自らを殺してもらうためにヒヴァに、集団で出かけていった。領主の手下はある老人に「(領主の扱いが酷いのに)どうしてそんなに喜んでいるんだ?」と問うと、老人は「お前は永い間わしたちに死ぬことを教え込んできた。わしらも今じゃすっかり慣れたから、みんなでいっぺんにやって来たんだよ。わしらがまた忘れちまわないうちに、早く死を与えてくれ!」と言った。ヒヴァの市場では人々は金を払わずに腹くちくなるまで食い尽くしたが、商人たちは黙ってそれを見ているばかりだった。そして、しばらくして彼らは元の地へと戻って行った。ついて来ていたラクダも別れようとはしなかったが、ある朝チャガターエフは死んだラクダを見た。スフィヤンは宝物の袋でも漁るように、内臓をかきまわし、綺麗な血のついた新鮮な肉を選り分けていた。
その後もサル・カムシュの住人たちは、芦や灌木の間をさすらっていた。老人とチャガターエフはその中で一軒の草小舎を見出した。暮らしているのは盲人のモーラ・チェルケーゾフで、娘のアイドゥイムが世話をしていた。チャガターエフはこの娘を旅に連れてい期待と申し出た。モーラをスフィヤンが世話をすることになった。そしてそのたびでチャガターエフは母と再会した。二十軒ほどの小舎の集まりの中で、母は孤独な生活をしていた。しかし再会をしても母は息子に対する愛情を示さなかった。もはや息子への愛より、現実に生きること、周囲の人たちの中でなんとか生きることを盲目的に受け入れていたのだった。チャガターエフは母にアイドゥイムの親モーラと一緒に暮らすように言った。
地区委員会の全権ヌール・ムハメッドがやって来た。彼はチャガターエフに対して、この民族は曠野や山中に連れていってそっとしておくのがいいだろうと言うのだった。「一人残らずくたばるまで葬りつづけて、ここを引き上げてしまいたい」とも言った。
チャガターエフは薬品を手に入れるためチムバイに出て行った。そこでモスクワからの手紙を受け取りヴェーラの死を知った。彼は考えることをやめた。二日かけて帰りつく前にムハメットが母やモーラを含めて十四、五人を率いて歩いていくのに会った。ムハメッドの目的は、人々の体力を消耗させること、のみならず理性や心の消耗で、目的地は故郷サル・カムシュだった。

この旅の途中で羊の小さな群れと交錯し、食糧とすることができたが、羊はいつかかき消えてしまった。人々にはもはや行き着く力も無くなってしまった。チャガターエフは帰還のためのさまざまな試みをした。砂漠の中で砂で塞がった井戸を見つけたが、濡れた砂をそのまま飲み込むことで渇きの苦しみをしのいだりした。また砂地の浅い墓の穴の中から草の茎を見つけ、これも丸呑みにした。砂地で眠り込んで夢を見た。起きると再び己の課題を考えながら生きていった。
ある時は、二羽の大きな猛禽に襲われた。一羽は持っていたピストルで殺したが、もう一羽の雌鷲が襲ってきて、彼の右足の肉を少し食いちぎっていった。傷の痛みと体力の回復のため横になっていたが、一方チャガターエフのいない間にムハメットは少女アイドゥイムを自分のものとして育てあげ妻とし、いつか男に売り飛ばそうと狙っていた。ムハメットは以前ジャンの人々をアフガニスタンに連れて行って、領主たちに奴隷として売り飛ばしてしまおうと思っていたのだが、今その体力気力が人々にないのに気づき、彼らを片付けることが自分の仕事だと思っていた。
アイドゥイムは砂漠を越えチャガターエフを探し出した。彼をそのまま寝かして、向かってくる鳥の肉をみんなのところへ持ち帰って配った。それからアイドゥイムはまたチャガターエフのところへ戻って行ったが、肉欲しさに人々も彼女についていこうとした。
チャガターエフは二羽の鷲と戦っていた。一羽は前に殺した鷲の片割れでもう一羽は新しい雄だった。鳥は彼の体を突つき胸と膝と肩の肉を食いちぎっていった。チャガターエフはピストルで一羽を撃ったがもう一羽は逃げていった。アイドゥイムはそこに現れ鳥を引きずっていった。彼女は今集団のリーダーのような存在となっていた。
ムハメッドはそのアイドゥイムに命じて、またみんなで旅をすることになった。彼女は命に従うよりしかたがなく、チャガターエフに別れを言いに行った。ムハメッドも付いてきた。チャガターエフは彼女を置いていくように言ったがムハメッドは相手の顔を蹴飛ばした。チャガターエフはピストルを取り出し、アイドゥイムはムハメッドの首に爪を立てた。ムハメッドは娘をやっと放り出したが、チャガターエフの弾が足に命中し、やっとの事で逃げていった。
ところが、彼女はチャガターエフにこのまま砂の中にいてくれるように頼む。鳥を誘って肉を取ってもらいたいのだという。

夜、チャガターエフは夢から叩き起こされた。数羽の大きな鳥に嘴でつつかれて、爪で身体を引き裂かれた。チャガターエフは傷つきながらなんとかピストルで殺した。そして、そのまま穴を掘り、身を縮めて横になった。いっぽうアイドゥイムは砂丘で二十頭以上の羊や山羊を見つけた。ジャン民族は四日続けて食事ができ、立ちかえることができた。チャガターエフも助けられ人々は目的地のサル・カムシュの近くまできた。スフィヤンは以前住んでいた洞窟に行きみんなにその周辺に定住するように勧めた。そこは生活するに適した土地だった。人々は、しかし、ここでも無気力だった。チャガターエフは皆を集めて、生きていく気があるのか聞いてみた。誰一人として何も答えなかった。苦しみが人々の魂を歪めてしまったのだろうか。
二ヶ月経つとこのウスチ・ユルトの渓谷には小さな小舎が数軒建てられ、住民のソビエトもできた。しかし冬になると食料が不足し、チャガターエフはヒヴァに行って食料を貸し付けてもらうために旅立った。アイドゥイムは人々のために立ち働いていた。そして人々は相変わらずたるんだ働きぶりだった。
チャガターエフは砂漠で二台のトラックに出会った。荷はジャンの人々への贈り物の物資だった。その食物が届けられて数日後の夜ジャンの母親は死んでいた。
その日母の遺骸を守りながら寝ていたが、アイドゥイムが朝起きると、昨晩みんなが泊まったはずの家はもぬけの殻で、誰一人としていないことがわかった。アイドゥイムは共同の財産を片端から点検し、不安にかられて家々の壁にまでさわってみたが、食料は全日そっくり残っていた。彼女は丘陵に登り近辺を眺め見ると、四つの人影を見つけた。彼らは遠く隔たって、一人ずつ歩いていた。
アイドゥイムはチャガターエフを揺り起こした。チャガターエフは一人で数キロ先の高台まで出かけ、そこで十人以上の人々をさまざまな方角で見た。チャガターエフはため息をつき、苦笑した。自分ひとりの偏狭な思想や意気込みからここに真の生活を作り出そうと思っていたのを知ったからだった。幸せになる方法は当人たちそれぞれで、彼ら自身が地平線の彼方で掴み取るものなのだ。
旧ソビエトの辺境 トルクメニスタン

中編というより長編かもしれない。全体としてひとつのテーマに的を絞ることは難しいかもしれないので、例の如く思ったことを言ってみてよ。
私自身はなんか宝物に当たった!っていう感じがするんだけど。今回初めて読んだ作家で、読んで良かったと思ったんだ。もちろん否定的意見でも全く構わないよ。

プラトーノフなんて初めて聞いた。また今回はどんなもの読まされるのかな、と思った。

でも、今まで読んだものにはない読後感だったなあ。それは、舞台の場所に関係する。中央アジアってのがイメージわかないのよ。アフガニスタンのことは少しニュースで知っていたけど、どの辺にある国なのか正直よくわかんなかった。しかも、二十世紀の作家でしょ。それなのに別世界の話なんだよな。

いやそれは同じような感想を持ったよ。ただ僕はそういう点も含めて面白かったよ。実はちょっと読み直してみて、ますます面白いと感じた。そりゃ、漫画やアニメを見るのとは違う面白さだけど、時間かけて読んでみる価値はあると思ったけどね。

文庫本の表紙に「人間の真の幸福とは何かを問う」という語句があるけど、これはどうかな。あたしにはこれ、読む意欲を削ぐ言葉だったなあ。確かに小説本文には「幸福」とは何か、みたいな記述はあるけど、ちょっとあたしの読み取りとは違う。この人たちなんで生きてんの?っていうほうがあたしの素直な感想。ひどいこといえば、無理して生きることないじゃんっていうくらいの感想。だって殺してくれって支配者の街まで出てきたりしたんでしょ、かつては……。生きるから、幸せを求めなけりゃいけない、っていうこと言いたいんだとさえ考えちゃった。こういう世界では、考えないこと、これが大切なんじゃない?

この小説の舞台って、トルクメニスタンってところ?どの辺?カスピ海に面している?申し訳ないけど、こういう知識がない私には、ぜひ地図が欲しかったわ。イメージがわかないもん。
でもこの砂漠っていうものが私に与えてくれる感覚は、渇きということ。そしてなぜか清潔ってことなんだ。そして、イスラムということ。なぜかこの小説には宗教というものがほとんど出てこなかったね。回避されているっていうことさえ感じた。ソ連時代の政治的配慮とかあったのかな?これは一つ気になった。
だから砂漠の民の死生観がどういうものなのかっていう興味がずっとありながら読んでいたんだけど、これは分からなかった。ジャンの人たちには宗教が関わっていなかったという設定なのかなあ。彼らが疲れてそして何か思考停止になっているというときに、当然問題になるのは宗教じゃないのかな。いや、政権が、宗教は民衆に入り込む毒薬っていうんなら、そういうニュアンスの言葉が出てきてもいいんじゃないかと思うんだけど。


そこは分からないけど、僕は政治的なことが引っかかってる。旧ソ連時代なんだよね、このとき。たぶんスターリンとかの時代なんじゃない?ボルシェビキが政権を握った時代なら、そこには見方によっちゃあ人類史上最大の実験が行われていた時代なわけでしょう?当然そのときには本当に民衆の生活の向上を考えていた政治家だっていたかも分からない。そういうメンタリティーを持った官僚たちだっていたかも分からない。そのへんがちょっと出ている部分があって興味深かった。悪名高き権力抗争や強引な社会改革ということばかりを連想しちゃう時代だから。そんななかで、まさしく共同体的な助け合い、援助が書かれている。もちろんそうではない政治の冷たさも書かれていたけど。
砂漠の民として生きること 幸せとは SF 自由……いろいろ読める

確かに幸せを求めるというテーマは本文にダイレクトに語られているけど、この小説の底辺に流れているものは、幸せとはなにかというより、生活とはなにかということじゃない?生活するということは幸せを求めようとすることかもしれないけど、でも人間の本来の目標は幸せよりも地道な生活だ、という気がする。

僕は、ちょっと変に思われるかもしれないけど、この小説、荒唐無稽なSFのような感じがするんだ。特にジャンの人々の食い物はどうよ?雑草の根を、鷲の肉をナマで食ったり、砂の中で寝たり、喉の渇きを湿った砂を食うことで癒したり。本当にこんなことで生きながらえるんかな?ちょっと信じられない。そして思考が麻痺させられるわけだろ。食えないことのせいだよ。
こういう非現実的(?)な世界での物語がこの小説なんだ、ということではないか。極端な状況を作ってそこに定住しない人々を実験的に置いてみた物語を読者は読む、とういうことじゃない?いやこれは現実なんだ、という人もいるだろうけど、少なくとも21世紀の、日本の、高校に通っているわたしの読解では、これはSF小説だね。

また、砂漠の風で転がされるさすらいの灌木ペレカチー・ポーリェ。もちろんこれは大事なイメジャリーで、流浪の表象。デラシネっていう言葉も聞いたことがある。チャガターエフはこれを擬人化して旅の友と見てる。彼の孤独を表しているし、親からも、さらにいつか国家からも見捨てられるということを予感させる。転がるためには根が強くてはならない。そして根があっては自由は得られない。そういうことを読者は思うね。そうそう、この小説は自由への物語であるんだね。

そうだ!自由って忘れちゃならない。注意して読まなくちゃならないのは、男と女の自由の問題よ。アイドゥイムなんか読者の期待からすれば、もっとチャガターエフに寄り添ってやってほしい、という感じで読んじゃうんだけど、彼からも一種の自由を保っているように思えない?彼にベッタリと依存してはいないように見える。若くても、集団のリーダーとしての自覚は強く感じる。老スフィヤンも同じような自分というものを持っている。チャガターエフに対してそれを理性的に伝えている。

いっぽうチャガターエフの母ギュリチャタイのちょっと独特な息子への感情というか……息子への扱い、それを語り手が説明するんだが、息子に対しても、彼女は自由だよ。自分の欲望にも素直。彼女こそ砂漠の民に相応しい、砂のような女かもしれない。

……とすると、砂や砂漠にふさわしくない人物っていうと?

ヌール・ムハメッドですね!
ジャンの人々に対する秘めた企みは語り手によって知らされますが、それはジャンを消滅させるということでした。陰湿という言葉は砂漠に似合いませんね。
ただし、彼の心のうちに私欲だけがあったようには書いていない。ソビエト社会への貢献という意欲による行動だったとも語り手は言っている。ムハメッドにしたら、ジャンの人々への企みは民族浄化という恥ずべき行為でも、それこそが仕事なんだということです。
ところが一方で確かにソビエト政府は少数民族への援助もしている。党と政府の違いがあるのかもしれないけど、とにかくこの矛盾はどういうことなんですかねえ。あるいはタテマエとホンネの矛盾なのか……。これを二人の人物、チャガターエフとムハメッドの対立で表象しているんということもあるんでしょうか。ちょっと不思議な矛盾でしょう?
それでも感じるのは基本的には二人は古くさい勧善懲悪の構図で生きているということです。というより僕はチャガターエフにあまりに強い正義感を感じ、ムハメッドに汚いエゴイズムを感じます。こちらは類型的な二項対立ですよ。そこがまた妙な感じなんです。

勧善懲悪って多かれ少なかれ、ほとんどの作品に当てはまるし、読者の期待でもあるね。必ずしも否定されるべきものとも思わないけど、確かにチャガターエフなんてケチのつけようのない人間だね。こういう単純な構造って私は気がつかなかったけど、この小説の欠点かね?

チャガターエフはソビエトという国家構造の子、党の子なんだけど、一面では非常につよい正義感を持つ、経済学士でもあるんだ。設定が面白い。こういうところをもっと人物創造に組み込めなかったかな、なんて生意気ながら思いました。貴種流離譚の要素も含んだ、新しい物語の可能性もあったんじゃないかと……。ヴェーラとの結婚、その娘クセーニャとの関係など、もう少し深められるところもあると思いました。

モスクワでのヴェーラとの結婚がどういう必要性に基づいているのか分からない、ということだね。

いや、それは「わからない」というより、いろいろ考えられることだといえる。
この子は母が手放した子だ。実際このままじゃあ育てることができないという状況にあった子だ。革命によって門閥をなくした政権にとってはまさしく自分たちの子供じゃないの?貧しい有能なテクノクラート、しかも正義感に富み、苦しい生活にあった子持ちの女性との結婚もする。結婚相手が、たとえば新しい特権階級の娘であったらどう?彼の人間性からいえば、この設定の方が好ましい人間像だろう?考えれば、こんな独創的な主人公像はないよ。いや、良いか悪いか分からないけど、『小公子』じゃないのが素晴らしい。

他と隔絶した貧しい集団の生きる道、なんてこと考えると、わたし、『楢山節考』を思い出しちゃった。そりゃ話は社会も自然環境も違うけどさ。集団の中でひとり際立つ人物が描かれる点では同じじゃね?
あの『楢山節考』での「おりん」の行動基準は「世間体」じゃないかという話は忘れられないけど、チャガターエフはなんのために生きているのか、つまり彼の物語は何か?これがいちばんの問いじゃない?
『楢山節考』と比べると

「おりん」との比較で読み取りをしよう、というわけね。
わたしは、チャガターエフの動力源は「使命感」じゃないかと思う。どうしようもない義務感ってあるでしょう。愛情とか恩とか……。自分がソビエトのおかげで生き延び、教育も受けることができた。それは生きる理由があったということだろう。流浪のジャンの人々を助ける、これが彼の生の意味なのよ。考えようによっては「おりん」の行動も世間体という虚飾だというよりも、その「世間体」なるものが共同体存続の要だったということがいえるんじゃない?「世間体」というものがあるからこそ共同体が保てる、とも言えるからさ。
ジャンの人々には世間体は人々のつながりのもとにはならない。だってもっともっと貧しいから。雑草の根っこを食べ、どんな鳥類の肉でも生のままかじらなければならない。そんなふうにしなければならない人なんです。楢山の人たちの問題はいかに「きれいに死ぬか」ということでした。この「きれい」というのが問題で、それによって「おりん」は読者から賞賛されたんでしょ?二人とも使命感で生き、死んだ人だったんだといえない?

ジャンの人々への使命感か。単純に故郷の人々への愛と考えてはおかしいかな。チャガターエフは大変な苦労を覚悟の上で仕事を始めるね。最初列車を途中の曠野で降りるところからそれは始まるのだけれど、目的地まで列車で行かないところから、彼の覚悟はなんとなくわかるね。それは砂漠や曠野や転がる雑草などへの愛とも映るんだけど。

故郷の人々への愛、という感覚は読んでいてありましたか。そういう記述はわたしは見つけられませんでした。彼らをなんとかしてやりたい、という気持ちはあったんでしょうが、まあこれも愛だと言えるかな。個人個人への愛情とはちょっと違うような感じがしますけど。

最初にチャガターエフがタシケントに出向いた時、党委員会書記のことばを覚えている?人々をサル・カムシュに戻るようにしてくれと書記が言う。「行きます」と答える。「向こうへ行ったら何をすればいいんですか?社会主義ですか?」とも言った。それに対してまた書記が言う。
「それ以上、何をすることがあるね?」書記は言った。「君のその民族はすでに地獄を知っているんだから、これからは天国の暮らしをさせてやろうや。僕らは精一杯それを助けてやるんだ……君は我々の全権になるわけだよ。地区からもだれか派遣してはいるんだが、何一つできやせんだろう。どうも、われわれとは肌あいの違う人間らしいからね」
この書記は社会主義の理想を持って働いている人物らしいね。チャガターエフの会話からも、故郷の人々や自然への愛というよりは、仕事として力を尽くそうという意欲、使命感を感じますね。

なるほど。いま引用してくれたところはそう読めるね。チャガターエフは大学卒業後の仕事として、たとえば行ったこともないシベリヤでだって、同じような情熱と態度で仕事をするだろうという想像が可能だね。

それから、本文ではチャガターエフが現地に入って行き、その場で自分の幼少期のことを思い出しますね。苦しい生活や母のことです。ただここからの記述がどうもすんなり諒解できないことなんだ。

まず母から言われたことば。「坊や、こわがるんじゃないよ、いっしょに死にましょう」
サル・カムシュで群衆の中にいた時のこと。彼らは虚脱感と無力感の中にいた。これがこの民族の権利のようにも感じてしまう。思考停止っていうことかな。ここらあたりが作者が示したかったこの小説のキモみたいなところじゃない?ラクダのエピソードもここだ。ラクダがチャガターエフの後についてくるんですが、そのラクダか死んでしまう。この時スフィヤンが「宝物の袋でもあさるように内臓をかきまわし新鮮な内臓を選り分けて食べる。チャガターエフもそれに倣う。動物の腹は宝袋だってんだよ。
さらに忘れられないのは、最後のほう。チャガターエフが鷲と戦い、その肉を食べていくあたりです。こんな猛禽類の肉が食べられるもんかね?それがまず疑問ですが、でも人間は食べることにはどこまでも落ちていける。
思想とか、理想とか、人間は作り出すが、いざ極限状況になれば、僕らは思考を停止し、何も感じなくなり、苦しみも回避できるようになるんだ、という「教え」です。ありがたいこっちゃ!チャガターエフの母親の、息子に対する不思議な対応も、そういうことです。
悲しみや苦悩などは幻影や夢にすぎず、そんなものはアイドゥイムですら、幼い力で一挙にうちこわし得るのだ、ということを彼は知っていた。人の心やこの世界には、籠にとらえたように世にまだ現れぬ、だれも試したことのない幸福が脈打っているのであり、人間だれしもその力やその接近を感じているのだ。
と書いてあります。作家が生きる現実のスターリンの治世では物凄い人が粛清されたと聞いていますが、そういう事実も連想しちゃう。
変な結末にしないでよかった

いったん食料がタシケントからの命令でジャンの人たちに与えられ、そのトラックが彼らのところに来たあと、母が死に、その後食糧を残して、人々はバラバラになって去っていく。話はそこで終わるね。
それについて、岩波文庫本の解説を読んだんだよ。訳者の解説だろと思うんだけど。それによるとこの小説には結末の違う版もあるんだって。ある版では離散した人々がチャガターエフの呼びかけによってまた集まってきて幸せな共同生活をすることで結末になるんだって。
驚くべきだね、ぜんぜん印象が違っちゃうね。作品台無しだよ。なんか異論のあるやついるか?いないよな。バラバラになることこそハッピーエンドだろ?
先生はどうおもう?

そうだな。それは同意するよ。
それにしてもこの小説はいろいろ独創的なところがあったな。
私は作品中で一貫した人物像になっていないようなことが多いと感じたんだけど、読み終わるとそれもプラトーノフの独創的なところのような気がしてきたんだけど、みんなはそんなことなかった?(何人かは頷いている)
小説の完成度が高くないということはないと思うが、自分の理解の未熟と思ったりも、実はしたんだけど、そういうところも『ジャン』という小説の特長と言ってもいいような気がしてくる。
ジャンの人々の知性

トラックの物資を彼らはただ食べたのではないんです。物資を送ってくれた人々を想像しながら、思い入れを見せながら食べるという意識を持って、おっとりと食べていた。ちょっと言葉が独特で気になるけど、言いたいことは想像できるね。
数日後、一軒の家で暖かく寝て、二日目の夜もすぎた。そして三日目に母が死ぬ。そして次の日に暖房の効いた家はもぬけの殻だったんだ。物資はほとんどそのまま置いてあって……。
つまり、この前日の夜までに彼らは彼らなりに話し合ったんだ。だってそんな語り合いがなくてもぬけの殻になることなんかありえないよ。ともかくこの生活から脱皮する必要があるんだと結論。それは各人の現実逃避ではない。何かしらの決意があったんだ。
思考停止に見えていた人々の変化こそ、この小説のポイントですよ。
チャガターエフは知っていた――人間に対するあらゆる搾取は、支配を目的としてその人間の魂を歪め、死に順応させることからはじまるのである。さもなければ、奴隷が奴隷にならないだろう。そして、魂に対する暴力的な損傷は、奴隷の理性が錯乱と化すまでつづけられ、ますます強められる。奴隷のうちに存する《聖霊》の征服から、階級闘争がはじめられるのである。
これはチャガターエフが人々に「生きてゆく気があるのかどうか」と聞いてみたときに感じていたこと語り手が語っているんだけど、その後ではスフィヤンに対しては、「昔の奴隷は、最初にまず魂が死んで、それから生命を感ずるのをやめた」と言っている。つまり魂の死んでいる状態が「ジャン」の人々だったということだ。

そして、最後の高台からの、去っていく人々を見る場面。これはどういうことなのか。この結末をどう読むかが作品解釈の全てだと言ってもいいと、僕は思う。
それは、チャガターエフが目指した集団で生きる安定が実はこれも奴隷扱いの一つであることを彼自身理解したんじゃないか。ということなんです。彼が食糧を確保しようとして命をかけているような時や、アイドゥイムが必死の働きをしている時、ジャンの人々は確かに「相変わらずたるんだ働きぶり」だった。でも、最後には自分の行く方角をそれぞれ決めて、物資に手もつけずバラバラに離れていくんだ。これ、感動的な場面です。
それを、彼らがまた食えなくなって集まってくるという結末では、それはそれとして現実の様相かもしれないけど、やっぱりちょっとその結末は希望がない。ソビエト政権としては、こっちの結末の方が都合がいいかもしれないが――。
要するに、授業で教わったこと、上部構造は下部構造が規定する、ってやつは果たしてそうだろうか。そういうことを描いているように、僕には感じられるんです。まあマルクスについてぜんぜん読んだこともないけど。

私の感じだと、ジャンの人々は、ほんの少しの欲望しか認めない人たち。たまに僥倖があってももっと大きな禍が私たちには起こるものだって思ちゃう、いつもそういうことを覚悟していないといけない、と思っちゃう人たち。メメント・モリって言葉もある。そういうことをスフィヤンは言ってたんじゃないかな。だから彼らは悪いことが起こる前に、安全で、貧しい、死んだふりの貧しい生活を選んだのかもしれないですよ
それは、確かに迷信のような生き方かもしれない。でも今の私たちの、行き着くところまでは何も考えず突き進め、っていうあさましさへの反省としても読める、と思います。

興味深かったのはチャガターエフが「エゴイズムと自己防衛の感情を少しでも彼らに覚えさせ」たかった、と言ってること。これは物資のトラックが来て、人々に食事を与えた時の語り手の表現です。
チャガターエフも、国家から与えられた道が「共同生活の本当の幸福」にたどる道だと信じていた。でもそれに対して、ジャンの人々は「 NO」を突きつけた。チャガターエフもその選択を認めた、という話だということですね。どうも私は、「人間いたるところ青山あり」という言葉を思い出しました。(オレだって検索なしでも知ってる言葉はあるのよ)
だからこの小説は「奴隷的な思考しかできなくなった流浪する民族が、いったんは指導者によって定住する生活に移ろうとしたが、結局自分たちの自立した生活を取り戻すことを選択した物語」である、てな感じで読み取ったんだけど。

ちょっと余計なことだけど、それって「にんげん」って読むのか、「じんかん」なのかいまだによくわかんないんだけど。それから「大志を抱け」なのか、「死に場は何処にでもある」というのか?これもちょっとニュアンス違うだろ?恥ずかしながら、自分で納得ができない。誰か調べてみてくれ。
さて、大野は共同体的な安定を拒否した、ということを言いたいんだな。もちろんそれも「幸福とは」というテーマと関わりがあることだろうけどね。こういうのは旧ソビエトの国家観では許されないことだっただろうな。

それにしても、チャガターエフが高台で人々がひとりずつさまざまな方角へ去っていくのを見て「溜息をつき、苦笑した」、と書いている。自分の偏狭な思想と意気ごみを自覚したからだ。怒りも落胆もない。ただ苦笑する。偉い人だなあと思わなかった?
私を含めて教員はみんなこれを読んで反省すべきだな。生徒に怒っちゃダメ。ただ、大きな心で苦笑する、これでなくてはならないんだ。このチャガターエフはほんとうに完璧な教師だよ。そして素晴らしい公務員だ。

まったくだ。共同体のまとまった幸福、なんて糞食らえだよ。おれもそれを学びました。どうせなら自分ひとりだけで大儲けをして幸福になりたい。音楽で一発ヒットを飛ばしてさ。今村、一緒にやらねーか?オレだって鐘ぐらい鳴らせるぞ。

まあ、お前さん。半鐘はおやめよ。……おジャンになるから。

こらー! お前ら最初からそれを狙っていたんだろう。いい加減にしろよ。


コメント