
意外に考えどころの多い小説。だから面白い。
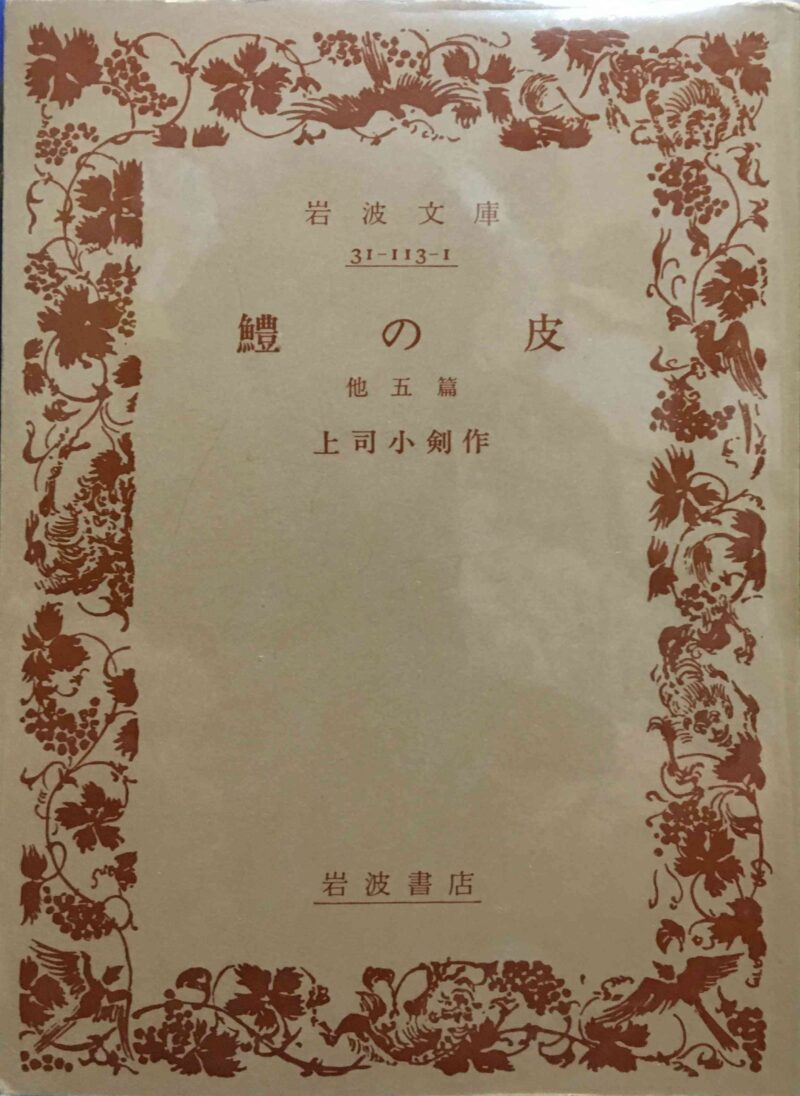
今回から、関西弁と江戸弁という対比から何遍か読んでみたい。君たち、今までこういう小説を読んだことがなかったと思うけど、私としては、この小説はみんなにぜひ読んでもらいたいと思っていたんだ。上司小剣という人のもの何編か読んだけど、相当な傑作と感じたんだ。私、今までは感動の強制はしてはならないと思って、なるべくそういう自分の評価は控えていたつもりなんだけど、上司小剣の作品はもっと読まれていいと思うんだ。でもみんなには自由な感想を聞いてみたい。
それでまず、『鱧の皮』ね。青空文庫にもあるから、こちらをどうぞ。

どう?自由に……。私の意見に左右されないで。だって現在は忘れられた作家の一人だろうから。古臭いとも思われるかもしれないし。自分に正直に言っていいよ。

登場人物が何人かいるけど、まず中心人物はお文ですね。改名したとありますけど、改名はどうもあまり話に影響していないと思う、ただお文は、読んでいて印象的な女性だと思います。36歳ということで、僕たちの母親とはちょっと下ですが、どうも夫婦の関係が微妙なものなんで、面白く感じました。決してくだらない中年の夫婦の物語という感じではないですよ。

彼女が讃岐屋を切り盛りしている。夫の不在のために、特に雇人たちの管理に気を遣っている。設定が明治大正の頃でしょ。これだけの使用人に目を配っているなんて、たいしたもんだ。先生、だいたいひとクラスですね。一人一人にちゃんと言わばちゃんと働いているかどうか、しっかり見ているのは学校よりも大変ですよね。帳場も使用人には任せておかないようですし。
このおばさん(あえて言ってるの、わかってね)すごいしっかり者ですよ。そして、それが逃げていった夫にも影響したんじゃないかっていうことを想像させる。奥さんが立派な経営者とはね。お婿さんもプレッシャーかかったでしょうね。

女主人のお文と母のお梶って絶妙な関係、その記述も絶妙

お文はお梶との関係でうまく母娘の距離をとっています。ほんとに上手にやっていると思う。これ、私にとってもすごく勉強になる。特別私の親が問題とは言わないけど、でもやっぱり世間並みの母娘の葛藤もあります。
世慣れていることは船上からの役人の注文に、代金を請求しないことでもわかる。お文の人間の大きさも読者は知りますね、この時代の役人の汚さへの批判が作者にある、なんて言えそうで、確かにそれはそうでしょうが、そのためのエピソードじゃあないですよ。むしろお文の内面のありようを表しているんです。役人のことなど、お文にとっては小さなことなんです。

叔父を連れ出し相談するが、母親にはぜんざい屋といいながら実は酒を飲みに行くくらいの女だからなあ。僕もこの人の現実的な才覚を感じたよ。年齢的にも30代後半になると僕らもこうなるんだろうか。仕事も順調にいき、使用人たちにもしっかり目を向けながら忙しく働く。そして、いったん離れていった夫との仲もけじめをつけようとする。夫はどうもまだ夢を忘れられないような男のようだが、彼女はまさしく現実的な経営者でありながら、夢見る夫も理解できる、という人なのかな。

東京の夫に会いにいくことになるが、その描写までは書かれない。これが小説というものなんだね。東京での二人の会話までは小説にしないんだな。

そうそう。そこまで書くと夫婦の関係性が明らかになりすぎて、読者の読みの余地を狭めてしまうんでしょうね。なんだか最近そういう「書かない」ことの重要性ということが理解できてきたような気がする。東京行きの前に、夫の言うとおり鱧の皮を土産にするため荷造りしておく。夫と決着をつけるために上京すると言ってるが、たぶん和解のつもりだろうことは、手紙の最後に小さい字で「鱧の皮を御送り下されたく候」と書いてあるのに対して、「夫の好物を思い出して、お文の心はさまざまに乱れているようであった」(p46)とあることで想像できる。だって、心の乱れの後で、夫に鱧の皮をあつらえるんだから、そういう意味でしょう?

そうなのかなあ。どうも私は変な手紙をよこしてきた夫に、きちんと別れを告げに行くんだと思っていた。新しい人をお婿さんに迎える決断をしたのかと……

最初手紙が来た時、「独りで見るのも心持ちがわるいよって、電話かけておっさん呼ぼうと思うてましたのや」って彼女は叔父源太郎に言っている。この「心持わるい」はどういうことだと考えるの?

私は単純にもう夫の手紙なんか読むのも嫌だ、という感覚だと思ったんだけど……。間違ってる?

意見が分かれるところかな。僕はとにかく決着をつける覚悟を持って東京に行く、ということだと思った。決断は夫に会ってからしようと思ってる。

僕は、夫を受け入れることを決心して東京へ行くつもりだったんだ、と読むね。彼女はすでに福蔵に帰ってきてもらうことを決めていたんだよ。お梶の条件なんかは、なんとか夫を説得するつもりじゃなかったのかな。そのくらいの駆け引きは、お文にはなんでもないって気がする。

じゃあそのへんは後でまた考えよう
甘い、男への視線は大阪の人の心の余裕?

では他の登場人物として……
叔父の源太郎が面白い人物。配役としては美味しいんじゃない、この人。お文にとっては良い相談相手であり、お梶とのクッションのようになっているような感じ。
夫の福蔵に対するお文の微妙な心理にも、或る程度の理解があるようだ。
福蔵の手紙に鱧の皮のことが書いてあったが、源太郎も「鱧の皮、細う切って、二杯酢にして一晩ぐらい漬けおくと、温飯(ぬくめし)に載せてちょっといけるさかいな。」などと、なんだか暢気に言っている。この家は基本的に男はお坊ちゃん。この構成は特に関西のドラマに馴染みが深い感覚もある。こういう家族がある意味で良い家族だという共通認識があるんじゃないかな。これも、物語の文法と言っていいんじゃない?


母親のお梶についても面白いよ。讃岐屋の先代女将で、たぶんお文の女将としての教育もしてきたであろうことは想像できるような、しっかりした女性。
現在は他所で孫を育てているが、店に出てくる場合もあり、店員たちにもその威光を感じさせている。
福蔵の帰還に関しては、厳しい主張をしている。その意向は娘や弟を従わせるような力を持っている。
福蔵への厳しい要求は、興行はしないこと、店の名義は戻った後の様子によること、借金は自分で片付けること。そして今後は出奔しないことを一札入れることを、店の者たちに聞こえるようにはっきり言った。(この時お文は知らぬ顔して帳場の仕事をしていた。ここが面白いね。)

あとは讃岐屋の「養子旦那」福蔵だけど、ちょっと影薄いわ。
芸事を好み、芸人を招き興行させるようなこともして失敗している。
今回は手紙で「二十円の金と店の名義を自分にすること、時々は好きな浪花節や芝居などの興行をさせてもらうことなどを復帰の条件とした。そして鱧の皮を一円分送ってもらいたいことも添えた。なんだか、関西の落語かなんかに出てくるような芸事の好きな旦那。道頓堀で忙しく商いしてる料理屋の旦那だと、船場あたりの豪商とはちょっとランクが違うんだろうな。お婿さんらしいし、自分の力でなんとか新しい商売を……なんて思っちゃったのかもね。それが興行師なんてやるもんだから、すぐ失敗してしまったんじゃないの?今の芸能プロダクションみたいなもんでしょ。それこそお坊ちゃんではだめよね。
お梶というお婆さんは、結構深みのある人間だ


いっぽうで、ゴッドマザーお梶の態度はさすが。なかなかの経営者だ。
お文がおっさんとぜんざい食べに行こうとすると、お梶は「いといで。」と帳場に座る。どこかで二人で福蔵について相談してくることは承知なんだ、このお婆さんには……。いま店の者に聞こえるように福蔵の帰還についての厳しい条件を言っていた、という話があったけど、むしろこれは「店の者に」聞かせるために言っていた言葉じゃないの?つまり店の従業員たちに、経営する立場の家族のけじめをきちんと聞かせておく意図があったんだと思う。だって、ずるずる復帰させるようなら「示しがつかない」じゃないか。お梶お文親子の経営姿勢を見せたんだよ。
でも、「いといで。」と二人を店から出してやったことから考えると、お梶はもっと穏便な方策を実は考えていたんじゃないか、と考えられる。だって、二人を外に出して話し合いさせるのは、当然福蔵のことを話し合え、ということだし、娘の気持ちも弟の性格もわかっていたはずだから。お梶はどういう結論になるかはだいたい予想していたんだろう。
そもそもね、婿さん復帰の条件をわざわざ「店の男女や客にまで聞こえる程の声を出した」と書いているのを、ただ「お梶はそう言った」と表現するのとの差を考えたら分かる。普通はそんなこと大声で言うのは憚るもんじゃないか。

そうだ。言語は差異の体系なんだからな。文章表現も読者が違う表現を措定して、比較してみることによって読みが深くなるっていうことがある。AとBと比較して、その差にこそ意味=価値がある、というのは単語だけとは限らない。文や文章にも言えると私も思う。ただこうした姿勢はもしかしたらもう古い考え方なのかもしれないけど。
でもまあ、新しい発見ができるかもしれないと思うんだよ。考えながら読むからねえ。『羅生門』で、なぜ羅生門なのか、どこかの荒れ果てた寺院じゃダメなのか。なぜキリギリスなのか。コオロギじゃあダメなのか。これも以前話したね。なぜKは真宗寺の養子なのか、日蓮宗じゃダメなのか。なぜ『源氏物語』を読みたいと弥勒に頼むのか。阿弥陀さんじゃダメなのか。ダメなんだよなあ。
というわけで、なぜ夫のことを店の人たちに聞こえるようにいうのか。なぜ鱧なのか、皮なのか。面白いねえ。いろんな気づきを言ってみ。

それじゃ、また他にも。この叔父姪の間で話されたこと。
「私(わたえ)ちょっと東京へいてこうかと思いますのや。……今夜やおまへんで。……夜行でいて、また翌る日の夜行で戻ったら、おかあはんに内緒にしとかれますやろ。……そうやってなんとか話しつけて来たいと思いますのや。……あの人をあれなりにしといても、しようがおまへんよってな。私も身体が続きまへんわ。一人で大勢使うてあの商売していくのは。……中一日だすよって、その間をおっさんが帳場をしとくなはれな。」
と、お文は叔父に留守の間の帳場を頼む。帰り道で彼女は道頓堀の蒲鉾屋で鱧の皮を買い、家に帰る。夫とよりを戻して大阪に帰らせようとしているのだ。彼女は決して夫を見離していない、と考える。そして、お梶もそうなると思って二人に時間を与えているんだ。
誰も悪い奴はいないんだよ、ここには。

タダで飲み食いするような権力ある奴らを除いてな。最初の郵便屋もそうかもしれない。

ここのお文の言う「話しをつける」の意味が人によって違うんだ。僕は、夫に帰ることを促すんだろうと思う。基本的に夫との和解というか、それが前提だと思うんだけど。
お文の「怖い」ってのは、何を怖がっていたのか

お文は最初に手紙を受け取った時に「私、何や知らん、怖いような気がするよって。」
と言っていた。まずその手紙を源太郎に呼んでもらいたかったのだ。
ということは、福蔵との仲が完全に壊れてしまうことが彼女の頭にあった、ということなのかと思うんだけど。夫から離縁の宣告をされるんじゃないかと……。そういう状況に夫を追い込んでしまったと思ったのか。だとしたら、お文の心情は、「怖いような」という表現がピッタリしている。その反省が東京行きだったんだな。もうぐずぐずしていられないという気持ちだったんだろう。

だとすると、鱧の皮を夫に与えるということは、和解のしるし?あるいはもしかしたら謝罪のしるし?それなら、この夫婦は何とか元の鞘に収まるわけ?。一時的にしろ……。そういう話しなの?。

大阪商人の一つの典型として、商売に身を入れないダメな男に、それを叱咤する妻、あるいはそういう男を上手に導いて、実は嫁ぎ先の商売を発展させることのできる妻。そういう典型の物語を生み出す物語に文法ができていたんじゃないか。いずれにしても愚かな夫と賢夫人という構造は「物語の文法」的な構造だ。

そういう構造ってジェンダー的な思考からいって否定的な見方しかできない。男が甘えて、その妻が苦労して成功するというのは、一見、女を優位に見せる形をしていても、その関係を男女の固定化した理想としているのは、正しいとは言えない。好きなことをする男のために尽くす女が理想なんて、冗談じゃないよ。

僕が思うことは、大阪の繁華街、道頓堀の料理屋が讃岐屋で、周りは芝居小屋も並んでいるような人通り。夕方は息つく暇もなさそうだ。そんな店をお文は一人で引っ張っている。三十歳代の女主人の気苦労は大変なものだっただろう、ということです。
そして、母親の存在がある。母はまだ頼らなければならないと同時に、それに頼ってばかりいられない、というのがお文の気持ちだろう、とも思う。
「ここへも電気点けんと、どんならんなァ。お母ァはんは倹約人(しまつや)やよって、点けえでもええ、と言やはるけど、暗うて仕様がおまへんなおッさん。……二十八も点けてる電気やもん。五燭を一つぐらいふやしたかて、何でもあらへん、なァおッさん。」
と、夫からの手紙を読むために薄暗い部屋に入って言う。こうしたひと言で母娘の関係が見て取れて、小説の読み取りの面白さ感じさせる。さらに叔父の源太郎の立ち位置も想像できる。厳しい母親と愚痴も言える叔父、という構図だね。

まず、この暗い部屋についての、お文のことばはほとんどストーリー進行に関係ないのに、この一言があることによって、いろんな情報が頭に入ってくる。建物が古いこと。客の部屋は明るく、綺麗であっても、たぶん店の裏方は暗く、古い建築のままであろうということ。先代の女将はそういう経費を極力抑えて、経営を順調に伸ばしていったであろうこと。そんなことを私たちの想像に誘導されるわ。この店の建物の構造まで読者に見せている、そんな感じ。
家族というか、一族の結びつきも温かく描く


そこで、叔父源太郎はお文の小学校の頃をふと思い出す。姪ももう36だと、しみじみした。そして、彼女のこれまでを彼が思い出すという形で、お文の結婚、夫の家出、外からの夫の手紙を読み耽る彼女の心情を、読者も共有していく。叔父姪の間にある心の繋がりを読者は理解していく。
もうこの時点で読者は、小説の底に流れているものの温かさを理解する。ちょっとこれは言い過ぎかな。
後の方で、お文が夫の福蔵の手紙に、鱧の皮を送ってくれと書いてあるというと、源太郎は、
「鱧の皮、細う切って、二杯酢にして一晩ぐらい漬けとくと、温膳(ぬくめし)に載せてちょっといけるさかいに。」
と暢気なことを言っている。お梶が聞いたらなんと言うだろうかね。
無論鱧の皮は、夫の、妻に対する甘えの言葉だけど、それが何よりの好物であるから、とお文も夫を拒絶はしていないのだ。叔父もその辺りの事情をよく理解しているのだろう。微妙なところがこの小説の面白いところだ。

いちばん厳しく言ってるのはお梶だ。さっきの話のとおり、福蔵が、好きな芸人の興行師になることを厳しく戒め、店の代表になることはしばらく様子を見てから、そして約束には一札を入れることを店のものに聞こえるように言っている。
娘が叔父とちょっと外で休息したい時に「いといで」と許可を出して、自分は帳場に座ったことに注意しなけりゃいけない。なにもお文は源太郎とぜんざいを食べにいくことはないんだ。手紙の事を考えたければ、一人で行けばいい。
しかもだよ、お梶も二人で出ていく意味をもちろん知っているんだよ。自分の前では二人が夫のことを相談できないこと、相談するということは、夫の帰還を意味するということも、わかっている。それでも、二人に「いといで」というよ。
お文は帰りがけに叔父に、夜行で東京への行き帰りを告げる。もうこうした状況をどうにかしようと決心する。しかしその決心は夫を迎える決心だった。(これは鱧の皮を用意していることから、当然の想像だろう)これも、お梶にとっては想像の範囲内だったろうと思う。
そういう読み取りができると思うと、なかなかこの小説はよくできていると俺も思う。少ない読書経験だけどこれ、名作じゃないか、と思う。お文の内心ははっきりとは書かれていなくても、夫に帰ってきてもらいたいということは明らかだと思うんだ。

ちょっと余計なことを一つ。道頓堀でお文と源太郎が店から出てきてお文の馴染みの店に来る時、源太郎がなぜかふと火事について口に出すところがあるだろ。
不思議な感じを持つところだが、少し年配の読者には、昭和47年(1972)の夜の「千日デパート火災」を思い出す。なんだろう。この源太郎の呟きは?もしかしたら、密集という現実の中で商いをする人々の危うさを感じたのかもしれない。なんて、あまりにおかしいかな。?
さて、お文やお梶、源太郎の心の内について他の読み方もあるんじゃない?

お文の福蔵への気持ちは、本当に愛情と言えるのかな。はっきりそうだといえないと思うけど。「私(わたえ)も身体が続きまへんわ、一人で大勢使うてあの商売をしていくのは。」といっているんです。
彼女の本心はその辺にあるんじゃないでしょうか。独りで背負い込むのに疲れたとか……。

確かに。そんなところかもしれない。
しかし、傭人の留吉とお鶴という二人の店内での密会を、夜が更けて帰ってきたお文は見つけて、寝ていた人々を起こすくらいの声で叱りつける。お梶も起きてきた。
この時のお文の気持ちはどうだったか考えてみるとどう?
お文は傭人に示しがつかないと怒ったのではないよ。若い二人への嫉妬、やっかみがあったはずだよ。彼女自身は気づかなくてもね。
なぜなら、このあと、寝しなに銀座の下に入れた鱧の皮の小包をちょっと撫でてみて、寝支度にかかったから。この最後の動作をどう見るかは、まさしく間主観的(?)に合意できるものでしょう?
なぜ鱧? なぜその皮? なぜ撫でる?

小説の一番大事な作用よね。包みに目をやった、と書かれないで、撫でてみたと書かれているんだよ!これ絶対に違いますね。
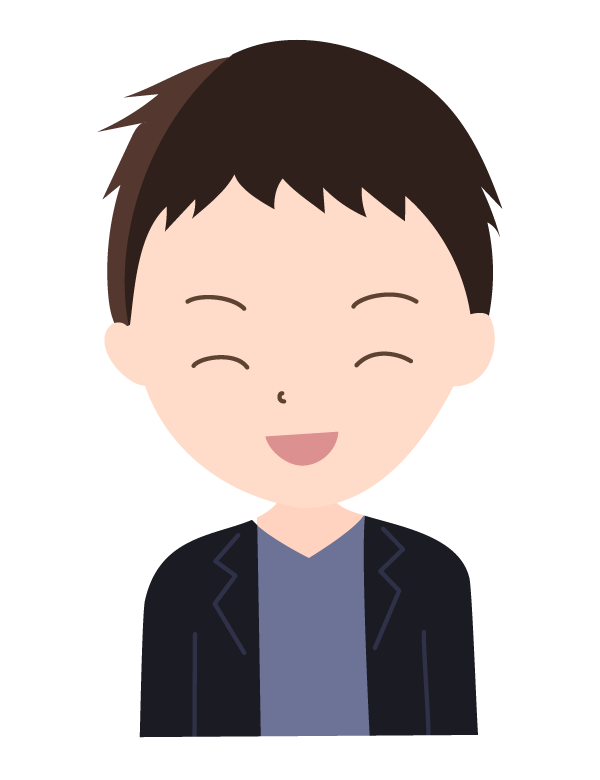
なぜ福蔵は鱧の皮を送ってほしいと小さな字で手紙の末尾に書いたのか?小さな字で、というのは自分でも瑣末なことを書き足すことに、羞恥があったということだろう。では、それをあえて書き足したか?その食味に執着があったからだ。でもなぜそれを上司は書いて題名にもしたか?これは前に出てきたド・マンの考え方からすると、「分からない」が正解としても、解釈はわれわれの自由。というよりそれこそが小説を読み、考える楽しみだった。そんなことを思いました。
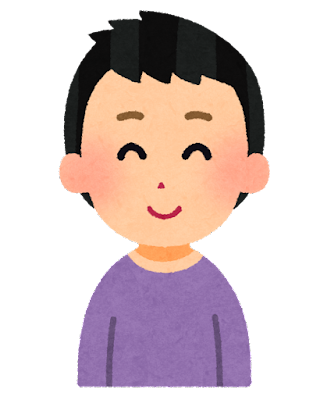
大阪らしい、大阪を象徴する食べ物とは別にないのか。現代的には大阪といえば「たこ焼き」か。でもそれじゃあ話にならなかったんだと思う。じゃあ、なぜ鱧の皮なのか?日もちとかは関係なく考えると、鱧ではダメだったんだ、と僕は思う。
鱧といえば旬は夏だって。そして鱧が非常な生命力を持つ魚であることが知られているらしいよ。その身を食し、残った皮を細長く刻んで酢の物にして食べるという。
すると、読者がこの食べ物に執着する、店を飛び出た婿さんと一緒にイメージすることは何なのか、これが大事なことになると思いました。
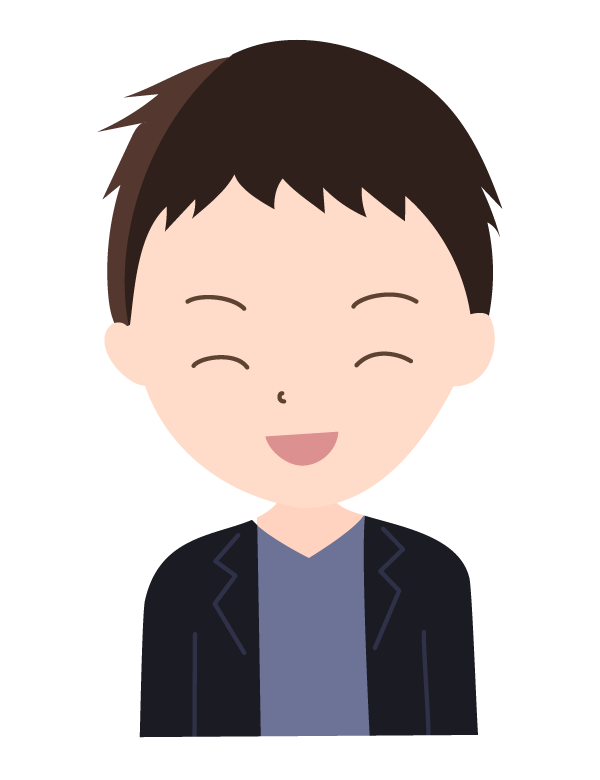
つまり、こういうことだね。
お文は鱧の皮をかまぼこ屋で買うのだが、鱧は身をかまぼこにして残った皮を刻んで売る。福蔵は夏になるとその鱧皮を懐かしく思うのだろうが、それはかまぼこ生産の余りなのだ。
たこ焼きではダメなのは、鱧の季節が大阪の暑い夏をイメージさせること、そして何よりも、鱧の皮はかまぼこ生産の余りの皮だからだ。どこかの普通の店で(かまぼこ屋以外で)鱧の皮を買うのとは違うということよ。
お文とすると、鱧の「皮」を夫に与えるということに、夫に対する申し訳なさを感じていたかも分からない。それでも、夫に与えるのは「皮」だから与えるんじゃないだろうか。彼女にとって夫は愛情を持つ対象であっても、夫に好き勝手にさせることは許さないんじゃないかな。それを暗示するのが「皮」だと思う。ちょっと強引?
でもねえ、ちょっと考えてみて。お文が夫との和解を決断したとしたらその原因は何?
店の経営がとても独りではできない、先行きも不安だ、ということだったかもしれないよ。だとしたら彼女の情愛は本当のものだとしても、それはリアルな生活が原因だとも言えるでしょ。今の話ではその証明が鱧の皮だ、ということになるじゃないか。


おう!つまり下部構造だってわけか。「生活」こそが根本原因なんだってことだな。若い恋人たちへの嫉妬も、そういうことなんだな。
そうするとこの作品の物語を説明するとき、皮肉な文章になりかねないなあ。お文の温かい情愛という評価も違ってくるね。
鱧の皮の包みを「撫でる」ことには確かに愛情を感じるが、それは見方によれば「打算の上に乗った愛情」と言えるのかもしれないなあ。

福蔵に送るものとして、そんなに粗末な食べ物でもないが、それでも身を取ってしまった鱧の皮がちょうど良い表象なのだ、というのは面白い。たとえば彼が鱧の身で作るかまぼこを要求しても、それは「養子旦那」の身分には合わないもの。彼ら一族の正統な中心はあくまで、お文の方。鱧の身はお文の方なんだ。
関西弁ということがどう受容に影響するんだろう?

さて、難しい話になるが、この小説に使われている会話文での、大阪弁というか、関西弁というべきなのか、こういう会話について、どう評価する?単なる方言の会話で、標準的な関東のことばで示されても同じことなのか?

置き換えてみればわかるが、二つの方言には大変な違いがあると思う。

そうだよな。あとでその関西弁について、ちょっと資料を見てもらってみんなで考えてみよう。しかし差し当たって、次回はもう一つ上司小剣の小説を。これまた私からしたら傑作なんだ。
おまけ
しばらくして、たまたまBSで小津安二郎『秋刀魚の味』を30分ほど見た。

その映画で、主人公たちが昔、旧制中学の頃漢文を教わった「瓢箪」というあだ名の教師を料理屋に招待する場面がある。その食事で鱧のお椀が出て、「この美味い魚はなんですか」と、「瓢箪」が皆に尋ねると、鱧だという。彼は美味いものだと関しながら、かつての教え子たちにペコペコ頭を下げる。そして食事会のあと飲みかけのウィスキーを土産にもらい、「瓢箪」は家に送られて行くのだが、彼の今の商売はうらぶれたラーメン屋の主人であり、娘と苦しい生活をしているのが明らかであった。かつての生徒たちは、教師の様子を、ああはなりたくないな、と語り合うのである。
このあたりまでで私はみるのをやめてしまったんだけど、裏ぶれた老後をかつての生徒たちに見せる老漢文教師。哀れな姿。なんだか自分の姿を鏡で見たような感じだったなあ。『秋刀魚の味』は非常に有名な映画だが、あんな場面があったとは全く知らなかったよ。
しかも「鱧」だよ。なんという偶然か。
ハモはここでも高級魚として出てくるんだ。そして、映画の題名は『秋刀魚の味』だよ。当時の秋刀魚は、大衆魚としてごく安価な、大衆にはお馴染みの魚だったんだ。その後の映画がどういうふうに流れて行くのか全く知らないけど、鱧と秋刀魚の対比は仕組まれているものじゃないかな。誰か、知っていたら教えて欲しい。
それにしても、君たちも将来俺にご馳走してくれるようになることを、願っていますよ。

任しておきなって、先生!


コメント