

さて、今回は東京の話。江戸言葉で言い合いするのを出そう。
内容は決して楽しい物語とは言えないけどな。我慢して読んできてくれたかな。
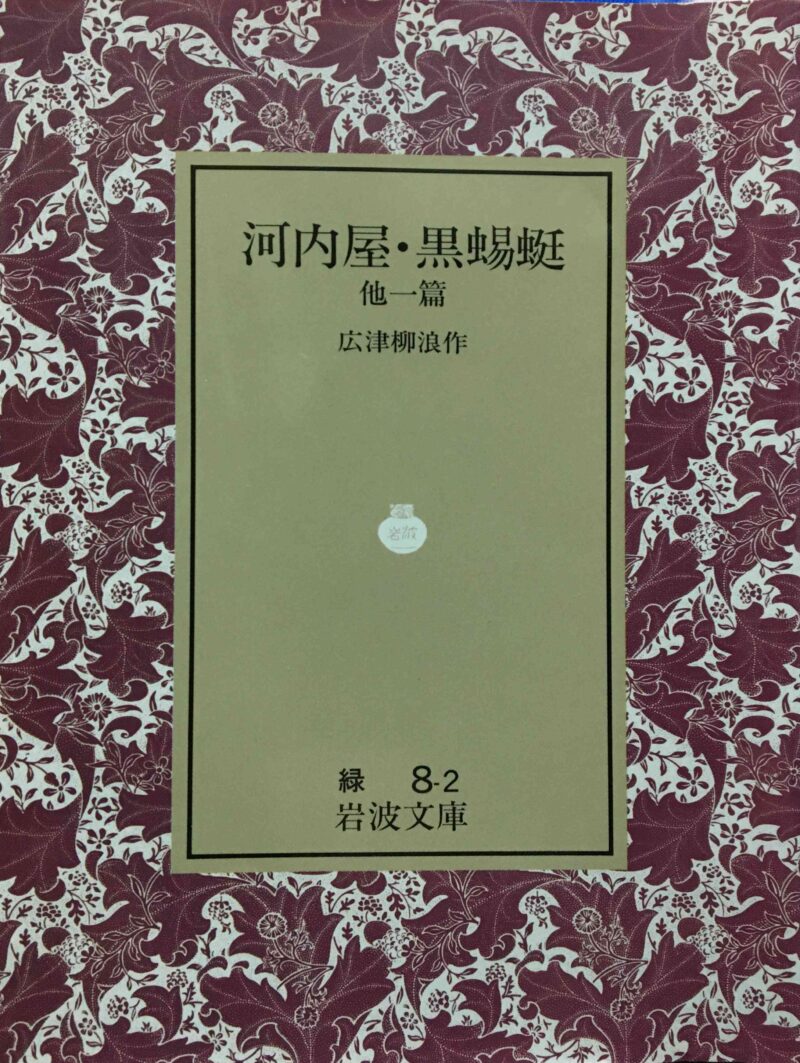

言葉遣いも古くて、難しかったけど、話のすじは大体理解できました。

私も内容は理解できたけど、全く共感できる登場人物はいなかった。正直言って面白いことも、目新しい技法や解釈も無いようで、読み通すことが辛かった。よくこんな話を読み切った、と自分を褒めたいくらいよ。

同じような感想ですが、単純な愛憎劇だな。なんだかどこかのドロドロしたテレビドラマのようだったな。もうちょっとなんとか読者の意欲に刺さる感じがあっても良さそうなものじゃないか。嫉妬と軽蔑、兄弟のいがみ合い。そんなものを交錯させて話を作っているようにしか思えないんだ。そうして、これがこの講座の材料になってるのか、正直分かりませんなあ。まだ江戸時代の勧善懲悪の話の方が読み応えがあるんじゃないかと変な疑問を感じましたよ。つまり、先生がおれらにつまらない明治時代の通俗小説を与えて、それを捏ねくり返してみろと試しているんじゃないかと。

私も同じような感想です。正直な気持ちでは、通俗的というか、そんな小説の裏がわに何か考えなくてはいけないものが隠れていて、それを見つけろ、という授業なのかな、なんて。でも、特別なことは思いつかなかった。やっぱり、つまらない、ぐだぐだした陰湿な劇のように思いました。
見たこともないけど、文学史で習ったあの「文楽」ね。あの中にあったでしょ、心中ものって言ってましたか?現代でもあの物語に美しさなんてちっとも感じないし。ああ、近松門左衛門でした。歌舞伎ではすごい人気なんでしょ。うちのお母さんなんて、「孝夫さま!」なんて言ってるの。あら余計なことでした、すみません。


悪者は、お弓だよね。でもこういう悪役を忌み嫌うという読者の感情を、ちょっと置いておくってのがこれまで授業でやってきた方法の一つだった。
まあ、良い悪いとか、好き嫌いとはいったん離れて作品を見てみようという態度。こういうことなの?

私、現象学という哲学の方法を参考にして授業で話をしたことがあったよ。
ここにある教卓ね、この教卓についての”ほんとう”は我々にはわからない、ということなんじゃないかな?(いや哲学の本についての理解ってこの程度でいいんだろうか、という疑念がいつも自分で感じちゃうんだけど……)
フッサールという人の『現象学の理念』という本の中でこう言っている。
すべての超越的なもの(わたしに内在的に与えられないもの)をゼロの見出しをつけて理解すること、すなわち、その実在、その妥当性をそのまま認めないで、たかだか妥当性現象として定立することを意味する。
超越というのは、絶対に疑いができない物事ね。超越的なものをそのまま信じない。これは超越ね、という態度で、突っ放して理解するってことかな。

この話の時、僕が思い出すのはエジプトの壁面によく見る人の絵だよ。これも、もしかしたら偏った観念かもしれないが、エジプト古代の壁面の人の絵って、みんな横向きじゃない?ヒエログリフも文字としては当たり前だけど、ほんとに画一的。正面から見た人の絵ってあったのかなあ?きっと人の顔を意識する際には、彼らの頭には「横顔」が浮かんでいるんじゃないかな。人の絵はこういうもの、というのを信じて抜け出ることができなかったんじゃないかな。そういう状況から抜け出ることはすごく難しいんだろう。誰かが顔を正面から描いたりして初めて「あれ!そういう描き方もあったのか」と気がついたのかもしれない。
また、以前、養護学校にいたとき、知的障害高等部(当時はそう言っていた)の生徒たちの描く人の絵が(障害の程度や様相によって違いはあっても)、同じように胴体から四肢が棒状に伸びている絵だったことを思い出す。あの生徒たちは本当に純粋な「心」を持っていて、それを素直に外に表現するから、外界からの表現の仕方などの情報が入ってくるとそこから抜け出ることは難しいんだろうと思ったよ。人間はこう書くもの、という観念に支配されていたんじゃないかな。
でも、それはたぶん私たちも同じなんだ。ある決まったルールで絵を描き、決まったルールで文を読む。決まったルールに従って考える。お勉強のできる高校生も、授業中寝ているだらけた人も、街の中にいる怖そうなヤンキーも、みんなそれぞれ無意識のルールに従って、それを疑わずに生きている。
読書もルールに従って読んでいる。よく「感情移入」っていう。これもフッサールの用語として簡単じゃないらしいけど、僕らは一般的な意味での感情移入して小説を読んでるよね。ここで言えばお弓に対する感情だよ。誰もが彼女を少なくとも悪い女だとして読んでいる。でも、そのいいとか悪いとか、それは本当か?そのいいとか悪いとかをフッサールは「超越的な定立を排除」という仲間に入れて議論しないわけ。
さてそこで、道徳的な観点を語ることはあってもいいのだが、僕らの小説の読みは、それから自分が自由になるということも考えてきたわけなんだね。改めていうとね……。
つまり、お弓が悪い女だというのはごもっともだが、それをひとまず置いといて、他になんでもいいけど面白い読み方できないかなあ、ということなんだ。

講談社『日本近代文学大事典』を図書館で借りました。広津柳浪の項に『河内屋』が説明されていました。「愛欲のもつれから破滅していく人々を描いたこれらの作品は、明治の心中ものとして好評だった。」として”名作”と評価してありました。この読み方については、今先生の言ったことと関連して、どう考えたらいいでしょうか。
僕は確かにこの事典の記述通りに「愛欲のもつれの小説」ということで納得しましたけど、一方で、だから面白くないんだよ、とも言えそうな気がしていたんです。少なくとも新しい読みをしているとは言い難いです。
でも、だからと言ってそれ以外どういう言い方ができるんでしょうか。「明治という近代化された日本の時代に心中ということに新しい価値を与えた物語」とか……。こんなの『こころ』の授業の時にそんなことを聞きましたね。何か実際の事件をモデルにしたということでもあれば、「近代の世相の中で、初めて起きたスキャンダラスな事件をモデルにした物語」とか言いようがあるでしょうけど。なんだか面白くもなんともない小説に違いはない。名作という評価だって、どうなの?

そうだな。他の人はどう?どう?悪い女が可哀想な女を追い込んでいき、結果として自分も破滅に追い込まれた物語、とかいうのとは違った小説評価はない?

えへへ。おいらちょっと思いついちゃったんだけど……。言ってみていいですか?お前らびっくりして座り✕✕するんじゃねえぞ。(おい『火焔太鼓』かよ、と今村)
普通はお弓とお染、この二人は対立しているものとして読みますが、そうとばかり言えないんじゃないでしょうか。お弓もお染も、生き方として一番影響を受けたのはその母親から、です。

お弓とその母のお倉は自分たちの店、桜家に重吉を泊めて、何日も家に帰さずにいた。ある日その重吉を、お弓はなぜか無理に帰宅させようとする。そんなお弓にお倉は小言を言う。なぜ金蔓を帰しちまうんだ?と。お弓はこれまでの母親の、自分への仕打ちの不当なことを責めて、自分が決断するべきことなんだと主張する。お倉は母親の人形になることを拒否した娘に反論できない。お倉の生活は娘にかかっているという引け目がよく感じられるところです。このぶつかり合いはこの小説のもっとも注目される部分ですね。
この母娘の言い合いあたりから、お弓は重吉の家に乗り込んで行くという方向に進んでいくんです。本妻のいる家に愛人が乗り込んでいくことになります。
この言い合いではお弓は母親に躾けられた自分を語り、母の思惑の失敗を責めました。これ以降も彼女はお染という本妻が存在する河重家に乗り込んでいくことを決めます。これが自分の意志を通した行為なんです。でも、それは母親からの脱却だったんでしょうか?そこが、この小説のいちばんの問題なんです。しかしお弓は母親の価値観から逃れられないんです。
彼女の戦略は金持ちの男を自分の思いのままに使って、自分の人生を拓いていくということですよね。そして、かつて自分を振った男を自分に靡かせてやろう、という欲望を持っていた。基本的に男と女の駆け引きに「勝つ」ということだ。これは母親の価値観と何も変わらない。そうでしょ?
じゃあお染はどうだ?なんで好きでもない重吉と一緒になったんだ?
実は、清二郎との結婚を諦めて重吉と一緒になったのは、同様に母親の価値観を受け入れたからだったんだ。(ここにお染の父親が表に出てこないのは非常に興味深い)
お染が母親と話したその内容をお染が女中のお花に話している。(十三)そのお染の語りはこういう内容だった。
おツ母さんがその事を言い出しては、一つには姉さんの遺志(こころざし)を継ぐため、二つには河内屋とは是非とも縁を結ばねばならぬ間柄であるから、お前はあんまりすすまぬようではあるが姉さんの亡くなった時のこころを思い、おツ母さんの頼みを聞き分け、家と家との続きあいを考え、是非とも承知してくれとのたっての言いつけを、私は涙ながら承知した時、世に捨てられた身の上とは覚悟した。私が河内屋の嫁になりますからは、たとい何様事がありましょうとも、私は離別(さら)れて生家(うち)の敷居は跨ぎませぬ。おツ母さんもまたただ私可愛さにどんな目に余る事があろうとも、決して離別(さら)せてくださリますなと、その時に堅くお約束もうしたのであるから、つい一昨日病気見舞いにとてお出での時、お弓の事から旦那の仕向きの気に入らぬ数々を数えたて、見込みのない家に一生を埋もれ木になろうより、今のうちに分別をし変えてと、さめざめお話があったゆえ、私が申したのはここの事でござります。今更夫が不足で、離別ってもらうくらいなら、あの時ここへは嫁(まい)りませぬ。姉様の代わりに身を捨てたからは、私はこの上いかほど辛い事悲しい事があろうとも、決して決して河内屋を出る心はござりませぬ。
つまり、お染は母親から重吉との結婚を言い出された時から、家のために身を捨てて従うことを覚悟していたのです。今さら母が娘を不憫に思っても、そんな母に従うものか、と強い意志を母に示したのは、母親への怒りでもあったでしょう。でも彼女は母親の元の指示通りの選択を貫くことになりました。
お弓とお染は二人とも親の示した世界を受け入れて生きていった女なのです。しかも、その親とは二人とも母親だった。当然、その世界とは二人ともに伝統的な日本の家という縛りですが、直接的には母親が縛り付けていたんです。

お弓は母親に反発しようとしていますが、それでも母が示した、男をいかに引きつけておくか、という道。お染は母に全く反抗せずに家のために身を捨てる、という道。両方仕組まれた道を歩くだけなんです。実は二人は同じなんですよ。親と同じゲームへの参加を強制された女たちなんだ。
この小説は、いわば表面的には敵対しても、本質的には同じくゲームに遅れてきて、そのルールに従う他なかった女たちの悲劇を描いたものだよ。

「愛欲のもつれからの破滅」の悲劇じゃない、というわけだな。上手いとこに気づいたなあ。まさしく普通の読者にはない視点だろうなあ。

よく言われる事だが、子は精神的に「親を殺して」成長しなければならない、なんて聞いた事ないか?河合隼雄というユング心理学者がいたんだ。その人の『昔話の深層』という本があって、そこに全てを受け入れて、全てを与えてくれる「母」なるものの原型があって、それを自立を阻むものとして認識し、それと否定していこうとするのが昔話に特徴的にある、という。『ヘンゼルとグレーテル』なんかそうだという。いずれにしても、親との闘いを描いている。みんなも聞いたことあると思うが『オイディプス神話』といい、昔話といい、親を乗り越える話は人間個人の根本的な課題なんだろうな。もちろんこの「親」も「殺す」も一種の象徴的な意味で使っているんであって、どっちも具体的な親や殺しを意味してるという事ではないからね。
私も、この『河内屋』という作品をそういうところから見るのは十分妥当性があると思うな。お弓もお染も、二人とも親を乗り越えるということを意識するところに至らなかったと言える。


うーん、ここまで女二人について興味深く聞いていたけど、この作品が女二人だけの物語というわけじゃないでしょ。
おれだってちっとは考えがあるんですよ。つまり男二人の対立ですよ。よくある兄弟の競争という物語、という単純な構図で言ってんじゃないよ。
おれ、どうも最初から引っかかってたところがあるんだ。重吉の事だよ。みんな覚えてないか、この兄ちゃん「保険会社の重役」なんだよ。家業は横山町で「糸屋」だったのに廃業してしまったのが河重だ。商人であっても別に構わないのに、どうして「保険会社の重役」だという設定なのか……。ここわからないよな。
ちなみに日本の保険会社を調べてみてよ。

ハイハイ。わかってるって。俺がやるよ。えー、日本に保険というものを紹介したのは、例の福沢諭吉だそうだよ。明治14年(1881)はじめて福沢の門下生が「明治生命」を創設したとある。この小説は文庫本に明治29年と書いてある。保険に関する法律ができたのは明治33年だそうだから、やっぱり保険という制度が日本に広まりつつある頃の話として読めばいいんじゃないか。

だとすると、重吉は日本という国がいろいろ整備されつつある頃に、その先頭に立ってリードしていった人物ということじゃないか、そうだろ?そういうことを本文は言ってるんだろ。たぶん、うまく家業から転換して、自分の生きる道を拓いてきたひとりがこの重吉だったと考える事ができる。

つまり、この兄は近代の日本を先取りして、その先頭に立っていこうとしている人物で、一方で弟の方はそれに取り残されてしまった男、という構図が見えると思う。ということで、ずいぶんこの作品は社会性を持っていると思うんだ。だって、保険という制度はサービス産業としての先頭を走る、近代的な産業であっただろうと想像できるから。
対して清二郎は全く取り残された形だ。親の財産で、すぐに働かなくてはならないということはないが、彼には全く将来が見えない。お染のために自分を滅することも厭わないが、兄から独立を匂わされるとかえって自分を追い払うつもりだと悟って諍いになっている。ついに最後はお染と死を選ぶわけだが、彼は所詮日本の次の時代に生きてはいけない人間なんだな。純粋な若者で人から好かれるし、好きな女性には自分を悪者にしても救いたいと思うような男なのだが、やはり近代には似合わない人間像ということだ。
さっき、女性像は意外に同じ世界にいると考えられるということだったけれど、男二人は対照的な世界にいる二人と見る。どうでしょ?

うん、これも同感だな。ドロドロした劇、という見方とはますます離れていくなあ。

でも、素直に、なんの前提もなく読んで、お弓の復讐の悲劇、と読むのはいけないということはないわね。核心はお弓の「ルサンチマン」と読むのだってひとつの、大事な読み方でしょう?その復讐という心理を深く検討することも、ひとつの読みの面白さに通じるはずよ。

そうよ。お弓の欲望の物語というのをまず考えたいわね。ドロドロした愛憎をまず認めて、そこを深く掘り下げる。つまりお弓の欲望ね。お弓みたいな執着についてはきっと哲学でも何か言ってると思うんだけど。

わたしも、このお弓という人がすごく執着する人、悔しがりの人であることにびっくりする。人を愛する、というよりも「恋することと勝ち負けをごちゃ混ぜにしている人」という感じ。以前に振られた相手に対して、すごい悔しさを感じてしまうのって、わからないわけじゃないけど、人を好きになることと勝った、負けた、という感情は、本来関係ないことじゃないのかなと思うんですけどね。
清二郎に対する感情を読んでると、本当に清二郎を好きなのか、それともそうじゃないのか。だって、清二郎に対する口説きは読むに耐えないわ。

前回紹介された『「自分」を生きるための思想入門』を授業の後で、ざっと読んでみたんですけど、「人間の欲望はゲーム的エロスを目指す」という記述を思い出しました。ゲームは勝つ事が目標ですからね。まさしくお弓の欲望はこの勝者を目指すことだけだったという事です。さっき母親のセットした世界の中で生きる、なんていう話がありましたけど、この世界とはまさしくゲームの場ですよね。
そうそう、私たちが毎日過ごすこの学校もゲームの会場ですよ。大学入試もそうだし、就職して仕事をするっていうのも、考えたらゲームですよ!当然恋愛もゲームですよね。それらの勝負に脱落したくないから、私たちは頑張るんですよね。お弓の行動もおんなじ事なんですね。
さっきの話で言えば、お倉はお弓にゲームのルールを教えて、自分の勝者への夢を娘に託し、お染の母もゲームのルールを教え、自分の価値観をお染に繋ぐ。どこかでルールが変われば、その変更したルールを後継者に伝える。それができなければ清二郎のようになってしまう、そういう事なんですかね。日本の近代化はこういうふうにされていったんだ。ゲームのルールに従いたくなければ、この参加者の椅子は他の人に移っちゃうんだ。
それでも、うまく時代に乗っていったはずの重吉の運命は悲惨だ。だって最終的には誰からも本当のゲームの参加者の資格を与えられないようになってしまったんじゃないの?小説の最後で重吉が引退したような記述があったが、彼の社会的な人生はこの事件で終わったという事だと思う。

見方によってはこの人が最も気の毒。お染に対して和解を求めたりしているのにね。しかし誰からも愛されない人だった。
そこで、どうして恋愛と勝ち負けとがリンクして捉えられてしまうんだろう、ということに目がいきますね。好きになるってことは負けたことなんですか?ちょっとそれって倒錯している感情じゃないかな。
(この発言を彼女が言った時、妙に教室は静かになった。)

そう考える時、
私を嫌がって、嫌われたのは此奴(こいつ)にばかりだ。その意趣返しをしないで、どうするものか、憎くって、憎くって、お染に会わせてやるものか。今思い当たらせてやるぞ。と、お弓はすぐにも怒鳴りつけたいのを無理に抑え、眼を半眼に開きながら、じっと重吉の腕に手をかけいざとばかり待ち構えていた。

と、お弓の心の内を、語り手が説明しちゃってるんだよね(十七)。僕はここがこの小説の残念なところだと思ってる。こういう執念を何か別の表現で示してたらよかったのに。つまり、語り手が説明しちゃうとお弓の心境が前提となっちゃうんだよね。彼女の「憎い」という感情の幅が狭くなってしまって。お弓だってそんな単純なもんじゃないだろうに。あまりに「憎さ」が際立っちゃって、どうして恋愛感情がこんなに変わっちゃうの?ってというところがわからなくなるんじゃないかな。
いや、実はそれも気持ちとしてはわかるんだ。わかるんだけど、その仕組みというか、気持ちの変化を、哲学だとかでどう説明されてるのか知りたいんです。そりゃあ本当の愛じゃなくてゲームの世界だ、というのは納得できたんですけど、「かわいさ余って憎さ百倍」という事がどうして起こるのかという説明を聞きたい。

それこそ、ギリシャの時代からいろんな人がいろんなことを言ってるようだ。
紹介した竹田青嗣の本を読むと、まず、ルサンチマンという言葉は、もともとは感情を反芻すること、辛いことや悲しいことを思い返して、その感情にいつまでもくよくよ、うじうじこだわることを意味する。

冷たくした父親、自分を振った女、自分を除けものにした他人や社会をいつまでも恨み続けることもできるし、何とか仕返しをしてやろうという気持ちを持つこともできる。しかし、肝心なのは、それ自体が人間にとって一つの存在可能、生きる理由になることがあるということだ。
このルサンチマンというのは自己中心性が挫折したときに、まず最初にやってくる人間の欲望の逃げ場です。ある場合ルサンチマンは、はじめの欲望よりももっと激しい欲望になって、強く人間を突き動かすことがある。それは「私」が傷つけられたことへのリアクションであり、いわば反動的な欲望です。
お弓の感情は、まさしくこのルサンチマンであり、この文のようにはじめの欲望=男への愛を乗り越えてしまう。彼女の「エロス」は清二郎の愛を得るということでは、すでにない。河内屋の秩序あるいは河内屋それ自体の崩壊が、彼女の欲望なのだ、と言えるだろう。それに例のショーペンハウアーによると、エロスの根本は自己愛だ。さっきの話で、ゲームの勝者になることがお弓の目的なら、確かに自己愛に取り憑かれたお弓は首尾一貫している、と言えるね。
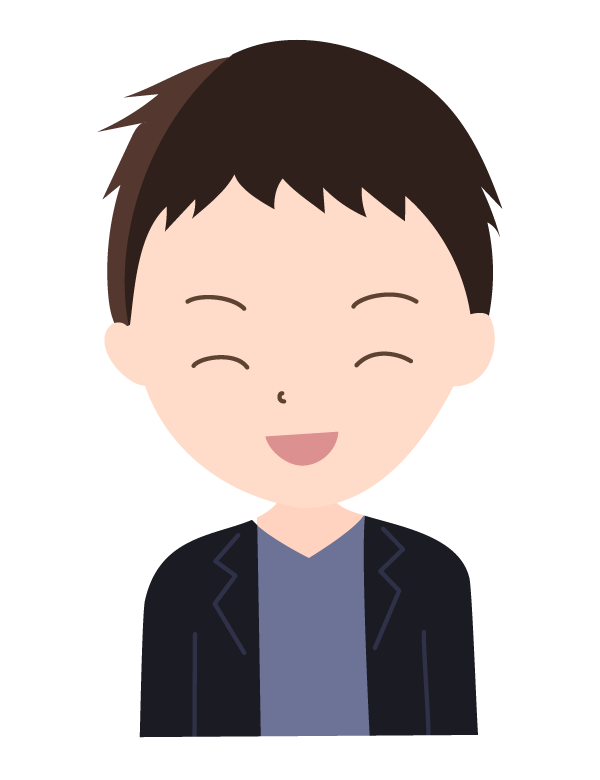
僕も竹田氏の本をめくってみました。
『人間的自由の条件』(講談社学術文庫)にヘーゲルの『精神現象学』についてコジェーブという哲学者が解説している、それを竹田氏が引用している。これって、「孫引き」になるんでやってはいけないことだろうけど、今回は勘弁してもらって、(『精神現象学』も分厚くて難しそうで、図書館から借りるのも嫌だったし、文庫本だけ借りてみた)こうあったよ。
例えば男女間の関係においても、欲望は相互に相手の肉体ではなく、相手の欲望を望むものでないならば、また相手の欲望を欲望として捉え、この欲望を「占有」し、「同化」したいと望むのでないならば、すなわち、相互に「欲せられ」「愛され」ること、或いはまた事故の人間的価値、個人としての実在性において「承認され」ることを望むのではないならば、その欲望は人間的ではない。
『ヘーゲル読解入門』 アレクサンドル・コジェーヴ
これは単なる所有したいという欲望とは違うと竹田氏はいうんですが、その通りですよね。ヘーゲルって僕も名前だけしか知らないけど、ここで言ってることはそんなに、わからないわけではないです。相手が欲しいということは、単純な所有欲ではなく、相互に認められたいという地点までの欲望だということでしょ?同化まで求めるのが人間なんだということでしょう。
それが憎しみになるのはなぜか。お弓が極めて竹田氏のいう人間だからですよ。自分のことを承認してくれなければ満足できないからですよ。先生の好きなショーペンハウアーでいえば、苦悩の中に入ってしまう運命にあるからですよ。……というのが僕の考えなんですけど。

愛欲の悲劇は悲劇で間違いないんだけど、それも単純な話じゃない、ということかな。
まあ、前回の『太政官』に見た「愛情」「欲望」と比べてみても面白いかもしれないな。人間というのは厄介なもんだな。
それとちょっと考えたんだけど、ゲームの世界を生きるということは私たち、君たちにも当てはまるよな。大学受験というゲーム、経済というゲーム、政治というゲーム、恋愛というゲームなどなど、我々はこのそれぞれのテーマを持つテーブルに座らされてるというわけだなあ。今そんなことを生徒に言っちゃあいけないけど、大変ことだな。だから、ちょうどショーペンハウアーの『意志と表象としての世界』に書いてある退屈と苦悩の話だ。そのゲームのテーブルから離脱することによってのみ安寧が訪れる、ということなんだな。

日本の明治時代のこんな小説を読む、つまり一見愛欲のドロドロ芝居を読むことで、そういう結論に到達するのは、本当に小説の面白いところだな。小説、読むべし、ということだよ。
最後に、昨日寝る前に読んだ本の一節を紹介する。これはまた後で参考に示す本だけど、この中で文学に関係する読書にはプロトコルがあるはずだというんだ。このプロトコルについてはまたどこかでみんなに紹介する。辞書にはそういう意味の表現が書いてないけど、私は手順といった意味だと思うんだけどね。違うかな?(辞書には、外交儀礼、議定書、と書いてあった。)
……読み方を学ぶことは単にテクストから情報を獲得するという問題に留まらない。それは、我々自身の人生というテクストの読み方、書き方を学ぶという問題でもある。このような角度から見ると、読みは単なる学問的な経験であるばかりではない。それは我々の生命には限りがあり、生の中で生み出していく充足感は全て、我々を取り巻く世界との関わりの強さに左右されるという事実を受け入れる一つの方法なのである。テクストの読み方を学ぶときに培った、まさにその集中力をもって読めばよいのだ。人は誰でも、表面的な理解だけでは済まないような経験に遭遇するのだから。
『読みのプロトコル』 ロバ^ート・スコールズ 岩波書店
こういうことですかね。
それにしても、『河内屋』は思いがけずいろんな面白い読み方ができたね。

ついでに一つ感想を加えていっていいでしょうか?
昨日家で、you tubeで社会学者の宮台真司という人の対談を視ていたんですが、対談相手の人がある政治的事件について、検察のリークにばかり報道が頼っていることの危険性を主張していたんです。確かにこれは本当で、検察のリークでしか記事になる情報は得られないようです。仕方のないこととだとも僕は思ってたんですが、今のメディアがそういう状態なのをみんなが自覚しているかどうかは大切な問題のようですね。
で、それについて宮台氏はそういう情報を「テンプレート情報」と言っていたんです。人間は既成のテンプレートに従って自分の情報を選び信じ、また作っていく。そういうことだと僕は理解しました。検察からの情報に慣れていき、そうでないものは切り捨てていく。だからメディアの方も、テンプレートに合ったものしか情報として流さない。特に日本の報道は今や全く硬直化している、そういうことを言いたいんだと思いました。もっとジャーナリズムがしっかり自分で取材しろと言ってる。
これは物語にもあてはまるんじゃないですかね。「期待の地平」とも関係してくるんでしょうけど、このテンプレート的人間像が『河内屋』の中に描かれている人々なんだと言える。みんなそこから逃れられないんですね。
そして、「テンプレ予想」という言葉も知りました。たとえばお弓や重吉という人間に対して、読者はみんなで軽蔑し、みんなで怒り、みんなでその破滅を期待する。それは思考停止だ、というんです。それがテンプレ予想なんです。それで、僕は……

なるほど。おまえ、それ学校そのものだ、と言いたいんじゃない?
いや、その通りだよ。学校とは「テンプレートを教えるところ」だよ。でも、それは一面で仕方がない、というか、君らの親も、社会も、そして君ら自身もそれを期待しているんじゃないかな。どう?
だって、今だって大学入試に対応できる授業してくれ、なんてしょっちゅうおれんところへ言ってくるじゃんか。こないだ授業見学に来た校長に、「先生の授業はいわば雑談で……」なんて言われちゃったよ。実は入試に対応する授業が、これなんだと自分では思ってるんだけどね。
まあいつかみんなで『リヴァイアサン』でも読んでみないか?評論読む練習になるかもよ。
(誰かが「ごめんだわ」と呟いた)





コメント