
残された家族は何を思うのか
今回はイギリスの小説家D.H.ロレンスの短編『菊の香り』。外国文学なんか全くの門外漢だけど、勝手に解釈しちまおう、というわけだ。話に流れをまた確認しておくけどね。


ブリンズレー炭鉱の夕暮れ。坑夫たちが地上に帰ってくる。
線路の脇で一人の女が鶏小屋から出て子供を呼んだ。二人で家に帰る途中男の子は咲き乱れた菊の花をむしりとり、道道花びらを撒き散らした。母は「おやめ——お花がかわいそうでしょ」。男の子はやめた。
女は菊の花を捨てるかわりにエプロンの紐にさした。家に帰る坑夫たちがいた。
汽車の機関士が彼女の家にきた。彼女の父親だった。父は自分の再婚について娘の了承を得たかったのだ。娘は「ちょっと早すぎるわ」という。父は娘ベイツ・エリザベスの夫があり金全部飲んでしまっていたことを話し、去っていった。
上の娘が帰ってきて、妻は夫を家で待った。
「あら、母さんたらー!」と女の子が大声を上げた。
「何よ?」炎にランプのほやをかぶせようとした手を止め、母親は言った。
「エプロンにお花がついてる!」女の子は、このめったにない出来事に大喜びして言った。
「びっくりするじゃないのよ!」母親はほっとしたように言った。「お家が火事になったかと思うでしょ。」
ほやをもとどおり取りつけると、芯を上げる前にちょっと待った。淡い影が、床の上を漂い流れた。
「匂いかがして!」まだ有頂天の女の子は、そばまでやってきて、母親の腰に顔を押し当てた。《……》その花を唇に押し当てつぶやいた。

「すてきな匂い!」
母親は軽く笑った。
「かあさんには匂わないわ。とうさんと結婚したときも菊の季節。あんたの生まれたときも菊が咲いていたし、とうさんがはじめて酔っぱらってかつぎ込まれたときも、とうさんはボタン穴に茶色の花をさしていたわ」
そう言って、子どもたちを見つめた。
母親(ベイツ夫人)は、子どもを寝かしつけながら、怒りに不安がまじりはじめた。
夫の母が10時15分前に訪ねてきた。息子が事故に巻き込まれて、自宅に来てくれと言われたと言う。妻はその時不意に年金の額などが頭に浮かぶ。夫の母は、息子が本当は飲んだくれなどではなく、良い人間であったなどと愚痴る。そこへ男たちが入ってくる。夫が落盤のために窒息したと告げる。老母も声を上げて泣きはじめた。
遺体は応接間に入れることにして、ろうそくを置いた。部屋の中には菊の花の冷え冷えとした死のようなにおいが漂っていた。エリザベスはしばらく立ったまま菊の花を眺めていた。そこへ遺体が運ばれてきた。その時男の一人が菊の入った花瓶を叩き落としてしまった。エリザベスは夫の姿を見ず、割れた花瓶と花を拾い集めた。
母と妻とでは感情の食い違いがあった。
義母と夫の体を拭きながらエリザベスはこれまでのことを振り返るのだった。結婚の時間がふたりの気持ちをどう変えていったかを。

では、みんなでこの小説をどう読んだか、どういうところが話の味噌なのか。いつものように自由に言ってみてごらん。ちなみに、私は初めて読んだ小説だったんだが、読後、女房の顔を見てしまったよ。こっそりね

最初は右棘さん。「うとげ」と読むが、珍しい名前だ。以前に男子と論争していたのを見たことがある。すごく論理的に発言しているのが印象的だった。にこやかなわりに鋭い目つきをする時がある

去年だったと思うんですけど、先生の雑談(ごめんなさい!)を聞いていて、人間は遺伝子の乗り物という話を聞きました。誰だっけ?ああ、ドーキンスという人でしたね。
この小説では最後のところで、夫の母親が言うじゃないですか、いい子だったって。それに「あの子はあんたの息子じゃないんだから、そこが違うの」って。息子の身体を「私にも拭かせて」とも言いましたね。一方で妻も自分の内心を繰り返して確認しようとする、それを作者は書く。
もう人間に洋の東西もない。人間を動かすのは遺伝子だって思ったんです。あまりにも遺伝子の乗り物論はバカくさいという批判があることは聞いていますが、この母の心のうちは一番に”嫉妬”じゃないでしょうか。行間を読めということがこの講座のテーマだとすると、これを読まない人はいなかったんじゃないですか。息子の死体を前にしてもしょうがなく嫉妬心が出てきていると私は思いました。
「おまえもかわいそうに!」「怖ろしさと母性愛の入り混じった忘我」ともありますが、遺体は「まっさらで。白くて」という点とは、この母の心は対比的に濁っていると感じました。

そういうふうに考えるのならば、奥さんの方も自分の遺伝子を残した子供は何よりも大切。遺伝子がどうのこうの、なんていう話はこの時代にはなかったんだろうけど、言われてみれば僕もそういう現代的な説の影響のもとで読んでたかな。遺伝子さえあれば、妻なんてもう無用!なんて感じね。僕もそうなるのかなあ。」
「なる、なる!」なんて言うやつがいる。青木がジロリと睨む。

つまりこの小説からは「死」が一人の男の終了を意味する、ということよりも、「生」の方からの捉え方を描いた物語、ということで、ある感銘を与える作品なんです
栄古が続いた。今日は珍しいやつが発言する。

それにしても、この奥さんひどくねー?
ちょっと際どい表現もあるけど、要するに、二人のあいだの深ーい溝を実感した、ということでしょ。裸で抱き合いながら孤立していたって、そう言うあたしって誰?という…。すごいね。二人は暗闇で戦ってきたんだって!
よし子、すかさず、

先生、夫婦ってそういうもんなの?

いや、ちょっと……。そうとは言えないと思うけど。でもこの小説が長く読み継がれているということから、どうなのかね。……まあ皆さんもだんだんとお分かりになるじゃろう。
さて、この物語には行間の読みを可能にするイメジャリーはあるかな

まず初めに出てくる汽車。これ意味あるんじゃないかしら。結果的に夫が命をかけたものがこういう科学的な発展に必須な石炭だった、というわけだから

簡単に言えば、イギリス近代発展の表象だった、ということだな。それを支えるために夫は命を失ったということか。確かにたとえば花屋が病気で死んだ、ということとは違うということね
右棘はさらに言った。

それにやっぱり菊でしょう。別の花なら違ってくる?

おい、大野!

もう、検索してありますよ。こういうのは俺の役なんですね。
菊の全体の花言葉としては、上機嫌、元気、そして真実、らしいです


それは皮肉っぽいね。僕、ある男が彼女へのプレゼントに菊の花を贈ったという実話を知ってるけど、考えてみればそれを笑うってのも、おかしな話だよ。なぜ、菊がいけないのよ。

でも、この小説では、母がエプロンに菊の花を指してるのを娘は大喜びしている、素敵な匂いって。私たちの想像する菊とはまた違うものなのかもしれないけど……

まあ。あんまり夫婦それぞれの孤独については深く立ち入らないようにしよう。おれも、泥沼に入り込みたくはないし。
しかし、もう一度みんなに考えてもらいたいのは最後の一文だ。
「目先の主人である生には屈服している。が、究極の主人である死からは不安と恥辱を覚えさせられた。」
そして、遺体の置かれた応接間に鍵をかけたんだね。これをどう読者は受け取るのかねえ。鍵はともかく、目先と究極の主人の仕打ち、これについてはうまく整理つかないかなあ。
ここがどうもあやふやな印象しか持てない原因のようなんだ

先生!だからこそ話をし合うのが面白いんじゃないですか。
すっきりした納得感を持って授業が終わらないのは、むしろこの講座らしいですよ。無理やり結論を出してまとめるのはかえって先生らしくないよ。
私自身は、作者はなぜエリザベスを妊娠させたのか、ということが気になって仕方がない。ですから。また考えてみるのもいいかな、と思います

そうだね。
ただし、今のよし子さんの言葉で、作者の意図が気になるような発言だったけど、そこは最初に言った通り、作者の意図が我々の読みと違っていいんだからね。あんたがこう感じてしまう、というところを探すんだからね。いいね。『作者は死ぬ』んだ。まあそうはい言っても、作者の意図への忖度は仕方がないと思うけどね。一応姿勢としては作者を殺して、我々が生きるということでどう読むかという問題は読者の権利ということを再確認して——
さて、最後のところどうかな。
一般的には、目先の主人には屈服
究極の主人には、?
この?の部分は、反抗とか闘争 とかがふさわしい。屈服に反する言葉が入るのが自然。それなのに、不安と恥辱を覚えてたじろいてしまった、とあるのがどうも腑に落ちない。ストンと胸に落ちてこない。
奥さんは思った。
このはだかの男、この他人は無惨に傷ついていたのに、あたしには何の償いもしてやれなかった。もちろん子どもたちは残されている。——だが、子どもたちは生者の世界のものだ。この死んだ男とは何の関係もない。この男とあたしとは、生命が流れ子どもたちに終わる水路だったにすぎない。私は母親だった——だが、妻であることがどれほど怖しいことか、今にしてはっきりわかる。この人も、今はもう死んでしまったが、夫であることがどんなに怖しいことか、感じていたに違いない。
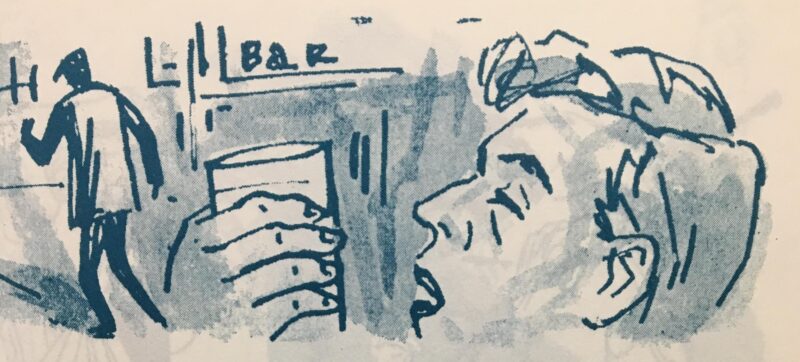
この死んだ夫に対する冷淡さ、反感はどうだろう?死んだ夫に微塵も同情を示さない。夫が妻に対してそれほどひどい仕打ちをしたとは、これ以前の文章からは想像もできない。家に帰らず、飲み屋に入り浸っていたくらいなものだ。夫婦仲は冷たい関係であってもこれほどの拒否感を持つような原因があったようには思えない。
エリザベスは、横たわる夫を見て超然としている自分を発見する。あたしは今まで何をしてきたんだろう。夫は既に過去に捨てられるべき存在だった。暗闇で戦ってきた相手でしかなかった。そんな夫は、私より先に手を引いてしまった。
二人の子どもとお腹の中の子は、生の勝者であるがしかし、このことを今まで理解していなかった。しかし勝者の自分に死がくることは不安であり、その究極の主人に自分も従わなければならないことに恥辱を感じた。そういうものとしての自分の一生を理解した、ということなんじゃないか、最後の文の意味は。
ということは、この文章の底に流れる根本的なテーマが、生と死の果てしない闘争、ということになると読み取れるんじゃないかな
岡野が突然言い出した。

ちょっといい?僕、先生には悪いけど読み違っているんじゃないかと思うんだけど。自分が考えたことうまく言えないけど…

おう!よくぞ言った。そういうのを待ってたんだ。説明してみ

まず、夫はなぜひとり炭鉱に残ったのか。これは、たぶん家には早く帰りたくなかったんだろう。もちろん酒場に長く居続けるということも同じ理由だろう。文中に夫の思いは出てこないけど、それだけに男の言い分は読者に行間から汲み取る権利がありますよね

そうそう!そんで?

夫と妻との表面には出ていない葛藤があって、それで夫が死んだ後、小説の最後には、目先の主人である生には屈服。究極の主人の死に対しては不安と恥辱。これなんです、問題は。死に「恥辱」ですよ。恥をかくんです、何に対しての恥ですか?妻は何に対して恥を感じて死ぬんですか、っていう話です。先生はそこんところどう解釈するんですか?


うーん。恥か。究極に支配者の死に対して、かなあ

なぜ、死に対して恥を感じるんですか?

うーん。夫との関係についてかなあ。夫に対してはやはりすまなかったという思いがあって、死の時は恥を感じる、ということなのかなあ

じゃあ、恥は夫との関係について感じているということですね。自分もいつかは死ぬ、その運命を強いる死に対して、夫に対する不誠実について恥を感じる。その基底音は生と死ではなく、男と女の関係、闘争ということじゃないですか?
菊の花を摘み散らかしたのは男の子です。また父の結婚話にいい顔ができなかった。エリザベスの敵は男という存在なんじゃありませんか。
夫をはじめとして、男に対する敵対心をずっと燃やしていったということは、この人の残りの人生でも不安として影響していくんじゃないでしょうか。
上手くまとまりなく、根拠もない読み方かもしれませんが、僕にはそう思えるんです。
よく、「父ごろし」とか「エディプスコンプレクス」とかいう言葉を聞きます。本来の意味とは違うんでしょうけど、そんな言葉も、僕は連想しちゃうんです。いや、この言葉の内容はよく知らないので間違っているかもしれませんが。

つまり、夫の死によって心の中にある男に対する敵愾心を知った女の物語、ということかな。そういうこととはちょっと違う?でも自分の読みをしているのがまず良いよ。
他の人は、何を読み取った?
他に発言しようとするものはいなかった。時間的にももっと読み込む余裕が欲しいところなんだ。

まあ、もう少し考えて、後で文章で自分の読みをうまく書いてみてね。
今また思い出した話なんだけど、昔旧制中学の国語の先生が、文法上の質問を受け、それにハッキリ答えられず、それから文法事項の研究に全てを捧げ大学者になったという話を聞いたよ。確か山田孝雄だったかな、助詞の分類についての疑問だっと記憶しているんだが。君たちの疑問がいつもいつも幼い問題とは限らないんだよ。何か言ってみることは大事だよ


コメント