
『西瓜喰ふ人』を読んでみよう。我慢して……。


小田原出身の作家として牧野信一、尾崎一雄、川崎長太郎と、3人がまず頭に浮かぶ。特に最近、この3人は評価が高いんじゃないかと思う。みんなは知らないかもしれないが、牧野、尾崎、川崎3人ともこの高校と縁があるんで(川崎は中退)、まず牧野信一を読んでみよう。テニスコートの裏に文学碑もあるし。そして、その裏には蜜柑畑というところだなあ、ここは。

余は32歳の理学士。これから一生をかける仕事を決めようと思っている。その余の友人が瀧という小説家であった。余はこの瀧を常に観察している。そして、瀧の小説がいつまで経ってもでき上がらないのを責める。あんなこともあったじゃないか……。どうしてできないんだ?と。余は瀧の行動を記しながら、瀧を励ましたり、呆れたりしている。滝は余に指摘された題材について、「あのときのことを話したらもう済んでしまった気がするんだ」と言い訳する。
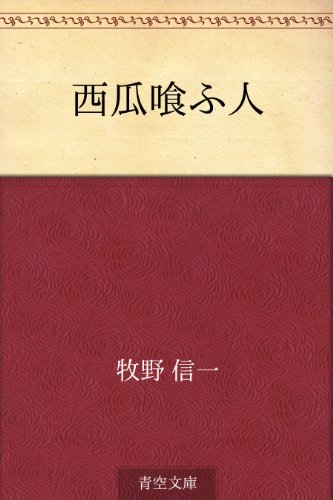
ひとつ、重要なエピソードが瀧が船酔いした件であった。舟で島に行こうとしたとき滝だけが船酔いして非常に苦しむ。胸に込み上げて船縁に行ったり胴の間に戻ったりと動く。その間他の人々も船のバランスを保つため緊張しながら動く。瀧は大迷惑をかける。こんなことも余は瀧にひとつのきっかけとするように話したりする。が、彼は仕事が忙しいということで片付ける。仕事とは凧揚げとか、見れば、何をナマケているんだと思うようなことばかり。だが余はその忙しさをどうも理解していてただの言い訳とは思っていないようである。
「僕の生活は、君のそれを眺めているだけのことで、そしてその君の生活がまた……。」と余は何となく息詰まる思いに打たれた。(それから後はBの家から見えた、瀧の家の様子である。)
瀧の家はBの家の段々畑の一つ下で、どうも瀧の書斎はまる見えのようである。そして瀧は寝る時はBの家に来て同じ部屋で寝るらしい。
瀧の部屋にはさまざまな人が来る。芸術家らしい男、ラッパの練習する母親、さらに妻(今別居している)にはダンスを教えたりする。彼はこういうことに忙しい。気まぐれやわがままで作家としての成果が出せないのではなく、逆に日々のことに圧迫されてしまい、傍にはまたとないナマケモノとみえるのだ、とBは思う。
ある晩には酒を飲んでいる。寝台にあがって最初の船酔いのように苦悶している。そしてこのあたりから船酔いの話とは違って転覆してしまった舟と客の救助などを一人芝居のようにやっている。空が白々とするころに瀧はBの方へやって来る。余は今ではなんとなく彼の言葉に対して言いようのない共鳴を感じるようになっていく。
そして最後に瀧とBについての(註)が書かれる。
彼は起き上るとBの机上にある日記を開き、その日その日にあらわれたことを原稿用紙に書き足す。
いわばこれが種明かしになる。
さらに、映画で見た、二人の男が隣りどおしで西瓜をガツガツ食べるという場面が説明されて小説は終わる。
全然わかんない。この気持ちをどう解消してもらえんの?
これが『西瓜を喰ふ人』のあらすじ(?)。さてこれをどう説明するか?

おれはこの小説、全然わかんない。何も言えない。いま、とぼけていないよ。

私もわけわかんない。正直、読むに堪えない。あえて発言することじゃないけど、むしろみんながこれをどう読み解いてくれるのかに興味があります。このモヤモヤした小説についてどういう納得感を私に与えてもらえるのか、それが可能なのか、と思っちゃってます。人任せのようで申し訳ない。

僕も我慢して全部読んだんですが、何と言ったらいいのかなあ?文字は続いていくが文章として伝達されてこない感じがしました。非常にストレスが溜まりました。

何だか、今回は評判悪いね。
ちょっとだけ文学史の話をさせて。
日本のこの頃までの小説の主流は「私小説」と呼ばれるものだったんだ。明治時代からの自然主義の流れから、建築のように話の骨格を組み立てていく小説、特に長編の大河小説よりも、むしろ研ぎ澄まされた作家本人の身辺を語り、本当の生の意味を語ろうとする「私小説」を芸術的に高いとする風潮が作家たちのギルド的な世界に広まっていた、と言われている。今でもこの傾向はないとは言えないのではないかと思う。
しかし、昭和の時代に入っていくところで、一方で政治の影響でプロレタリア文学が広まっていき、あるいは大衆の娯楽のための小説が出てくる。私小説の作家たちは段々と活躍の場を狭められていくようになっていった。
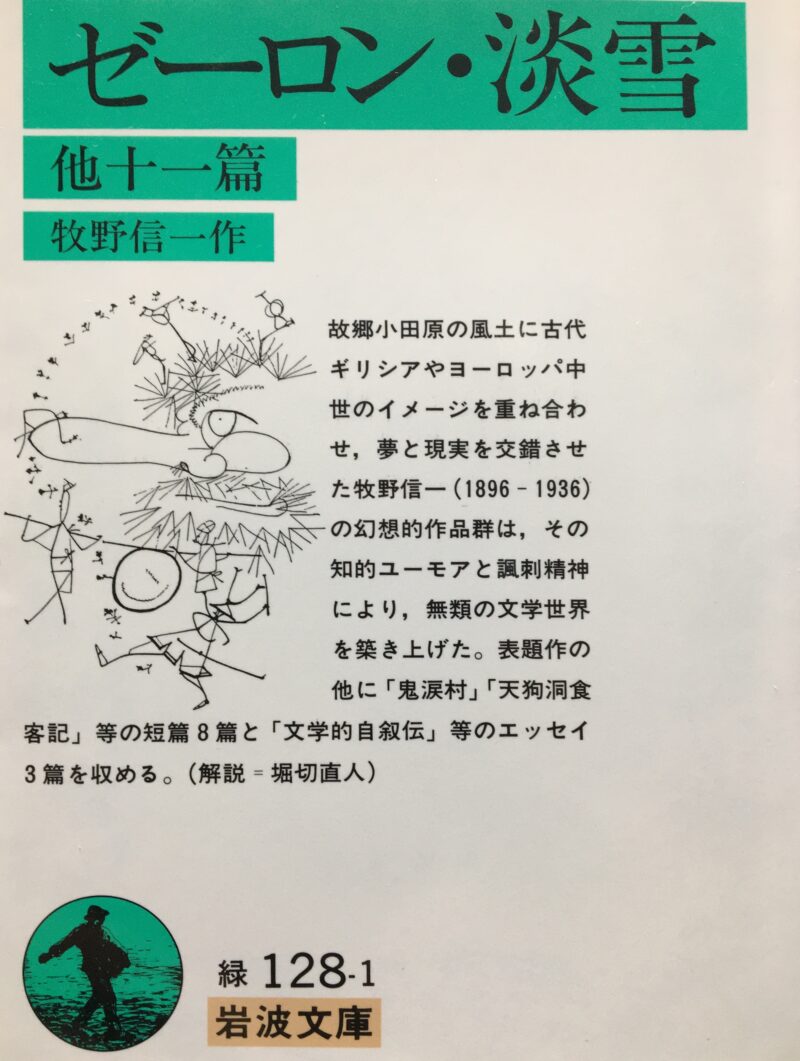
私小説の作家の中でも、方法的に行き詰まりを感ずる人が出てくるのも、ごく自然な成り行きだった。たぶん牧野信一もそういうところにあったんじゃないかと思う。『ゼーロン』という作品がある。道了と猿山なんていう地名も出てくる。ヤグラ岳なんて山も南足柄だよ。そのくせ、話の内容はギリシャの話のようになっていて、何だかよくわからない話なんだ。ギリシャとは関係ないが、この『西瓜喰ふ人』も作者独特の小説なんだろうと思う。現代作家に牧野評価が高いのも独特の雰囲気が感じられたことも理由の一つであったろう。
実は私も大学時代に初めて読んだのだけど理解できず投げ出してしまったんだ。何を言いたいのか理解できなくて。感動がなくても、せめて何か文章の了解感みたいなものを掴みたいよね。それがなかったんだが、今回は、ちょっと読み直して、みんなの意見も借りてみようというわけだ。「こんな読み方ができる」とか「この辺の表現が気になる」とか気づいたことをなるべく言ってみてくれよ。
さて、この小説だ。いっぺん読むだけでは何が何だかわからないのはよくわかる。どうも鉛筆片手に疑問をはっきりさせながら読まねばならない、という感じがする。単に、何となく好きとか、感覚的に自分と合う、なんていう読み方ではダメなような作品だ。
『西瓜喰ふ人』という題名からしてすごく変だ。なぜこの題?。それについては最後にこう書いてある。
「ついこの間余が見た夢は何か連想がある気がして考えて見ると、それは余が六七歳の頃初めて見た活動写真の記憶であった。大写しになって現れた二人の男が西瓜を喰う光景なのだ。半月型の大西瓜を両手で支えて男たちは大口をあけて貪り食った。傍を向いてペッペッと種子を吐いては、熊のように首を振りながら一心に西瓜を食うのだ。二人とも余りに夢中で、どうかすると自分の手の西瓜と隣の男のそれとを見損なってかじったりする……。」
「夢のことは一切日録には記さないことを掟にしているのだが、馬鹿に明瞭に頭に残っているのが我ながらおかしな気がした。余が日録の筆を執りはじめたのは七歳の時からだから、当時の日誌にこのことは記してあるかも知れない。思えば、当時の写真はことごとく筋や意味のない単に写真が動くということだけを示した標本的のものばかりであった。「煙草を喫している人」とか、「笛を吹く人」とか、「駆ける馬」とか、「演説をしている人」とか、「黒板に絵を描く人」とか――。」
これは、なんだ?
(註)をまず考えたい。整理してみよう。

僕も順序よく考えようとはしたんです。それでまず最後の部分へ行く前に、まとめておかなきゃならないことがあると思ったんです。
夢に「何か連想がある」って書いていますが、それは(註)があってその内容と夢が関係していている、というんでしょう。まずこの(註)というのが変ですよ。この小説の前の方にも(註)って出てきますけど、こんなもの普通の小説にはありません。少なくとも本文中には。絶対的な第三者としての作者や解説者が本文の外に示すものでしょう?これは違うんです。話の中で解説をしてくれる人が読者に話しているんです。
ざっと見たら、(註)は4ヶ所ありました。
1 この文章は瀧と同年のBという理学士が書いていて、これから自分の一種の仕事を見つけようとしている、ということ。
2 瀧とBの住居はみかんの段々畑にあって、Bの住居は多岐の住まいはその真下にあること。《(註)の筆者は段々畑を映画館のスクリーンのように眺めているようでもあると、これは僕のイメージ。》
3 瀧は自室にカーテンがつけられるまで、ということで、仕事を終えるとBの住まいに来て枕を並べて寝る。
4 瀧はBの家でBが寝ると起きだして、Bの日録を開いて原稿用紙に書き写す。これはBも承知のことだった。小説のために意識的に観察したり、思考したりするときが時間的に互い違いの場面でやっているように見える。
それから、Bは自分の実験道具が瀧の方に持ち込まれていたのを見る。いつの間に持ち出したのだろうと不審に思う。自分が彼を見張っているのに、とBは思う。その答えが(註)によって示される。Bが寝ている間に瀧は起き出して、持っていったのだと。
この整理から、何かが出てきますかね。僕としてはBが理学士であるという理由は、ここで瀧がほとんど意味のない実験の真似をBに見せていたということで、Bに対して自分がBの真似をしているということをわざわざアピールしていたんじゃないか、というところにあるんじゃないかなという仮説を持っているんです。つまりこういう状況を作り出すために、Bは理学士というものにされていたと。
ところがそれが何で?、ということはどうも思い付かない

確かに、(註)を語っている人がいることで、改めてBの存在を気にさせるね。
この(註)の部分だけがいわばこの小説の語り手のセリフです。たとえば、1のBの紹介は必要だろうか。必要だとしても、Bの発言の中で自分の専門、年齢などを示すことは簡単だし、示唆することもできるだろう。「余は自分の専門の理学についてはこのところほとんど放っておいた」とかどこかに入れれば良いことだ。というよりそれが普通だろう。なぜ、この語り手をわざわざ表に出してくるんだろうか。
ここが最も気になるところなんです。Bか、あるいは(註)の書き手は、どちらかは必要ない役目なんです。存在理由がない、と思います

確かに。語り手の信頼性、というのを聞いたことがある。小説の中で狂言回しを全面的に信じることはできないという
信用できない語り手

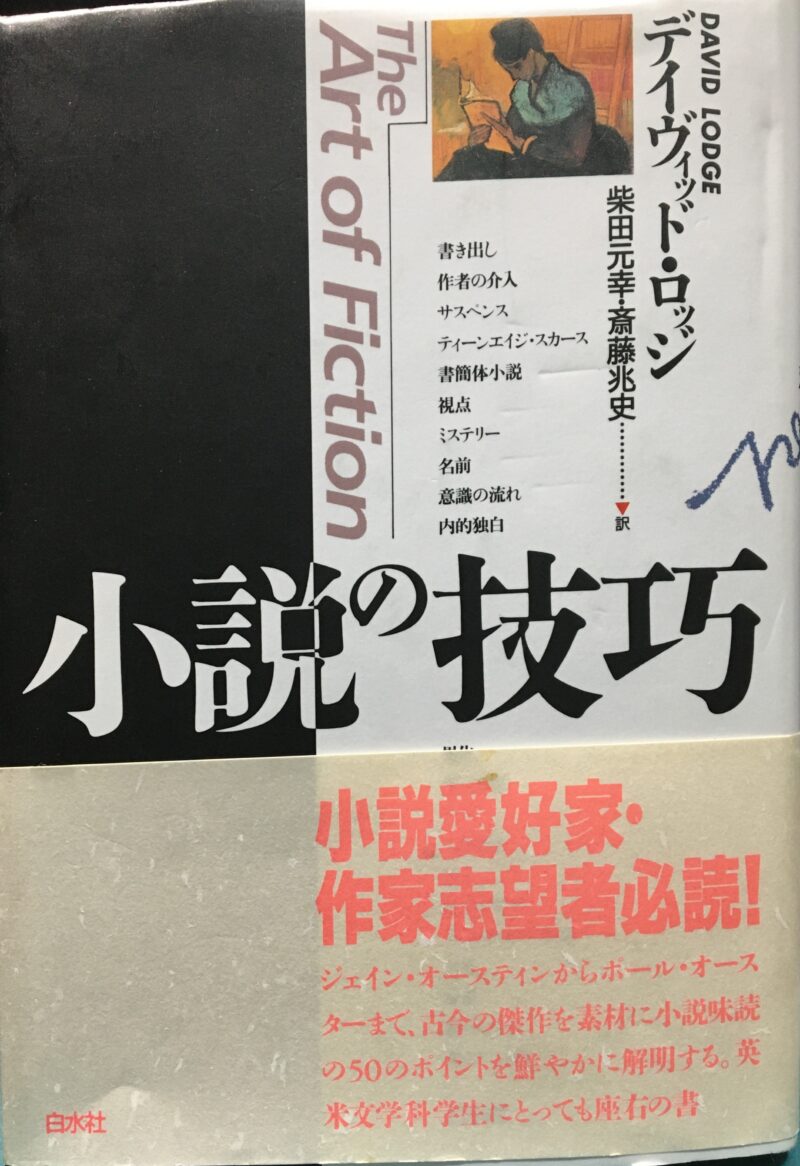
『日の名残り』って小説知ってる?私のごく少ない大好きな小説なんだが、あの中で主人公の執事が出てきて、この人が喋ることが、自己正当化に満ちているという。彼が仕えるイギリス貴族である主人がヒトラーにおもねる人物であるというのがだんだんわかってくるのだが、執事の喋る言葉では主人あくまでは完璧な人物なのである。執事の堅苦しい言葉を使わせることでその頑迷さを表している、という。(デイヴィッド・ロッジ『小説の技法』)
この『西瓜喰ふ人』でもBという人物のやっていることは、もしかしたら信用できない語り手なんじゃないか。その役を担っているんじゃないか、と思ったんだ。
それにしてもあの映画『日の名残り』もよかったなあ。まあ君たちにはあの映画は30年くらい早いけど……。

ここでも、そういう人物として、Bを創作していること?

さあどうかな。なんかそう思わせるところがある?
Bって読者にとって信用できない語り手なのかな。そう言われてみるとこのBも全部を理解している全能の語り手というわけではないね。確かにプレーヤーであって、マネージャーではないね。
しかし問題はこのBという存在が何のためにあるのかということだな

なんか、やっぱりわからんけど、瀧という人とBという人は一人の人物を分解しているのじゃない?どういう言い方したらいいのかなあ、二人の行動や思考が凸凹しているんだが、その凸凹を合わせてみるとほとんどピッタリあっているような感じ。わかる?

うん、そう。人格が裏腹なようで妙に理解しあっている。単に仲がいいというより、互いに補完しあっている双子のような感覚を持つ。しかも、Bは瀧を観察して日録に書いておくのが仕事のようだ。
つまり、ここでは登場人物の小説家とそれを見届ける役の人物を配置し、単純な行動記録や感想の羅列にはせず、その人物を批評し同情する。さっきの話に出てきたんで面白かったんですが、Bは、だから決して万能の語り手ではない。えーと、これ今気づいたんですが、Bが「彼(瀧)に対する余の無理解を余自身が勝手に掘り下げて行くような気がすることもある」って言ってますよ。まさしく信用できない語り手、ですね
身辺の打明け話を乗り越えようとしていた?

そういう工夫によって単純な小説の構造に風穴を開けようとしたのかなあ。
母親が来て、何か瀧と言い合っている。その後母の姿は消えると瀧は「卒倒したのかと思われるばかりに寝台に打ち倒れる――たしかに、あれは泣きくずれた動作だった。そのまま、ここに出かけるまでは起きあがらなかった。」と書いてある。瀧のその場面をBは覗き見ていたのだ。この母親と瀧の関係の暗示はBという観察者の存在理由になるんじゃないかな。Bの観察の描写がちょうどいいんじゃないか

言わんとするところはわかった。すごく面白くて、私もなるほどと思ったよ。話の流れにには関わらなくても、作品全体の表現上の工夫として存在させているんだね。
そういえば、気になったところがあったぞ、Bの言葉だ。
「瀧の書いた小説は幾つか読んだことはある。それは余の知っている瀧そのままのものであったから、元々芸術のことに関しては趣味も理解もない余であるが、解った。そして、創作とは称するものの余の日録と大差ないものばかりであった。主に身辺の出来事とか果てないものばかりであった。彼の口調に似たたどたどした文章で書き綴ったというふうなものだった。ただ彼は、昔から余とはいつも裏腹な変に歪んだ生活をしている。それを、そのまま投げ出しているだけで、知っている余らにとっては至極自然なものだった。」
これは大事な証言だ。Bが文学に素人であるということを示しているとも読めるけれど、つまりBから見てこれが”私小説”だ、ということなのではないかな。こういう批判を意識してこの小説が書かれていることは間違いないね。
ということで、この小説は従来の私小説の枠組みを方法的に突き破っていこうとした実験的な小説、ということかな。こんな読み方でどうだ?そんなに頓珍漢な解釈ではないと思うが。
さて、まだ問題は残っているぞ
『S/Z』を見よ。題名は何かを語る。

題名でしょう?何で『西瓜喰ふ人』よ、っていうこと。最後の(註)の後でやっと西瓜が出てきます

『S/Z』という本がある。ロラン・バルトがスタンダールの『サラジーヌ』という小説を段落よりもっと細かくバラバラに分解して、その一つ一つがどのような働きをしているかを判定していったという、病的とも言えるような本で、記憶によると彼が教えてる生徒を動員して作っていったものらしい。これを構造分析と呼んでいる。
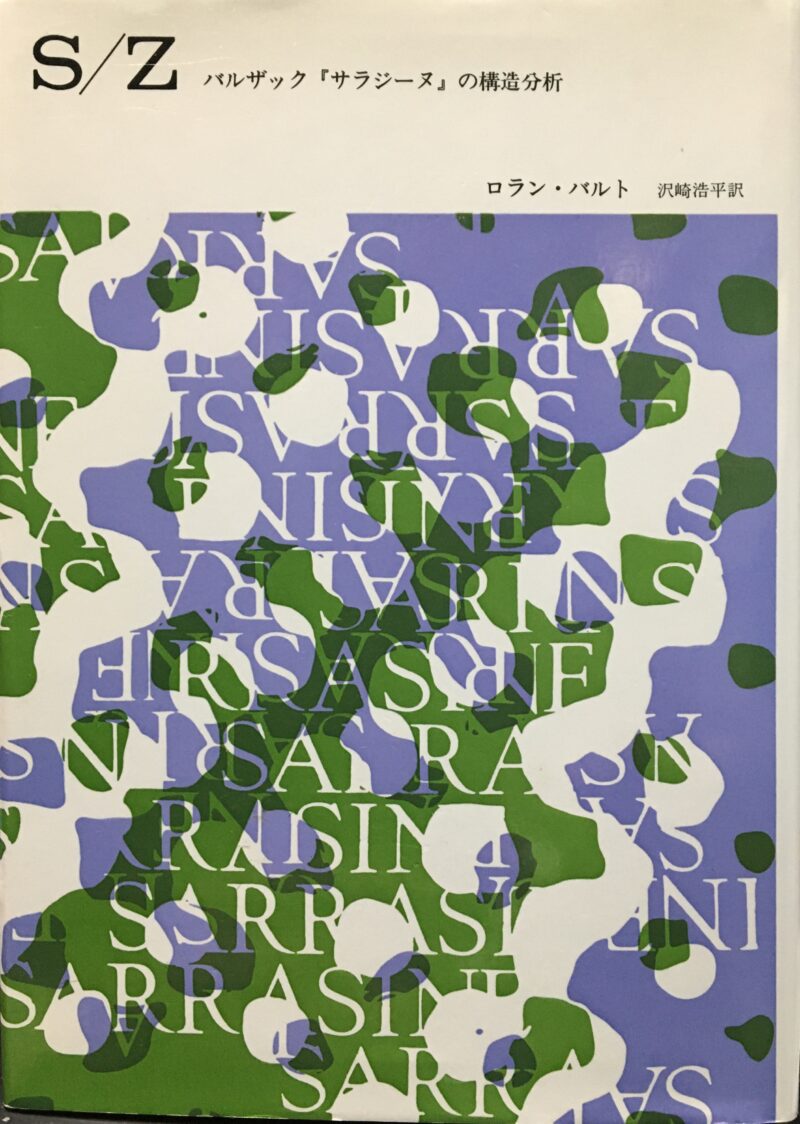
その『S/Z』で最初に書いてあることが、『サラジーヌ』という題なんだ。Sarrsineという綴りの最後の「e」がフランス語では「女性的なコノテーション」を想起させるというのである。この語が何を表すかはっきりしないまま、読者は何か女性的なもの、こと、という予感を持ったまま、その答えが示されるところまで読み進めるのだという。
実際この小説は男と女という性をテーマとして持っているのだが、そういう世界に読者は最初から引きずり込まれる。フランス語という、ほとんど全てを男か女かに振り分ける言語で書かれる小説はどうしてもある制約を受けるし、ある暗示を与えることもできる。というわけだ。
大事なことは、小説を読むということは大まかに話の筋を理解して面白かったというばかりでなく、同じ話なのにどういう仕掛け(らしいもの)を読み取ってしまうのか、を鵜の目鷹の目で探し出すという、見方によっては倒錯した読み方をするのもあるんだ、ということだ。
では『西瓜喰ふ人』はどうか。ずーっと西瓜なんかあ出てこなかったねえ

つまり『西瓜喰ふ人』という映画があるんでしょ。二人の男が西瓜をガツガツ食う映画。あまりに夢中で隣の男の西瓜か、自分の西瓜かわからなくなるくらいに。この二人が瀧とBだということじゃないでしょうか。二人、とはいっても実質には同じ登場人物なんだ、ということを題名で示していたんじゃないですかね

いや。ちょっと違うと思う。この映画について、Bは「ものを食う表情を端的に誇示する目的で写した写真なのだ」と言っている。
「思えば、当時の写真はことごとく筋や意味のない単に写真が動くということだけを示した標本的のものばかりであった。「煙草を喫している人」とか、「笛を吹く人」とか、「駆ける馬」とか、「黒板に絵を描く人」とか――。
これが終わりの部分だ。
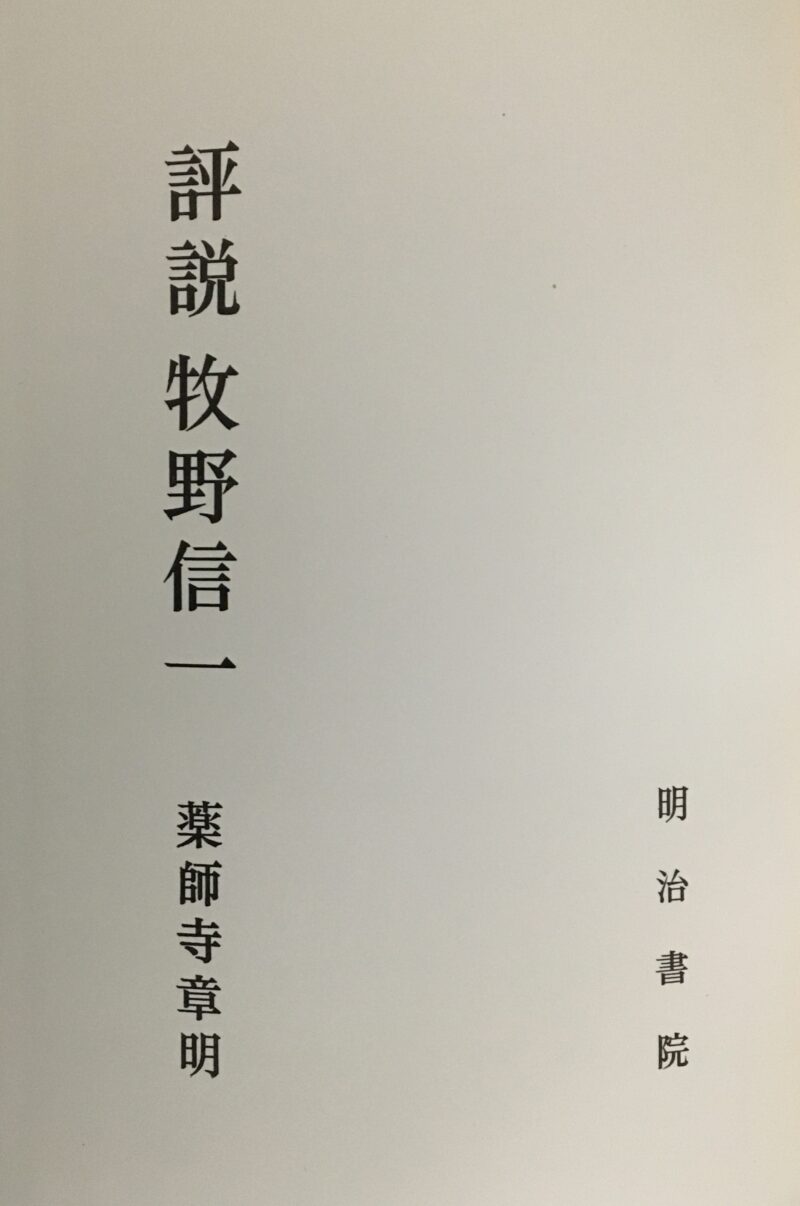
Bはこれらの映画について、内容は無いんだ、ということを言っているんだ。動く絵というものの「標本」だって言ってる。「筋や意味のない」ことの表象として『西瓜喰ふ人』を小説の題名として掲げている、ということなんですよ。先生がいまバルトの本の紹介をしたけど、この小説の読者は最後まで読んで、やっと題名の意味すること、つまり内容や意味を求めるな、ということを了解する。こういう仕掛けなんじゃないでしょうかね。
文学史のことはよく知らないけど、私小説を抜け出すひとつの道を試してみたということなのかな、と読んでみたんですけど、どうでしょうか。成功したかどうかは全然わかりません。でも、意味のないものを題名にしている小説の、意味についてあれこれ批評するのはナンセンスじゃあないかな……って、すみません。批判しているつもりはないんですが

いや、いま聞いたことはいいんじゃないか。面白いよ。感心した。みんなどう思う?
中身のない形はないよ。 でも……

私小説がどうとかはわかんないけど、話の内容や流れを問わないというのはどうでしょうか。どんなナンセンスな話でも、ナンセンスという内容は意味を持ってくるんじゃないかと思うんだけど。形式を保つためには内容がなけりゃならないような気がするし、実際理科の実験道具を弄んだり、母親との関係を覗かれたりするというエピソードは紛れもなく読者を誘導しますよ。
『西瓜』は夏や赤い色や、みずみずしさということを示してしまうし、二人の男が同じ動きをしていれば、たとえば鏡像を連想しても仕方がないです

そりゃそうだなあ

もちろん意味を持たせない文章はありえない。だけどそこに新たな(だと思うけど)実験をしていることがこの小説の価値である、ということで「主人公とそれを観察批評する人を設定し、その全体を見ている語り手を置くことで、小説の新たな形式を目指した物語」などと言っていいんじゃないかと思います

最初に言った通りどう読むかは正解がない。私の意図は自分の読みをうまく表現してみんなの了解を得ようとすることなんだから、それでいい。
さて他の人はどうまとめたかな。よく自分の考えをまとめてみることが必要だな。ではこれからゆっくり自分の『西瓜喰ふ人』論を考えてみてくれ



コメント