
思いがけず、面白い短編小説だった
今日は『藤十郎の恋』 菊池 寛 を読もう。

元禄も10年を過ぎたころ、京都では人々の話は坂田藤十郎の名人芸でもちきりだった。藤十郎はやつしの名人と呼ばれ、日本一の色男を演ずる歌舞伎役者としての不動の名声を得ていた。この藤十郎に挑んだのが江戸から来たまだ年若い中村七三郎だった。
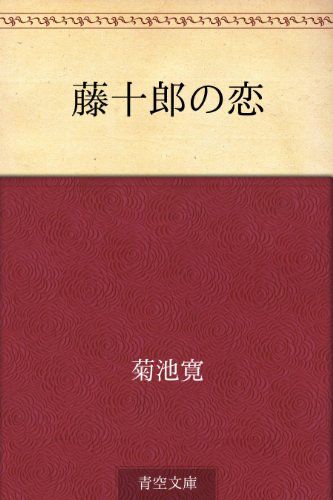
はじめは七三郎を認めながらも余裕を持っていた藤十郎だった。しかし、七三郎が初春狂言に出演してからは徐々に藤十郎の地位を脅かすような評判になってきたことである。王者としての藤十郎に対する評価もだんだんと変わってきた。舞台上の傾城買いの狂言に馴れてきた都人の評価に、、七三郎の新しい世界が波となって襲ってきた。そしてそのことを一番実感していたのが、藤十郎自身なのであった。自分が過去の自分から抜け出せないことで、藤十郎は内心もがいていた。
弥生狂言の人々の顔つなぎの宴で、藤十郎は他の役者から、次の演目で新たな藤十郎を見せてもらえるものと期待された。
あと数日のうちにどういう役を見せていけるか。新しい狂言では単なる濡事師ではなく、命がけで人妻に恋する役を演ずることになっていた。その役こそ新たな藤十郎を見せなければならないはずであった。彼は窮した。
宴の酔いざめに小部屋で横になっていた彼に、夜着を着せかけてくれた美しい女を眺めていた彼は突然その女、この屋の主人の妻お梶に対して、かつてからの恋心を打ち明ける。彼女は啜り泣いているばかり。藤十郎は20歳のころ、お梶と連舞(つれまい)を舞うた頃よりの心を打ち明けた。お梶は「毛髪がことごとく逆立つような恐ろしさと、からだじゅうの血潮がことごとくわき立つような情熱で男の近寄るのを待っていた」
しかし突然藤十郎は去っていった。覚悟を決めていたお梶を置いて、酒宴の席に入っていった。そこで彼は、今度の狂言のくふうができたと声高に笑って見せた。
藤十郎の新しい芝居は真に迫って洛中の評判すさまじく、七三郎の評判は反して蛍火のように消えていった。そして京童は、藤十郎がある茶屋の女房に偽って恋を仕掛け、そこで工夫がなったことを噂した。座は大当たりで見物が押し寄せたが、ある朝楽屋の片隅でお梶が首を吊っているのが見つかった。

あらすじを言いやすい小説だ。あらすじだけでも、この短編小説の価値がわかるような気がする。菊池寛という小説家はなかなか素晴らしいね。私は個人的に、うまいなーと思った。みんなはどう?
話としてすんなり入る 面白い

わたし、全然知らない小説家だったので、びっくりした。面白いって本当に思いました。菊池寛って聞いたことなかったので

そう?文藝春秋という出版社の創設者だよ。なかなか経営者としても力のあった人らしいよ。芥川の友人でもあったって

話として、僕も面白いと思いました。ただ、小説の解釈としてはなんか……。つまり解釈の幅が狭いというか。うまい、とか感じるその理由くらいしかあれこれ言うところがないような気もします
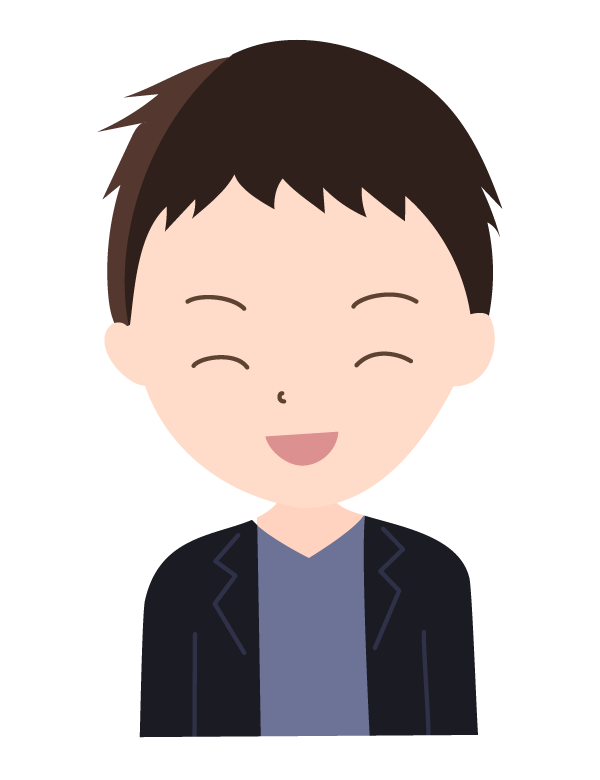
話が面白くまとまり過ぎて損している。テレビの時代劇を見ているような感じがする。

ただ、恋よりも”仕事”とか”名誉”とか別のものを選択する、というテーマでは『舞姫』とも共通する部分はある。国家への貢献とか役人としての出世とかでない分だけ、この話の方が受け入れやすいだけ、ということだよ。
こういうのを芸術至上主義というのか、芸のためなら~という歌と同じだね。
でもどうしてそれが悪いの?という問題もある。芸にしろ、国家への忠誠心にしろ恋愛より尊いという見方を批判される筋合いはないという見方だってある。人の心を弄ぶということについては、責められるべきだとは思うけど

良いとか悪いとかっていう話はそれぞれの人に任せておこう。でも、お梶を哀れだと思う気持ちは当然だよね。はっきり言って、歌舞伎にしろ何にしろそんなに大事なことなの?っていうことはあるけどね

そこはともかく、もちろん、小説を読ませる”芸”とはどういうものか、ということは考える対象とする価値はあるでしょう?

それは、うまく説明できれば素晴らしいことだよ。創作に関する”芸”とは何か?これは大変興味深いテーマだね。何か言える?

言えません。でも、菊池寛っていう人が”芸”を持っている人だということは感じます。たとえば、接続詞の選択とか倒置とかの研究が必要なんでしょうね。私にはちょっとそれは荷が重いな。あと、話の”間”ということを、話し言葉なんかでは言いますね、そういうことが書いた文章でもあるんじゃないでしょうか

なるほど、ではそれは今回は無しにしよう

時代設定がうまいと思いませんか。元禄時代なんて。強いイメージを持たされますよ。いかにも芝居に命をかける役者がでそうな時代ですもんね。
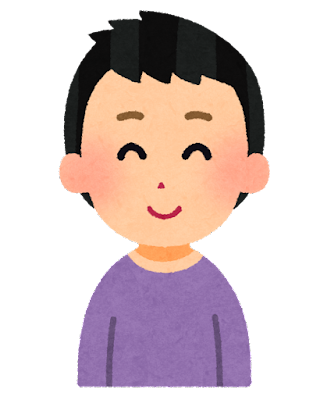
なるほど。単なる演劇の世界ではなく、江戸時代の天下泰平の爛熟期。この時の役者って、最下級に位置する人々でありながら、人が人生を賭けても納得させるような職業であり、価値を認められる職業だったんじゃないか。今の芸能界のスター以上の憧れの人々が歌舞伎役者というものなんだろう。

藤十郎の恋とはいうものの、「藤十郎は生まれながらの色好みじゃが、まだ人の女房と念ごろした覚えはござらぬわ」と言っている。色好みと言っても無条件の恋愛賛美とはなっていないんです。それくらいの役者であっても後ろ指をさされるようなことはしない。はっきりした言及はないんだけど。自分の仕事に強いプライドを持つ人物像として作られています。この人はプロフェッショナルなんです。
そこで、お梶へ言い寄っていく様子には、藤十郎のすごみみたいなものが想像される。
ある面からすれば、むしろ普通の遊び人より酷い男だよ
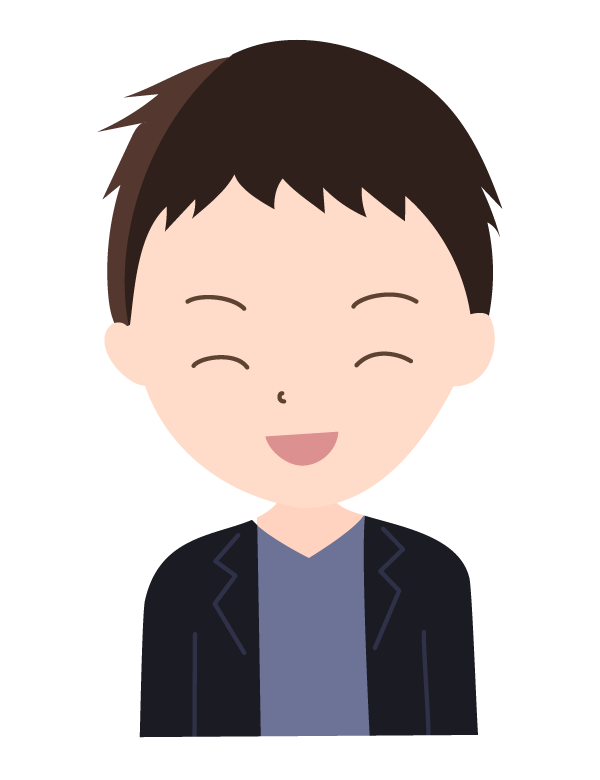
それが七三郎との競争意識ということも絡んでくる。負けるくらいなら何だってやる、という男なら、これは芸術至上主義ではないね。
去年、授業で先生がやたらフェティシズムってことを言ってたけど、(え?あんまり言うな?いいじゃん。真面目な話なんだから)あの話の、文化はフェティシズムということと大いに関係する。藤十郎が、役を作るということに最大の価値を置くというのもフェティシズムと言っていいでしょ。
演劇というものを社会的に認めるという余裕が時代にあったということもすごいことだ、と思います。そう考えると、藤十郎の価値観は称賛されるべきものだよ。”こだわる”ことができる、というのは素晴らしいことだ
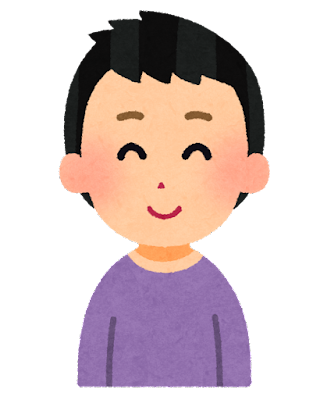
そりゃそうだ。歴史上の話でも、隣国を侵略する意欲ばかりの国に比べたら、歌舞伎に命をかけることが許される社会がどれだけ健全か、ということだ。
前回の『肉親再会』でいえば、芸術選択派の妹が、ここでは成功しちゃう物語なんだから、これこそ教科書に載るべき作品では?でもそのぶん通俗的と見られちゃうのはなぜなんだろう
芸術至上主義がどう読者に提出されるのか、が問題

藤十郎に対する良い、悪いという観点以外に、何かこの作品の新しい読み方がないかな。つまり、「藤十郎という歌舞伎役者が、新しい狂言の役柄のために、若い頃からの知り合いの人妻を騙し、自分に夢中になる過程を観察し、新たな役者としての境地を作り出したという物語」というような解釈ではない考え方はないか?藤十郎に対する良い悪いという評価とは別のものは?

芸術こそ絶対の価値あるもの、という考え方にはいろいろ意見があると思うけど、これも古文では『宇治拾遺物語』の「絵仏師良秀」という説話を読みました。その話が芥川の『地獄変』になった、ということも知りました。芥川と菊池寛の二人が、芸術の価値をどう描いているか、を考えてみると面白いかも。同じように自分のこだわるものに対する執着を描いているらしいけど。これが、つまりフェティシズムというものなんでしょうか?主人公二人、良秀と藤十郎は同じですね

それについて言えば、菊池寛のうまさは私は上方歌舞伎という設定にもあると思います。藤十郎とお梶の二人きりの場面で、お梶が夜着を藤十郎に”ふうわり”と着せる。

この感触を肌で感じて、藤十郎は”危うく爆発しようと”なる。この柔らかさは江戸歌舞伎には似合わないですよ。江戸っ子にはこういうのはわからないんじゃないかしら。芥川の小説にこういう雰囲気を感じさせるものがありますか?

どうかなあ。芥川という人も江戸っ子中の江戸っ子みたいな生まれだし、和事、荒事という言葉もあるけど、しっとりとしたこの描写、雰囲気は独特だね。でも、ひとまず作者を離れて、どんな物語と言えるのか、はどう?

「芸術至上主義の元禄期歌舞伎役者の厳しい心情を、上方の柔らかい雰囲気の中で行われた行動によって特徴的に描いた物語」。ちょっとくどすぎるかな。でも、芸術にこだわる心情は他と同じで、特別に秀でているとは言えないと思って

この小説の価値は、芸術にこだわる人の凄さではない、ということですね。なるほどね

映画でいえば、ハリウッド映画に対する、フランス映画みたいなことが物語になってる、ということかな。江戸歌舞伎って、SFXっていう感じで捉えられていたのかなあ。確かにそういうニュアンスをを解釈の文に入れたいね
藤十郎は自分を観察していたのでは?
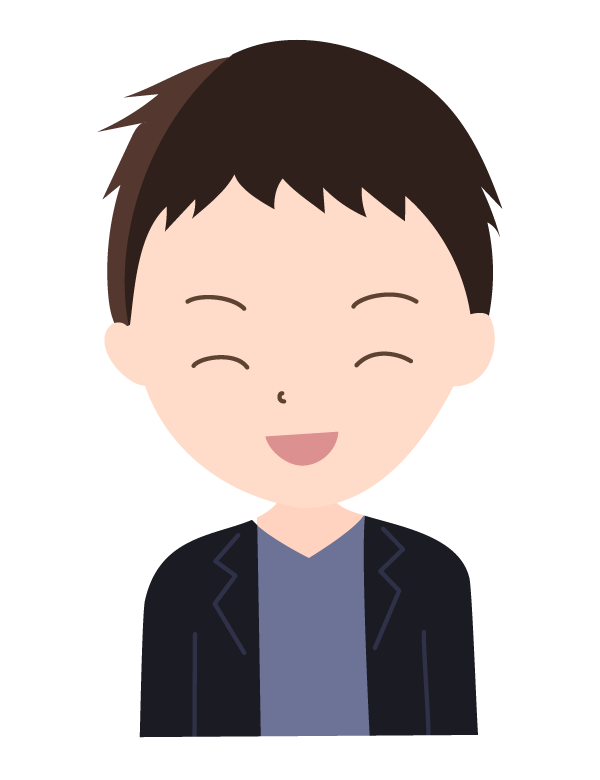
実はもう一つ言いたい。
藤十郎はお梶が自分を受け入れていく様子を観察する。そこを
こういいながら、藤十郎は座にもえ堪えぬような、巧みな身もだえをして見せたが、そうした恋を語りながらも、彼の二つのひとみだけは、相変わらず爛々たる冷たい光を放って、女の息づかいからようすまでを恐ろしきまでに見つめている。
と書いている。
藤十郎は、でも男の役をするんですね。女の様子を観察しても仕方ないんです。だからここは女を口説く男である自分を第三者として見ているのかもしれない。女の仕草を見て、そうさせている自分を観察している、ということじゃないでしょうか。
残念ながら、本文には、藤十郎が自分の言葉、仕草などを自分自身で研究ながら、お梶に言いよる、ということは書いていないので仕方がないが、女の様子をただ観察するということでは話が破綻しているような気がします。自分を冷静に観察しながら、口説く自分が女を騙す様子を工夫する、ということが考えられるのなら、この小説はより素晴らしいものになったと思います

女を騙し、口説いている自分を、少し上の方から観察している自分かよ。そういう情景を想像するのは面白いけど、ますます恐ろしい男だな、山城屋!



コメント