
病に苦しむ異国の人
あまり詳しくはわからないが、松永延造という、大正~昭和期の小説家の作品。横浜の人だそうだ。私、今回初めて読んだ作家だった。作者自身、病気で苦しんだ人で、この小説も病院を舞台としている。ラ氏とはラオチャンドというインド人の商人。たぶん伝染病で、横浜の病院にいる。そのため彼は経済的にも苦しい立場に追い込まれている。

大正×年の秋。私は副院長の助手としてB病院で働いていた。私の友人のラ氏は私が頼んで入院させてもらっていた。ラ氏はインドの商人で、濃い眉毛に密接した奥深い眼が懶げであった。病気で急激な痩せ方をしており、私の紹介で格安な病室に入院してきたのである。
その晩、泥水に満ちた深い谷間、というようなところにある病室に入ると、彼はベッドの下で、吐いていた。四つんばいの身体で血に染まった門歯、苦痛のために濡れたまつ毛で。彼は異国で一人病と戦っていた。

翌朝、ラ氏の病室へ入っていくと、彼は私に「何か話して」と懇願した。それは心中の寂寥を暗示させることだった。
私は彼に言う。病んでいることは不幸だが、健康が幸せだとばかりとは言えない。一人の工夫が生活苦で発作的に気を取り乱し、自ら指を断ち切ってしまった。今治療を受けているその工夫の話をして、私はただあなた一人が苦しんでいるのではない、不幸もあまた集まれば何かしら強力なものになると言った。ラ氏はそれを聞いて俄に声を隠して泣くのだった。
ラ氏は風呂敷の中に、一枚の絵画(インドの神の絵)と横笛とを持っていた。彼は笛で巧みにインドの古調をひびき出すことができた。
その後ラ氏は良い諦めのために鎮められて気持ちも落ち着いてきた。が、考えが冷たい理性に支配されていったようだった。ある夜彼は病院の物干し台へ、笛を持って一人で昇っていった。10分ほど経ってインド人の貧しそうな女がそこへやってきた。私は彼女を避けて目だけ台の上に出して二人を見ていた。
女はしきりに愛を訴えていた。男はそれを疑っていた。すると男は、横笛を取り出してほんの一節を吹き鳴らした。女は喜んだが、男はすぐ笛を女に突きつけ、吹いてみろと英語で言った。女は驚いて身を引いた。
ラ氏は私を招いて「魔女を追い払った」と言った。「あの女は昨晩もきました。そして誰もいない所で会いたいと要求したのです。女は私の病が治りしだい結婚してくれと嘆願するのです。私はそれを聞き入れなかった。女は20円ばかり至急借りたいため結婚の話を出してきたのを私ははっきり分かっていたからです。」と彼女を追い払うために笛を吹くよう言ったことを説明した。しかしラ氏は唯一の女友達を失ってしまい、なお強い寂しさを感じているらしかった。
一週間ほどのち、某教会の日曜学校を監理している青年が彼を訪れた。しばらくの会話ののちラ氏は笛を取り出し古調を一節吹いた。それが終わるとすぐ青年の前へ突き出して「プレイ、プレイ」と重い音調で要求した。青年は拒んだが、ラ氏が絶望的な表情をすると、青年は直感的にラ氏の心を理解してその笛を取り上げた。笛の口を自分の唇へと接近させようとする時、ラ氏は「危ない!」と言って、笛を取り上げ幾度も深く頷いたのだった。

院長はラ氏のために彼を施療部へ移し、彼は死と向かい合って日々を過ごすことになった。ある時は口から血を吐きながらわざと身体の安静を破って、はげしく起き上がり、声を立てて天へ祈りを上げはじめた。
月の夜、やっとの思いで物干し台へ昇りしばらく私と話をした。彼は自分の叔父の話をした。叔父は月の欠けているのは、半分失ったからではない。何ものも失ってはいないのだ。自分が死んでも何も変わることはない、と教えてくれたそうだ。さらに彼はこう呟いた。
「私はどんな場合でも、ごく自然に幸福を自分のものとした例を知らない。では、どうして私は幸福をかち得たか?いつも不幸でもって、幸福を買ったのである。たとえば、私は幼い時から、日本へ渡ってきたいと憧れた。しかし、その願いが果たされたのは、横浜で病にかかった叔父を看護する目的からであった。
また、私は君と大変親密にしてもらって嬉しいが、そうなるためには、私の病気が色々と機会を造ったのではないか。」と。
ラオチャンド氏の死は意外に早くきた。私は病院の用事のため旅行に出ていたので臨終には立ち会えなかったが、私の机の引き出しには、ある船の乗組員で彼の知り合いのインド人からの手紙があった。私や病院からの援助に対する礼と、同情への感謝が書いてあった。
私は思う。彼の言った幸福について、どこに彼の死をもって買った幸福が発見されるのだろうか。

あまり読むことができない小説なので、ちょっと詳しめにあらすじを述べたが、どうだったかな。例の如く自由に発言してほしい。

若いインド人が病苦の中で死んでいく話ですが。苦しみながらも穏やかな諦念をもっていった、というところがみそなんですかね。この時代では肺病は死の可能性が高く、そんな時どうしても「なぜ、こんなことになったのか?」とか、「こんなことになった運命を呪いたい」という感情が、病人に起こるのは当然だと思います。
そんな苦しみの時に、不幸せでもそれが集まれば何かの力になるという話だの、弱みにつけ込んで財産を奪おうとする女だの、が出現すれば、誰でも精神的にも生活面でも自分を守ろうとするでしょう。僕はこういう罪なき人に降りかかる過酷な運命と、それに耐えながら最期を迎えた異国人を描いたもの、という受け取り方をしているんです。どうでしょうか

そうですね。残酷な現実、ということですね。ただ、日本の人々も、語り手を含めてラ氏に対して親切に接していると言えるんじゃないでしょうか。少なくとも非難されるような人は一人もいない。周囲の人々のおかげで多少なりとも彼の心は落ち着きを取り戻したと言っていいと思います。それが不幸によって幸福を買う、という表現で出ています。叔父さんに言われた言葉ですが、それを彼は実感することができたんでしょう。語り手は最後まで理解できなかったし、読者も理解することはないでしょうけど

僕はちょっと今までの話とは違う感想を持っています。
誰も言わないんだけど、このラ氏の行動についてはみんなはどう思っているのかなあ。まず、”私”の紹介で入院してから、彼は感謝のために握手をする。その時の表現が「彼は感謝の意を表すため、言葉を口走るよりも先に、たいそう慌てて、私へ握手したが、その掌は一種不快な温かさで、不用意な私をいたく驚かした」とあります。すでにここでこの小説のテーマらしきものは明らかに読者に届きますね。咄嗟のことで仕方がないのかもしれないが、伝染病感染者への忌避感、差別の問題かもしれません。これは今日の問題ですよ。
ところが、僕が感じたのはそういうことだけじゃない。
むしろこのラ氏が、素晴らしい音楽を奏でるはずの笛を、その感染者への忌避感を試す装置として使った、ということです。これは気にならなかったですか。
感染者への思いやりのない忌避意識は当然非難されるべきだと思うけど、彼のこの行動(女に笛を吹かせようとする)は、はっきり言って僕は醜いと思う。ラ氏にとっては当然の、理由ある行為かもしれないけど、自分を守るためにやむを得ないように見えて、「魔女を追い払った」と言った彼は、その時悪魔に支配されていたのかもしれない。結婚と、借金を求める女を撃退したとき、彼はある面で憂いを忘れるような爽快さを感じたんじゃないかと思います。だから後でもう一度その方法を試す。悪魔の誘いですかね。
……と、なんだか大げさに演説してしまいましたが、ここがこの小説のキモのように思ったんです

僕もそこは同じような読みです。
ここで彼は女を撃退した。笛を使って。しかし、それで彼の気持ちはおさまったのか。「しかし、そのような愛情の行き違いから、唯一の女友達をさえ失ってしまったラ氏は、時とすると、満足な心の中に、なお険しい寂しさを感ずることもあるらしかった」と書いてあります。
そこで出てくるのが某教会の日曜学校の青年との出会いですね。この時ラ氏は女との会話の時と同じように、自分の使った笛を青年に渡し「プレイ、プレイ」と言った。青年は結局決心し、笛を唇に持っていった。その時ラ氏は笛を彼から取り上げた。という話です。いま悪魔の誘いという言葉がありましたが、やっぱり、前回の自分の気持ちを恢復させた成功を実感してたからですよね。
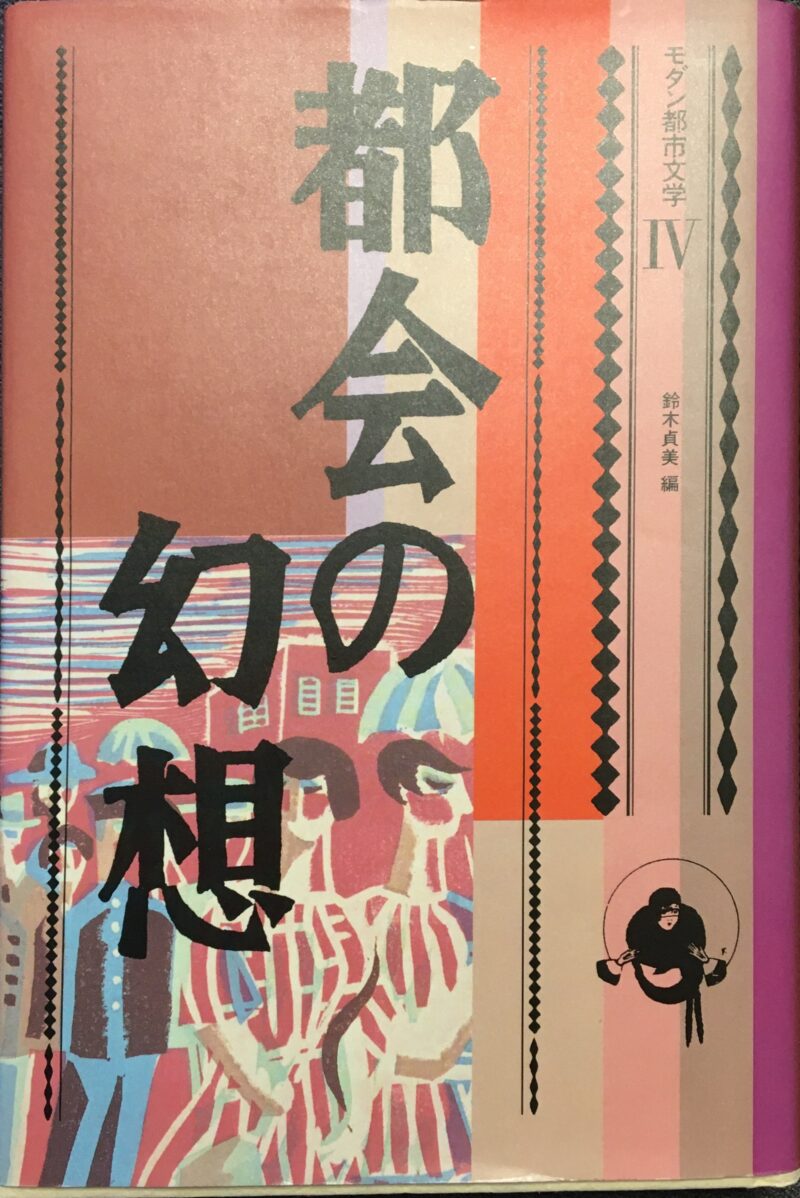
もし、この青年が感染が嫌で笛を拒否していたら、ラ氏はどういう心情で旅立ったでしょうか。また笛を取り上げるのが遅れて、青年が感染していたら、これもどんな最期を迎えたでしょうか。読者の想像は、怒り、苦しみ、絶望、悔恨(こんなもんしか言葉を知らないですけど)の絶命しかなかったろうと思います。この小説ではそのところは何もないですけど、語り手がいなくても、そんな最期の場面を想像しないのじゃあないかなと思います。つまり、人間を信じられるという境地を取り戻すことができて、その境地での死を想像します。
つまりね、異国の地で、死に臨む病気の中、一度は悪によって貶められた自分の心を、同じく穏やかな境地に立ち戻すことができた男の物語、というように記述できるんじゃないか、ということです。
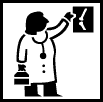
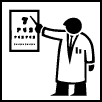
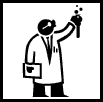

そう、僕は……一度死に至る病の迷いの中で人間不信になった男が、誠意を試そうとした対象の青年によって浄化され、穏やかな心を取り戻した物語、と思ってたんですけどね。確かに、ラ氏の心情が一度は恨みや悪意に引っ張られていく。それを本人は自覚できていなかった。そういうことがやはり必要ですね。
そう考えると、うまくいっていた状況から一度は失敗したり、失ったりしたものを、低迷を経験した後で取り戻し成功に至る。これは物語の文法通りです。この場合、その最終結果が、不幸という代償によって幸福は買うことができる、という考えへの到達、ということですかね。あくまでラ氏自身の心の中の問題で、ということですね。一度は他人の心の中の良心に疑心暗鬼となりながら、最後には良心を信じることができたという物語なんですね。悪魔に売ろうとした心を取り戻して旅立つことができた物語、ということですね。

まあ全体の流れとして頷けるな。
私が付け加えたいことは、この人を悪にも、善にも導くものが、笛だったということだよ。笛は日本の竹でできていて、インドの古い調べを奏でていた。笛が二つの国を結んでいたということだ。いかにもこの小説がある調和を得て終わり、悲劇的なものになるはずはない、と思わないか。
また、変な連想を言いたくなっちゃって。

ロシアの作家トルストイの『イワン・イリイチの死』という小説を読んだことある人いないか?それを若い頃読んで、言いようのない妙な気持ちになったことがあった。イワン・イリイチというロシアの裁判官が不治の病を得て死にいたる日々を描いたものだが、覚えているのは死の時に彼は自分を苦しめていた全てのものが自分から出ていくのを感じた。「死は終わった。もはや死はない」と言って(思って?)彼は死ぬ。
トルストイが何を言いたかったかは、私にはわからない。ただ私は単純にそうならいいな、と思っただけだった。そこまでのイワンの苦しみをトルストイはけっこうひどいものに書いていたはずだ。でも最後は綺麗さっぱりしてしまう。その結末だけ覚えていて、いま思い出した。
そういう死への歩みを信じているわけではないが、今回の小説と同じく、物語は同じ方向を示しているなあと私は思ったわけだ。



コメント