
有名な小説だが、小僧が神様を感じ取ってしまった話なのか、それとも神様と勘違いされた男の話なのか
仙吉は神田の秤屋の店に奉公している。秋のある日古参の番頭と若い番頭が話をしている。「そろそろお前の好きな鮪の脂身が食べられる頃だネ」と鮨屋の話をしていた。与兵衛という名の店の息子が出した、新しい店のことだった。仙吉は知らない店のことを、「どういう具合にうまいのだろう」とその鮨のうまさを想像しながら聞いていた。

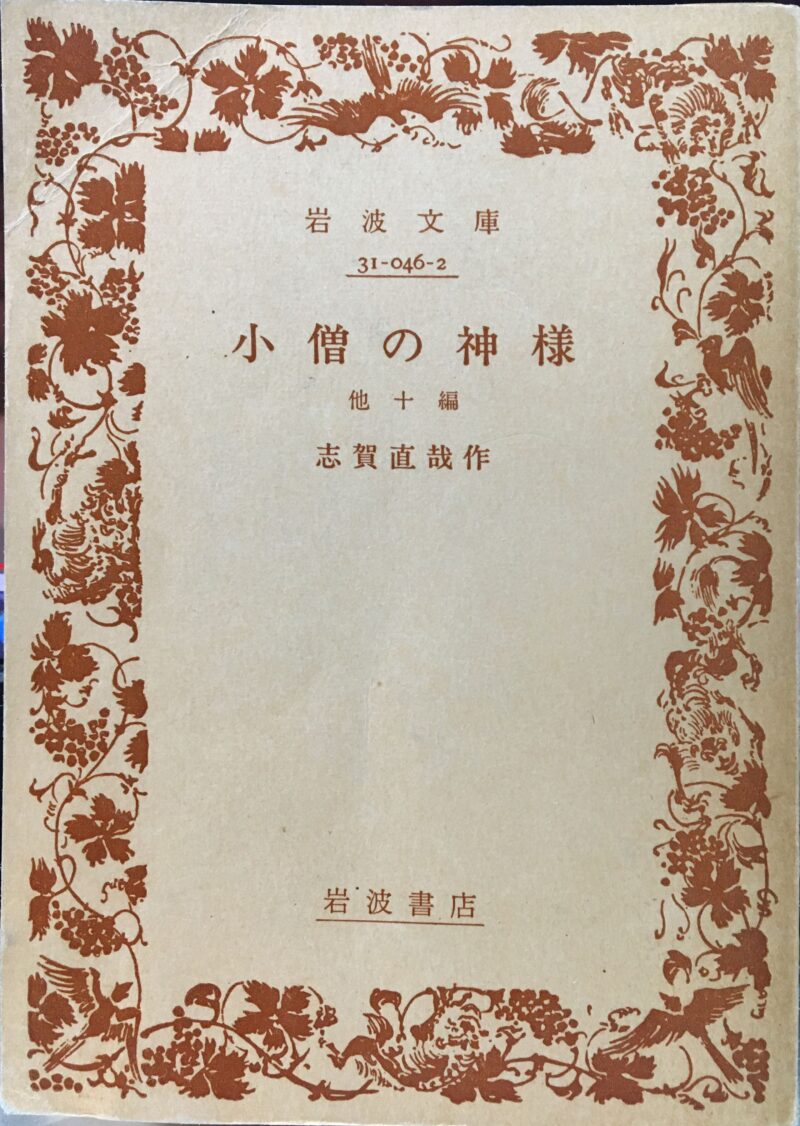
それから二、三日して仙吉は京橋まで使いにでた。電車を梶谷橋で降りると、鮨屋の前を通った。彼は「一つでもいいから食いたいものだ」と考えた。片道は歩いて帰ることをよくしていたので、帰りには四銭ふところにあった。その鮨屋の反対側の屋台を見てノソノソと歩いて行った。
貴族院議員のAは、同じ議員のBから鮨の通(つう)というのは、握るそばから手づかみで食うものだと聞いていた。

ある日Aは京橋の立ち食い鮨屋の屋台に行ってみた。
その時不意に横合いからAを押し退けるように小僧が割り込んできて、「のり巻きはありませんか」と尋ねてきた。鮨屋はジロジロ見て、できないと言った。小僧は思い切って厚い欅板の上にのっていた鮪の鮨の一つをつまんだ。こんなことは初めてじゃないように。
ところがなぜか勢いよく延ばした手を引いてしまって、妙に躊躇した様子を見せた。主人が「一つ六銭だよ」と言った。小僧は一つを落とすように黙って鮨を、また台の上に置いた。
「一度持ったのを置いちゃあ、しょうがねえな」と言って主人は自分の手元へかえした。小僧はちょっと動けなくなったが、すぐある勇気を起こし暖簾の外へ出ていった。主人は「当今は鮨も上がりましたからね。小僧さんにはなかなか食べきれませんよ」と言って、一つ握り終わると、空いた手で今小僧の手をつけた鮨を器用に自分の口へ投げ込むように食ってしまった。
後にAは見たことをBに話した。
「なんだかかわいそうだった。どうにかしてやりたきがしたよ」
「ごちそうしてやればいいのに」
「そういう勇気はちょっと出せない。すぐいっしょに出て他所でごちそうするならやれるかもしれない」
後日Aは子供のために体重計を買おうとして、偶然神田の仙吉のいる店に来た。Aはそこで仙吉を認めた。そこで買った秤を持たせて車宿の車に積ませた。仙吉には「お前もご苦労。お前には何かごちそうしてあげたいから、その辺までいっしょにおいで」と笑いながら告げた。小さな鮨屋に行って仙吉だけで三人前食べさせてもらった。そしてAは先に金だけ払って逃げるように帰っていった。
おかみさんは「粋な人なんだ」と言った。

しかしAは後に変に寂しい気を感じた。人を喜ばすことは悪いことではない。自分は当然ある喜びを感じていいわけだ。ところがどうだろう。この変に寂しい、嫌な気持ちは。なぜだろう、何からくるのだろう、と。
小僧は不思議でたまらなかった。自分のここまで見通したあの男を彼は神様かもしれないと考えた。Aは、おれのような気の小さい人間はそんなことするもんじゃない、と思った。
まだ残りの代金の分があるとおかみさんに言われていたが、仙吉はその鮨屋には行かなかった。
最後に、作者が作中に姿をあらわす。
作者は、この後仙吉がAの伝票に書かれていた住所を教えてもらって行ってみると、そこには小さな稲荷の祠があった、としようと思ったが、それは小僧に残酷な気がしてやめた。

さてこの小説は教科書で読んだという人もいるんじゃないかな。そういう人は中学校での読みを思い出して、どういう物語なのかまとめて言ってごらん。


お寿司を食べたかったけど経済的に食べられないかわいそうな商家の奉公人が、思いがけず客にごちそうしてもらった。
その人のことを自分の神様ではないかと思った、というちょっとほんわかした、いい話。そんな印象です。中学校の授業でもそういう方向でまとめられた記憶があります。

それになぜか若い貴族が寂しいという感情を持った、というところがよくわからなかった、ということを覚えてる。人にちょっとした親切をしてやった時のくすぐったい感情ですかね。
それとどうにもならない経済的格差をもっと問題視するべきだとも。いい話、というふうな読み方には僕は反対。現実に小僧が受けた勘違いが、どういう問題の上に成り立っているのか、下部構造を無視しちゃあいけない。

僕は小説として、わかりやすいと同時に、子供っぽい話のように感じた。それは今もそうです。
最後はほろ苦い感じでね。あんまり社会正義と関連した読み方は、賛成できないなあ。

今回の講座では新しい読み方ができないか、ということだったけど、『小僧の神様』に新しい光など当てられるのか、子供むけのお話っていう感覚だと言われたけど……。それ以外にも、別の読み方はないかな。もちろん子供らしい勘違いの物語ということを否定するものではないけど。

小僧の神様は、小僧にとっての神様なんだから、僕たちの視線はまずAという人物に対して向かっていかなければならないと思うよ。貴族院議員として設定されていること。たとえばこれも例何かと対比してみる手法で考えてみると、ただ単なる大金持ちということでも、別に構わないわけだろ。なぜ貴族院議員なのかということよ。

鮨という食べ物もそれに合わせて考えていくことができる。別の食べ物だったらどうなのか。Aは握ったそばから食べるという鮨の通の食べ方を知らなかった。鮨屋に行ったこともなかったんじゃないかな。

そういう階級だったということは明らかだね。下々のことは何も知らない階級だった。単なる経済的な富裕さなんじゃなくて、爵位を持っているような階級だったんだろう。小僧は鮨でさえも食べたことがない階級だ。

じゃあなぜそれほどの小僧との格差を、話の設定で広げなければならなかったのか、ということは。

僕は、世界の違い、ということをきわ立たせないといけなかったからだと思う。作者から離れた言葉を使うと、格差が広いほど、その二人の世界の違いを納得できるからだ。

つまり、夢のようなおとぎ話のようで、実はAの心情こそが小説のキモだ、ということね。

ええ。二人は完全な別世界の住人でなければならない。世界が違うからこそAは仙吉にごちそうしてやることにいろいろと葛藤を持つ。その後にも後悔らしい感情を持つんです。金持ちのおじさんが少年に奢ってやる、ということとは違うんです。彼の複雑な心情は違う世界の住人に対する微妙な感情なんです。


なるほど、鮨という食べ物について、Aも仙吉もよくわかっていない。しかし、それはベクトルが全く反対方向だ。Aはたぶん庶民の食べ物としての鮨であって、もちろん憧れの食べ物ではない。
むしろ”通”というものについても、下に向かっている知識をイメージとして持つものだったろう。仙吉にすれば鮨は憧れだ。自分の将来を考えればあと何年、何十年先に出世した時に口に入れることのできるものだ。

二人の世界の隔たりはわかった。でも、なぜAは小僧にどうにか食べさせたいと思うんだろうか。そう思うのに「冷や汗」という言葉も出てきているよ。最後の寂しい感じも不思議だ。
それはなんだと思う?

うーん、どう言ったらいいのかと思うけど……。一つには自分に「偽善的な匂い」みたいなものを感じてしまったということかな。今の話に即していうなら、「自分は別の世界への歩み寄りをしたい。しかしその自分の心に自信が持てない、という迷い」という感じでしょうか。

それ、別世界への欲望とかいうとかっこいいな。そういえば、「秤」というものもイメジャリーとして効いてるね。だって一方は生まれた子供の体重を測るもの。子供は体重を管理されて大事に育てられている。一方で仙吉なんかは自分の体重を測ってもらった体験なんてなかったかもしれない。対比的だよね。奉公人としては重たい商品で、お客のために持っていくのがたいへんだ。歳幼くしてそういう店に親から送り出されて住み込みで働く世界だ。

そうだな。落語で、『藪入り』っていうのがある。あんな感じだろうなあ。みんな知らないか?まあいつか聞かせてやろう。
また、ちょっと思い出すんだけど、いま「秤」っていうものから連想をした。こういうのって志賀直哉はうまいんだよ。『母の死と新しい母』という短編では、母の死後新しい母が来て、その母にハンカチを渡す場面がある。初めて新しい母と二人だけで口をきいた後の私の行動を「私は縁側を片足で二度ずつ跳ぶ駆け方をして書生部屋に来た。」とある。スキップだね。実母の死を悲しみながらもちょっと恥ずかしいような、うれしいような、子供の気持ちをよくあらわしている。それだけじゃなくて、この家庭がずいぶん広い家に住んでいることもわかるよね。
だから、秤を売る商店に仙吉が奉公しているということは、意味を持っているだろうね。
それから、最後のお稲荷さんの部分は、必要だったんだろうか。これも考えてみなければならないだろうね。文章を削ぎ落とすのが志賀直哉だから、何かあるのかもしれない。

先生、一つ質問していいですか。
先週トーマス・マンの小説を取り上げました。今週は志賀直哉です。なぜ、この二つの小説を続けて取り上げたんですか。

いや、小説で何を取り上げていこうかということは、あまり意図していないんだけど。なんでそういうことを訊くの?
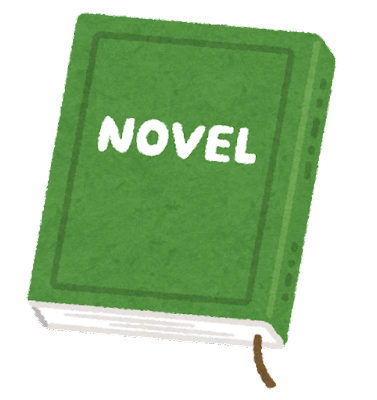

二つの小説に同じ構造があるんじゃないかと、ふと思いついたんで。

どんなとこ?

二つの隔絶した世界から一方の世界に手を差し伸べたいという欲望を持つものが、その反対の世界から弄ばれたり、自分の欲望の正当性に自信が持てなかったりして結局失敗する。そういう構造です。全然違っているように見えて、実はそれぞれの人物の関係性は似ているのではないかと思ったんです。

なるほど。面白いし、まさしく詩学的な読み取りなのかも。ただマンの小説のフリイドマンとゲルタ夫人、志賀直哉の小説の仙吉とA。この人々の、自分の世界以外の世界の人との手の切り方は違うよね。どう違う?

Aは仙吉という別世界の人間への同情心を持った。でもそれは根源的なものとはいえない。その自覚があるから彼はその心を引っ込める。そうした自分に寂しさを感じる。そういうことですかね。結局自分に限界があることを知った、というか知っていたんだと思います。限界というのは、階級というものです。Aは所詮「貴族院議員」なんですよ、穏やかな生活を保障された階級の人間なんです。
手を出しちゃあいけなかった、という気持ちじゃないですか。

フリイデマンと夫人についてはもっと気分が悪くなるような結末ですね。夫人にあるのは単純な戯れでしかないんじゃないかな。僕にはそうしか思えません。退屈さを慰める戯れでした。障害のある人に対する同情なんか初めからなかったんでしょう。優位者が劣位者に対して持ついやらしい感覚しか感じられず救いがない。退屈が軽い概念でないことは学習しましたけどね。そういう意味では夫人も悲しい人なのかもしれない。
二つの物語に、そういう違いがあることはわかりますが、でも基本的な結末は両作品とも、二つの世界の違いはどうにもならない、という点です。そしてそれでも、僕たちはそれをどうとるのか、ということですよ。健常者が障害を持つ人たちをどう見るのか、とか、社会の中の疎外された人たちを私たちがどう見ているのか、そういうことを読者が突きつけられているということじゃないでしょうか?
そうだ、別世界への欲望という点でフリイデマンと仙吉との違いをお蜜いたんだけど、いいですか?
フリイデマンは自己抑制を続けてきたがそれを中佐夫人への恋で破滅してしまった。いっぽう仙吉はAによって鮨を食べることができる世界を体験したが、そのAを神様として遠ざけることによって、自己抑制することができた。考えたら、西洋と東洋との現実受け入れの違いがよく出ているんじゃないでしょうかね。僕たちがつい仙吉を選んじゃうという悪癖があるという反省も、感じてしまいます。

連想は続くね。それこそが、鑑賞の価値だね。Aについては、まさか誰に対しても戯れでの同情や共感はあってはならないというものの、それをどこまで自分自身に問えるか、ということは難しいなあ。でもそういう読み方があってもいいんじゃないかな、と思う。



コメント